10月
2013年10月21日
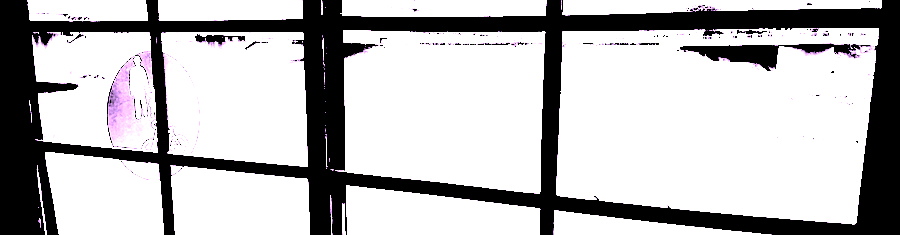
かつてスターバックスに行った夜にレジで「これどうぞ」と言われてカップの上でドリップする商品のサンプルか何かをいただく機会があり、その時だったかその時でなかったか忘れたけれどスターバックス、パーソナルドリップ、オリガミ、いずれのアルファベットの単語の横にもレジスタードトレードマークを意味する丸に囲まれたRが付されており、このペースで世界に登録商標が増え続けた場合、私たちはいつの日かまともに会話するだけで何かしら請求されるようになるのではないか、という話を今晩彼女として、そのときに私たちが武器にするのは言い淀みや吃音であるといった結論に至ったわけではなかったが、どこを引いても似たようなものが見つかるのでそれは本当にどこでもいいのだけど、例えば「その短い合間に女の前腕を撫でながら、二人の間で一節一節を際立たせるようにして話すその姿は、言葉を積み重ねていけば痩せこけた顔を少しはごまかすことができる、女がありきたりの質問をしてこないかぎりは大事な何かを救い出せる、そんなことでも考えているようだった」というような文章は、バス停の前のカフェというのか酒場というのか何かそういった類の店の店主の視点から描かれている文章であって、あるカップルの行為を見つめる店主がずいぶん勝手に妄想を膨らませてそんなことを思っているというわけなのだけど、ここにはどんな躊躇も、思考の吃りも感じられず、嬉々として何か、「文学」的とでもいうのか、そういった世界に安心して身を委ねているような気がどうしてもしてしまって、フアン・カルロス・オネッティの『別れ』はだから、一つも面白く読めないままに終わってしまった。このウルグアイ生まれの作家のものは、先月か先々月に読んだ『屍集めのフンタ』も全然楽しく読めなかったのだけど、ホルヘ・エドワーズの『ペルソナ・ノン・グラータ』を買いに行ったら在庫がなくて、それで代わりにというか、水声社の「フィクションのエル・ドラード」シリーズの第4弾ということで、出ていたんだ、というのを店頭で知り、どうだろうという懸念はありながら、このシリーズは追っていきたいような気でいるので買ったのだけど、懸念はそのままに的中し、私はオネッティの小説は今後は読まないようにするべきだという結論に至った。オネッティの文章は私にはすごく気持ちが悪くて、どこまで人の思考みたいなものにずかずか無遠慮に入っていけば気が済むのだろう、無礼だ、みたいな気になるというか、要すると「うるせーよ」と思ってしまうので、そういった人間にオネッティの読者になる資格はきっとない。バルガス=リョサを始め多くの作家がオネッティを「すごい」と言うらしいのだから、きっとすごい作家なのだろう。表題作とあと短編2つを収めたこの作品集の中で、唯一、本当にたぶん唯一、私がいいねボタンを押したのは「他方、青年といえば、極度の臆病者、そして皮肉屋だったが、ある冬の日の夕方、恐怖と風邪、やましい心とあの世と三十八度の熱に怯えて眠るバルテーのベッドへ近づき、用心深く、それでいてはっきりと、こう呟いた。「二つお許し下さい。私を共同経営者にすること、すでに公証人とも話はついています。嫌なら私は出ていきます。薬局は店仕舞い、これで商売も終わりです」」というくだりで、「バルテー弱り目に祟り目www」と思った。そのため今日は「どうしていつも、うまくいかないのだろう……。」と帯文にあるジュノ・ディアスの『こうしてお前は彼女にフラれる』を買って素敵なカフェ的な場所で読んでいたのだけど、買う時はなんだかそう乗り気でなく、いくつかの場所でやたら面白いと目にした『HHhH (プラハ、1942年)』を読んでみたいというような、ラテンアメリカから私を引っ張りだそうとする磁力を感じたりもしていたのだけど、「まあとりあえず2666読むまでは、年内は、小説についてはラテンアメリカ縛り継続で…」という内なる声に従って買ったのだけど、読んでみたらやっぱり面白いもので、4編ほど読んだけれどもどれも充実していた。「アルマはメイソン・グロスの学生で、ソニック・ユースを聞きマンガを読むオルタナ系のラティーナだ」とか、別になんていうことのない一文だけど、もうそれで十分という気になってくる。この短い「アルマ」という一編もまた、すごくいい。「なあ、これはおれの小説の一部だよ」とか、笑わないではいられないけれども、笑うその笑みもこわばりを覚えてしまう。とてもいい。ジュノ・ディアスの文章も軽やかで好ましいけれども、私がそれを読む向かいで彼女が読んでいた『スローターハウス5』の、「So it goes.」、そういうものだと何度も書くヴォネガットのありようを、まあなんというか、私の人生にもインストールしたいし、オネッティに欠けているのもそういうものだの精神なんじゃないかと、たいそう立派な作家の肩を叩いて私は言ってやりたい。今度は私が「うるせーよ」と言われる番だろう。うるせーよ、本読めねーよ、と思って私はジュノ・ディアスを途中で切り上げてカフェを出たのだけど、横のテーブルの若い女性お二人がたいへん賑やかに話をされていて、びっくりするぐらいに大きな声というか、耳に入り始めると全部持っていかれる程度には大きな声だったので読書どころではなくなって、本を閉じ、試しに「新潮のクレストブックスシリーズは始まって15年なんだって。長いね。なんかもっと最近なのかと思ってた、長くてその半分ぐらいの感覚。読んだことあるのは数学のやつとなんか忘れ物の駅のやつだけかな、あとオスカーワオと」と、若い女性のボリュームを自分も体験してみようと思って同じぐらいの大きさで発話してみたのだけど、その感想としては「やっぱり過剰に大きい」というもので、とてもじゃないけど、恥ずかしくて続けられなかった。「今日はよく話したねー」みたいな満足の声というものがあるけれど、あれはもしかしたらどれだけ多くの言葉を発したかという以上に、会話という運動の中でどれだけカロリーを消費できたか、が競われているのかもしれないと感じたのは、そのときだった。帰りの車ではそのことを話しながら、寄ったマクドナルドで購入したフライドポテトを食べた。いくらか前にSIMI LABの何かのyoutube動画を見ていたら、マクドナルドの添加物感がたまらない、死んでも死体も腐らなくて済みそう、みたいな会話がたしかなされていて、それを思い出したのだけど、そういう添加物ライフを謳歌みたいなものと正反対をいくであろう岡山の北の方、真庭市は勝山に店を構えるパン屋さんタルマーリーの方の本『田舎のパン屋が見つけた「腐る経済」』を最近読んだ。一度か二度は食べたことがあって、おいしくて、でも店には行ったことがなかったのだけど、本屋に行ったときに出ているのを見つけ、ただの岡山の人が出しましたという本であれば買うこともなかっただろうけれど、冒頭でレーニンの言葉を確か引いていて、なんだろう、ちょっと面白そう、と思って買ったのだった。わざわざ買った経緯と理由を言い訳がましく書くのはただ岡山の人が出した本だから買ったというふうに思われたら、いやあすっかり岡山に染まっちゃって、などと指をさされそうで嫌だなという奇妙な防衛意識からで、でもまあ多分、関係ない土地の、まったく聞いたことのない店の本だったら手にとってないんだろうなとは思うのでなんとも言えないところなのだけど、でもまあその本は、思った以上にとても面白かった。パンについても、「なんという…!」というこだわりというか実践が知れ、「うわーなんかもうパンの世界とか一切知らないけどこれはきっとたぶんものすごいことされてるわ~…」という思いをいだいた。ほとんど畏怖ぐらいにすごいなあと感じました。私はいったい何を実践できるのだろうと、そういうことを考えだすとわりと気が塞ぐというか、半端な自己嫌悪に陥るので自戒というか自重しないとと思うのだけど、とりあえずのところ思ったのはゲスなところに引き下げてという感じが否めないけどやっぱりテキストというのはこれからの時代すごい力になるはずですよねということで、いいものを作っています、いいものを売っています、いい場所を提供してます、それ自体はそれぞれに素晴らしいことですねと思うのだけど、だから、選んでくれますよね?という姿勢ではダメで、それならまだいいけれど、なのに、なんで来てくれないんですか?みたいなことを口走り始めたらもう最悪で、何かの信念を持っている人ほどそういういいもの作ってるのに売れないのは時代のせいとかお前のせいみたいなことを言う人が見受けられるような気がして、自己満足したいのか他人に認められたいのかわからないというか、社会とか他人に呪詛の言葉を吐いてそれでお腹が膨れるなら、口座に金が充当されるならそれもいいけどそうじゃないので、信念を持っていいものを作ってメイクマネーして生活を立てたいならばちゃんと伝える努力もしなきゃと私はいつも思っていて、この本を読んで「うわーそれ超行くっすわー、食べたいっすわー」と思わせられ、改めてそれを思った。ただそれとて手法として取り入れればいいというものでもなく、まず内実というか、信念とか何やらがあってこそなんだろうから、それは決して「うまいことをやる」というのが先に立つものではなく、まず何か信念というか実践というかそういった何かがあって、それをストーリーに仕立てて価値をちゃんと伝えるみたいな、その情報までパックして価値を高めるみたいな、書いていてどんどん気持ちが悪くなってきたというか吐き気がしてきたというかビールを煽りたくなるというか指が腐ってきたというかなんだけど、まあなんかそんな感じだよねーということを、それは再認という形というか補強という形だけど思ったのでいい読書だったのだと思うのだけど私の生きる場所は岡山ではなくてラテンアメリカなので話を戻すと『売女の人殺し』は最後まで本当に面白く、どれも面白く、特に印象に強く残ったのは「ブーバ」という作品で、「中盤にいた二人のディフェンダーがその場に釘付けになったように見えたんだ。俺は相手右サイドバックにぴたりと背後につかれたまま走り続けた。ブーバも同じく相手左サイドバックにマークされたままペナルティエリアに近づいてきた。そのときあいつがフェイントをかけてセンタリングを上げた。俺はこのボールには届かないだろうと思いつつエリア内に入っていったが、相手センターバックがボケッと突っ立っていたというか、急に気分が悪くなったみたいだったのと、ボールが変な動きをしたせいもあって、確かなことは、俺は奇跡みたいにエリア内でボールをキープして、突進してきたキーパーと俺の左背後にいた相手右サイドバックが反則覚悟で当たるべきか迷っているあいだに、簡単にシュートを放ってゴールを決め、俺たちが試合に勝ったってことだ」とあるようにサッカーが扱われているのだけど、サッカーの動きのある描写と、マンションでのスタティック(かつたいへんダイナミック)な描写、それらを回想する現在の描写の連携がなんかこう、たまらない類のものだったのだろう。そのことは「俺たちは、何年ものあいだ互いに音信不通だった。それがついこのあいだ、史上初めてチャンピオンズリーグを制覇したチームを懐かしく振り返るという趣旨のテレビ番組が作られた」というなんということのない箇所でほとんど涙が出そうになったことが証明している。とにかくボラーニョコレクションのこれからの刊行が楽しみなのだけど、年二冊ずつという予定らしく、しかも次はすでに読んでいる『通話』の改訳版ということなので、まあでも、今『通話』は人に貸しているということもあるし、「せっかくなので」みたいなところでこれも買って再び読むような気がしているが、年二冊ということはボラーニョコレクション全部読んだら『2666』行こうみたいなことをやっていたら何年も後になってしまうということで、やはり今年最後の一冊みたいなところで読むべきだろうかと、なんとなくそろそろラテンアメリカ縛りは終わりでいいような気もしてきた、つまり下火な気分が出てきたということもあるので、そろそろ、というところだけど、『売女の人殺し』に挟まれているボラーニョコレクションのアナウンスのチラシに煙草をくわえながらレンズを見つめるボラーニョの写真があって、「roberto bolano」で画像検索していろいろ見てみてもその印象は揺るがないのだけど、ボラーニョの顔はわりと佐々木敦に似ている気がする。『HHhH (プラハ、1942年)』で検索したら最初の方に佐々木敦の書評のページがヒットして、今は早稲田で教えられているのか、そして教授なのか、と知る。かつて私は毎週とても楽しみにして「ポップメディア史」という講義を聞いていた。大きい教室はオメガ館とかいったっけ。アルファ館だっけ。そういうことはどんどん忘れていってしまう。