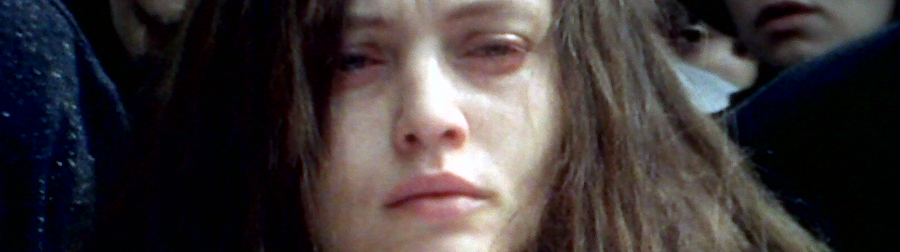text
2013年8月1日

3年ぶり11回目のフジロックに行ってきた。
わりと直前まで行くかどうか決めかねていて、チケットを買ったのも出発の前日だった。幸いにもレインコートは父親がゴアテックスのやつを持っていたし、テントは友人のところに潜り込ませてもらい、椅子も友人から借りたし、車も乗せてもらった。今までもずっとそうだったけれども、いろいろな人におんぶにだっこのフジロックだった。
音楽、音楽、音楽と、何かあるたびにPSGの『愛してます』を思い出すのだけど、今の私にとって音楽がそんなに大切なものなのかどうかは行ってみたけれど結局はわからなくて、それよりも友人たちとたくさんの時間を過ごしてたくさんの会話をすることが掛け替えのないことだった。やっぱり、どう考えても、ことごとくに極めて楽しかった。
25日(木)
前夜に友人から連絡があり、もともと私が乗せてもらうことになっていた車の持ち主が仕事の都合で翌日発になったため他の車に乗ってもらうことになったと告げられたため集合場所である高円寺に私は緊張しながら向かった。完全な人見知りではきっとないのだろうけれどもけっこう人見知り要素を私はたぶん強く持っているため、待ち合わせ前は想定していた以上にドキドキした。
車に乗って苗場に向かった。雨が降ったりしていたし様々な音楽が鳴らされた。それなりにうまく振る舞えたような気がしたけれども、何かと気を使わせてしまっているのだろうなという気持ちは拭えず、恐縮する車中だった。「どのように振る舞うのがベストなのかはまるでわからないけれど、この人たちはそれぞれにとても好ましい人物なんだろうと節々の挙動から私は判断する」というのが感想というかそのとき抱いた感覚だった。でも、わからないと言っても、その「好ましい」を判断できればそれで十分なのかもなとも思った。知る限り、本当にいい人たちで、好ましい人たちだった。もっと臆せずに関係を作りに行ったらよかったとも反省した。雨がたくさん降って、そういうときにヘッドライトに反射する水たまりはいつだって好きだった。場内駐車場へ入るゲートを車が通るとき、「戻ってこれた」というような気分で泣きそうになった。11時ごろに着いたような気がした。乗せてもらった道中に感謝しつつ乾杯をした。
今回は11回目ということでけっこうな回数フジロックに行っていてすべてキャンプサイトを利用しているにも関わらず私はアウトドア的なノウハウを一つも蓄積させることなく、それはいつも他人におんぶにだっこで行っているからなのだけど、今回もタープやテントの設営に対してまるで無力で、あたふたとしながら、(これは本当は俺は触れない方が速いのではないか)という疑念と闘いながら、「すいませんアウトドア的なノウハウ全然ないんですけど何かできますか」と断りを入れつつ手伝える範囲で手伝った。私が打ったペグは、何日目かに見たら外れていた。
夜中に出発した友人たちが3時とかに到着し、ちょうど歯磨き前に夕飯を食べようと下に降りていた私は彼らを発見し、会話をおこなった。リストバンドの交換の列がやたらに長いことになっていて、それは運営側のミスとしか言いようのない性質の長蛇だった。空が明けるまで、友人たちと何を話していたのかは忘れたが話した。テントを設営し、明け方に眠ったのだと思った。苗場に着いてから雨はまだ降っていなかった。
26日(金)
じわじわとテントの中をボイルしてくる太陽光にやられて早い時間に目を覚ました。iPhoneが壊れたかと思った。何を押しても画面がつかない。なんでだろう、なんでだろう、と思っていたらかすかに文字が映っているのが見えた。電池の持ちをよくするために画面の明るさをいちばん暗くしていたので、画面が見えなかったせいだった。そのおかげか、一晩経っても80%以上電池が残っており、誰と連絡を取るわけでもないにせよ、何か安心する心地だった。結局お風呂に行ったときに充電できたりしたため、前日に購入していた丸2回充電出来ます的な充電器は不要だった。4000円だった。
起き抜けにビールを何杯か飲み、タープの人たち(行きの車に乗せてくれた人たち、それは友人の友人たちで、その集落に15から20人ぐらいいて、すごくアウトドア的なスキルが高い人たちだった)が作った食べ物をいただいたりしながらダラダラした。
私の熱はまだ全然冷めていないらしく濱口竜介の『親密さ』の話を私はなんのきっかけだったか、今の私はなんだってきっかけにしてしまえると思うのだけれども、『親密さ』の話をした。期間中、「親密さ」ではなく「厳密さ」という言葉が会話の通奏低音に流れることになった。厳密であること、その倫理、そしてそこに生じうる暴力。
だいぶ長い時間そこに留まり、出発したと思っていたら下からビール買って戻ってくる、みたいなことが繰り返されながら、次第にタープから人は少なくなり、最後までいた人たちが「普通にみんなで集まってキャンプやったらいいよね」「フジロックって言い訳がないとなかなか集まらないから」と言っていたのが印象に残った。そうだよなと思った。私たちは、フジロックという動機を利用して友人たちと会って時間をともにするために苗場に行っている、部分が大いにある。
おそらく空腹などを理由にして下におり、オアシスとかに行ったような気がするけれど定かではなかった。まだ晴れていたのでビールを飲んだし、豆腐飯を食べたのは翌日からだった気がする。
マーキーでロン・セクスミスを4曲ほど見て、全部がまさに「ザ・ロン・セクスミス印」という曲で、とてもいい曲だったのだけど、一つのザ・ロン・セクスミスのバリエーションという印象が拭えなかったためもういいやと思って出た。今思い出したけど、一方で私は最初の曲を聞いたところで涙をあふれさせたのだった。何かがこみ上げたらしかった。中学生のときにナンバーガールに衝撃を受け、そのあとに「初めての洋楽入門」的なものとして友人が貸してくれたいくつかのCDの中にロン・セクスミスがあったということはその涙の理由ではないような気がした。なおそのCD群には他にポーティスヘッド、ペイヴメント、ジェームズ・イハあたりがあった模様。
マーキーを出た私はグリーンの左後ろの方の芝生のところに椅子を置いてケムリを見た。ボーカルの人がタオルを回せと会場に指示を出してそれに則って人々が一斉にタオルを回す光景を目撃しながら、私はまたもや涙を溢れさせていた。抑えきれない、という涙の出方だった。この日、私は少し何かに感銘を受けるたびに「やばいよ涙、涙がとめどなく溢れてくるよ」という状態だった。ケムリのそれはとても、いい光景だった。最後の方で眠りに落ちた。
目が覚めると外国の人たちがバンド演奏をおこなっており、ポップな曲をとてもスキルが高そうな演奏でやっていて、パフォーマンスとしてもとても格好よく思い、この人たちはいいバンドだなあと思った。横にいた友人にあれは誰なのかと問うたところ今年のグラミー賞を取ったバンドらしく、「なんと私はグラミー賞バンドを見出してしまった!」という滑稽味を感じた。それはとても健全でいいことでもあった。
そのままマイブラを見た。とてもよかった。ヘヴンに移動してピザを食べた。みなが絶賛するピザで、都合3度ほど食べたが、とてもおいしかった。このころには雨が降りだした。ヘヴンではなんとかというギタリストか誰かがバンド演奏をおこなっており、私はピザでお腹が膨れたためか、椅子に座って眠りに落ちた。
目を覚ますと20時過ぎで、友人たちの姿はもうなく、この日初めてタイムテーブルを開くとFlying Lotusが始まっていたので気持ち的には急いだ感覚でホワイトに向かった。グーグル日本語入力は「ふらいんぐろーたす」でちゃんと「Flying Lotus」にしてくれるので優しいし、スペルの間違いがなさそうで心強い。
Flying Lotusは格好いいという話以外は聞いたことがなかったのだけど、そのステージはもう素晴らしくよかった。でっかいスクリーンをスペイシーな風合いの映像が音と連動してバキバキと覆い、スクリーン裏のDJブースに立つFlying Lotusがマイクを持って煽ってくる。アンコールではずっとラップをしていた。ものすごい格好いい映像と音楽と、そしてその人物の粗野そうな感じがものすごくよかった。今年のベストアクトは?と問われたらそれだった。
椅子をヘヴンに置いていたので取りに戻ると人々がいて、目の前ではチャーたちが演奏していた。友人に先ほど見たFlying Lotusが格好良かったことを告げるとその友人も見ていたらしかった。私はそのとき、そのことをすごく話したいと思っていて、どうもここのところ、いいと感じた物事について私は他者に言いたくて仕方がないのかもしれない、とそのとき思った。それはもしかしたらある種の自己顕示にもなりかねないけれど、「私は・これが・よかった」と意思表示することは、コミュニケーションにとって有用なことでもあろうから、他人との接続という、前向きかつ社会的な身の変化の仕方なのかもしれないとも思った。
雨は振り続け、雷が空を何度も明るませた。音が遠かったこともあり、また、落ちたとしてもこれだけ会場に人がいたらその対象は自分ではないだろうという無根拠かつ無責任な気分から雷怖いということにはならず、むしろぬかるんだ道を照らすツールとして雷光がありうることを発見して喜ぶふうでもあった。
ホワイトの、名前の読み方(ロゴの文字が読めなかった)がわからないトリの人の演奏を見た。大きな竜の頭を模したDJブースで、炎やスモークがふんだんに使われる、とてもバカらしく大味な舞台で、音は全然好きでもなんでもなかったけれども見世物としてすごくいいと私は思って、途中でご飯とビールを買いにアヴァロンに行って戻ってきたら竜の頭がすごく高いところまで上がっていて「バカだなあ」と思ってとても好ましいと感じ、道が混む前にと思いオアシスに向かった。
しばらくしたのちにオアシスで友人たちと合流し、酒を飲むなりご飯を食べるなり各人の好きなことをした。パレスに行って、また人々とはぐれる格好になり一人でテントの中で揺れてみたり、フジウジちゃんというろくでもない催しを見たり、危険そうなバイクのやつを見たり、火を吹くドラゴンのやつを見たり、ルーキーステージの演奏にちょっとグッとしながら過ごした。これまでパレスで遊ぶことはほとんどなかったのだけど、なんだかとてもいいところだと感じた。マーキーに行き、DJシャドウを待ちながら椅子に座っていたら眠りに落ち、起きたらDJシャドウが始まってだいぶ経ったところだったし、疲れていたので帰ることにした。
歯磨きをリュックに入れておけばよかったと思ったのはこのときで、歯磨きをリュックに入れていれば帰りがけに歯磨きをおこなってテントに戻ることができた。反省をしてビールを飲み、同宿の友人に「音を立てて申し訳ないなあ」と思ってから寝た。
27日(土)
またもや朝は晴れるということで暑くて目を覚ました。友人たちと車でお風呂に行った。ダラダラと過ごした。ずっとここにいてもいいぐらいの心地があったが、ちゃんとテントに戻ったし、会場にも行った。
何を見たいということもなかったためにオアシスでパエリアを食べた。途中で強烈な雨が降ってきて、人々と同じ考えからマーキーの中に避難したが、人々で埋め尽くされていて、仕方がないというか無気力な心地で私たちはマーキーの屋根から数メートル離れた雨ざらしのところで立ち尽くしていた。煙草に火をつけてみたが途中で濡れて消えた。それ以外なにかをやる気にもならず、雨にただ打たれていた。気持ちとしてはしかし悪いものではなかった(日常の中では雨に打たれたまま立ち尽くすということはなかなかしないため)。
雨が一向にやまないので、私たちはマーキーの演奏を見ることにして、ずいぶん前の方まで行った。なんとかという鍵盤と歌唱を生業にしているマコーレー・カルキンみたいな人が率いるバンドの演奏を聞いた。あまりピンとこなかったけれど、よかった。
マーキーの中にいると、雨だれの勢いを見て「ああまだ雨あんな強く降ってる」と思いがちなのだけど、小用目的で外に出てみればそう降っているわけでもなく、「なんだ、これしき」と思った。マーキーに戻り、ダークスターだかダークスターズだかそんな名前の人だか人たちだかの演奏を見、1曲目で見事に眠りに落ちた。目を覚ましたらライブが終わったところだった。そこにいた4人とかの友人のうち誰も感想を言っていなかった気がするが、もしかしたら全員が寝たのか。すごく格好いいと聞いていたので残念な事柄だったが特別後悔することはなかった。
ヘヴンに向かった。途中でグリーンでアンダーワールドの人が一人でやっていて、友人が「うーん」というようなことを言っていたけれど、アーティストの人は大変だよなといつも通り思った。ライブだと、特にフェスのライブだとその傾向が強いのかもしれないけれども、私たちが舞台上のアーティストに期待するのは、そのアーティストの現状を見せてもらうことではなくて「私のフェイバリットのあの曲の再現」であることが多いような気がして、つまり、変化なんて誰も求めてはいないみたいなところがあって、だけどやっている人たちも当然いろいろやりたいことは変化していって「あの曲」なんてもはやどうでもいいとか思っていたりもするのだろうけれど、多くの観客はそんな気分の変質なんて知ったこっちゃなくて、いいからあの曲をやれと、やってくれと、イントロドンで「わー」って大歓声って、予感に対する賞賛じゃなくてすでに完成したあの曲の記憶をすっかりそのまま見せてくれよなという脅迫でもなり、「わー」って、あれはけっこう、すごいことだ。ヘヴンでまたピザ食ったと思う。
3人組のブルースかカントリーかよく知らないけどきっとアメリカ人なんだろうなというバンドがやっていて、ペダルスティールを用いたちょっとアンビエント気味のスタートからすごく気持ちのいい音を聞いて、「これはとてもいいぞ」と思っていると友人たちがオレンジに行くというので執着もまるでなかったのでついていった。ブラジルの人たちがやっていて、そこで懐かしい友人にも出くわした。うれしい出来事だった。
それからグリーンに戻り、ビョークをほんのすこしだけ見た。4曲ぐらいだったと思うけれど、格好良かった。しかし気持ちとしては今一番かっこういいラッパーということを友人が言っておりそれはたいへん信頼出来る筋からの情報だったのでケンドリック・ラマーを見たく、すぐにホワイトに行った。
ケンドリック・ラマーは立派なバンド編成で、すごく煽ってくる感じで、あとものすごいオーディエンスに話しかけてくる人で、多くの人びとは英語を解さないという場所だったのでトーンだけを聞き分けて「イェー」と言ったりして、「何言ってるかさっぱりわかんないけどお前のこと応援する気持ちに嘘はないよ」ということを伝えた。ラップはとてもうまいし格好いいと思ったのだけど、演奏が大味な感じで「うーん」と思っていたら、気づいたら眠りに落ちていた。目を覚ましたらライブが終わったところらしかった。どうも、面白い/つまらないの体感に対して眠気がものすごい正直に反応しているみたいで、動物みたいだったし見栄も何もあったものじゃなかった。それは健全なことではないかと思った。
ザ・バンドの誰かがやるというのでヘヴンに行った。そこでも何かを食った。たしか生姜丼みたいなやつで、太陽食堂という名前のところだったと思う。3日で3回行った。3日目に食ったラグーパスタと枝豆のコロッケが今年一番ぐらいに美味しかった。それにしても3年前に比べても「食堂」というショルダーネームを使っている店が増えている感じがして、まあこれ完全にそのトレンドだよなと合点がいった。
ザ・バンドのバンドは、白ひげのおじいちゃんと、ずっとおじいちゃんだと思っていた車椅子黒サングラスのおばあちゃんと、あとは一回り二回りは若い人たちという編成で、懐かしいあれやこれやの曲を聞くことが出来たという思い出消費的な満足ももちろんあったけれど、おばあちゃんが車椅子に座って杖をどんどん叩いてリズムを取りながら、枯れながらも張りのある声で歌い上げるあの様子に感動しないわけにはいかなかったし、おじいちゃんのピアノ、それからオーディエンスの歓声に応える際の、おじいちゃんのあの両手を伸ばしてぴょんぴょんと指を振る動作、そういったあれこれがとてもハートフルで好ましい光景だった。
私にとって「あの曲」に相当するのは「The Night They Drove Old Dixie Down」で、聞きたいなあ、聞きたいなあ、とても聞きたいなあと思っていたら、ライブ終演後のSEの一発目で流れ始め「そんな形で聞きたいと思っていたわけじゃないんだよ!!!!」と大笑いをした(一人で)。でも何にせよとても心を打たれて、いい気分でいたし翌日もずっとその曲を口ずさんでいた。
ホワイトに移動し、ジュラシック5の最後の15分ぐらいを見ることが出来た。当初はジュラシック5はこの日とても見たいものだったのだけど、ザ・バンドの人のバンドがとてもよかったので最後まで見てしまったため最後の方しか見ることができなかった。それはたしかにその通りなのかもしれないけれど、ケンドリック・ラマーを見て「うーん」となったことが影響しているかもしれなかった。「今はもしかして楽しくワイワイヒップホップみたいなものを見ても楽しめないのではないか。それよりも老アーティストたちの姿を思い出消費とともに見る方がいいのではないか」等という原因。
15分見たジュラシック5はすごく楽しく、かつザ・プロフェッショナルという一分の隙もない完璧なパフォーマンスで、魅了された。やっぱり最初から見たかった。
それにしてもいくらビョークが早い時間に終わったとは言ってもジュラシック5はけっこうものすごい人の量で、ヒップホップってこんなにみんなに愛されていたんだ、と感慨深かったというか別に感慨深くもなかったけれど、人が多いと思った。
そのため帰りはすごく行列だったので、友人たちとところ天国に退避してウダウダとした。男はつらいよの上映をおこなっていた。
人がすいてからオアシスに戻り、ご飯を食べたり飲酒したり、各々が好きなことをしながら、友人たちとこの夜は延々と話していた。それはやはり有意義で親密で大切な時間だった。ライブを見て「あれ、意想外に面白くない」と思うぐらいだったら友人と話していた方がずっといいなと今の私は思っていた。
帰りがけにパレスに寄ろうとしたところなんとかテントとかいう名称のなんとかというところに行列が出来ていたのでスルーして帰って、寝る前にハンバーガー食ってビール飲んで寝た。とてもいいおこないだった。
28日(日)
また朝は晴れていた。友人の一人がヨ・ラ・テンゴを見たいらしく、前日ほど風呂でゆっくりはできないぞ、という認識からてきぱきと風呂に向かおうとしたところ、そのヨ・ラ・テンゴを見たい友人が「俺も(お前が昨夜食ったという)ハンバーガーを食いたい」と言い出して、しかも思ったよりも受け取るまでにずいぶん長い時間が掛かったので、皆、「あ、これはヨラテンのために焦る必要はなくなったということだな」と認識した。この日も車で温泉に行った。気持ちよかった。ゆっくり過ごした。
それでもその友人は風呂から戻るとテントに戻らず直接グリーンに向かって、あとでテントに戻ってきた。10分か5分ほど見れたと言っていた。「すごい行動力だなあ!」私は感嘆した。豆腐飯を食べた。
どうもこの期間中、胃に優しいものを体はずっと欲していて、うどんやオクラ納豆丼とか豆腐飯とかそういうヘルシー系のものをわりと何度も食べていた。そのせいか、快便が維持された。
グリーンに行くと、晴れていたので格好よさそうなバンドが演奏をおこなっていた。おじいちゃんの3ピースで、すごい格好よかったのでビールを飲んで見た。たぶんそのあとにまた雨がたくさん降ってきて、今年はとにかく雨に降られる年だった。
マーキーでHAIMというガールズバンドを見た。エネルギーに満ちたとてもいい演奏で、私は勝手にその女性たちのことを「『スプリング・ブレイカーズ』のあのスプリング・ブレイクを終えた少女たちが組んだバンド」という設定で見た。春休み、はっちゃけたくてなんかはっちゃけるところいって、すごいいいねと思っていたらヤクでしょっぴかれた縁で知り合った危険そうな男たちと過ごすことになって、銃とか手にしたけれど私は元気ですという、あの素晴らしい感傷とエネルギーに満ちた映画のあの少女たち。春休み終えてキャンパスライフが始まって、なんかやっぱり楽しいことないかなって誰かが言って、楽器を手にする。やってみたら下手くそだけど楽しいねとなって、はまって、ああいった演奏をおこなう。有名になって海外のフェスに行くことになっちゃった。
そんな彼女たちの演奏はすごくよかった(あとでウィキペディアで見てみたら全然そういう鬱屈から発奮系のバンド結成経緯ではなく、音楽好き一家のプロジェクトからの延長、ということがわかった)。
激しく催したので渋々マーキーを出たらすでに友人たちも出ていて、どっかに行くというからついていった。ヘヴンでレゲエの人たちがやっていた。少し見ていたら、気づいたら眠りに落ちた。一人になったこともあり、特別興味はなかったがトロ・イ・モワを見にホワイトに行って、座ってみていたらやはり特別興味がわかなかったと見え、眠りに落ちた。今年は一度寝たら演奏の途中では絶対に起きない、みたいなことになっていて心強い。
そのあとどこかに行こうかとも思ったけれどどれがということもなかったので相対性理論を見ることにして待った。相対性理論は2曲ほど聞いたけれど「わたし今こういう音ぜんぜん楽しく聞かない」ということが発覚したので出た。相対性理論は好きだし、ツインドラムでびっくりした。
ヘヴンに移り、Lotusの最後の方を聞いた。最初からこっちにいればよかったようにも感じたけど、一方で元気すぎるかもとも感じた。
アヴァロンでお腹を満たそうと向かった屋台のお兄さんが親切だったので、そのあとにビールを飲みたくなったときにどうせ同じビールを飲むならさっきのところにお金を落とそうと向かったところいくらか並んでいて面倒くさくなったので一番並んでいないところでビールを買った。キャット・パワーを見るためホワイトに戻った。
キャット・パワーは今回わりと見たかったもので、私は一時期彼女の音楽が大好きで、新譜が出るたびにちゃんと買う、という立派なカスタマーだった。高校生のとき、『You Are Free』が出た記念のライブが下北沢のラカーニャだかラマーニャだか、そんなところであり見に行った。それが最初で最後のキャット・パワー体験だったのだけど、背が高く髪の長いショーン・マーシャルはライブ前に恋人と腕を組みながら道を歩いていた。ライブはギターとピアノの弾き語りで、しばしば失敗して「ソーリー」とか言いながら演奏する姿はすごくチャーミングで、いいライブを見た、そんな記憶があった。
そのあと興味を失ってから、たまに新譜が出たとかニュースを見て、YouTubeで聞いてみたりするものの、私が好きだったあの感じはずいぶん薄まってしまったらしく、遠のいていた。だから今回のライブも楽しみではある一方で、おそらく私が好きだったころの雰囲気はもうないのだろうから、楽しく見られない可能性大、という予測はすでにつけていた。で、実際そういう感じで私が好きな音ではなかった。それは私が3,4曲目で眠りに落ちたことで実証された。そりゃそうというか、10年前のあの曲を、あの感じでやってくれよだなんて、そんなことを思ったってまるで仕方がないことだった。彼女は彼女の変化をして、私は私の変化をするという、実にシンプルなことだった。
The xxを見た。とてもかっこうよかった。
長い時間一人でいたので寂しくなっていたところ友人を見つけたのでうれしかった。キョロキョロしていると、PUNPEEが若い人たちに写真を頼まれてカメラマンをしている光景を見かけた。すごくいい人そうだった。
相変わらずホワイトの行列がたいへんだったのでところ天国に退避してホットワインを飲んで、それからオアシスに向かった。なんか食うか飲むかして、そうこうしていたら時間になったのでパレスに。The Otogibanashi’sは今回のフジで一番見たかったアクトかもしれず、とても楽しみにしていた。そのため最前列で見ていたら、最前列にいるのはだいたいメンバーの友だちとかのようで、メンバーに「俺、俺」みたいな感じで手を振ったりしていた。ライブはとても楽しかった。雨がまたどんどん降ってきたのでかすうどんを食べて、パレスのテントの中でキューバ音楽とダンスみたいなのを見ながら楽しく踊った。4時頃だったか、帰ることにしたのだけどお腹がすいた気がして寄り道をして、スタミナうどんを食べた(立て続けにうどんを食べているという認識はこのときはなかった)。何がスタミナだったのだろう、油揚げぐらいしかない気がするが、と思っていたのを、戻ったあとタープにいた人たちに言ってみたところ、ニラが、ということだった。
タープで楽しいおしゃべりに花を咲かせ、5時頃寝た。
29日(月)
初めて朝に雨だった。片付けをしなければいけない時間になんでまた、と思いながら9時前に目を覚まし、一服をする間もなく片付けをした。みんなすごく効率的に片付けをおこなっていた。
雨のせいか、「さようなら、苗場」みたいな感傷もまるでないまま荷物を持って車へ向かい、乗り込んだ。猿ヶ京の温泉に行った。景色もよく、とてもいいところだった。15分ほど湯に浸かった。そのあとにそこの2階でご飯を食べた。そばを食べた。おいしかった。
3台の車の人たちがそこにいたのだけど、そこで他2台のタープの方々とは別れを告げた。お世話になった。
帰りの車は友人たちの車にお邪魔した。大きな車で、すっかり眠った。高円寺に着き、安いピザを食べたあと、なんとかという焼き鳥屋だか焼きトン屋に行って飲んだ。疲れていたこともありこの機会はこれ以上は楽しくは話せないかなとも考えていたので帰ろうかとも思っていたのだけど、まあ行ったら楽しいかなと思って行ってみたらすごく楽しくて、私はきっといきいきとしていた。あれはでも本当に、少なくとも私にとっては、素晴らしく実り多い豊かで快適な時間だった。肉をたくさん摂ったせいか、直後に猛烈な腹痛に襲われ、腹を下した。それはそのまま苗場の期間中に危惧していたことだったので、最後の最後で本当によかった。
高円寺で一人、中野で一人おり、新宿まで送ってもらい、車の主にありがとうを告げた。新宿駅で別れを告げてベルクでビールを一杯飲んでから埼玉まで帰ろうと思っていたら一緒に新宿でおりた一人がこれから友人たちと飲みに行く、その場所はベルクである、ということが発覚したので「じゃあ俺は君らの席からは離れたところで飲むからここで」と言ってベルクの前で別れを告げ、一杯飲み、さらに埼玉で一杯か二杯飲み、帰った。
30日(火)
起き、ご飯を食べ、母親に二週間とかお邪魔しましたと言って家を出る。新宿に行ってベルクでビール二杯とジャーマンブランチと大きいウィンナーを食べ、東京駅に出、バー的なところでウィスキーを飲み、新幹線、ビール。岡山へ。帰る。20日ぶりに。大学生のとき以来の長い長い夏休み終了。8月からまたしっかり働きたい所存。
book
2013年7月25日
7月に読んだ本の短い感想。
アドルフォ・ビオイ=カサーレス/パウリーナの思い出に
パウリーナの思い出に (短篇小説の快楽)
アルゼンチン。短編集。どれも凄まじく面白い。精緻さとデタラメがとても仲良く共存している印象。とてもよかった。
どういう感じで面白いかというと以下のようなところとか。読もうとしている人は読まない方が面白く読めると思うのでという親切な注釈。
「影の下」という作品。愛した女も財産も失って今ではどっかの島の掃除夫として働いている男が長々とその転落の経緯を話していったら最後に突然こんな感じになる。
似ているのと同一であることは、まったく違う。もし何か説明が必要なら、ニーチェとか他の連中が語っている永劫回帰を思い出してもらえばいい。とりあえず一匹の猫について考えてみようまずホテルで火事が起きたとき、その個体を形づくっていた物質は、一度ばらばらになった。そのあと、何かの偶然が作用して、寸分たがわぬ形で再び結合した(P203)
え、えええ!!!いきなりSFに!!??というこの怒涛というかいきなりの転換がすごい。そしてこのよどみのない口調。何度も何度も演説してきたようなそんな様子がすごい。「解説しよう」と言って眼鏡のフレームを上げる博士という様子。今までよれよれの中年男だったのに…
今の私にとって、何かが出現したり、もどってきた場合、自然の出来事というよりも何かの印に見えるんだ。レトという近似的な人物があらわれ、猫は本物のラビニアで、次は君というわけだ。(…)君や他のものの出現によって、ひとつの像が描かれる。それはやがてレダになるんだ(P204)
ガブリエル・ガルシア=マルケス/誘拐の知らせ
誘拐の知らせ (ちくま文庫)
コロンビア。ジャーナリストとしてのガルシア=マルケスによるノンフィクション。コロンビアの麻薬カルテルがアメリカに引渡しをされる法律を変えてほしいがために色々な要人を誘拐して大統領その他大勢の方々を困らせた事件を細かく描いていく。数人の犠牲者は出たもののわりとみんな解放されていてかつ人質にジャーナリストが多いので観察する意志が強かったのだろう、細かい証言が描写の内容をとても充実させている。
人質の見張り番の少年たちに共通するのは宿命を信じて生きているという点だという。そしてみんないい子。
(悪いことに手を染めるのは)自分の母親の幸福を願うためという理由があった。彼らは母親のことを誰よりも愛していて、彼女のためならいつでも死ぬ覚悟ができているのだった彼らは人質たちと同じ聖人たち、「神の子」や「救いのマリア」にすがって生きていた。その庇護と慈悲を求めて毎日、異常な熱意をこめて祈りを捧げ、自分らの犯罪の成功を手助けしてくれるようにと誓いを立てたり献身を約束したりした(P90)
人質と見張り役の奇妙な共謀関係とか、人質先で歓待を受けて「早く出られるといいわねえ」と言われたりする感じとかとても面白くて、人質の夫でけっこうキーマンな人が、(いろいろ政府側が要求を飲んだため)投降するカルテルのボス、超大物、妻を誘拐した主導者と初めて会うときの様子とかも、なんだろうその親密さは、という。
手入れの行き届いた温かな手を差し出し、落ち着きはらった声で言った。「いかがですか、ビヤミサル先生」「元気ですか、パブロ」と彼も応じた。(P405)
まあめでたしなんだけど、解決までには多大な血が流れていて、ものすごい殺戮が起こっている。メデジンというカルテルの拠点となっている、今だと人口200万人ぐらいの町。
そこでは1991年の最初の二ヶ月間に、1200件の殺人事件があり――1日平均20件――、4日に一度は大量殺人事件が起こっていた。(…)457名の警察官が数ヶ月のうちに殺害されていた。(P258)
で、最初の見張り番の少年たちも同じなのだけど、そういう情勢とか経済状況のコロンビアにおいては、まともに働くよりも悪に手を染めちゃう方がわりといいみたいなところがあったりとか、あと警察とか軍自体も市民に対してかなり酷い、無差別に殺すぐらいの感じのことをやったりしていることもあって、市民感情的にもなんかカルテルがちょっと人気だったりとかしている。
「郊外町村にはエスコバル(カルテルのボス)のために働く者が2000人おり、そのかなりの部分が警官狩りを生業としている若者だった。彼らは警官をひとり殺すたびに150万ペソを稼ぎ、負傷させるだけでも80万ペソになった。(P258)
なんというか、それで結局最後にエステバルは死んで、それによってコロンビアを制圧していたメデジン・カルテルが解体されて、他のカルテルも次第に弱体化していって、コロンビアが覇権を握る時代が終わって、現在のメキシコの大変な状況になる、みたいな流れと聞き、へーえ!という次第。
スーザン・ソンタグ/他者の苦痛へのまなざし
他者の苦痛へのまなざし
他者の苦痛をどうまなざすべきなのか、みたいなことを考えていたので、京都の恵文社で見つけたので買ってみたのだけど、基本的には「写真論」で、写真として我々に日々提供されている世界各地での戦争の様子を、どんな態度で見るべきなの、みたいな話だった感じがあったりなかったりするのだけど、他者の苦痛へのまなざしというのはいいタイトルだなあと。
面白かったのは、アメリカは自国民の死体の写真をメディアに載せるのは嫌がりながら、他国民に対してはそうではないという指摘。アフリカや、中東やボスニア、そういうところでの死者を載せることは厭わないと。へーえと。
真ん中らへんでジョルジュ・バタイユがずっと大事にとっていた写真に言及する箇所があり、それは凌遅刑と呼ばれる刑を受けている中国人の写真で、ジョン・ゾーンか何かのアルバムジャケットにも使われているものらしいのだけど、そこから私は、凌遅刑を調べ、「絶対にググってはいけない言葉」みたいなやつでいくつかのページを踏み、モントリオールかどこかで去年話題になったらしい四肢切断及び視姦みたいな凄惨な動画を見、メキシコの麻薬戦争の記事及び写真を見る、みたいな流れを取ってしまっていて、なんというか、それこそ、他者の苦痛へのまなざしとして一番下劣なところを存分に発揮してしまったらしかった。
苛まれ切断された死体の描写のほとんどは確かに性的な興味を喚起する。(…)魅力的な身体が暴力を受けるイメージはすべて、ある程度ポルノ的である。だが忌まわしいものもまた誘惑力をもつ。誰もが知るように、恐ろしい車の事故の現場を通り過ぎるさいに高速道路の交通の速度が落ちるのは好奇心のためばかりではない。それは、多くの場合、ぞっとするものを見たいという欲求のためである。そのような欲求を「病的」と呼ぶことは、それが稀な逸脱であることを示唆しているが、そのような光景に引きつけられるのは稀なことではなく、内的葛藤の絶え間ない源なのである。(P94)
マリオ・バルガス=リョサ/アンデスのリトゥーマ
アンデスのリトゥーマ
ペルー。これも恵文社で買ったもの。ガルシア=マルケス、ソンタグ、バルガス=リョサは著者名こそもちろん知っているしども人のも読んだことはあったけれど、買ったのは今まで聞いたことがなかったタイトルだったので、いい出会いを出来たと思いました。
結局、私はすっかりラテンアメリカ三昧だけれども、むごたらしい虐殺の歴史に惹かれているだけなのだろうか。こういうページが折られている。山岳部から解放を目指すセンデロ・ルミノソ(やたら強い)の手先の人たちが、虐殺を指揮する。
「死刑を執行するために、彼らはひざまずかされ、頭を井筒の上に載せられた。体を押さえつけられている間、住民たちは町の集会場のそばの建築現場から拾ってきた石で彼らの頭を砕いた。民兵はそれに加わらなかった。(…)自ら行動し、参加し、人民裁判を行う中で、アンダマルカの住民は自分たちのちからに気づくだろう。自分たちはもはや犠牲者ではないのだと気づいて、解放者になりはじめるのだ。(P83)
暴力が生まれる時、そこにはきっと多くの場合に交通の遮断があるのだろう。教訓かというとそんなわけではないけれども、ディスコミュニケーションのありようはぞっとするものだ。
彼女はいろいろなことを話し、訂正し、具体的に説明した。(…)しかし、質問者たちの表情や目を見る限り、完全に誤解していて、いくら説明しても分ってもらえそうにないと確信した。彼らはスペイン語でしゃべっているのに、私は中国語で答えているようなものだわ。(…)男は無表情な目で彼女を見つめ、抑揚のない声で独白のように説明した。「あなたは帝国主義とブルジョア国家の道具でしかないのに、そのことに気づいていない。その上、何を勘違いしたのか、自分が良心的な人間であり、ペルーの立派なサマリア人であると思い込んでいる。まさに典型的な例だ」「申し訳ないのですが」と彼女は言った。「おっしゃっている意味がよく分かりません」(P133)
そういう陰鬱な空気の中でも明るい材料はあって、隊員がリトゥーマ伍長に向かって延々と話し続けるかつての恋人のエピソードのあたりは、読んでいても悪くない心地だった。「え!!いま隊員めちゃくちゃ話してんのに伍長完全に無視!!??なのに話し続けるの!!??」みたいな喜びがあった。あと伍長が山津波に遭ったあたり、風景描写がすごくきれいだった。
それにしてもバルガス=リョサはどれ読んでも本当に面白い。技巧的なところが鼻につくし鼻白む感じもあるのだけど、まあ、ストーリーテラーっていうんでしょうけれど、すごいどんどこ読ませるなあと。リトゥーマはどうも『緑の家』とかにも登場するリョサおなじみの登場人物らしい。読んでいきたい。
アドルフォ・ビオイ=カサーレス/モレルの発明
モレルの発明 (フィクションの楽しみ)
アルゼンチン。とても面白かった。先日少し話題になっていた3D写真のもっともっと先を行ったバージョンみたいなことが孤島で行われていた件。踊っている具合がとてもいい。あとうじうじしている感じがものすごくうじうじしていていい。
あの女に会いに行った。私の計画はこうだった、――例の岩のところで彼女を待つ。彼女が来てみると、私は放心したように夕陽を見つめている。驚いた彼女は、きっといぶかしく思うが、それもやがて好奇心へと変わってゆくはずだ。私が彼女同様に夕陽に取り憑かれていることに好感を持って、私の名を訪ねる、そうやってわれわれは友だちになる……(P44)
とても美しい場面。
心の準備ができたので、同時に作動するいくつかのカメラのスイッチを入れた。七日間が記録された。われながら上手に演技した、――よほど注意深い観客でなければ、私が闖入者であるとは気がつかないだろう。一所懸命準備したのだから当然の結果だ、――この二週間というもの、絶え間なくリハーサルを繰り返し、検討に検討を重ねた。演技のひとつひとつを倦むことなく繰り返した。フォスティーヌの言う言葉、彼女の問い、答えをすべて研究した。何度もそこへ私が巧みに言葉を差し挟むので、まるでフォスティーヌが私に答えているような具合になった。いつも彼女のあとを追いかけているわけではない。彼女の動作はすべて承知しているから、ときには彼女の前を歩くようにした。全体として、ふたりが、はなれては暮せぬ仲良しで、言葉を交わさなくても心の通じ合える仲に見えることが私の希望なのである。(P172)
カルロス・フエンテス/澄みわたる大地
澄みわたる大地 (セルバンテス賞コレクション)
現代企画室のセルバンテス賞コレクションから。ほぼ同じ日にやはりセルバンテス賞コレクションからセルヒオ・ピトル『愛のパレード』も買ったので、次はこれを読みたい。
メキシコ。詩人たち。旅する聴取者による数々のインタビュー。そのあたりだけなので何も深みを持ち得ない感想なのだけどボラーニョの『野生の探偵たち』と通じる部分があった。
しんどかった。なんだか、技巧がどうのこうのという以上に、そのいかにも文学的な感じのする仰々しい文章の連なりがけっこう耐えられないものがあり、あと登場人物が漫然と読んでいると誰が誰なのかわけがわからなくなることもあり、まあ、だらだらと読みましたみたいな感じになってしまった。
ちなみに冒頭はこんな感じ。
私の名はイスカ・シエンフエゴス。生まれも育ちもメキシコ・シティ。大したことじゃない。メキシコに悲劇などない。すべてが屈辱になる。屈辱、この血が竜舌蘭の刺のように私を突き刺す。屈辱、この狂気に麻痺した私の体が、あらゆる曙を凝血の色に染める。そして明日に向かって永遠に続く死への跳躍。遊びも行動も信仰も――運のいい日も厄日も、日ごと私は自分の暗い毛穴を眺める――、谷間に広がる大地の奥底に深く葬り去られた。(P8)
……しんどい。
1950年ごろのメキシコ。上流階級が連夜のパーティーで自分たちの社会的価値を値踏みしあう感じ、落ちぶれていくもの、上昇するもの、これは何カーストっていうのかわからないけれども、そういう様子のえげつなさと、虚しさ、そのあたりは面白かった。
上野清士/ラス・カサスへの道
ラス・カサスへの道 --500年後の〈新世界〉を歩く
吉祥寺の百年で買ったやつ。すごくよかった。だいぶワクワクして前のめりになったために一日で読んでしまった。
16世紀あたりに新世界にどんどこ入植していくスペイン人たちの原住民に対する暴虐を糾弾してがんばった聖職者ラス・カサスにまつわる土地を辿りながら、21世紀のその土地土地のあれこれの状況も重ねてあれこれ書いていく紀行文。著者は14年間グァテマラやメキシコで暮らしたジャーナリストの方とのことで、現状をこれ以上ないほど肌身で知っている人。時折り、ちょっと憑依してるというか物語にしてるなーという感じは目に付くのだけど、全体的にはすごく面白い。これがもっと様々な文献であるとかを用いてアクロバティックに織り込んでいくと、きっとゼーバルトみたいなことになるんだろうけれど、もっと軽やかで、もっと気ままなスタイルだった。
いろいろといいのだけど、ラス・カサスに対する評価、回心してアンチ虐殺になるまでそこに自身も加担していたことや、いざ回心したけど実際はそんなに効果を上げられていないんじゃないかみたいな疑問とか、そういうところがフラットでとてもいいし、妻子がありながらこういうことをけろっと書いているところも「いいのか!?」という感じでとてもいい。
途中、シエンフェゴス市郊外の団地に住むという女子大生を拾った。助手席に乗せ、それとなく当世女子大生気質などを聞きだす。キューバで車を持つことの利点は、日本では考えられないがガールハントが容易であるということ。時間がかぎられているから(?)、よこしまな心は捨てないといけないが、若い女の子たちを、その気になればよりどりで拾える。(P148)
いろんな土地の小説を読んでなんとなくできてきた歴史のあれこれが、何度も地図のページを行き来しながら読む紀行文のなかでなんとなくリアリティを持っていく感じが心地よかった。
今日はルイサ・バレンスエラ『武器の交換』を読んでいる。
cinema
2013年7月25日

岡山でも今現在一日一回倉敷のシネコンにて、という上映になっているということは8月に岡山で見ようと思っても終わっている公算が大きいと判断したためヒューマントラストシネマ渋谷でウディ・アレン『ローマでアモーレ』を見てきた。
当初その邦題を見たときは、これは『恋のロンドン狂騒曲』の流れの失敗作なんだろうなと勝手に期待値を下げていたのだけど、期待値が低かろうが高かろうが見るのだけど、どうも評判がいいみたい、というのはなんとなく見る前から空気では知っていたのだけど、いざスクリーンの前に座ってしまえば、私にできることなど笑いながら泣くこと以外なにもなかった。
『人生万歳!』、『ミッドナイト・イン・パリ』に続いての、諸手を上げて快哉を叫びたくなる傑作。第二か第三なのかはわからないけれど(私にとっては1977年『アニー・ホール』から1987年『ラジオデイズ』の10年間が最も実り多き季節なので第二ということになるけど)、ここ数年のウディ・アレンは彼のキャリアにおける黄金時代に入っているのではないだろうか。それは長年のファンである私にとって、すごく幸せなことだ。
冒頭の交差点の車の流れ、交通整理の男の身ぶり、そして画面の外で起きる衝突事故。何度となく繰り返されたウディ・アレンのなんか今までもあったよねそういう感じという場面に胸が温かくなる。『アニー・ホール』のコカインだかヘロインだかわからないけど白い粉をくしゃみで吹き飛ばしてしまう場面を見ているときと気分がとても通じる。
そしてフィアンセの親からご両親とも会いたいなと言われた娘が「両親は今向かっているところです」と言った瞬間、妻と飛行機に乗る年老いたウディがたぶん飛行機が揺れるとかそういう事柄に対して過剰な恐怖心をいだいてそれを解消するために早口でまくしたてる場面が脳裏によぎり、そして実際に、飛行機の外観のショットに続いて、機内の座席を縫って進んだ先にカメラがとらえるのは怯えきったウディ・アレンの姿なのだった。彼が予想通りにまくしたて始めただけで、私はわりと胸が一杯になり、目頭から涙的な液体を落とさざるを得なくなった。
そこから先はもう、笑いを引き起こされると同時に涙があふれる、ということに終始して、その涙は、まったくもって、嬉し涙という以外に形容できない性質のものだった。
ペネロペ・クルスの突き抜けた野蛮さとか、文字通りに爆笑させられた葬儀屋のオペラ歌手とか、スィ、グラッツェしか言えない迷った新婦とか、身振りが小気味いいロベルト・ベニーニとか、夫の言動を呆れながら解釈し続ける精神科医とか、どの俳優もどのエピソードも本当によかった。
その中でもエレン・ペイジがスノッブな小悪魔を演じるエピソードはわりと異様で(ベニーニのも異様だけど)とても好ましかった。未来からとも現在からとも言える場所から現れた幽霊がエレン・ペイジの、浅薄な知識から詩行や固有名詞を一行取り出してさもよくわかる女みたいに自分を演出する様子を痛烈に批判するわけだけど、その批判っぷり以上に、幽霊を画面内に留めた状況での会話のあり様が私には面白かった。完全にそこに肉体として存在しながら、Aと話すときにはBには聞こえない、Bと話すときはAには聞こえない、AとB3者で成立する会話もある、というあの自由さ、でたらめさは、すごく健康的でいいものだと思った。
一方で、というかちょっとした懸念というか穿った見方だけれども、ウディ・アレンのだいたいの作品において今回のエレン・ペイジにあたる痛々しいスノッブって出てきていると思うのだけど(『アニー・ホール』の特に書店でアニーに教えを垂れるときのウディ・アレン当人であり、『マンハッタン』でも冒頭の煙草をふかすウディ・アレンであり美術館でいい加減なことを言うダイアン・キートンであり、『ハンナとその姉妹』で自作を朗読するダイアン・ウィーストでありそれを聞いてアメイジングとか言うやはりウディ・アレンであり)、というか多くはウディ・アレンがその痛々しいキャラを背負っている気がするけれど、いや、そんなこともないな、思い出せないけどたぶん全然ウディ以外の多くの人にもそれを負わせているはずなのだけど、知識や教養めいたものを振りかざす厚かましさみたいなものに対してすごく恥の意識みたいなものがあるように見えるし、実際見ていてもすごく恥ずかしい気分にさせられるのだけど、今回みたいにその恥ずかしさを画面上で直接的に揶揄する、もっといえばその恥ずかしさの内実を解説するものって今まであまりなかったような気がして、いや、これは懸念でもないし別にそうだとしても見ていてとても面白かったからなんでもいいのだけど、これ、その解説がなかったらその恥ずかしさみたいなものが現代の多くの観客にスルーされていたりして、とふと思っただけなんだけど、だから何ということは本当にないのだけど、いやそうだとしたらウディ・アレンは歯痒かったりするだろうなと勝手に推測するだけだし別に歯痒くもなかったりするのかなとも思うのだけど、なんかこう、そういうことをふと思った。面白さ及び必要性で幽霊が召喚されたのだろうかと。いやきっとそんなことはないのだろうけど。
まあなんにせよつまり、『ローマでアモーレ』はそこここにウディ・アレン印に満ちた極上の一作で、もう最高だよ!という気分で泣きながら映画館を出ることになった。
cinema
2013年7月25日
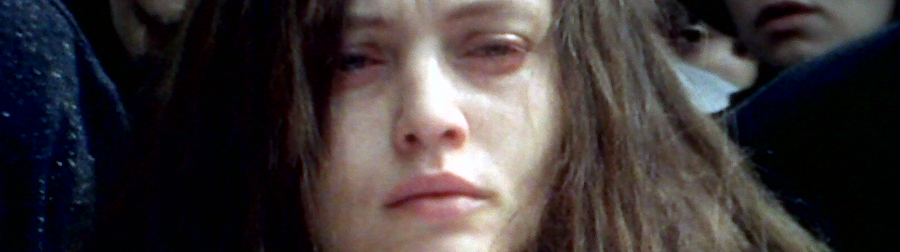
見たのはたぶん大学生のとき以来で、たしか文芸座のオールナイトでフィリップ・ガレル3本と『ポーラX』という夜があったんだと記憶しているというか記録していたはずで、最初に見た高校生のときには、「なんて退屈なんだ!死ね、フランス!」みたいな気分があったのだけどその夜に見たそれはまるで別の映画のように、いきいきと私の目を照らし、「なんて格好いいんだ!万歳、フランス!」みたいな興奮を持って見たのだった。そういう変化は、とても好ましいものだった。それからもう、たぶん7年とか8年とかが経った。バウスシアターでカラックス特集がやっていると知り、行った。同じ格好よさとして、私の目の前に現れた。
太陽の光を受けたスプリンクラーに濡れてきらめく明るい芝生の庭からぐいぐいと、閉じ切っていない二階の窓に向けてカメラが上昇していく最初のところから、映像の一つ一つがとにかく鮮烈だった。薄暗い森を歩きながら発せられるカテリーナ・ゴルベワの声。剥がれまくったマスカラのカトリーヌ・ドヌーヴを乗せて夜の田舎道を疾走するバイク。気づいたら片足は使えない視力は失われそうという状態になっていたギヨーム・ドパルデューの重々しい走り。
私はここに描かれるような世界を生きるだけの切実さを持ちあわせてはいないので起こってしまった出来事に対しては「うわ、すごいなそれ」というぐらいしかないのだけれども、まあなんせ格好いい。それはとても大切なことだった。
冒頭の、世界の箍が外れてしまった、それを直すために生まれるとは損な役回りですな、みたいなナレーションのあとの、都市を破壊する爆撃の様子とともに流されるやたらに勇ましくどえらい感じの音楽からしてそうだったのだけど、コミューンのノイズオーケストラの様子に限らず、この映画に流れる音がひたすらに格好良くて、バウスだからというわけではないけれどもこれは爆音上映で見たら凄まじいのだろうなと思いながら、音がとにかく、とてもいい。
ちょっと落ちぶれぐらいのタイミングでいとこの援助を求めて訪ねるパーティー会場(いま思い出したのだとヴァレリー・ドンゼッリの『わたしたちの宣戦布告』でもあったけれども、こういうやたら広いマンションの一室を使ってやたら楽しくパーティーしますみたいなやつって、音量とかの問題は大丈夫なんだろうか、今日はパーティーなのね、という近隣の暗黙の了解と許容があるのだろうか、すごい防音壁なんだろうか、それとも勝手にマンションだと思い込んでいたものはクラブだったりするのだろうか)のシーンで流されるかなりヘビーなドローンとか、パーティー中だからその轟音かと一瞬思うのだけどあんな音が流れているわけがなくて、もうただ、ドゥオーンってやりたいんだなっていうカラックスの暗い意志みたいなものが横溢していてとてもいい。
エンドクレジットで、音楽:Scott Walkerとあって、ああ、そりゃあ、という気になった。去年買った『Bish Bosch』が、私にはまったく理解不能というか、理解とか使いたくないのだけど、どのように音に身を委ねたらいいのか不明というか、まあとにかく、激しい異物感の塊みたいなアルバムで、この人の音楽のゴツゴツとした、それこそ血の急流を下るような強靭な突飛さ、凹凸みたいなものは、『ポーラX』とものすごく親和性が高いのだろうなと納得した。その影響で2日ぐらい続けてスコット・ウォーカーを聞いている。やっぱりわけわからない。
『ホーリー・モーターズ』も見ようかなとも思ったのだけど、岡山で9月ぐらいにはやるみたいなので、そちらに譲ることにした。
book cinema text
2013年7月25日

とにかくビールを飲もう。そんなふうにして相変わらず過ごしている。コーヒーよりもビール、そんな生活を送っている。昨日もオーディトリウム渋谷に「はじめての小川紳介」特集の土本典昭『パルチザン前史』を見に行って、ついてから時間が余ったので下のカフェで茶でもしばこうかと思ったら気づいたらレーベンブロイを頼んでおり、ビール飲んでから映画とか眠くならないといいけれども、と懸念していたら懸念通りに眠くなり途中ウトウトとしてしまった。上質な映画体験よりも、アルコールを摂取することが優先されるらしい。
小川紳介の特集だからと、『パルチザン前史』も小川さんが監督だと思っていて、見る前に「これから小川紳介『パルチザン前史』を見る」みたいなことをツイートして、そのあとに小川さんでなかったことが発覚し、「小川さんでなく土方さんだった」と私はツイートして、たぶん私は土本典昭という人と舞踏家の土方巽を混同しているというか、どちらも、字面では見たことあるけど発音したことないし作品にも触れたことない、ということでまあ、何一つ自分の中にリアリティのある記憶として持っていなかったのだろうということが顕になった格好だった。そもそもそんな「見ます」みたいな「なう」みたいなツイートする必要があるのか、みたいなところは問われるべき問いだろうけど、最終日とはいえ夜の回もあったし、私がそれをツイートすることで何か効果が生まれるとも思わないけれども、万が一にも私のツイートを見て「あ、やってたんだ、夜もあるんだ、行ってみよう」みたいな人がいたとしたら、それは社会的に意味と価値のあることかなみたいな意識がそう強いわけでもないにしてもある感じがするということでそういうおこないをしている面というのはあるからそれに免じて自らのおこないを許したいと、そのように思うというようなことはそうあるわけでもなく日々自己嫌悪と自己憐憫を繰り返す。自己陶酔もあるのでは?と誰かは言うかもしれないけれどもその通りなのかそうでないのかは私が判断するには難しすぎるような気がするというか自己陶酔は避けたい香りがあるということかもしれなかった。
『ポーラX』のピエールが書いている小説なんて本当に自己陶酔まみれみたいな感じがするというか丘のうえに卵みたいな岩があった、僕はそれを恐怖岩と名付けた、なぜならその岩の隙間には狂気が入り込む余地がなかったからみたいな。なんなんだよそれは!!!うるせーよ!!!!!と言いたくなった。
その『ポーラX』を見に吉祥寺に行ったついでに、何で知ったのか覚えていないのだけど百年という本屋さんに寄った。ものすごく好みな書店で、A)作者に還元されない B)読み終えてカバーを外して本棚に収めるまでが私にとって読書という行為であるためブックカバーをつけてもらえないことがものすごい大きな障壁となる C)それ故か買っても読みきることがまずない という理由からほとんど古書というものは買わないのだけど、それにも関わらず6冊も買ってしまって、1冊はすでに読み終えたし、2冊目も今日読み終えそうという順当な、そして私にとっては極めて珍しい消化のされ方をしている。
買った本は以下。
上野清士『ラス・カサスへの道 –500年後の〈新世界〉を歩く』、ルイサ・バレンスエラ『武器の交換』、ホセ・マリア・アルゲダス『深い川』、フアン・ルルフォ『燃える平原』、フリオ・コルタサル『かくも激しく甘きニカラグア』、マリオ・バルガス=リョサ『緑の家』(1981年新潮社刊の単行本)
バレンスエラとアルゲダスは名前すら知らない人だったので、いい出会いだった。この二冊はともに現代企画室のラテンアメリカ文学選集という1990年から始まった企画のもので、セルバンテス賞コレクションもそうだし、ラテンアメリカ小説を読もうとすると本当にすぐに現代企画室の名にぶつかる。楽しい。
『パルチザン前史』は私が学生運動についてまったく理解がないためか、全体としては「なんだかわからないけどがんばっている人たちがいたんだなあ。町が燃えてる!燃えてる!」みたいな感じというか、途中は眠ってしまったぐらいなのだからそう面白く見れたわけではなくて、京都大学前とかの大通りでの学生と機動隊の攻防の、火炎瓶投げ込んで本当に燃え盛っているあの感じ、投石して投石して踵返して走りだすあの感じを見ていたら、フィリップ・ガレルの『恋人たちの失われた革命』とか、ベルトルッチの『ドリーマーズ』とか、ああいうフランスの映画で見ていた光景に似ているなあ、というか日本でもこんな感じになっていたのかあ、みたいな照合作業がされて終わっちゃう感じもあって、いや、攻防戦(この言い方すらわからない)のあの様子はすごい格好良かった。
でもそれよりも、滝田修の予備校での授業風景(ものすごくいい)とか、自宅でローザ・ルクセンブルクの写真を並べながら好きな一節を読み上げるところとか、あるいは議論中の若者たちのくだけた関西弁の響き(一人すごく端正な顔立ちをしてすごくいい笑顔をしてすごく柔らかい関西弁を話していた)とか、そういうところがよかった。顔が見えてくると面白がれる、というタイプなのだろうか私は。
今日は映画が終わって埼玉に戻って必要な買い物をして立ち飲み屋でビールを2杯飲んで家に帰った。完全に休み飽きてきた。毎日疲れるし虚しい。私は基本的にうまく生きることができないタイプというかメンタリティじゃなくてエネルギーじゃなくて、体力、何かそれに該当する単語があったはずなのだけどあ、やっと出てきた、バイタリティ。継続的に生きていく上で必要なバイタリティみたいなものがないんだろうなと、それを実感する。実感する。今なんとか生きていられているのも、親であったりという存在に庇護されてるからであって、自分一人じゃ立つことすらできないんだよなと、それを実感する。痛感する。
cinema text
2013年7月22日

カレンダーをあまり見ていないこともあって今が月のどのあたりに位置するのか曖昧な認識のままに日々を送ってはいるとは言えできるだけビールを飲むようにしている。出来る限り早い時間から飲めるだけ、飲むようにしている。そういうこともあって今が月のどのあたりなのかは、わからないままになっている。
それでも今日が選挙の日であったことは把握していたこともあり、夕飯を一家四人で取るという催しが開かれて夜に家にいたこともあり、テレビ東京の選挙特番を見ることはおこなって、池上彰の選挙特番はどれだけ面白いのかと期待をしていたのだけれども思ったよりは面白くなかったこともあり、こういう番組は選挙前にあった方がいいんだろうなという思いを強くしたわけだったし、そうは言っても家にあるテレビはアンテナに繋がっていないので見れない身分なのだけど、ツイッターで人々はどんなふうにリアクションしているのかなと、そういうのを見ながらテレビを見るという現代的なテレビ鑑賞をおこなった。そこでわかったことは面白ツイートみたいなものをわりと丸パクリして自分のツイートとして投稿する人というのが本当にいるんだなということで、短いツイッター閲覧の時間のあいだで複数のそれらしいツイートを目撃することになった。そういうおこないは私刑に掛けられたりはしないのだろうかと、人ごとながら心配をした。
この一週間、一週間なのか、10日ぐらい経っているのか、そのあたりもいまいちわかっていないのだけれども、埼玉の家で過ごしているなかで、私は本当に特別やることが見当たらない。やることが見当たらないというか、やることが見当たらなくなった瞬間にとんでもない空虚さに一気に見舞われる。いくらか友人と会って飲んだりをしてはいるけれどそうでない日はなんとなく東京に出て映画を見て、そのまま帰って、ということをするぐらいで、あとはぼーっとインターネットを徘徊したり、本を読んだり、ベランダに出て煙草を吸ったり、ビールを飲んだり、それぐらいしかない。そのため日夜、むなしさと孤独感が強まっていくような心地がある(バカンス慣れしていないため)。今日などは、休みに入ってからiPhoneのテザリング機能でパソコンを使っていることが祟り、通信料が6GB超えましたよ、7GB超過で通信速度制限ですよ、という警告のメッセージを受け取ることになってしまった。きっと今日明日にでも超過するのだろう。インターネットを剥奪された私は、いったいどのようにこの生を生きたらいいのか。
ある日の昼ごろ、通夜に出るため会社を一日休んだ父親と私が居間で鉢合わせ、私は残っていたご飯を納豆で食べ、食べ終わったぐらいで父親が買ってきたパンを一人で食べる、という状況があった。母親はもう10年レベルで続けているパートに出ていた。
27の息子と60を越した父がいて、母がパートのため不在の平日正午の居間、なんとまあ、それはなんというかなんとまあという光景だった。別段、二人ともにやましさがあるわけでもないけれども、それは一つの可能性の提示として、なんとまあという光景として体感された。
一つの可能性を可能性として勝手に感じることと、それを言表することのあいだには大きな違いがある。『親密さ』で言えば別れ話の喫茶店の席で「今何考えてんの?」と問われた女が「このコップの水をあなたに掛けたらどうなるのだろうかと考えていた」と答える場面、今考えていることは何かと問われて今ちょうどたまたま考えていた一つの可能性というかそのシチュエーションによって紋切り型的に想起されていた一つの可能性を答えることは、女にとってみれば質問への返答として妥当な行為であったわけだけど、それを不意に聞かされた男はその考えを不愉快で不穏当で不適切なものだと感じてしまう。その瞬間でなければ、女の答えはもしかしたら「コーヒーこぼしたわけじゃないのにソーサーが濡れてるけど特に気にはしない」とかにもなりえたわけだけど、相手に与える印象はそう変わらないだろう。この別れ話という場面においてその答えは不適切、不謹慎、と。だから、ふわふわといくらでも分散される考え=意識などは質問すべきことでは多分なくて、男が求めていたようなことを聞きたかったのならば「今のこの状況と流れを踏まえて自身の責任において発言するならばそれはどういった発言になるとお考えですか」と尋ねるべきだろう。しかしそう考えるのは、正しいけれど間違っていることなのかもしれない(そもそも正しくもないかもしれないけど)。
昼前に起きて簡単にご飯を食べて、東京に出る。映画館に行く。映画館を出る。茶をしばくこともなく、埼玉に帰る。夕飯を食べる。友人と飲む日以外は、そういう暮らしを暮らしている。母と二人でカフェに行ったこともあった。連れられて行ったその店は意想外にとてもいいところだった。母とカフェに行った日は、昼前に起きて簡単にご飯を食べる、母とカフェに行って茶をしばく、駅まで送ってもらって東京に出る、ひげも切ってくださいと言ったら追加で800円取られながら髪を切る、友人と飲む、という一日だった。その日は映画を見なかったが、人と話すことは素晴らしいことだった。
日々東京におもむいて見た映画は今のところ次の通り。
ホン・サンス『3人のアンヌ』、ニコラス・レイ『We Can’t Go Home Again』、ハーモニー・コリン『スプリング・ブレイカーズ』、ミゲル・ゴメス『熱波』、ミゲル・ゴメス『自分に見合った顔』、アントニオ・レイス/マルガリーダ・コルデイロ
『トラス・オス・モンテス』、ロバート・アルトマン『ナッシュビル』、ベルナルド・ベルトルッチ『孤独な天使たち』
何が楽しいと言えば、それら8つの映画を見るために7つの映画館に行っているということが楽しい。それだけ選択肢があるということに対して地方に住む身としては羨望するかといえば特別そういうものはなくて、ただ単に、その動きが懐かしい。そうそう、そうだったよねと。かつて体に馴染んでいたあの感覚が蘇る。そうそう、これだった。
大学時代からの友人と五反田で飲んだ。五反田のあとで流れて行った野毛ではそうでもなかったのだけど、五反田で飲んでいた4時間とかのあいだは、話しながら驚きを覚えるほどに映画の話以外していなかった。
その友人がまだ見る機会を作れていないことなどまるでお構いなしに、店が賑やかだったことも相まって極めて声高に、私は京都で見た濱口竜介の諸作についてまくし立てていた(いや、もう超ほんと、だからもう、悪いけど超やばいから、という塩梅に)。
東北の3部作は思い返してみても本当にすごく素晴らしいものだったのだけど、それと同時にやっぱり不思議で、いったいどうしてそうなったというのが全然わからなくて、なんだかわからないけれどもすごいことであるなあと感心というか驚愕するばかりなのだけど、当初は、この素晴らしいいくつもの顔の現れの感じというのは、印象に全然残らなかったり退屈だったりした対話を考えると逆説的にわかるのではないかと思っていた。監督二人が聞き手を務める回というのが大体においてその退屈だった回で、なんでだろうと考えてみると、それはその時間を通して話し手/聞き手という役割分担がなされてしまっていることも作用して、こちらの記事で言うところの「語り」ではなく「証言」に近いものになってしまっているからだじゃないのかと。その時の聞き手の顔が、「通じてる顔」ではなく、「しゃべる顔」を跳ね返してしまう「見る顔」になっているからじゃないのかと。見ていて「うわー」という思いを私に与えてきた対話はことごとくに、対話者二人の関係性が画面から横溢するような感じで、そこでおこなわれるのはどこまでも語り合いで、どこまでも通じ合いで、二人の親密さがカメラという異物感を乗り越えたことによって、無防備で開かれた顔や言葉が立ち現れたのではないかと、そういうふうに思っていたのだけど、あの真正面の切り返しショットを撮るにあたりカメラがどのように置かれていたのかを聞いてしまったあとでは、ただただ、「不思議で、いったいどうしてそうなったというのが全然わからなくて、なんだかわからないけれどもすごいことであるなあと感心というか驚愕するばかり」だ。というその驚愕の部分は、飲みながら友人に伝える段階では「ていうことをしていてそういうことが起きてるっていうさ、えー!?なんでー!?っていうさ、やばくないこれ!?」みたいな感じに変換されている。
ところで、監督たちが聞き手の回がわりと退屈と先ほど書いたのだけど、ただ、濱口監督が聞き手の二つ、図書館員の方と、亡くした友人のことを話す方の回は、他の対話での「なんという親密さ!」みたいな面白さとはまた別種の面白さがあって、その面白さはけっこう、えげつなさというのと同義だったし、それはそれで、なんというか「うわー」というものだった。
なんというか、そういうことを飲みながら延々と話し続けていたのだけれども、これは前回の日記でも書いた気がするけど、これだけ何度も蒸し返したい、人に話したい、人の話を聞きたい、と欲望させられることは私にはそうない経験なので、なんというか、これはそうそうないことであるなと、人に会って話すたびに実感している。
その夜はその友人の家の近所の野毛で朝方まで飲み、白み始める空は見えない部屋で眠った。そのマンションの部屋は、最近友人が購入したものだった。同い年の友だちが分譲マンションを買うのかと、投資目的とかいろいろあるらしいけれども、マンションなんていう桁違いの買い物をするのかと、それはけっこう、考えれば考えるほど「すごいなあ」という気分になる。
翌日、ジャック&ベティに初めて行き、『孤独な天使たち』を見た。予告された滂沱の記録。ベルトルッチ前作の『ドリーマーズ』で3人組が一番新鮮な光を受けるためにシネマテーク・フランセーズの最前列に座るみたいなことがあったような記憶が蘇ったこともあり、再見の余裕みたいなものもあり、最前列に座って見た。最初は最前列きついかなと思いながら見始めたがそんなことは問題ではなくなった。
水の中で息を止めるロレンツォの背中。14歳の少年のやわらかそうな肩甲骨周辺の隆起、全体を覆う金色の産毛。なんとまあ、素晴らしいことか。オリヴィアは相変わらず、一挙手一投足が素晴らしかった。デヴィッド・ボウイ、親密さ、親密さ、親密さ…
カルロス・フエンテスの『澄みわたる大地』を今は読んでいる。いくらか、ボラーニョの『野生の探偵たち』と通じるところがあって、そこが面白いからというわけではないけれども、漫然と読み進めている。夢は終身雇用ですと言う人がいたからいい冗談だと私たちはゲラゲラ笑ったけれども夢は詩人になることです、革命戦士になることです、そう言うのを聞いてもお前らはやっぱり高らかに笑うのか?
駅からの帰り道、ピーター・ブロデリックの「Hello To Nils」を聞きながら歌っていたら涙がこみ上げてきた。どうせならば大声で泣いてしまいたかった。それもこれもあと少しで7GBを超過するせいであると言い切ってしまえばお前らはここぞとばかりに笑うのか?俺が明日は『ポーラX』を見て惨めさここに極まれりみたいな状態を目指したいですと言えばお前らは腹を抱えて笑うのか?
仕方がないので冷蔵庫に一本だけあったロング缶を開けた。ろくでもない言葉を発するぐらいなら酔っ払ってゲロを吐いた方がこの口の使い方として正当であるため。
text
2013年7月16日

京都の旅行でけっきょく疲れてしまうわけだったし、旅行向きの人間ではないこともあって、京都から東京に一気に出て、そこで2つの映画を見たのが週末、金曜日のことだったらしかった。ホン・サンスの『3人のアンヌ』とニコラス・レイの『We Can’t Go Home Again』で、イザベル・ユペールのシューとか言いながら風を起こすみたいな格好をするあの感じであるとか、海に向かいながら焼酎を何本も飲んじゃう感じであるとか、セ・ブー、セ・ブーの歌う具合であるとか、牛の鳴きマネをしてみせるあの感じであるとか、年齢不詳のチャーミングさを画面いっぱいに湛えていて、それは見ていて、すこぶる心地のよい時間だった。フランス人と韓国人が母語ではない言語で交わすやり取りの、それだけで生まれるサスペンスみたいなものに終始魅せられながら、シネマート新宿の画面はなんと小さいのだろうかと、当初覚えたそんな気持ちはすっかり忘れて、それはとても充実した時間だった。
一方でニコラス・レイは、ホン・サンスが4人ほどの鑑賞だったのとは反対に7,8割が埋まる座席の中で見たニコラス・レイは、思いのほかにしんどい時間になってしまい、途中から体が気持ち悪いいつもの症候群に襲われたこともあり、まだ続くのか、まだ続くのか、という時間になってしまい、マルチ画面で映されるいくつもの画像についていくことなど、そもそもついていくことなど想定されていないのだろうけれども、ついていくことなどできないし、ついていきたいような気にもなれず、実験映画ということに拘りを持つ必要はないだろうしこの作品をそういう括りにしていいのかわからないにしても、つい数日前に見ていた牧野貴や、世界の実験映画の先端のようなものに触れたあとにあって、この眼の前で行われていることはそんなに刺激的なものなのだろうかと、わからず、いつだって人間は、その時々に抱えるバイアスに左右されるものなのだろう。
そのあとに、田舎に帰った。長い電車の旅の果てに、週末をただただ穏やかに過ごそうとしたのだった。あとになってみればフリードミューンがあったのか等、後悔めいたものはあるにしても、ここはやはり休息が必要だったらしかった。
実際、私は田舎のその家で、眠ってばかりいた。初日は夕方に一寝入りして、早い夕飯を食べたあと、10時にもならないうちに眠りに落ちたのだったし、2日目など、早い夕飯を食べたあとに8時にもならないうちに眠りに落ち、そのまま11時間ほども執拗に眠り続けたのだった。あとはずっと本を読んでいた。バルガス=リョサの『アンデスのリトゥーマ』で、以前読んだ短編「ある虐殺の真相」の舞台をそのままにしたような、アンデスの山間部でおこなわれる様々のむごたらしい死を描いている。人々は、のべつ幕なしに語り続ける。自身の物語を語ることだけが、センデロ・ルミノソやその手先たちに襲撃される時間を先延ばしにする方策であるかのように、人々は語り続ける。バルガス=リョサはどれを読んでも、興が乗ってしまったらあとは勝手に進むジェットコースターみたいに、ものすごいドライブを掛けて私の目を進ませる。要は、まあとんでもなく面白い、ということらしかった。
それは初日の光景だった。父親は私を駅まで迎えに来た。そのあとの昼時に、母親は昼飯の素麺を食べるためのめんつゆを買いに出、昼食後には二人で家電屋に行って洗濯機を買った。そして夕方に母は夕飯の食材である肉を買いに出かけ、その間に父親は何かの用を足しにカーディーラーにおもむいた。そして父は戻ってきてから、ビールを買いにまたどこかに出、さらに今度は二人で胡椒や納豆を買いに行こうなどと言って出て行った。都合何度、この人たちは買い物に出かけるのだろう、何度、この人たちは車を出すのだろうかと私は本を読んだりうつらうつらしながらその様子を目撃し続けたのだった。退職後に住むことが決められており、当初住んでいた祖母がとっくに亡くなっているために今は無人であるためほとんどセカンドハウス的に使われている田舎のその家での週末の過ごし方は、間断のないショッピングにおいて充足されるのだろうか。
田舎の家の近所の風景は、ずっとほとんど変わらずに私の前に現れていた。
死にたくないなと考えていた。最近はいつだって体調が万全ではないような気がして、リョサの簡単に死んでいく人たちを見るにつけなのか、ガルシア=マルケスが描き出したコロンビアのある時代の状況(一つの町で2月のあいだに2000人が殺されたとか)を見るにつけなのか、なんとなく、死というものを考えることが多く、まだ全然死にたくないな、死んでも死に切れない場所でまだ生きているな、と思っていた。なんとなく、健康診断を受けたい(何か致命的に健康を損ねているわけではなく、ちょっと胃が痛くなったり、ちょっと前立腺がおかしいぞとか思ったりするたびにこれが癌だったらどうしようと思って強い不安に陥るだけで、まるで「これはまずいんじゃないか」みたいな症状があるわけではない。誰に向けてかはわからないけれども念のため)。
田舎滞在二日目に、私は近くで、といっても車で30分40分だったが、近くで行ってみたいカフェがあったのでそこになぜか母と伯母と出かけ(そのあいだ父は車で30分40分のアウトレットに何かを買いに行っていた)、そこは食べログを見たところものすごい人気を誇るカフェであり、駐車場もやたらに広く、店もやっぱり広かった。気持ちのいい緑に囲まれたその店のテラス席で私たちは時間を過ごした。
そこではいくつかの、先日も書いた、一定以上の広さを持つカフェが知性や品性を持つにはどうしたら、ということの処方箋になるような状況が見られ、私は気がついたところをメモしながら、なるほど、こういう形が、形というかあり方があるのかと、嬉しいような気分になった。
そこがとてもいい場所だと思えたため、その午後に父親の腰痛か足の関節痛の湯治という名目でやはり車で30分40分の場所にある温泉に行って、私もしばらく浸かったあとに先に一人で出、そのカフェの本店という場所にやはり30分ほどを掛けて行った。そこではウェイティングが4組ぐらいあり、私も名前を書いて待っていたのだけど、湯治の父との待ち合わせの時間が迫ってきたこともあり、諦めてドリンクをテイクアウトだけして帰ることになってしまった。それでも、そこで見られたいくつかのスタッフの対応は心のあるもので、心とか、アホらしくて使いたくない言葉ではあるのだけど、やはり心としか言いようのない、悪くない気分にさせてくれる空気があった。けっきょく入れなかったにも関わらず、私はまったく嫌な心地をせずに帰ることができたのだった。ネガティブなところから反面的に学ぶことも、最低限のクオリティの醸成という面では重要だけれども、やはり、どうせなら、これは学びたいですな、というポジティブな学び方を私だってしたいわけで、その店は何か、そういうものを見せてくれたような気がした。
それにしても驚いたのは、その本店がある場所は駅からたぶん歩いたら10分15分程度の場所ではあるけれども、まったく過疎っている土地で、鄙びた、という描写以外に受け付けないような雰囲気になっている。それにも関わらず、そのカフェをたぶん完全に起点にして、本当に狭い範囲にいくつかの古着屋やバーや、何かそういった若者スポットめいたものが連なっている。一つのカフェが町の文化のはじまりとなるその光景は、「すごいなー」というものだった。ただ一方で疑問もあって、あそこで働いて、あの場所で薫陶を受けた人間は、そのあとどういうキャリアを踏むのだろうか、ということだ。わかりやすい出口は独立しかなくて、独立を果たせない場合、その若者たちを受け入れる経済は、恐らくあの土地にはない。総じて、がんばれ若者、よいしょ、よいしょ、というところだった。
だけど本当に、どん詰まったかに見える地方の本当に地方の場所で、ああいう空間が存在し、多くの人に支持され続けているということは、きっとすごいことだった。端的に言って感動しました。
帰りの車でもたくさん眠り、私は実家に帰ってきた。
幼馴染と言っていい友人たちと飲みに出た。気のおけない、というのはこういうことだろうなといつだってそれは実感できる時間になった。随所で私は『親密さ』の話を出しながら、そこを起点に話や質問をおこなった。こういうことが起きるということは、『親密さ』はやはり、というかもはや、一つの映画という枠を軽々と越えて、人生や生き方を考えるうえでの一つの教材となっているらしかった。それはフェアな言い方ではないかもしれなくて、映画という枠を小さいものに貶める気はないのだけど、いずれにせよ、私にとってはあまりにアクチュアルな様々だったのだろう。強さとはどういったたぐいのもので、それはどう用いられるべきなのか、信頼とはなんなのか、他者をありのままを受け入れてみることとは何か、書き言葉的な硬さを帯びる言葉が強固なリアリティを獲得するのは映画に限った話ではなく、私たちの対話においてもまた、書き言葉的なものが求められているのではないか、それこそが実は円滑というか、いや、円滑とは程遠い、ギシギシとした、絶えず摩擦を意識させるような、芯のあるコミュニケーションをもたらすのではないか、それを軽視し抑圧しようとするこの空気にいかに対抗するべきなのか、対抗の端緒は、規則が設けられたゲーム的な状況を作ることなのではないか、それは東北の三部作で前面に出ているものであり、『親密さ』のいくつもの箇所で、あるいは『PASSION』でもえげつない形で採用されているもので、あのえげつなさ、面と向かわせられる緊迫、それこそが、いま私たちに必要なことなのではないか。親密さとは、その絶え間ない、やたらに暴力的で気まずい、多くの負荷を与えられた状況を通して初めて、生まれうるものなのではないか。そうやって生成されるからこそ、その親密さは大切で、代えがたいものになるのではないか。
前を向く。私は今、少しだけ前を向く。
text
2013年7月12日

長い夏休みを作ったので京都に行ったのでその日記というか走り書き。日記とはそもそも走り書きみたいなものかもしれないけれど。
主な用事は濱口竜介の映画を見ることと牧野貴の映画を見ることだった。結果としては、映画を見ることと同じくらい、京都のよしとされるカフェに行ってみることに時間と労力が費やされた。カフェの名はすべて伏せた。なんとなく、そうしたかった。
写真は唯一の観光的な事柄となった下鴨神社の参道。この時期、京都では祇園祭というものが催されていたらしかったが、それは3晩目ぐらいまで知ることもなく、けっきょく行くこともなかった。
0708
9時頃起床。21日に閉店するためこれが最後の機会だとマチスタ納めに向かうも、月曜定休を忘れており果たせず。スターバックスでコーヒーを飲む。家に帰り荷物をまとめ、二人で駅まで歩く、20分。寄った好日山荘で、格好良かったのでパタゴニアのリュックを買う。駅の中のうどん屋で荷物を入れ替え、その途中で今読んでいたカサーレスの『パウリーナの思い出に』と間違えて『カフカと映画』を持ってきてしまったことに気が付き、歩いて家まで戻る。往復40分、汗だくになりながら歩く。
駅で彼女と別れ、岡山から京都まで新幹線。到着後、友人に教えてもらったゲストハウスに連絡し、そこにひとまず向かいチェックインをする。そこから立誠小学校に向かう前に本屋に寄りたいと思い、四条烏丸の方に出るも、本屋がどこかわからず、そして上映の時間が迫ってきていたため本屋は諦めて小学校に向かう。早歩きで、やはり汗だくになりながら向かう。上映ギリギリで間に合い、濱口竜介『親密さ』を、念願のそれを、見る。
節々に親密であり、苛烈である関係が捉えられ続け、私は、何にそう戸惑っているのか、焚きつけられているのかわからないまま、多くの涙を流す。汗が乾き、寒い。休憩の時間にTシャツを脱ぎ、裸の上に長袖のシャツ(着いた時には汗でびっしょりだったが、よく吹く冷風のおかげで2時間のうちに乾いていた)を着るというセクシーなスタイルを導入し、上映を乗り切る。空調が効きすぎていた。緊張感が張り詰めていた。私はその一言で、これからも生きていけるような気がします。洪水のような言葉を浴びながら、何が大切なのか、何がそうではないのか、私には何もわからず、電車がふた手に分かれていく瞬間に立ち現れる親密さを、どう捉えたらいいのか。強く、マッチョであることとはなんなのか。強さは人を傷つける。それは、岡田利規が『現在地』で描いたこととも通じ合っていた。受精。私とスクリーンのあいだに、いったいどんな親密な、intimateな関係が結ばれたのか。呆然としながら、私は映画館を出た。
そこからぐっと上がり、ジャポニカにて、牧野貴『The Intimate Stars』を目撃した。親密な、もっと言えば肉体関係のある星たち、というタイトルだった。素敵なカフェで、それはおこなわれた。その作品は、先の岡山での上映においても私の中でもっとも何かアクチュアルな作品だった。雲かと思っていたものが実は波しぶきであり、つまり波しぶきは雲であった。空中ブランコは、いつだって落下傘部隊のように座る人を落下させた。観覧車は、明滅する宇宙ステーションでしかなかった。イメージの奔流のなかで、ぼんやりと、色々を見過しながら、つかみながら、その時間は、夢のごとく過ぎていった。終映後、そこにいた人々と話した。相変わらず、知らない人とどういった関係を結んだらいいのか、何を話したらいいのか、私はわからなかった。ビールを飲むことにした。
歩いてゲストハウスに帰った。BGMはアンチコンで活躍していたsoleの最近の作品だった。まったく耳に入らなかった。ゲストハウスにおいても、私はどう振る舞ったらいいのかわからなかった。一人、煙草をのみ、そのあとに眠った。寝苦しかった。
0709
早い時間から目が覚め、もう少し寝よう、もう少し寝ようと粘りながらも、どこかのタイミングで諦めて起きた。他者がその場に介在することで、私は多分、リラックスとは別の睡眠を取ることになった。そう思いながら、2泊延長の手続きをした。
四条河原町からのバスに乗り、それは5系統だった。一乗寺の方に向かい、運転手の指示に従って一乗寺のあたりで降りた。iPhoneが朝のあるときから「simなし」の表示に固定されてしまい、難儀した。ここ数日ずっと起きていた現象だったが、再起動すれば治った。それが今日は一向に治らなかった。それはとても不便なことでありながら、一筋の快適さ、世界と接続されていない安心感を私にもたらした。恵文社は、以前行ったときには体調が悪くなったせいもあり、何も面白くない、と思っていたのだけど、今回はなぜかとても行きたく、行ってみたが、やはりそう刺激的なこともなかった。といっても、私の判断基準は結局、現代企画室だったかどこだったか忘れたが、ラテンアメリカ文学のコーナーにセルバンテス賞コレクションのものが置いていなかったからというだけであり、とても偏ったものだった。結局、そういう確たる欲しい本がある人はAmazonなりで買えばいいのであって、個性的な書店に行くことは不意の出会いのためだと、頭ではわかっているのだけど、なんだ、セルバンテス賞コレクション、ないじゃん、という短絡。
その中でも、ソンタグの『他者の苦痛へのまなざし』、バルガス=リョサ『アンデスのリトゥーマ』、ガルシア=マルケス『誘拐の知らせ』、そういったものを買った。それらは不意の出会いであり、満足な買い物だった。買ったあとに、店の人に勧められたカフェに行き、飯を食らった。美味かった。食べていると汗が噴出して、当初ホットコーヒーを頼んでいたところを、アイスコーヒーに変えてもらった。恐縮だった。
前日に人に勧められた萩書房は、前は通ったが、まだやっておらず、恵文社のあとに行こうかとも思ったが、これ以上本を買っても仕方がないのでやめた。そう言いながら、飯のあとに再び恵文社に行き、京都のカフェの本を2冊買った。それをレジに持っていくことは、恥ずべきことだった。ただ、映画以外に予定もないことだし、職業柄、いいとされているカフェを体験してみよう、ということだった。
再びバスで、四条河原町まで行った。迷いながらたどり着いたカフェでコーヒーを飲んだ。美味しかった。素敵な場所だった。店の方と常連らしき男性客がガルシア=マルケスと莫言の話をしていた。私は『パウリーナの思い出に』を読み終えたため、ソンタグとガルシア=マルケスを読んだ。
そこからは程近い、立誠小学校に再び行った。酒井耕/濱口竜介の『うたうひと』を見た。うたわれ続ける民話に最後の方はやや飽きを感じながら、随所で、なんだかすごい瞬間を目撃しているような感覚に陥った。語ること、真摯に聞くこと。すごい関係が、そこで結ばれていた。朗々と歌われる民話は、まさに歌以外なにものでもなかった。いくつもの、ハッとする、美しい顔の瞬間。
それは『親密さ』でもまったく同様で、パッと見たところそう印象的でもない女の顔が、まさにきらめき輝く瞬間をいくつも捉えている。冒頭の電車に乗り込んだ直後の、恋人の顔を見上げる表情。いくつものあまりに輝かしい瞬間。フィクションは俳優をめぐるドキュメンタリーであると、ジャン=ピエール・レオーを見るにつけ、大学時代から私は何かモットーのように掲げていたのだけれども、それが、この映画のなかにもずっとあった。苦り切った顔、怒った顔、よろこぶ顔、すべてが、俳優をめぐるドキュメントだった。それが映画内演劇の中で重なり、印象がぶれる時、私たちはいったいどの顔を信じたらいいのか。目の前のその顔を信じるしかなかった。演じること、その、とてつもない力。
時間的な逼迫と金銭的な余裕からタクシーで同志社大学寒梅館に向かい、早歩きでホールに向かった。小学校から大学へ、妙な流れだった。そのことには後で気がついた。
地下のホールに下りると、すらっとした女学生たちがすっと立ち、来る客、来る客に頭を下げていた。不思議で過剰な光景だった。
そこで[+]上映会と呼ばれる、何人もの実験映画作家の作品を目撃した。目眩のするような時間だった。牧野貴の『2012』は、先日見たときにはただ純粋に光の乱舞として私の目に映っていたのだけれども、今日はいくつものイメージが見えた。市民マラソンのような千人単位の人々の群れがぐるぐると、ロータリーを回るタクシーのように反時計回りで走っていた。牛か馬が、猛っていた。そういったイメージがどんどんと頭の中に生成された。そういったイメージを、頭は受精した。抽象的なものにあたった時、私たちはつい具象のきっかけをつかみたがって、それがつかめたら安心できる、ということがあるように思われ、牧野貴の映画に対して、これが見えた、あれが見えた、ということは果たして正当なのだろうかといったん考えていたが、作家本人が言うように、見る人各人の頭の中で異なるイメージが立ち上がることが大切ということであり、私が抵抗を覚えるのはたぶん、だから、「あれこれが映っていたよね」という正解を求める思想であり態度であり、そうでなく、ただ私は、そして今回は、これを目撃した、という、その表明である限り、それは暴力につながらない、ということだと思った。
上映後、友人と二人で大学の中を少し探検した。あとでわかったことだがそれは法科大学院の建物だった。リュックを背負った男が二人、のったりのったりと校舎の中を歩いていると、視界がふいに『エレファント』めいたものに変わり、私たちはこれから銃を取り出して乱射するのだと知った。大学という場所は、私にとっては極めて美しく感傷的な場所だった。友人は、そういった私の発言に驚いていた。
そのあと、今回の関西ツアーの打ち上げというところに参加した。知らない人たちの中に入ることに対して強い抵抗、逃げたいというような気持ちすらあったが、参加してみたところ、隣に座った方と話をさせてもらえて、それは貴重で有意義な時間だった。だから参加してよかったように思う。五条駅から歩いてゲストハウスに帰り、ビールを一杯飲み、そして、simの抜き差しを経てiPhoneの不能を脱することができた。
ゲストハウスのラウンジでiPhoneに四苦八苦していると、店にたまにバイトに入ってくれている方に出くわした。にわかには信じがたい顔の現れだったため、顔を見ても最初はそれが誰だったのか認識しなかった。それは確かに不思議な感覚で、笑いがこみあげた。全体に酩酊した。酔いながらこれを打った。寝ようとすると胃が強く痛み、態勢を何度か変えた。
0710
ゲストハウスでは十分に寝続けることができないのか、良くも悪くも早く起きられる感じがあり、8時台に勝手に目を覚ました。
シャワーを浴び、いただいたカフェフォレを飲むと外に出た。この日の予定は16時から立誠小学校で2本見ることだけだったため、時間がありあまるほどにあった。歩いた。たぶん三条とかそこらへんの古くからの喫茶店でトーストとコーヒーを飲みながら、なんとなく時間を過ごした。腹をくだした。11時過ぎに出、お腹がすいたので見かけたおばんざい屋的な場所で飯を食らった。うまかった。みなちゃきちゃきと働いていた。有線でボニー・ピンクの「ヘヴンズキッチン」が流れた。大好きな曲だった。
そのあともう少し上がったところにあるカフェに入り、スムージーを飲んだ。広々とした場所で、好ましい空間だった。厨房のわりと近くだったこともあり、洗い物の音がやたらにうるさかった。実際、あれだけ音が鳴るのならばその手つきはたぶん荒々しかったはずだ。また、店員の方が帰った客の皿なりを下げるときの様子もそれなりに賑やかだった。提供時にはそっと置こうとかそういう気が回るけれど、下げるときの音に注意できない人というのは多いように思われる。アルバイトの人にもよく注意をしている。客として実感してみるのが一番いい。スムージーはおいしく、過ごしやすいいい場所だった。
そのあともう一つ、今度は小さいカフェに入ってコーヒーを飲んだ。たまらない場所だった。私にとって理想的な空間だった。感動した。自分にとって本当に心地がいいという店に入ってそこで時間を過ごすと、なんというか、じわりと腹にとどまるような喜びとけっこう泣きそうな感動がある。たいへん好きだった。明日も行こうと思った。
立誠小学校に行き、酒井耕/濱口竜介『なみのこえ 新地町』『なみのこえ 気仙沼』の2本を続けて見た。どちらも入りは3人程度だった。『親密さ』を見るというか知る以前から、多分マイケル・マンの『コラテラル』を見てからずっと、私は何かを見るにつけ親密という言葉を考えていたのだけれども、この日何人ものインタビュー、対話を見ていると、何度も何度も、バカの一つ覚えのように親密ということを思った。どちらもひどく充実していたけれど、特に『気仙沼』の何組かの話がやたらによく、それは喫茶店をともに営む兄弟であったり、着物屋を長年一緒にやっている女性二人であったり、やはり長年一緒に会社をやっている夫婦であったり、そこここに、親密という言葉以外なにものでもない時間が流れ、なんで私は今、こんなに親密であけっぴろげな他人の会話を目撃することができているのだろうという不思議な感覚に襲われた。そして最後の若い夫婦のぎくしゃくとした、最後までうまくいかなかった時間の愛らしさ、緊張感。それにしてもいったいあれらの会話は、どのような拘束というか規則のもとにおこなわれているのだろうか、どのような下ごしらえをしたら、あれらのような瑞々しい会話がカメラの前で生み出されるのだろうか。
映画が終わり、またカフェに行った。毎日、本当によく歩いている。歩いてばかりいる。2分も歩けば汗が背中を濡らす。
入ったカフェはこれもまたとてもいいところだった。私が入ったときはそう多くはなかったが、食べログを見たところ大人気店のようだった。カフェというものについてそこのお店の人に話を聞いてみたいというような気持ちに駆られ、わざわざ席を移動させてもらってカウンターの席に移ったのだが、完全に慣れない、そして不得手なカウンターという席にいて、いったいどこに視線を向けたらいいのかもわからず、仕方がないので本を読みながらビールを飲んだ。やっている人の思想を感じるとてもいい場所だった。
それにしたって、話を聞いてみたいと思ってカウンターに座ったはいいものの、実際何か質問事項があるわけでもなかったし、なんせ、働いている人に話しかけるなんてしていいのだろうかとも思ったし、私みたいな若造がいったい何を、どんな顔をして、と思うと何も話を切り出せず、けっきょくなぜかカウンターに移ったうえに無言のまま帰っていった男、という謎の客として過ごすことになった。店の人に話しかけることなど、私にはできない。ときおり、よくこんな人見知りが店なんていうものをやっているなと思うのだけれども、本当になんなんだろうか。立誠小学校においても、一日目二日目ともに濱口監督がおられたので、以前共通の友人が運営している「Loadshow」というweb媒体に『何食わぬ顔』の感想めいたものを寄稿したことがあったこともあり挨拶をしたほうがいいかとも思いながら挨拶できず、三日目のこの日にやっと、「あの」と言うことができたほどだ。
いくつもの対話を見たあとの今となっては、自己紹介とは「阿久津隆、27歳、今年28になります。岡山でカフェをやっていて、だから今は岡山市に住んでいます。出身は埼玉県で、大学を出るまではずっと関東にいました」という形以外ないように思えてくる。
なか卯でご飯を食べてからゲストハウスに帰り、しばらく本を読んだあとに寝た。孤独だった。
0711
この日はよく眠れ、10時のアラームが鳴るまで起きなかった。シャワーを浴び、行く場所もないのでおすすめされた下鴨神社に行くことにして出町柳まで電車に乗った。カフェに行ってコーヒーを飲んだ。浅煎りをあっさりめで淹れてもらい、それはいい具合の酸味が口の中にずっと留まる、おいしいコーヒーだった。ネルドリップをずっと見ていた。格好良かった。
下鴨神社はそういえば行ったことがあったのだけど、覚えていたよりは小さく、ぐるっと一周、ゆっくり歩いて1時間も掛からなかった。参道で多くの人たちがスケッチをしていた。木漏れ日でゆれる地面を見ていると、なぜかフアン・ホセ・サエールの『孤児』の集落を考えた。
再び四条に戻り、昼飯を食いにカフェに入った。ヘルシーなご飯で、それなりに美味しかった。一定以上の広さを持つカフェに、ある種の知性や品性をインストールすることは可能なのだろうか。これは多分、私にとってとても重要な課題だ。
時間が余っていたのでもう一つカフェに行こうかと思ったのだけど、店の前に来るととても大げさな看板が出ていたのでこれは間違えた時間を過ごすことになるだろうと思い、結局タリーズに入って本を読む。
この日も立誠小学校へ。『なみのおと』。上映前に映画館のスタッフの方に、あの正面のカメラはどうやって撮影されているのですかと尋ねてみると、先日おこなわれた監督のトークの時にも同じ質問があったそうで、そこで答えられていたものを教えていただく。「なんとそんな!」という方法で、愕然とする。
『なみのおと』は、やはりとてもすごくて、凄くて、特に夫婦の対話に感動した。その手には助けられたね、もう大丈夫だって安心した、という妻の発言に私はボロボロと涙を流した。最後の姉妹もよかった。なんであそこまで、カメラの前で、しかも真正面にすえられたカメラの前で、あんなにも笑顔をはじけさせ、率直な言葉を放つことができるのだろうか。もうほんと、なんだかわけがわからない。
上映後、この日もこの日とて時間が有り余っているため前日に行ったカフェに行き本を読んだ。サンドイッチを食らった。美味しかった。やはり、最高に素晴らしい空間だった。京都に行くたびに行きたい。
閉店が早い店だったのでそのあと、これもまた前日に行った、洗い物がやたらにうるさかったカフェに行ってビール等を飲みながらガルシア=マルケスの『誘拐の知らせ』を読み終えた。夜に行ってみると、それなりに賑やかながらも席の配置がちょうどいいのか、快適に過ごすことができた。この店が岡山にあったら私はけっこうな頻度で行くだろうなとも思った。よかった。
ふらふらと歩いて帰る。毎日3時間4時間は歩いたような気がする。健康的でいいことだった。
リュックを背負ったままゲストハウスのバーに入ると人々が名刺交換的な催しをおこなっていて、とても盛り上がっていたので、ビールを頼んで誰もいないいちばん奥の暗いところにいく。明朗さ、健全さ、そういうものに対する苦手意識がどうやったって拭えない。
ビールを2杯飲みながら、宿の人とお客さんとしばらく話をして、その人は芸能事務所のマネージャー的なことをやっているということで、全然知らない仕事なので何かと「へー、そういう」と思いながら面白かった。こうやって静かに、笑いのようなものが必要とされない条件下でおこなわれるならば、会話は私にとって愉快なものとなった。
話が終わって遅い時間で腹が減ったのでなか卯に行って飯を食った。けっきょく三晩連続でなか卯に行った。カツ丼とすだちおろしうどん、親子丼とすだちおろしうどん、衣笠丼とすだちおろしうどん。
ゲストハウスに戻り、ソンタグを読みながら寝た。他者の苦痛。自らの苦痛。
0712
4時過ぎに目が覚めると、空は白み始めていた。こんな時間に起きてもどうしようもないため薄い睡眠を9時まで取った。
チェックアウトをし、京都駅へ。前夜までは鈍行で名古屋か滋賀あがりまで行って何かとか思っていたのだけど、お金の減りも激しかったし、そもそも私には旅行者の素質めいたものがないというか、どうやって過ごしたらいいのかがやっぱり結局わからなかったこともあり、東京まで出、今晩栃木の田舎に帰るという両親たちとそっちに行って週末を過ごすことにした。世間は3連休ということだし、そういう賑わいの中から身を離すにはとてもいい方法だと思ったことも一因だった。
そう思って京都駅からどうしようかと考えてみたが、昼の高速バスで行くと親たちが出る時間には間に合わず、東京からさらに3000円ぐらいかけて栃木まで行かなければいけないし、そうなればまた夕飯を一人で食べたりするためにお金を使わなければいけないし、何かと出費がかさむだろうし、それならいっそ新幹線で帰って、両親の車で栃木に行くのがいろいろなコストが減るような気がしたのでそうしようかと思ったが、どうやらニコラス・レイの『We Can’t Go Home Again』が今日までで、そしてそれは21時からで、ということで、バスで東京に戻り、映画を見て埼玉の実家に一泊して電車で明朝栃木、というコースがにわかに妥当性を獲得した。そのためバスを取ろうとバスセンターに行くとバスは12時ではなく10分前の11時半に出ました、と知らされ(iPhoneで調べていたときは12時という便があったが古い情報だったようだ)、方法が新幹線しかなくなったので新幹線に乗った。けっきょく一番金が使われる動きになってしまった。
本を読む気にもなれず、ぼんやりと『親密さ』のことを思い出していると涙があふれてこぼれ、何が私をそう刺激するのかわからないまま目を拭くために眼鏡を取ると、ゆるんでいたネジが外れたらしく、眼鏡の耳にあたるところが外れた。小さなネジを入れようと一生懸命しているとそれが床に落ち、探すのに一苦労した。ゆるい状態のままはめて品川から新宿に出、メガネ屋でネジをちゃんと入れてもらった。ベルクに行き、ジャーマンブランチを食べた。ビールを飲んだ。これからシネマート新宿でホン・サンスを見る。
book text
2013年7月5日
夜になるまえに
カストロは言った。諸君はとても誠実で、完全に政治化し、革命的であらねばならない、と言った。(P90)
「完全に政治化し、革命的」というのがいい。
ミゲルは短気で規律を守らなかったが、人生が大好きだった。(P111)
いい。
伯母は自分と寝ようという男ができるたびに夫を裏切った。でも、数は多くなく、食料雑貨屋、日用品店を接収された老人、自分の親友グロリアの夫で国家公安局で働いている男、その三人だった。伯母がそういった男たちと部屋でセックスしているあいだ、伯父のクチョは台所で皿を磨いていた。(P204)
皿磨きでは音は全部聞こえるのだろうなというところがいい。
「共産主義体制と資本主義体制の違いは、いずれの体制もぼくたちの尻を蹴飛ばすものですが共産主義体制では蹴飛ばされると拍手しなくてはならない、ところが資本主義体制では蹴飛ばされると叫ぶことができるということです。僕はここに叫びにきたのです」(P370)
だが、ノーベル賞はフォークナーの模倣、カストロの個人的な友人、生まれながらの日和見主義者であるガブリエル・ガルシア=マルケスに与えられた。その作品はいくつか美点がないわけではないが、安物の人民主義が浸透しており、忘却の内に死んだり軽視されたりしてきた偉大な作家たちの高みには達していない。(P389-390)
数カ所でガルシア=マルケスをこき下ろしている。それを読んで初めて私はガルシア=マルケスがカストロを擁護し続けていることを知り、結構なところびっくりした。それに伴い、ガルシアマルケスという日本のブランドがあることを知った。生きていさえすれば、何かに興味を持ちさえすれば、いろいろなことが知れるものだ。
休みである昨日は一日中、レイナルド・アレナスの『夜になるまえに』を読んでいた。一日中というのはそう誇張でもなく、起きている時間のだいたいすべてはそれに当てられた。一つの国が牢獄と化すその状態を私はまるで想像できないし、彼の歩んだ人生の困難がどれほどのものであるのか、一日読んだ伝記で推し量ろうだなんて、できるともしたいとも思わないけれど、そういえば人生は途方もなく虚しかったのだと、私はこの2年間を除いてずっと、虚しさとともにあったのだと、そのことを改めて思い知らされた。それは情けないくだらない唾棄すべき休日を過ごしてしまったためであり、アレナスのためではなかったが。雨が、昨日は一日中、降っては止みを繰り返していた。今もそれは変わらないが。
自伝はとても面白かった。迫害と緊張の日々の様子が生々しく、どの友人がいつ裏切り者、密告者になるのかまるでわからない、疑心暗鬼の日々のありようは、読んでいて戦慄を催させた。基本的には計算高い性格だと私は自身について思っているので、その自己評価が確かであるならば私は即刻密告者になるだろうし、仮に作家であったら、ここに描かれた何人もの作家がそうしたように、カストロ体制を賛美する文章を書く側に転向するだろう。本当にタフな人でなければタフに生き続けられないキューバの様子が、ありありと描かれていた。
それにしても、この自伝を読んでいると、キューバの男は全員がホモセクシュアルなのだろうかというぐらいにみんなホモというような感じで描かれていて、それについては「とても開放的な空気があったのだ」みたいな記述である程度納得したのだけど、それにしたって、みんなあまりにもセックスしすぎじゃなかろうか。アレナスにいたっては、中盤ぐらいだったと思うけれどすでに5000人はくだらないというようなことを書いていて、その途方もない数字にはびっくりするだけだ。凄まじい。
ところで今日行った本屋で見かけたエドムンド・デスノエスの『低開発の記憶』ではキューバ革命直後のハバナの様子が描かれているという。これも面白いのだろうか。映画は以前シネフィル・イマジカか何かで放送しているのを録画していたが、焼いたDVDをデッキに入れても読み込まないため未見のままだ。『夜になるまえに』も映画を一度見てみようかしら。不思議と、今のところアレナスの他の小説を読んでみたいという気にはなれていない。
強い、アスファルトの地面に落ちては跳ね返る雨の中、鞄を守るようにしながら歩き、入った店でハンバーガーとポテトを食らい、ハイネケンとモルツを飲んだ。そこに15時半から18時前までいて、ずっとアレナスを読んでいた。そのあいだ、店内では感覚としては20分ぐらいでリピートされるアルバムがずっと流されていて、出るときに教えてもらったバンドの名前はBleachedというものだった。あとでyoutubeで検索して見た。たまに、こういう音を聞くのはとてもいい。それはとてもエネルギッシュで若々しく、素晴らしい音楽だった。
雨がまだパラパラと降るなかで店を出、家に帰ってビールを飲もうと思っていたところ、大きいテレビが置かれている、いつも誰も人がいないように見えるバーというのかわからないけれど酒を飲む用途に使われるためにあるのであろう店の、そのテレビで野球の試合が流れていて、どうやら日ハム対ソフトバンクで、古くからの日ハムファンである私はたまには野球を見るのもいいかもしれないと思い、その店に入った。いつも人がいない店で、いったいどういった目的で存在している店なんだろうと不思議に思っていたが、入ってみてもやはりその疑問は解消されない、何一つとして取り柄ややる気の見つけられそうにないその店のありかたに困惑しながら、ビールを注文して奥のテレビの前に座って野球を見たり、iPhoneをいじったりしながら時間を過ごした。壁にはビールの生樽やあれこれが無造作に置かれていて、その中に紙パックに入った2リットルとかそういう仕様のワインを見つけ、こういうものを客に見せても平気というところに、ある種の凄みを感じた。うちの店で出しているワインはこういった超廉価品です、と堂々と見せつけられ、私はどうやって平気な顔で野球を見ていればよかったのだろうか。案の定というか、私がいた1時間ちょっとのあいだ、それも19時から20時という、たぶん、いくらかでも稼がないといけないだろう時間帯に、やはり誰も人は来なかった。
そういえばその前にいた店も、2時間以上いたわけだけど誰も人は来なかった。雨だから客足が減ることは確かだろうけれども、こうやって立て続けに私以外の客がいない店というところに居座ると、なんともわびしい気分にならないわけではなかった。最初の店はけっこう気に入って時折り使っているし、実際いろいろな側面からいいお店だし一本何かの通った場所だと思っているのでその時間帯、その日に客が他になくても心配めいた感情は湧いてこないのだけど、野球を見た酒場はどうだろうか、そろそろなのか、もう少し粘るのかはわからないけれど、早晩テナント募集の貼り紙が貼られることになるのだろう。残酷な話だけれどもきっとそういうものなのだろう。その前夜と翌日つまり今日、僕らの店も客入りはとてもまばらだった。やることがなくて持て余すという事態は久しぶりで、どのように振る舞ったらいいのか、戸惑ってしまった。
20時すぎに野球にも飽きてその店を出、コンビニでポテチと金麦2本を買って家に帰り、アレナスの続きを読んだ。ポテチとビールが空き、腹がどうにもおさまらない私は再び、今度は別のコンビニにいき、ポテチのビッグサイズと金麦2本とあろうことか豚キムチ丼的なものを買って、その場であたためてもらった。家には電子レンジがないためだ。
私の人生はコンビニ弁当的なものに対して反旗を翻すことで成り立っていたようなものなのだから、この購買はおそろしいことだった。たぶん、失敗した虚しい休日の虚しさをせっかくだから増長させてみたかったのだと思う。
家に帰り、それがあたたかいうちに食い、金麦を2缶空け、ポテチを開いて貪り食っているうちに睡魔が襲ってきたらしく、寝ていた。23時にもなっていなかった。
つまり、10時間も起きていなかった一日のなかで私はほとんどの時間をビールを飲んで過ごし、ほとんどの時間をアレナスの人生とともに過ごした。ビールは7杯飲まれた。酒の弱い私からしたら驚異的な数だ。これではまるで、水代わりにビールを摂取する、あの糞暑く輝かしい苗場の一日みたいだ。虚しさをもたらすのか、陽気さをもたらすのか、その違いはあるにせよ。
今日は最近設けているアイドルタイムに本屋に行ってアドルフォ・ビオイ=カサーレス『パウリーナの思い出に』を買っていくらか読んだ。今のところどれも面白い。宿屋の夫婦の話を読んでいたら、デュ・モーリアの短編の何かの雰囲気を思い起こさせた。どういう共通点があるのか、いかんせんデュ・モーリアのどの話なのかを思い出せないので判然としないけれども、今のところ、全体に流れている妙な、胸騒ぎを覚えさせる妙な不穏さがとても魅力的だ。
book
2013年7月3日
日曜の閉店後、月1回と定めているグリスト清掃作業をする折りに、音楽でも聞かなければやっていられない単調な作業であるためiPhoneで5lackとolive oil、Otogibanashi’s、Fla$hBackSの、つまりここ最近買ったヒップホップを詰め込んだプレイリストを作り、そのプレイリスト名を「グリスト」としたことは記憶に新しいが、例えばいつの間にかグラビアアイドルが自分よりも年下になっていくことの驚き、いつの間にか一線で活躍するスポーツ選手が年下になっていくことの驚き、それらに似たものとして、私の耳を格好良く刺激する音楽家たちが自分よりも年下になっていくことに対して驚き、一抹の羨望のようなものを抱きながら賞賛している。生き続けていると、こんなことがあるのだ、という思いにとらわれる。だけどどれだけ格好のいい音楽であっても、私を見舞ういささか度を越した疲労を、休めども休めども消えない慢性的な倦怠を、慰め和らげてくれるわけではまるでなかった。
孤児―フィクションのエル・ドラード
本を読む時間と気力を取り戻せないままにちまちまと読んだフアン・ホセ・サエールの『孤児』は、勝手に設定していた低い期待を軽々と越える、実にいい小説だった。
帯に「アルゼンチン文学の巨星が放つ幻想譚」と書かれていることもあり、幻想譚なら別段、どうでもいいんだろうな、マジックなリアリズムの変奏だろうかな、と高をくくっていたのだけれども、これも帯にあるロブ=グリエの「現実世界の強烈な存在感」という評価の方がずっと実情にそぐうものだった。実に、存在だった。現実がただ、そう、ある、という強さが充溢していて、それがそのまま小説としての強度につながっていた。
走り出すと、二人のインディオはまた同じように私を丁重に扱った。二人は、黙ったまま両側からそっと私の肘を掴むと、両足が地面から数寸離れるようにして体を持ち上げ、私が走らなくてもすむようにしてくれたのだ。最初はわけがわからず足をばたつかせていたが、やがて彼らの意図を飲み込むと、少し前腕を上げて指を丸め、宙ぶらりになった両脚を揃えて、両腕を少し体から離した状態で正面を向いていれば、両肘に大きな負担をかけることもなく、言ってみれば自然に、二人の手が私の体を前へ押しやってくれる。担ぎ方も手慣れたもので、裸足の足で地面を踏みつける震動が私の体にまったく伝わってこない瞬間するあり、そんな時には、凸凹のない平らな地表を滑ってでもいるように、両側の景色が静かに後ろへ流れ去っていった。震動がある時には、私の肘を掴む鋼鉄のような手が動いて位置を修正し、できるだけ私の体に揺れが伝わらないようにしているのがわかったが、いずれにしても、彼らは、そのぐらいの揺れにはまったく動じていないようだった。インディオたちは、そのまま休みなく丸一日小走りで進み続けた。それでいて、経験の成せる業なのか、以外なほど静かな行進であり、誰一人として隊列を乱す者はいなかった。あまりにも整然と事が進んでいくので数時間後にはすっかり単調になり、私はとうとう眠り込んでしまったほどだ。(P34-35)
運動の細かい描写がとてもいい。休みなく小走りで丸一日というのがとてもいい。両脇を掴まれて運ばれながらスムースすぎて眠り込んでしまうというあたりがとてもいい。
ただそれも終始こんな具合というわけではなく、インディオに誘拐され十年以上彼らと生活をともにしたという経歴を持つ語り手の、常に記憶を疑いながらおこなわれる語りの中に紛れ込む思弁的な言葉はそう刺激的なものではなかったのだけど、思弁者としてではなく観察者としておこなわれる語りはけっこうどこまで行っても十二分に読んでいてワクワクさせられるものだった。
観察される子供たちの遊戯の様子は、レーモン・ルーセルの『アフリカの印象』を思い起こさせるものだった。(ソローキンの『青い脂』の松明人文字のときも同じことを感じたが、私は一様に、奇異な運動が細かく描写されているところを読むと『アフリカの印象』を思い出すようになっているのかもしれない。それは多分、保坂和志の『小説の自由』シリーズのどれかでけっこう細かく言及されていたこともあり、記憶の上っ面にこびりついているせいだろう。それにしても今日、暇な時間になんとなく本棚にあった『この人の閾』を読んでいたら、私はこの短編集がひどく好きなのだけど、やはり以前と同様にすっとその場所に入っていけるような感覚があった。今日は十数ページを読んだだけだったが、一瞬にして、人と場所が目の前というか頭の中に見事なまでに、奥行きのある時間をともなって立ち現れてくる。これってやっぱりすごいことだよなと、改めて感じ入った)
男女混ざった二十人ほどの子供がそこに集まっており、年長者でも十歳ぐらい、年少者は三、四歳ぐらいだろうか。皆裸で、明るく健康的に岸辺で遊んでいた。遊びといっても、単純、奇妙なもので、まず、川に沿うようにして全員が縦一列に並んだかと思えば、一人また一人と地面へ倒れ込み、そこで死んだふりだか寝たふりだかをして、そのままじっとしているだけだった。列の最後尾が倒れると、他の者たちが走ってその後ろへつき、最後尾にいた子が立ち上がると、また最初から同じことが始まる。やがて、列は輪になったが、私が子供の頃よく目にしていた輪とは違って、全員が横並びになって中央を向くのではなく、相変わらず横並びのまま、前の子の肩に両手を掛けて繋がっているので、先頭の子が最後尾の子の肩に手を掛けた時、ようやく輪が完成する。時には、誰も倒れることなく真っ直ぐ長い距離を進んだ後、ある者は手を打ち鳴らして笑い、ある者は何か話しながら、まるで遊びの第一部が終了して再開前に束の間の休息でも取るように、皆一目散に消えていくこともあった。(P44)
こうやって書きだしてみると、そう細かいわけでもなく、そう面白いわけでもないような気がしてきた。ただ、子供たちのこの後もまたいい。
やがて全員川縁の草地に倒れ込み、息の上がった体を静かに休め始めた。直後に、七歳にもならないだろうという男の子が立ち上がり、一団から離れて何か物思いに耽り始めたかと思えば、すぐにまた仲間のもとへ戻り、演技でもしているように、妙な仕草と歩き方をしてみせた。他の子供たちから笑いと喝采で迎えられて気をよくしたのか、その子は、一段と大げさな仕草と歩き方を繰り返し、ある時から言葉を交え始めたが、これがまた大いに受けて、仲間たちが頭を振りながら叫び声を上げて囃し立てるので、私のいるところまでその騒ぎが聞こえてきたほどだった。(P44)
そもそも語り手は、15の年のころに探検隊の一人としてインディアスにおもむき、上陸中、仲間全員が矢で貫かれて死ぬなか、一人誘拐されたのだった。死体はすべて部族の集落へ持ち帰られ、見事な手捌きで切り分けられ、香草を振りかけられ、バーベキューにされる。溢れ出る唾液を飲み込みながらその様を凝視し待望する人々へ、調理人から切り分けられた肉片が手渡される。人々はそれを一心不乱に貪り食う。しかし、そこにあるのは狂喜だけではなく、むしろこの部族は先ほどの子供がそうであったのと同様に、何かと物思いに耽る。
どのインディオを見ても、過度な熱狂に食事の楽しみを妨げられるのは同じらしく、彼らの内部では、欲望の殻をかぶった責任感が、常に罪悪感と手を携えているようだ。食べれば食べるほど。朝彼らが見せていた陽気な表情は消え、次第に重々しい沈黙と、沈鬱な敵意に取って代わられた。思いつめでもするように、咀嚼の速度も緩慢になり、不機嫌な物思いに沈んでいくのだ。時々噛むのを止めることもあるが、そんな時には、食べかけの肉片を口に入れて、頬を膨らませたまま、背中を木の幹に預けた同じ姿勢で、長い間、虚空をじっと見つめている。(P54)
人肉食の宴、喜悦からの沈鬱のあとには酒宴が始まり、息を吹き返した彼らは性的な狂乱を繰り広げる(ただ部族全員がそこに参加するわけではなく、人間狩りに参加したもの、それから人肉の調理にあたるものは一切に加わらない。離れたところでいつも通りに魚を焼いて食う。語り手もそこに招かれ魚を食う。とても静かに)。そしてその後に待つのは意味に回収されないいくつもの死だ。
このあたりの過程がとても、「現実世界の強烈な存在感」という感じで、理由とかわからないけど、もう、それでしかないんだよね、という強い、読むものをねじ伏せる説得力を獲得している。
夜も更ける頃になると、辺りの砂地や空き地には、重い灰や焼けた草、火で黒くなった棒などに混ざって、生気のなくなった体が散乱していた。まだ機械的な抱擁に体を絡ませて動いている体もあれば、時々しか動かなくなった体もあり、苦痛に低い声で呻く体、ぴくりとも動かなくなった体もある。(…)七人か八人の体は、どうやらこのまま永眠してしまうようだ。一人が起き上がり、数分間、何か考え事でもしているようにじっとためらっていたが、いきなり踵を返して頭を木の幹に打ちつけたかと思うと、続けてますます激しく何度も頭を打ちつけ、ついには口と耳から血を流しながらその場に倒れ込んだ。(P69-70)
この部族は一年に一度、人肉食の饗宴から始まる一連のダウナーを経験するが、それ以外の日々はとても慎み深く、礼儀正しく、清潔好きで、おとなしい。
また、言語をめぐる観察も面白かった。
エン・ギという言葉は、人間、人々、我々、私、食事、ここ、見る、内部、一つ、目覚め、その他多様な意味を持つ。(P139-140)
多様すぎでしょ、という喜び。
「いる」や「である」に相当する言葉は、彼らの言語には存在しない。あるのは「ようだ」に類する言葉だけなのだ。冠詞や助詞に当たる言葉も存在しないから、「木がある」とか「木である」とか言おうとすれば、「木、ようだ」と言うしかない。だが、実際には「ようだ」は、類似よりも不信感を表す。つまり、肯定というより否定であり、比較であるより反駁なのだ。すでに知られた内容に言及するというより、知覚を欺き、確実性を減じるような表現に用いられる。つまり、同じ一つの言葉が、見かけであり、外観であり、嘘にも、日食・月食にも、敵にもなる。(P140)
ちょうど、先日彼女が買ってきた『ピダハン―― 「言語本能」を超える文化と世界観』を少し読んでいたところだったというのもあって、このあたりの言語の構造の話はエキサイティングだった。
それにしても、徐々に彼らの持つ世界観の途方もない脆弱性が語られる時、読んでいる者はけっこうなところ、「うわー…」という気分にさせられる。彼らから間断なくデフ・ギーと呼ばれる語り手は、まさしく彼らがそう望んだ通りに観察者に徹し、そして語り手になった。いや、でも、それは本当に悲しいことなのか、私にはよくわからない。
訳者解説を読むとこの話は実際にインディオたちに誘拐され12年のあいだそこで暮らし帰還したものがいた、という史実にインスピレーションを得て書かれたものの、その他のところは作者の想像力の飛翔以外なにものでもないらしいのだけれども、観察部分を読んでいるときに起こる感覚は、ものすごい面白いルポタージュを読んでいるというものだった。ただ、そうは言え、やはり、運動や身体の描写が強度のあるリアリティをもたらしていることは間違いないので、やはり、小説として、この作品は私を圧倒したのだろう。風景描写も充実していて、特に月の光に照らされた集落の美しさは格別のものだった。大満足です。『ピダハン』もぜひとも読んでみよう。と思いながら、なぜだろうか、今は波瀾万丈な人の自伝、それもラテンアメリカの歴史に存分に翻弄された、という観点からなのか、よくわからないけれどもレイナルド・アレナスの『夜になるまえに』を買ってきて読み始めた。雨の匂いがする。そう思ってから一分ぐらいで、雨音が耳に届いてきた。
←
→