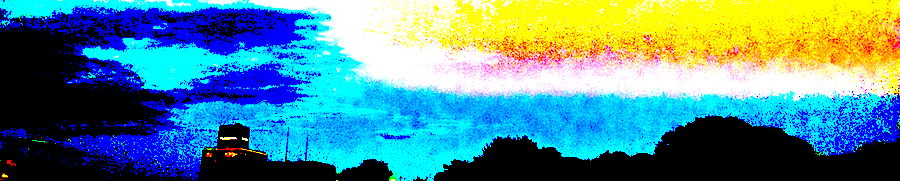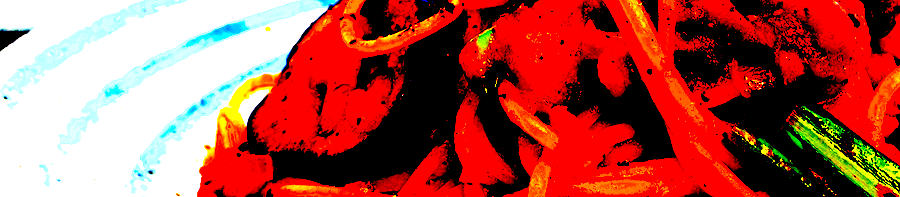text
2013年10月10日
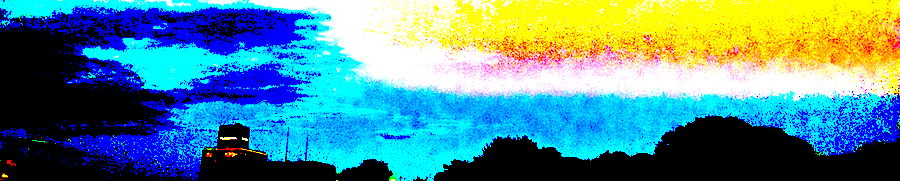
台風来ないかなと、予報を見ている限りきっと来るのだろうとわかりながら私は教室の窓から半身を乗り出して空を仰ぐ工藤夕貴の姿が思い出されて、その翌朝に同じ教室の同じ窓から飛び降りることになる三上祐一がその死の直前に厳粛な生を生きるための厳粛な死が僕たちには与えられていないというその現状を嘆きとも異なる調子で唱える姿もまた同時に思い出され、その二つの時間のあいだに夜の校庭の乱痴気騒ぎがあることも思い出されたが、その場面はどこか透過化されたような、薄い皮膜の次の層に置かれたように見えたのもまた事実だったし、その夜、期待したような強い風や横殴りの雨というのはまだ見られない夜、傘を二つ手に持った私はそれらをライフル銃に見立てて手当たり次第に、ちゃんとどこかを狙っているようにはとても見えない格好で撃ち続け、次第にその歩みの速度を上げ、駆け出し、なおも撃ち狂い、最後に(深夜に合わせて落としたトーンで)絶叫するという真似をして自転車をゆっくりと漕ぐ彼女に「はい誰の真似でしょう」と言うことになるが、それはその日の朝のバス停のベンチに黒いサングラスをかけた白髪の、レオス・カラックスに似た年齢不詳の男を見かけたからに他ならなかった。屋根のある、こぎれいなバス停にその男は座っていて、ちょうどよくやってきたバスに乗らなかったところを見るともしかしたら夜が来るのを待っているのかもしれなかった。私たちはそうやって物真似をして家路につき、二人でソファに並んでOMSBのアルバムを聞きながら「かっこいいね」と言い合うのかもしれなかったしそれは何日か前の昼間の出来事だったのかもしれなかった。そんな時間が現実にあったためしはないのかもしれなかった。けっきょく書かれることが何であろうとも私は構わないのだった。書くことは私にとってはセラピーのようなもので、こうやって打鍵を続けること、それ自体が必要とされているらしかった少なくとも今の私のモードにとってはそれはそのとおりだったし「貧しさ」を事件として生きながら、収奪の二重構造が具体的に機能しつつある限界的な一点に不意撃ちをくわえ、わずかなりとも可視的な領域に露呈せしめんとする試みをここで改めて「批評」と呼ぶならなどという、打ち震えるほどに格好のいい文章を書くことができないとしても何一つ悲観することはなくて、ここで引かれた蓮實重彦の『表層批評宣言』を夜ごとちまちまと読みながら重力の重みによってまぶたは次第に閉じられ、気を失ったあとに見る夢は決して恩寵ではなく悪夢の類である場合が多い今となってみても、そのことに一つの意味合いを持たせるように昼の人生を暮らすわけでもなく、悲観ではなく静観を、メロドラマなどでもなく、窓の、外に映るいくつかの光、反射する店内、そこに見えないものを見ようとする惰性を排し、ペラペラのその表層を見つめ続けようとして努力してみせること、舞城王太郎のおそらく『みんな元気。』で書かれていた恐怖を克服するためには恐怖の根幹を見つめること、その教えを、私はわりと今もまともに愚直に信じている。見つめること。シンプルに。それは染みであり、それは反射であると見つめ知ること。同時に読み始めたロベルト・ボラーニョの『売女の人殺し』の中でも同じようなことが書かれていて、Bは一瞬、白いワンピースの女を見つめながら(このとき初めて女がとても美しく見える)、ナチスの賛歌が血の色をした空へ昇っていくあいだ、まるで従順な子羊のように地上から跡形もなく姿を消したギー・ロゼのことを考え、そして自分自身がギー・ロゼに、アカプルコのどこかの荒野に埋められ、永遠に消え失せてしまったギー・ロゼのように思えるが、そのとき、父が元ダイバーを何か咎めている声が聞こえ、自分がギー・ロゼとは違って孤独ではないことに気づく、とある「この世で最後の夕暮れ」は父と子の短い休暇の様子が淡々と綴られた作品だが、ボートが転覆しても死ぬことにはならず、賭けポーカーで勝ち抜けしようとしても死ぬことにはならないそのバカンスのあり方を、プールサイドで出会った初老の婦人と寝る逞しい父の姿を、私は今一度信じてみたいとそのようにたった今思った。これはいずれもとても好ましい出来事だったしプールサイドで何かの実験とfla$hbacksのjjjが言って、それをつい先ほどまでこの耳は聞いていた。彼らのアルバムは何を歌っているのか何度も聞いているけれどさっぱりわかっていないのだけれども私の耳にはひたすらに都合よく響き続けるため何度でも聞いていて、febbのソロアルバムはいったいいつになったら出るのだろうかと心待ちにしていた矢先、ホルヘ・エドワーズの『ペルソナ・ノン・グラータ』が出版されたことをhontoカードのメールがお知らせをしてくれて、『売女の人殺し』と同じ松本健二訳ということでよく仕事をされていることがわかるし、次に読むものはこれか、あるいは『売女の人殺し』を買いに日曜の晩に行った本屋で、どうにも見つからず、クソみたいな本屋だと嘆きながら店員の方の姿が見当たらなかったため店内に響き渡る大声で「売女の人殺しは置いてませんか、売女の人殺しは置いてませんか」と言ったのだが誰も取り合ってくれなかったため仕方がない格好で保坂和志の『未明の闘争』を買ったのでそちらを読むかもしれないけれども、今年いっぱいは少なくともずっとラテンアメリカのものを読んでいたいような気がするというか、今現在蓮實重彦も読んでいるのであれなのだけど、小説に関してはラテンアメリカのものだけを読みたいような気もしているから『未明の闘争』はいつ読むかわからわないしいつか読み始めたらいつだって泣く準備はできているようなメンタリティの私は何かを決壊させたりするのだろうかとか、今まで保坂和志で泣くという経験はしたことがないにもかかわらず妙な期待をしている部分があり、書き出しの一文で「何やらものすごい」みたいなものを与えてくるらしい小説としてピンチョンの『重力の虹』がよく引き合いに出されるというかよくかどうかは知らないけれども何度かそういう場面には出くわした記憶があるけれど、ボラーニョのそれだって引けをとらないというか、まだ3編しか読んでいないけれども、奇妙なことに、マウリシオ・シルバ、通称目玉は、たとえ臆病者と見なされる危険を冒してでもつねに暴力から逃れようとしたが、暴力、真の暴力からは逃れられないものなのだ、というのが最初の「目玉のシルバ」で、人生最悪のある時期、僕はゴメス・パラシオを訪れた、というのがその次の「ゴメス・パラシオ」で、「この世で最後の夕暮れ」は状況は次のとおり。BとBの父は、休暇でアカプルコに出かける。早朝、午前六時に発つ、という感じで始まるが、何がぐっと来るといえば、それぞれ、マウリシオ・シルバ、ゴメス・パラシオ、アカプルコであり、つまり見慣れない地名であったり人名であったりのカタカナたちであり、それだけで私の中のフィクションのエンジンが駆動されるような、小説の中にぐっと引き寄せられるような、時間と場所から解き放たれるような、そういう心地がある。それはとても好ましいものだ。翌朝、空は晴れ渡っており、楽しみにしていた台風はどうも終わったか、逸れたかしたらしかった。店に向かっているといつも顔を合わせ、おはようございますと言い合う仲の人がやはりその朝にもいたので台風はどうなったのですかと尋ねてみるともう隠岐の島の方に行って、思ったよりも速く動いていったみたいで、というようなことを教えてくれたその日、私たちはいつものように働き、昼寝をし、夜まで楽しく働いた。どれも、極めて好ましい出来事だった。私の人生は好ましい出来事の連なりとして基本的に構築されていると頑なに信じる姿勢を崩したくはない。以上すべてを同時に考えながら家に帰った私は一目散に服を脱ぐと、「やれやれ」とつぶやき、シャワールームに入った。両手を壁につけてうなだれた後頭部に42度のシャワーを浴びながら、村上春樹はジャズ喫茶をやっていたらしいけれど、一日の売上はどのぐらいのものだったのだろう、と考えた。営業後に小説を書いていたというけれど、体はしんどくなかったのだろうか、とも考えていた。
text
2013年10月3日
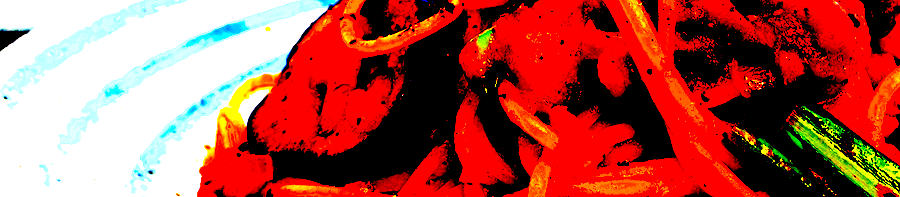
夜、驚くぐらいに暇だったのでたっぷり驚いたこの夜、ぼーっと外を見ていたら光るおばちゃんが通り過ぎていったのを見たのだった。腹にまくベルト式のライトの光が散って着ている白いレインコートっぽい服全体をぼうっと明るませるようになっていて、だから全体に白い光を発散したおばちゃんがゆっくりとした歩調で通り過ぎていったのだった。そのどこかアンゲロプロス的な光景を見ながら私は以前友だちが書いたテキストを思い出した。そこには夜中の東京の静かなビル通りを、大八車を引いたおじさんが歩いていく姿が描かれていた。星とか散っている夜だった。大八車には確か、高い高い何かが置かれていた。ビルぐらいの高さのものだったかもしれない。描き出されるその光景は不思議な静謐さをたたえていて、そのテキストを書いた友人であろうところの「俺」はそのあと警察にしょっぴかれるのだった。所持していたカッターがいったい何なのかを、共通言語を持たない警察官たちに問い質されるのだった。奇妙なテキストで、私は都合、三度ほどはその長い文章を読んだ。繰り返し読んだわけではなく、思い出して久しぶりに読む、という三度ほどだった。どれだけ読んでも、いびつな力強さを溢れさせた圧倒的なテキストだった。それを思い出したのだった、驚くぐらいに暇だったのでたっぷり驚いてみせたこの夜。そしてまた真夜中が訪れて私は3時、YouTubeで延々とヒップホップの動画を見ていたら気がついたら3時になっていたためビールを開けるのかコーヒーを再び淹れてみせるのか、冷蔵庫にホイップクリームが仮にあるとすれば、ウィンナーコーヒーにしてみせるのか、そのことについて迷っているうちにまたこうやって指をカタカタと運動させ始めるのだった灰皿に置かれた煙草の煙が顔に流れてきて副流煙の被害に今あっているということについて私はたいへんな憤りを感じている。今朝はsimi labを聞いた朝だったのでそのあとに久しぶりにotogibanashi’sを聞いて、久しぶりに聞いたそれはやはり好意的に捉えられるべき一枚ではあり続けていた。今の私はもっと過剰な音が欲しいから、その過剰さはsimi labであってもいいし、fla$hbacksであってもいいし、vanadian effectであってもいいけれど、そういった音が欲しいからそういった音をたいがい聞いているけれどotogibanashi’sの流れ方や遊び方もまた、好ましいものであることには今でも違いはないことが判明した朝だったそのあとはよく働き午後はシエスタで夜は暇なのでいくらか溜まっていた伝票をエクセルに入力し続けた。データ的なものを取ることが好ましいことであることも開店以来ずっと変わらない気分であるために伝票を一枚一枚私たちはエクセルに入れていてそれで日の売上、月の売上、その他もろもろ、きっと興味深いデータを抽出できるようになっているのだけどいつも思うけれどもどういった指標をもって経営の様子を見るのが適切なのか。金の専門家みたいな人に5時間1万円ぐらいで教えてもらいたいマンツーマンで。エクセルとにらめっこしながらこういう指標を出してみたら色々と一目瞭然ですよねということを親切心からではなくて職業意識から教えてもらいたいしそれを学んで今後の経営的なことの糧というか参考にしたい。それをこの暇な夜には考えていたし消費税率が引き上げられることがとうとう正式に発表されたというニュースを今朝見て驚くことはもちろんなかったけれどもいったいいくら消費税を払うことになるのだろうと心配というかメニューの値上げとかも検討しなければいけないのだろうなと思うと煩雑で面倒くさい。消費税の納付は開業2年間というのは免除されていて、私たちは今3年目になるので今年から対象なのだけれどもどういう手続きで引き落とされるのかあるいは振り込むのか、それは帳簿上どういうふうに処理されるのか、まるで消費税のことはわからないので、どうやって計算するのかとか、はっきりしたことはわからないので、どうやって計算するとか、私はてっきり売上の今なら5%をシンプルに払うとずっと思っていたのだけど以前読んだフリーランスが云々の節税が云々という本で教えてもらったところによると5%シンプルではなく仕入れ等の段階ですでに消費税を払っているのでそういったことを加味して売上の5%の数十%とかを見なし方式で計算するとかなんとかだった。売上が5000万とかを越える事業者はなんかものすごい細かいことをしなければいけないとかなんとかだったし、私たちの商売においてそういった数字が出ることはありえないというかありえないことはないというかありえなくないとしたら太っ腹の老紳士が「とてもいい店だったから5000万円を払うよ、500円なんてけちなこと言わずに」と言ってぽんとキャッシュで5000万円を払ってくれたときだけだったから、めったになさそうな気がするから、関係のないことで、みなし方式でどうこうすることになるのだけど消費税が増税された暁にはどういった事態が起こるのかとか、そういうことを考えようとしても考えたことが今までなかったからまるでよくわからなくてそれはいいからヒップホップできれば暴力的で泥臭い音や声を聞きたいと私の耳は希求しているし、今年一番にぐっと来ているのは間違いなくvanadian effectで、毎日でもいいので聞きたいし今朝simi labを聞いていたらやっぱりすごいすごかったので特に最後の曲とか大好きなのだけどすごいものすごい通して格好いいし、そういえばomsbのアルバムはまだ聞いていないと、そう思いまたYouTubeを用い、その曲を見てみたところわけわからない音の連なりでこれは私の耳には大変好ましいかもしれないという思いを強めたので今日これからか明日かにでも買うだろう。ダウンロードは便利だ。ということで買った。ototoyで買った。ototoyは心配になるぐらい一瞬で買えるので便利だし、どうもダウンロードのペースが遅く、なんだか最近ネットの接続が変なようなところがあって一抹の心配を抱かないでもないがバルガス=リョサの『緑の家』も150ページぐらいまでは遅々として進まないというか何が起こっているのかまるでわからないので進まないというかページ進まないという印象だったのだけどどこからか読むスピード自体にはドライブが掛かり300ページとかを確か超えたはずで、あとはちょっとしたら終わるのだろうしだんだん何が起きたのかはわかってきたけれども、ダウンロードもいつの間にか終えていたからドライブが掛かったということらしかったけれども『緑の家』はドライブが掛かったからといって特別面白いわけではない。バルガス=リョサの書くものはこれまで読んだものはどれもそうだったけれども、すべての材料が作者の手の中に完全に掌握されているふうで、作者はそういった用意したパズルを面白く読めるように配置したり調整したりする役のようで、どこか鼻白んでしまうときがあって、『緑の家』も、一直線に過去から現在へと書いていけばいいところを時系列をごちゃごちゃと入れ替えまくってミステリアスな体裁にしていて、そういう作者の全能感みたいなものに対する違和感というか疑念はずっとあるので、それは村上春樹に対してだってもちろんそうだったし、リチャード・パワーズでも確かそれを感じたはずだったけれど、どうも、どうなの、という気がいつだってあるしリチャード・パワーズは新しいやつは読んでいないけれどもどこまでかは追っていて、それらはすべて完膚なきまでに面白かった。村上春樹は『1Q84』の2まで読んだけどそれはそう面白くなかったし村上春樹にはまりまくっていた高校生の時以降で面白く読んだというか一番いいんじゃないのかと思うのは『アフターダーク』だった。あの作品には、妙な手触りがあって「お、いいじゃん、チャレンジしてんじゃん春樹」と、なぜかフレンドリーに話しかけた記憶があった。私たちは誰一人として無垢でも無辜でも無害でもない。そのことを忘れた愚かな人間だけが使うある種の言葉がいつだってある。そういうことを思い出した。私は愚かには生きたくはない。人の挑戦や前進をあげつらい、ゴシップだけが話題の醜い人々とは一緒にいたくもない。3時半、ポットに水を入れ火に掛けた。火に掛けるで正しいのだったか火を掛けるかどっちだったかいつもというか使うたびに少し混乱するのだけど火に掛けるで正しかったはずで火を掛けるだと火を投げ込む感じがするし、ジャンヌ・ダルクを火に掛けるだから火に掛けるで合ってるような感じがするし、いずれにせよ3時半、私は今からどうやらコーヒーを淹れることにしたらしいし同時にiPhoneに今買ったばかりのomsbを入れてイヤホンをしてそれを聞こうとしているらしいし冷蔵庫を見たらホイップクリームがあったのでウィンナーコーヒーにしてみるつもりらしい。こういうとき飲食店は便利でとてもいい。リスペクトしたい所存だった。ここ数日、プロ野球の各球団の戦力外通告の記事を何個も見かける。え、あの選手が、ということもしばしばあり、それは何年か前に新人王を取った榊原諒だったりした。榊原はその年、ロングリリーフ専門というようなポジションで投げていて、いっときは投げるごとに勝ち星をえぐり取っていたような印象があった。きっと先発に回るんだろうな来年は、と思いながら、そのあとさっぱり見なくなった。そういえば宮西って今年どうだったんだろう、と思って成績を見たら今年もがんばっていたみたいだった。中継ぎは、本当に長持ちしにくい。増井もそろそろきついか。で、え、あの選手がの最たるところというか衝撃度が大きかったのは榊原もそうだったけれどもそれ以上に横浜に移籍した森本稀哲だったし今コーヒーが入ってウィンナーにしてみた。普段はブラックでしか飲まないけれどたまには飲んでみようと思ってそうしたのだけど想像以上に「ああ、おいしいな」と思えたので安心した。森本稀哲は日ハムから横浜にFAして2年になるだろうかあっという間に戦力外になってしまった。俺は一度だけ森本稀哲の実家の焼肉屋に、何かが決定する試合、パ・リーグ1位だったか、CSでのパ・リーグ優勝だったかが決定する試合を見ながら焼き肉を食いに、行ったことがある。その試合、日ハムはロッテに勝って何かを決めた。そのあと日暮里から池袋、新文芸坐、ゴダールのオールナイトだった。充実した一日だったそれは。俺はかつて一度だけ鎌ヶ谷の二軍球場に、小学5年か6年のとき、友だちと二人で電車を乗り継ぎ、秋季練習だか何かを見に行ったことがある。厚沢投手あたりからサインをもらった。そのときの私のイチオシ選手は石本だった。ソックスを長く履く。一軍でも、一時期いい具合に活躍した。東京ドームでも見た。その日の鎌ヶ谷でも見た。電車を乗り継ぎ、知らない町を歩き、スーパーか何かで買ったパンを昼飯として食らい、肌寒いか寒いその日、小さい僕らにとってそれはまさに冒険と呼ぶべきものだった。
text
2013年10月1日

夏だろうが秋だろうが指はすぐにあかぎれを起こして曲げるだけで痛いという状態に簡単になるのだけど今日からは右手親指の爪の近くにちょっと深い割れ目ができて少し動かしただけでひきつるので早く保湿剤を塗って手袋をして眠りたいと思ってもいるのだけど、今日も今日とて、休憩時間は深い眠りに落ちてしまい、それ以外の時間はよく働いていた身であったので、このまま一日を、1ページの本も読まずに、一文字の言葉も打たずに、一秒の映画も見ずに終えてしまうのは惜しいというよりは、腹立たしい気がして2時になってからコーヒーを淹れて、今が2時25分であることが画面の右上で確認された。コーヒーは酸味の奥に少しえぐみを感じる気もするのだけど全体的にはそれなりに美味しく淹れられたような気がしたが、私はもっと美味しくコーヒーを淹れたいとこの2週間ぐらい思うようになった。多くの物事に対して私は中途半端な姿勢のままに生きていて、それなりであればいいような感覚でいるのだけど、追求型の人間の話を聞くと羨ましい思いもした。私には基本的には真似が出来ないことだとは承知した上で、私はどのように善く生きていくのか、今一度考えなければならないような気があった。先ほど読んだツタヤの社長のインタビュー記事で、光沢のある顔色をした白髪のその男性は、かつて人に「会社の成長ばかり考えないで、増田さん個人の成長を考える目を持たないと絶対にダメになる。最終的には会社もダメになる」と言われたということを言っていて、それはなんとなく、今の私にとっても多少迫ってくる言葉のような気があったし、”増田”という人名はもはや、匿名ダイアリーの書き手のことにしか見えなくなってきてしまっているという点から言っても、私は少しいくつかのことを休ませたりストレッチしたりした方がいいのだと思われた。夜中だ。少し前に読んだ体罰問題に関するブログ記事で、私はインターネットは怖いところだと思った。もはや、型に則ったような、スムースでクリアな言葉以外は、インターネットの人々には届かないのかもしれないと思うと、恐ろしいことだった。届かないというか、そういう言葉以外を受け付けないような人々にも誤送されてしまう怖さがインターネットなのだろうと思った。過激と言えば過激なタイトルにだけ引き寄せられてきた人々が、中身も読まずにタイトルだけをあげつらって非難する。あるいは読みにくいと言って非難する。最後まで読んだものだけが石を投じるべきではないのかと思うけれどもそういうことではないらしかった。長すぎる、というのが非難の言葉として有効だと本気で信じている人間がたくさんインターネットにはいるのだということが私には恐ろしかった。また、書き手の手癖や、あるいは技芸のようなものがまったく無視され、「要は」ですべてが片付けられる世界が恐ろしかった。プロセスが生む、紆余や曲折が生むドライブのようなものは、多くの人間にとってノイズでしかないらしかった。ノイズこそが面白いではないかという主張は、受け入れられる余地がなかった。人々の余裕のなさ、遊び心の持てなさが恐ろしかった。いやそれは違うのかもしれなかった。全編がノイズでしかないような、私にはとても魅力的なものに思えた記事がホットエントリーに入った直後に書かれたその記事が、今度は炎上のような形でホットエントリーに入って、自分に届けられたと勘違いした誤送先の人々が盛大に叩いている姿が怖かったのかもしれなかった。わからなくなった。同じインターネット、同じ村の住人でも、こんなにも違うのかというところが怖かったのかもしれなかった。隣人はストレンジャーだった。私は移住者といえば移住者であるが、それは村においても、あるいは現住する町においてもそうだけれども、移住者といえば移住者であり、私が住むこの町は、他の町もそうなのかもしれないけれども、少し歪んでいるような気が、ここのところいくつかの箇所で感じられるのだった。15世紀だか16世紀だかわからないけれどもヨーロッパからアメリカ大陸に人々がこぞって移住していった。原住民は迫害された。原住民は「正しい」キリスト教の教えを受けるべきだとされ、強制された。ラス・カサスはがんばったが、及ばなかった。時々、この「正しさ」を私は感じて、息苦しくなった。それは移住者個々が持って振りかざしているというよりは、ラテンアメリカのそれとは異なり、原住民たちが崇めることによって形成されている部分もあると感じた。私たちは遅れた者で、彼らは進んだ者であると、だから彼らは正しいのだと、原住民たちがその空気を固めていっている気がした。わからない。こう書いてみたけれども、本当にそうなのかはわからなかった。いずれにせよ、私は移住者でありながらも、いわゆる移住者ではない性質を持つので、気分が中途半端な場所だった。いわゆる移住者、というその感覚自体が、考えてみればとても奇妙なものだった。本来であればいつ移住したものであろうとも移住者は移住者であるはずなのに、いわゆる移住者であるための条件としてある時期以降に移住した者という項目があることが不可思議というか、いびつだった。それどころか、いわゆる移住者であるための条件というか、原住民側がこぞって歓迎する、いわゆる移住者というのは、結局のところ何かしらの手に職を持った、それこそノマドなワーキングのスタイルを持ちうる者たちであるという項目すらあるような気配があり、それらにより二重に移住者と原住民のあいだにスラッシュを引くような嫌いがあった。ひがみ根性のようなものに端を発する私だけの感覚なのかもしれないが、どこか、そんなような気がした。そもそもそんな議論はすでに出尽くしていて解決済みなのかもわからなかった。私はどこにも参与しないために、知らないだけなのかもしれなかった。知らずして、私だけが私こそが勝手に特別視し崇めているだけなのかもしれなかった。いずれにせよ私はとても中途半端だった。私が上げる声は原住民のものでもなく、移住者のものでもなかった。自身を定義づける都合のいい枠組みを持たないストレンジャーだった。私にとってさよならは、ストレンジャーではなくアーバンギターだった。今朝もランダム再生にしたそれらの楽曲を聞きながら口ずさみながら、私は厨房の中で汗をかき準備をおこなっていた。私は、ナンバーガールを熱狂的に好きである、ということによって高校時代、最も自分を定義づけることができたような気があった。先日店にきた多分高校生ぐらいの男性は、持ってきたCDを掛けてもらえるんですよね、と言ってきたので、いや、それは基本的には嫌です、と言った。ただし、もう閉店時間も近く、他に人もいないし、新しい人も来ないような気もするので、今日は掛けてもいいです、他の人が入ってきたら変えますけれど、と言った。それによって、店の中にきのこ帝国というバンドの音楽が流れた。その高校生ぐらいの男性は、連れてきていた男性一人、女性二人と一緒にその音楽を聞いた。話もせずに、それぞれ本を読んだりして過ごしていた。その高校生の男性の目つき、大人なんて信じてたまるか、というような気分を感じさせる硬直した挑発的な苛立たしげな目つきは私をしたたかに打った。彼はきっと、自分が何を好きであるかということだけによって、自身を定義づけ、世界を定義づけられると感じる高校生ぐらいの男性なのではないかと思うと、私は、私はいてもたってもいられなくなった。自分が愛する固有名詞だけが、自分を定義づける。その気分を、私の勝手な憶測のその気分を、私はすごく美しいものだと感じた。それは過去の自分を肯定する身振りでもあった。私は、その男性に何かCDを貸したいような気がした。こういうのを聞いたことがありますか、もしよかったら聞いてみますか、と言って何かを渡したいような気がした。だけど何か、そんな大人の手引みたいな振る舞いは私はしてはいけないような気がしたのでやめた。その男性はその男性だけの獣道を自分の手でかき分けて進むことを望んでいるのではないかと、全てが憶測ながらに思ったからだけど、その男性が10年前の私であったならば、もしかしたら喜んでその申し出に乗ったかもしれないと後になったときには思った。もっと屈折しろ、もっと思い悩めと、そう思った。どんどん固有名詞で自分の人生を彩っていけと、そう思った。その先には一つの明るい未来もないんだと、そう思った。それでもそうだとしてもとにかくその感じで闇雲に歩を進めろと、そう思った。それはほとんど、願いや祈りのような性質のものだった。10月になった。
cinema text
2013年9月27日

「強い風が吹き、ガラス壁を隔てて目の前にあるそれなりに大きな木がゆさゆさと重量を感じさせるあり様で揺れている。道を歩く人々は少し前のめりだったりして、風にそれなりに抗ってみせている。バカどもの巣窟と化したような感のあるファーストフード店で主に若い人たちが傍若無人な振る舞いを続けている。私はその店のカウンター席に座ってカタカタと打鍵を続けている。今日は休みの日で、久しぶりに店のブログを書こうとがんばっているのだけど、一度途切れた習慣というか重力というか恩寵は、そう簡単に私を回復させないで、何を書いたらよかったのか、何がこれまで書かれてきたのか、わからなくて指が動きあぐねる。大量のバンズを持った業者が扉から出て行った。そういう姿を初めて見た。
今日は休みの日で、昨夜間違って店で寝てしまい、その寝心地が悪いためにどうしても早起きになって、三文得をしたと思って早くから活動を開始した。具体的には銀行に行って両替をおこなうということだった。天気のいい日だった。おしゃれなカフェに行ってバルガス=リョサの『緑の家』を読んだ。すぐに疲れた。いくつかの物語が並行して描かれるのだけど、150ページぐらいまで行ってもいまだに誰と誰がどういう関係でエピソードの時系列がどうなっているのか、把握できないでいる。その状態で読書を続けるためには目の前に描かれる情景や行為のシンプルな強さや美しさだけが頼りで、だけど今のところ、そんなにグッと来るところもなく漫然と読んでいる。グッと来ていないことは、一つも折られていないページを見れば一目瞭然だった。
必要な買い出しをおこなった末、店に戻ってきた私たちはそのまままた店で眠りに落ちてしまい、目を覚ませば外は薄暗くなっていた。人生の黄昏時、と思って悲しくなった。
先日、やっとレオス・カラックスの『ホーリー・モーターズ』を見てきた。冒頭、カラックス、寝起きの夜中もサングラス、と思って格好いい思いをしたのち、晴れ上がった朝の邸宅から出てくるドニ・ラヴァンの姿。上がり下がりする肩の動きからその人物がドニ・ラヴァンだと確信されるが、こんなに老いたのか、こんな顔だったか、と「うわー…」と時の流れの酷薄さを思わされる。そしてそれとともに「え、ドニ・ラヴァンが資本家!?」というところでなんというか、なんか何かとえげつない気になる。リムジンに乗り込み、今日のアポの件数を運転手に確認する。
そのあと車から降りてくるドニ・ラヴァンがみすぼらしい老婆に変装してボディーガードに付き添われて歩いていき、橋のところで金を乞う姿を見ながら、「この資本家はこういう奇癖があるのだろう。ドニ・ラヴァンはどれだけ資本家になってもやっぱりこういうところがあるのだろう」みたいに見ていたら、そのあとに車を降りたあたりで、ああ、アポとは、そういう、ということがにわかに得心される。そこからはただただ七変化するドニ・ラヴァンの姿、その運動の強さや美しさに魅せられ続ければいいだけで、極めてシンプルな規則のゲームではあったのだけど、繰り返されるうちにこの職業の苛烈さがのしかかってきて、役者とは、なんという…!というところで愕然となるというか、「うわー…」という気になってくる。二つの場面で運転手がプレイ中のドニ・ラヴァンに介入してくるような場面があって、どこまでがそれで、どこまでがそれじゃないのか、というこの「うわー…」という感じ。あるいはドニ・ラヴァンの顔、どれがいったい、僕らがかつて見たあの若者の十数年後の顔、本当の顔なのか、本当の顔なんて果たしてあるのか、というなんか「うわー…」という感じ。そしてまたかつての恋人の死。全体に漂う死の予感というか死の空気。ドニ・ラヴァンもまた、クライアントの指示によって、一つのアポをこなす行程の中で本当の死を死ぬことになるに違いないのだろうという「うわー…」という感じ。これ大変な一日だよなー実際と思いながらも、彼は仕事を終えれば朝出てきた家に帰るものだと素朴に信じていたところを、あ、そうじゃないんだ、というのがわかるときのいよいよなんていう暮らしなんだ…!という「うわー…」という感じ。
行為の美しさ。俺はわりとそれを信じたいしそれを目撃するために、人間の行為の美しさ、体の運動の美しさ、表情の美しさ、つまるところ人間の存在の美しさみたいなものを目撃するために映画を見たいんだよなという思いは、ドニ・ラヴァンの疲弊した声を、夜中のリムジンたちの嘆きや諦めの声を聞きながらも、まるでなくならないわけで、いっそう強くなるわけで、本当に、えげつない、美しい、素晴らしいものを見てしまったという強い喜びを抱えながら映画館を出て店に帰ってパスタを作ったというのがその夜だったわけだけど私は良く生きたい。
まずはこのろくでもないファーストフード店を出てから酒を飲みたい。」と打ってパソコンを閉じ店を出て酒を飲むべく、どうしようかと散々、それこそ30分ぐらい悩んだ挙げ句がんばって一人で居酒屋に入ってみたけれどビール2杯と肉豆腐を飲み食いしながらひたすらiPhoneを見ていただけで、すごく虚しい気持ちになった。虚しい気持ちになったけれど妙に酔っ払ってしまって家に帰りそのまま寝た。一日があっという間に過ぎていく。今日はその次の日で夜で、休憩時間にパソコンがないことに気が付き、まさかと思ってマクドナルドに電話をするとパソコンの忘れ物があるということだった。こんなケアレスミスをするとは、と本当に驚き、盗られなくてよかったという安心よりも自分への落胆の方がずっと大きく、非常に鬱屈した心地になった。今日とて、一日は本当にあっという間に終わってしまった。何も成し得ないまま、私はどうせ死ぬのだろう。わりと気分が塞ぐ。
book text
2013年9月21日
盆栽/木々の私生活 (EXLIBRIS)
ここ一週間か二週間ほど忙しめの日々が続いているような気配があって、オムライス等の仕込みのペースが上がっていること、もっと言えばブッチャーへの肉の注文のペースが上がっていることがよく物語っているようなところがあり、電話をすれば、2キロとか1.5キロとかの肉塊をブッチャーはいつだって届けてくれる。私は太ることが今のところない体質なのでよくわからないけれども、女性の方であるとかが1キロ太ったとか2キロ太ったとかそういうことを言うのを聞くと、その赤々とした、あるいはミンチになった肉塊を思い出し、それはけっこうなところ、大きな変化であるということが実感される。ダイエットをしたい人は一度1キロとか2キロの肉塊を目で見て手で持ってみれば、きっとぞっとするだろうし、いけない、ちゃんとダイエットしなければいけない、という思いを強めることもできるだろう。ここ一週間か二週間ほど忙しめの日々が続いているような気配があって体についてもよく疲れるところが散見され、今は人的な状況によるアイドルタイムを設けているのだけど、その15時から18時までの3時間のあいだも、眠るばかりをしていて一日がすり減ってもったいない。今日もずっと眠っていた。
ここ一週間か二週間ほど、これは一週間ほどだろうか、『親密さ』の二人の男女が別々の時間に別々の場所で、それはともに飲食店で、アルバイトをする姿のことを何度か思い出した。ただ思い出すだけなのだけど、何度か思い出した。濱口竜介の新作『不気味なものの肌に触れる』は先日購入してダウンロードをしたのだけれどもまだ見ていない。LOADSHOWはとても楽しみなサイトではあるのだけど、ストリーミングで見られるといいのになと思う。1.6ギガの動画を落とすのはけっこう大変というか、時間が掛かる。
今日もその男女の、男はファミレスで、女はバーらしきところで働く姿を思い出しながら、もう一つ何かを思い出していたのだけど、何を思い出していたのか思い出そうとすると記憶がつっかえて思い出すことができなくなった。代わりに思い出したのはゼーバルトの、ロウストフトの描写だった。さびれた町の、かつて栄えたときの姿だった。都合のいいことに、12月に出来たばかりのそのスタバに行ったのは今日で二度目で、というふうに書き始められる昨冬に書かれた日記の中で引用していたので、それを読んで済ませるというインスタントなことを行った。晩年に焼身自殺を図った男からゼーバルトが聞いた、そのロウストフトの光栄の時代の描写を再度引用すると、慈善舞踏会の晩、むろん入場を許されるはずもない庶民たちが、とフレデリック・ファラーはゼーバルトに語った。百艘はくだらぬ小舟や艀に乗って埠頭の突端まで漕ぎだしていったのだと。そして波にたゆたいときには流れゆくその見物席から、上流階級の人々がオーケストラの音にあわせてくるりくるりと回るさまを、光を浴びて、初秋の霧に覆われた暗い海面の上にあたかも浮き上がっているかに見えるさまを眺めたのだった、というものだった。やはり、美しい情景だった。
ずっとラテンアメリカの小説を読んでいると、何を読んでもけっこう賑やかで、私はその賑やかさに魅了されていた節があるのだろうとも思っていたのだけど、先日読んだアレハンドロ・サンブラの『盆栽/木々の私生活』はまったく静かな小説で、その静けさはゼーバルトとも通じ合うようなたぐいのものだった。ポスト・ボラーニョ世代ということで、サンブラは1975年生まれの若い作家だけど、この二つの小説のたたずまいは本当に大好きなそれだった。特に表題作の「盆栽」は、裏表紙に「盆栽のように切り詰められたミニマルな語りから、過去と未来に広がる無限の時空間」とあるけれどわりと本当にそんな感じで、同じモチーフが幾度か繰り返されながら、静かに、ものすごく微かに、しかし確かに高まっていくようなところがあって、気がついたら息を止めながらページを繰っていた私は、どこかの場所で何かがあふれ、ほとんど泣きそうになっていたか、泣いていた。小腹が空いたのと、金を使いたくないなと思っていたことから入った騒々しいマクドナルドでの出来事だった。
フリオがエミリアについた最初の嘘は、マルセル・プルーストを読んだことがあるというものだった。読んだ本のことで嘘をつくことはあまりなかったが、あの二度目の夜、何かが始まりつつあることが、その何かがどれだけの期間続くにせよ大切なものになることが二人にわかったあの夜、フリオはくつろいだ調子の声で、ああ、プルーストは読んだことがある、十七歳の夏、キンテーロで、と言った。(…)
その同じ夜、エミリアはフリオに初めての嘘をつき、その嘘もまた、マルセル・プルーストを読んだことがあるというものだった。(…)つい去年のことよ、五ヶ月くらいかかった、だってほら、大学の授業で忙しくしてたから。それでも全七巻を読破してみようと思って、それがわたしの読書人生でいちばん大切な数か月になったの。(P22-23)
それを読みながらこの話題なら、私は嘘をつかないで済むと思って少し嬉しい気になった。ああ、プルーストは私も読んだよ。大学生のときに何年も掛けて、たしか三年ぐらいかな、読んだり、やめたり、他の本を読んだり、また他の本を読んだりしながら読んだ。しんどい思いもたくさんあったけれど、特に徹夜明けの電車に乗っているときとかに、朦朧とした頭で読んでいるとふいに何か力強いものが頭に吹き抜けてくるような感覚があって、そういう時おり訪れる瞬間を求めながらなんとか読みきったよ。どんな話だったかなんて一つも覚えていないけれどね。
それにしても、そのプルーストを巡る嘘のあとの、嘘に嘘を重ねるここのくだりは素晴らしくて、読んでいる方が気恥ずかしくなる。その気恥ずかしさは、なんというかとても好ましいものだった。気高さ、とでも言いたくなる気恥ずかしさだった。
それぞれを『失われた時を求めて』を読んだこと――というより読んでいないこと――へ結びつけていたあの打ち明けがたい秘密のせいで、二人はプルーストを読むのを後回しにしていた。二人とも、今回一緒に読むことが、まさしく待ち望んでいた再読であるかのように装わなくてはならなかったので、特に記憶に残りそうな数多い断章のどれかにさしかかると、声を上ずらせたり、いかにも勝手知ったる場面であるかのごとく、感情あらわに見つめ合ったりした。フリオに至っては、あるとき、今度こそプルーストを本当に読んでいる気がする、とまで言ってのけ、それに対しエミリアは、かすかに悲しげに手を握って応えるのだった。
彼らは聡明だったので、有名だとわかっているエピソードは飛ばして読んだ。みんなはここで感動してるから、自分は別のここで感動しよう、と。読み始める前、念には念をということで、『失われた時を求めて』を読んだ者にとって、その読書体験を振り返ることがいかに難しいかを確かめ合った。読んだあとでもまだ読みかけのように思える類の本ね、とエミリアが言った。いつまでも再読を続けることになる類の本さ、とフリオが言った。(P37)
これらの箇所だけだと、未熟でディレッタントでスノッブな感じの若者二人の鼻につく物語っぽい感じもするけれども、本当に美しく悲しく、素晴らしい短編だった。
ポスト・ボラーニョ世代、それこそあの素晴らしい短編集『通話』の最初の「センシニ」のような読後感をもたらした。それらはいずれも「私が読みながら涙を流した短編」という括りに入るものだった。
どちらも、本を読むこと、それから文章を書くことが自分をアイデンティファイする行為であると自覚する者にとっては、泣かずにはいられない小説なのかもしれない。
フリオはファミレスで働いた。エミリオはバーらしきところで働いた。二人は別々の電車に乗った。
book
2013年9月11日
「AV女優」の社会学 なぜ彼女たちは饒舌に自らを語るのか
まずもってあとがきの文章がすごくいい。これなんかは名文だと思う。
私たちの生きる街の売春がややこしいのはそれが黒い部分ばかりであるからではなく、どうしようもなくピンク色だったりキラキラしていたりするからなのである。売春にまつわる悲惨はそのキラキラであるが故の悲惨について描かれるべきだと思うし、売春を肯定する内部からの声もそのピンク色に自覚的であるべきだと思う。(P301)
なぜ今の仕事についたのか、という問いを向けられる機会はサラリーマンの時よりは確かに増したとは言えそう頻繁にあるものでもないし、日常会話の中で発せられる問いであり、答えがなんの面白みもない退屈なものであってもなんの差し支えもない。仕事を辞めたいとずっと思っていたところで、ちょうどタイミングよく話があって。それだけだ。
だいたいどんな職業であろうともそんなものだろう。なぜその職業を選択したのかと問われる機会はそうないだろうし、そもそも問う側も、そう問うてみたところで興味深い話が聞けるとはあまり期待しない。なんせ、シューカツという定型化された活動期間を経た私たちは、ほとんどの人がなんとなく、あるいは企業が選択してくれたからその職業についていることを知っている。
そういう中で、本書が取り上げるAV女優という職業はどうも特異らしい。
私がAV女優に興味を持った理由のひとつが、彼女たちの語らされる機会の多さにある。全国区で顔をさらけ出し、裸の肉体をむき出しにして、名前を持ってAVに出演する者は常に自らの性を商品化する理由を問いかけられ、動機を語ることを余儀なくされてきた。(P21)
そう言われればたしかに色々なインタビューがありそうな気がしてくる。読んだことも意識して見たこともあまりないが(早送りするため)、VTRの中や週刊誌の中でそういうことがおこなわれている様子は想像できるし、多くの職業にとって面白くもなんともならない問いでも、それがAV女優という「「名誉回復が不可能である」ほど、緩慢で大胆な(性の商品化に対する許容の)線の引きかたをする」職業であれば、十分に興味深いコンテンツとして成り立ちそうなことも、感覚的に理解できる。
本書が着目するのは、「なぜAV女優になったか」ではなく、「彼女たちはどのようにしてその流暢な語りを獲得したか」という点だ。その獲得の過程が、AV女優という職業の具体的な仕事内容とキャリアの変遷を見ていくことで浮き上がってくる。
AV女優と言ったらその仕事はカメラの前で裸になって撮影をすること、ぐらいの一面的な見方しか今までしていなかったのだけど、プロダクションに所属し、単体契約を取るためにメーカー面接に何度も回り、契約にこぎつけて向こう半年の仕事が決まり、監督面接をおこない、VTRの撮影する、ジャケット写真や広報写真の撮影をする、取材を受ける、単体から企画女優へと転身する、単体とは異なった目的のメーカー面接を受ける云々、といった具体的な業務とキャリアの流れを見ていくことはとても興味深いものだった。
そしてまた、その獲得へ至る道程には、端的に言って感動した。
最も重要と思われるのは、繰り返される動機語りが、いつしか戦略性を離れて彼女たちの勤労倫理にすり替わっていくことであるからだ。
本書を書き進めるにあたって、そのような「世間の興味」を逆手にとった戦略的語り口が、いつしか彼女たち自身に向けて発せられるようになっていく様を目の当たりにした。業務として、AV女優になる動機について彼女たちは饒舌に語る。その動機は、業務から派生して独立し、実際の彼女たちの動機として意味を持つようになる。彼女たちは一度目は業務の一環として、二度目は彼女たち自身のものとして動機を再び獲得する。そしてその動機は、実際に「彼女たちがAV女優になった動機」とは無関係であれ多少ひもづいたものであれ意味のないものだったかもしれないが、二度目の獲得によって彼女たちの働くよりどころ、「AV女優であり続ける動機」として機能しだすのだ。(P27)
結局、なんで(AVに)出たんですかって原点みたいなこと聞かれると、適当には答えてるけど、ちょっと考えもするっていうか、なんでだっけ、みたいになって。思いつかないもん、適当に言っていいって言われても。で、結局わかってほしい方向性って自分がやりたい方向性だから、そのために無理やり言ってるわけじゃなくて事実とそんなに遠くなくなってくる。最初、対インタビュー用って感じで、人のことエッチな気分にさせたりするのがうまくなりたいから、みたいなしゃべりはしてたけど、考えてみれば、そういうことのプロになっていくのもいいんじゃないかっていうか、実際にそうなんだよね(Y)。
インタビューで語られる動機は、確かに戦略的につくられたものであったかもしれない。しかし、それが事後的に内面化し、実際に彼女たちのものとなっていくことがある。ありのままを語っていたわけではないのに、事実が語れる言葉に寄り添うようになり、結果として語られる内容と現実の彼女たちの意識が一致してくるのだ。
それは、AV女優という仕事を続けるにあたって彼女たち自身が、「なぜこの仕事を続けるのか」といった問いにぶつかり、その理由を希求しだす、といった事情と、繰り返し聞かれ、自分のストーリーを語らなくてはならない日常が、同時的にあるからこそ、起こりうる現象だと言える。(P248-249)
また、語りの獲得と不可分に、彼女たちは次第にプロ意識を先鋭化させていく。驚いたのは、ほとんどの場合、受ける仕事の内容や引退の申し出などに対して強制が働くことはないらしく、彼女たちが自身の選択として、何に強制されることなく、仕事を選び、続けていく。単体契約という単価の高い仕事が終わると、自身の選択として企画という単価の低い仕事に身を移し、精力的に仕事をこなしていくようになるという。
様々な面接や現場を経験していく中で、当初彼女たちの中にもあった若さや美しさみたいなものを頂点とするヒエラルキーが消え、技術であったり受ける仕事の幅であったりなんやかなんやの、まったく一元的でない多様なヒエラルキー構造を認識し、「それなら私は海賊王になる」みたいな心境の変化、プロ意識の先鋭化がなされていく。
多くのAV女優が誰かに強制されるまでもなく、より多くの仕事をすすんでこなすようになる。ごく自然な仕事の変化の流れの中で、生活全体をAV女優としての活動にからめとられていく。その変遷を追うことは、性の商品化の渦中にあるということが一体どういった事態なのかを具体的に考える契機になるだろう。性の商品化は、確かに女性たちを夢中にさせる側面をもっている。AV女優たちが語り出すのはその「夢中になる」トンネルを幾度かくぐりぬけるからだ。その過程のなかで彼女たちは性の商品性との付き合い方をも定めていく。それはまさに、彼女たちが逞しく誇り高い存在になっていく過程でもある。(P180)
先ほど感動したということを書いたけれど、そのあたりはなんというか、私も店をやり始めて2年が経って、この先どういうふうに仕事と付き合っていくのか、何を目標にして働くのか、生きていくのか、という自問自答をぐるぐると、とても狭い射程の中で繰り返している最中だったからというのが多分あって、そういう中で彼女たちの姿を知るにつけ、「わ、なんか逞しいぞ」というので感動したのだと思う。
それとともに、私自身の経験としても、店のブログ等で「お客さんにひたすら楽に過ごしていただきたいんだよなー、そういう場所を作りたいんだよなー」みたいなことを繰り返し書いているうちに、その思いがより深く内面化していって、「いやそれほんと思ってるわ俺、しかも強く希求してるわ」みたいな驚きを覚えることがあって、そういう意志の強化みたいなものに出くわしている実感があったから、読んでいて、なんか、あー、それそれ、というのもあったのかと。
とか言いながらも、感動とか言っちゃうのはきっと私の中にあるAV女優に対するある種の偏見みたいなものと関係ありそうな気がしてちょっと気が引けるというか、とても程度の低いギャップ萌えというか、知らなかったけどがんばってるんだなーすごいなー感動したなーとか言ってるんだろ自分みたいなところもあって、なんというか、その、あの…という口ごもってしまう感じではあるのだけど、まあほんといろいろと、ここに挙げたことに限らずいろいろと面白かったしすごくよかったです。がんばるぞー、僕もよくよく考えるぞー、しっかりと働くぞーという思いを強くした次第。(俺はこの本をキャリア論として読んだということだろうか…)
本書を読んだのは、今フアン・カルロス・オネッティの『屍集めのフンタ』という、架空の街サンタ・マリアにおける売春宿を巡るあれこれのお話を読んでいるからという理由ではなくて、大学のゼミの先輩である著者の鈴木さんが本書を送ってくださったからというだけなのだけど、だから私は売春の是非を巡る議論やセックスワークに関する議論についてまるで知らないし、強く興味を惹かれることもないのだけど、冒頭に引用した箇所を筆頭に、鈴木さんの文章には、本書でもしばしばその語が出てくる「逞しさ」を感じずにはいられなかった。実感やアクチュアリティがそこここに強く溢れている感じで、とにかくなんかかっこよくてぐっとくる。のでいくつか引用。
性の商品化を問題視する議論の多くが、強制/自由意志であるというところに異様なまでに執着することに私は懐疑的だ。彼ら/彼女らが語る「売春(あるいは売春婦)」につきまとう不幸や悲惨は、この街の女子としての私たちの日常とは別のところにある気がしていた。それは何かについて重要な指摘や枠組みを提供しているはずなのに、私たちについて語ってはいないような気がした。私は、彼ら/彼女らの語る売春婦を空想上に仕立ててその枠組みの中で遊ぶよりも、この地続きの先を見たい。私たちが慎重にしろ無防備にしろ線を引きながらつきあってきた自らの商品性と、私たちを内包する街について知りたいと思った。(P12-13)
私は性的な女の身体を持つ者の立場で本書を綴る。(…)私は今でも、女の身体をもって東京で生きていくためには、性の商品性と向き合わなければならない場面はいつでも起こりうるし、そこを生き抜かなければ幸福が訪れないと感じている。(P37)
不安や経済的苦境やつまらなさや、そんなものがあっても決して親の悲しむようなことをしないで良いオトナになる女たちもいる。そんな女たちのことも私は高潔だと思う。けれど、そうなれない女たちがぶりぶりの服をきて上目遣いできらきらの画面で動機を語る姿もまた、同じように私を惹きつける。魂が汚れようが汚れまいが、後ろ指を差されようがちやほやされようが、キラキラした性の商品化の現場に居続ける彼女たちもアンビバレントな東京の女の子たちの姿だ。
女が身体を売る現場で働く男たちを人は時に売春婦以上に蔑視する。女衒を攻めるほど私たちは初じゃない。子供ながらにバブルもそのはじけた虚しさも冷めた目で見ることを強要されてきたのだ。私たちは資本主義の申し子だ。ピンサロ嬢が以前私に言った。「私たちは商品だから、大事にしてもらえるよ、そこにつけこんでうまくやればいいんだよ」。値段のつくものに人がむらがる、そんなことを別になんとも思わない。彼らもまた必死に生きているのだ。(P302-303)
全然しゃべったことのない先輩なのだけど、鈴木さん、かっこいいです!と言いたい。
book
2013年8月28日
機械との競争
先日更新した店のブログで、私たちの店においてはいかに人間らしく、つまりいかに知性的に立ち振る舞うかが肝要だと考えている、みたいなことを書いたときにこの本に触れ、これからは非情な勢いで人間の労働が機械に取って代わられるのだろうけれども、飲食店というのはわりとそういう意味ではいいポジショニングかもね、ということを書いたのだけど、実際どうなんだろう、と思って読んでみた。大体において、「まあ、そうだよね」ということが書かれていた。読後にググったところ議論としては目新しいものは何もないみたいな読まれ方もしているんだなというのは知ったけれど、そういった知見を持たない私には面白く読めた。
曰く、これまでの労働の機械化は次なる雇用を生み出していったのだけど、IT技術の進歩が速すぎるために新たな雇用の仕組みができる間もないため、けっこう、労働する人間にとって過酷な状況になっているしなっていくよね、ということだった。
コンピュータは、この先さらにパワフルに、さらに高度になる一方である。そして仕事、スキル、経済全体に、これまで以上に大きなインパクトを与えるようになるだろう。いま私たちが直面している問題の根本原因は、大不況でも大停滞でもない。人々が「大再構築」の産みの苦しみに投げ込まれているということである。テクノロジーは先行し、人間のスキルや組織構造の多くは遅れを取っている。(P23)
IT技術の進歩の人間の予想を上回る速さを物語るエピソードとして車の無人運転が上げられていて、2004年ぐらいの段階では、運転行動をプログラミングするために必要な情報は膨大すぎてそうとう先にならないとコンピュータで全部を処理することはできないだろう、という認識がされていたのに、その後たった6年で、高い精度でそのことをグーグルがやってのけちゃった、びっくり、ということだった。また、知識労働的なものにおいても、今では一台のコンピュータで弁護士500人分の仕事をやってのけちゃうことができるようになった、ということだった。すごいね。
そういう中で、機械に任せることは今のところできないし、わりと難しい分野だよねと言われているのが、肉体労働と何かしら創造的な仕事ということだった。
肉体労働に関しては相当高度な認識能力を必要とするらしく、今のところその点においては機械はだいぶ遅れを取っているらしい。人型ロボットみたいなものを見ても、なんだ、まだこんなものか、と思ったりすることからなんとなく納得。ただ、この分野についてはどうなんだろう、その認識能力とやらが非情な速度で発達していきさえすれば取って代わられそうな気がする。人型ロボットが道路工事をしている様子は、けっこう容易に想像がつく。
そしてもうひとつが創造的なお仕事ということで、何かしら芸術的な事柄であるとか、ビジネスアイディアの創出であるとか、そういった面では全然ダメ、ということだった。
要するに「人の心を動かす」みたいなことはそう簡単には機械化できそうにない、ということだと思うのだけど、そこが飲食業を営む私にとってはわりと肝で、やっぱり、接客を大事にしていかないとな、と改めて思うまでもないのだけど思った。というか、接客が重要視されない限り、飲食店はきっと簡単に機械化され得るだろうなと。例えば吉野家とかピザーラで機械がすべてをまかなったとしても(マンションの扉を開けたらロボットがいたら最初はけっこう面食らうだろうけれども)、そもそも接客が期待されていない以上、たぶん満足度みたいなものが今より下がることはない気がする。
人間がいないと得られない安心感、人間じゃないと感じられない感情というのを提供していくこと。もうこの人が作ったものじゃないと満足できないというぐらいに美味しいものを出せるのでない限り、そういう人間ゆえのみたいな価値を提供していくことしか、飲食店が生き残る術はないように思える。
それはつまり、芸術(この言葉は使いたくないけど他になんて言い換えたらいいのかわからないのでとりあえず)が、クオリティの高低によって良し悪しを定義付けられるものではないのと、接客というものも同様なんじゃないかということだ。というか、何かの高低がスコアリングできるフィールドにいる限り、いつか機械に取って代わられる気がするので、その軸からいかに外れてみせるか、いかにファジーな、ノウハウ化できないもの、陳腐化しにくいものを体得するか、ということが大事なんじゃないかと。
私や彼女がそれをどこまで表現できているのかはおぼつかないにしても、そういうことじゃないかと思うんですよ、接客って超スペシャルなことですよ、ということは一緒に働いている人たちにも伝えていかないとなあと強く感じた次第。(真面目)
面白かったところ:アメリカにおいて、所得の中央値が下がっている一方でGDPは増加している。つまり富の一極集中化が進んでいるとのこと。学歴という点においても、この本の中では「高校中退、高卒、大卒、一流大卒、大学院卒」の賃金の推移がグラフ化されているのだけど、IT技術の進歩に伴ってすごい勢いで所得格差が開いているのだという。グラフを見ていて面白いのは、1980年前後ぐらいだと、大学院卒だけはわりと高いところにいるのだけどその他の学歴はほぼ拮抗していて、年によっては大卒がいちばん低いところがあったりする。「へー、そりゃあなんともまあ」という感じだった。
そうなんですかということろ:で、教育が大切というのが上記のことでわかって、そこで本書がおこなう提言というのは教育のさらなる充実というところなんだけど、肉体労働がまだいける、創造的な仕事が全然いける、という分析と、教育の質の向上っていうのはどこまで相容れるものなのかが私には説得的に響かなかった。高等教育の充実とかよりも、それちょっと機械化するメリットどこにもなさそーみたいな超ニッチな分野をいかに開拓していくかの方が多くの人が生き延びていくためには必要なんじゃないかと思った。と思ったら書いてあった。ハイパースペシャリゼーションの時代、ということらしかった。でもそれならやっぱり、教育に関して「遅れを取る」とかそういう表現が出るのは変というか、遅れとか進みとかじゃなくて、多様性とかいうとバカみたいかもしれないけれど、耳だけなぜか5メートルぐらいあるみたいな局所肥大的な能力の伸ばし方を推奨していく方が理にかなっているんじゃないか。ただ、どんなことをやっても機械化の流れからこぼれ落ちてしまう人は出てしまうと思うのだけど、そういう人たちをどうフォローするのか、本当にフォローなんてできるのか、そのあたりの答えがよくわからなかった。
それにしても(物質的に)読みにくい作りの本だった。洒落た作りのつもりなのかもしれないけど、紙が厚くて片手で開いていたら手がつるかと。
最後に。引用されているNASAの報告書の文章がとてもいい。
「人間は非線形処理のできる最も安価な汎用コンピュータ・システムである。しかも重量は70キロ程度しかなく、未熟練の状態から量産することができる」(P54)
安価な汎用コンピュータ・システム、重量、量産。一文字の無駄も隙もない、なんとも言えないジワジワした可笑しみを誘う素晴らしい文章。
book
2013年8月28日
巣窟の祭典
フアン・ルルフォ(1917年)、カルロス・フエンテス(1928年)、セルヒオ・ピトル(1933年)と、メキシコ生まれの小説家の作品をここ1ヶ月ぐらい、特に国は意識してはいなかったけれど立て続けに読んでいて、ルルフォでは乾いた土地の埃っぽい匂いと農民たちのなんかどう見てもどん詰まりだよねという感じを、フエンテスやピトルでは社交界の人たちの片腹痛いスノッブさや凋落の悲哀みたいなものを目撃し、メキシコいろいろあって面白いねと読んでいたのだけど、今回読んだ『巣窟の祭典』は、大学でスペイン文学と併せてマーケティングを専攻していたフアン・パブロ・ビジャロボスさん、1973年生まれの若い作家のデビュー作と2作目を合わせた作品集だった。
2011年8月、それから2012年9月にスペインで出版されたものが2013年2月に邦訳されるこのスピード感はとても好ましいし頼もしいなと喜んだ次第。
表題作「巣窟の祭典」も次の「フツーの町で暮らしていたら」も、扱われている題材は麻薬戦争の惨たらしい殺戮や、家族の失踪や土地からの追放といった、べつだん楽しいものでも笑えるものでもないのだけど、それを語る調子は、どんな状況でも冗談を言っていないと気が済まないというような軽やかなもので、この軽さはこれまでラテンアメリカの小説で読んだことのない類のものだったので、新鮮だったし面白かった。「フツーの町で暮らしていたら」のある場面(それは特に目新しいものではないにせよ素晴らしく痛快で、「そうだ!それだ!そのとおりだ!」と無闇な快哉を叫びたくなる場面だった)から単純に思い出しただけだけど、前田司郎ぐらいの軽やかさがあって、べつだん、私が何かと闘っているわけではないにせよ、過酷だったり残酷だったりする現実と闘おうとするときにユーモアがそれに対抗するための強い武器になるのだよねと、再認識というか学んだというか、だからべつだん何かと闘っているわけでもないから学ぶも何もないのだけど、ユーモアっていいよねっていうところだった。ユーモア、軽さ。ヴォネガットのような。サローヤンのような。要は、すごく好ましかったということだった。
2篇いずれも、宮殿や土地に幽閉された少年が、アクロバティックな展開によって外の世界を見に行く物語だ。名前を変えたり、あるいは巡礼者の列に加わることによって。父親たちは、あまり息子たちに外の世界を見させたくないらしい。
「フツーの町で暮らしていたら」の父親が発する言葉がとてもいい。
「見たか?ラゴスと同じだ」
父は言った。世界を矮小化しようとする企みを暴露した。今や彼によると、あろうことか、ラ・チョーナが世界を代表していた。(…)
「何のために行くんだ?」
父は繰り返し僕らに言った。「全部同じだ。ラ・チョーナに行っただろ。どの町も一緒だ。大きいか、小さいか、汚いか、いくらかきれいか、でも、どれも同じだ」(P132)
あることが起き、基盤を揺るがされた父親を射抜く息子の言葉がとてもいい。
「こんなことあるはずがない」父は、僕らを迷いから覚まそうとあたふたした。
「どうしてだよ?」
「どうしてありえないの?父さん」
僕らはそういう国に住んでるんじゃなかったのか?いつも幻想的な素晴らしいことが起こる国じゃなかったのか?死者と会話する国だったんじゃなかったのか?ここはシュルエアリストの国だってみんな言ってたんじゃないのか?(P240)
「巣窟の祭典」はこういうトーン。
ニュースの最後で、男のリポーターが神妙な顔つきで安らかにお眠り下さいと言った。バカじゃないの。今この瞬間、彼女はトラのお腹の中でぐちゃぐちゃになっているっていうのに。その上お腹の中にいるだけではなくて、消化が終わったら、しまいにはトラのフンになるっていうのに。体もないのにどうやったら安らかに眠れるっていうんだ。もし安らかに眠れるとしたら、それは左足だけだろう。(P29)
とてもいい。
book text
2013年8月26日
ここのところまかないでパスタを作ることが多く、何を作ってもやたらに美味しくて、いったいなんなんだろう、この美味しさは、と愕然としていたのだけど、そうなってくると今度は「基本を、学びたい」みたいな妙な探究心が私にしては珍しいことに芽生え、本屋に行って『落合務シェフのイタリアン』なるレシピ本を買ってきてまずはトマトソース、と思ってトマトソースを作った。それを使い、ブカティーニはないのでスパゲッティで、アマトリチャーナ的なものを作った。アマトリチャーナはブカティーニを使ってこそ、というもののようだからスパゲッティの時点でもはやそれじゃないような気もするし、グアンチャーレという、豚の頬肉の塩漬け的なものを使ってこそというもののようだからベーコンの時点でもはやそれじゃないような気もするので、もはやトマトソーススパゲティという感じだったけれど、美味しかったし、レシピ本で「ブカティーニのアマトリチャーナ」という料理名を見たときに彼女が言った「のしかわからないね」という発言はとてもよかった。本当に、のしかわからなかった。でも散々ググったりしたあとの今なら大丈夫。ブカティーニは穴の開いたパスタの名前、アマトリチャーナは町の名であるアマトリーチェから。今ならそれがわかる。これが進歩というものだろうか。
そのあとは同じくトマトソースを用いたプッタネスカ的なものを作ったけれど、プッタネスカはその名称が娼婦風という意味である、という以外にどう定義されているのかをまだ調べていないので、私が作ったものがどこまでプッタネスカであるのか、わからないでいる。
次はラグーを作りたい。先日なんとなくのやり方で作ったボロネーゼがやたらに美味しかったので、落合シェフのレシピを使ったらそれ以上に美味しくなるに違いないと考えると、それはいったいどんなに美味しいものなんだと、期待がやたらに膨らむ。ちなみに先日適当に作ったボロネーゼは冷蔵庫にあったという理由だけで長ネギやミョウガといった香味野菜を加えてみたもので、これは我ながらに妙案だったように思われる。なお、今年のフジロックで一番おいしかったのはヘヴンの太陽食堂のなんちゃらのラグーパスタだった。やたら美味しかった。
昨日、店の地下で平賀さち枝のライブがあった。平賀さち枝さんのライブがあった。たくさんの記憶を想起させるような、不思議で、素晴らしく魅力的な歌声だった。歌声も、話し方も、話していることも、異様な存在感を持っていて、それを聞き続ける2時間はすごくいいものだった。
それはそれとして、私が感心というか、いいよねと強く思ったことがあって、それは今回のライブを企画したのが呼び屋でもなんでもなくてただ平賀さんの音楽が好き、それを人々に聞かせたい、と強く思っただけの、音楽業界とかまるで関係のない一人の若者だったということで、そういうオーガナイズのあり方は、とても健全で、とても好ましいものだと感じた。こういう動きは本当に、たくさんあっていいものだと思う。私もいつか何かそういった「これを聞かせたい!見せたい!岡山に来てほしい!」みたいなものをやりたいし、そういう人がたくさん、意思表明したらとてもいいなと思っている。例えばギャラが10万という案件のときに、「それはもうぜひ!」という人が10人集まれば、1人1万円の負担でその催しは実現できる。お客さんがちゃんと入ればペイもできる。1回のリスクが10万だとさすがに結構あれだけど、それが1万とかまで下がるのであれば、サステイナビリティという点でもいいと思う。とかなんとか、サステイナビリティとか言っちゃう感じがあれだけど、そういう打算めいたものとは正反対にある、今回の平賀さんのライブを企画した方の熱意みたいなものは、本当にとても素晴らしく大切なものだと感じた。
本、7月と比べれば完全に低調で忸怩たる思いの中、読んでいる。ルルフォのあと、長い時間を掛けてセルヒオ・ピトルの『愛のパレード』を読んだ。そのあとホセ・ドノソ『境界なき土地』も。
『愛のパレード』の、推理小説の結構を取りながら解決を放棄するようなあり方というのは私にとってはとても魅力的なあり方で、そういうすれすれ感、宙吊りの時間の愉悦みたいなものって最高ですよねと、頭では思っているのだけど、いざ読んだらモヤモヤだけが残るというとても相反することになった。答えほしい。答え、ください。という。というか、答え、とは確かに思いはしたのだけど、たぶん私は『愛のパレード』のわりとスタティックな、ただただ人が語りまくるという、身体性に乏しい文章に嫌気がさしただけだったのだと思う。これがとてもダイナミックで、人が動く、動く、体が、動く、みたいなものがあれば、答えとか解決とか度返しにした楽しみを覚えられるはずだと思うのだけど、描写がその喜びを与えてくれない場合には、解決が必要とされるのだろう。『愛のパレード』は私にとってはいささか退屈な読書となった。
一方で『境界なき土地』は面白かった。勝手にもっと何か凄惨で劇的なことが起こるのかと期待していたのだけど、その期待は裏切られたのだけど、どん詰まりの人々の息づかいや、土地の荒廃や、雨の匂い、クラクションの騒々しさ、そういうものが充実した描写の中で立ち現れて、やはり、小説を読む私にとっての喜びはこの、要するならば時間と呼べるような、そういうものを感じることなんだろうなと思った。
今はフアン・パブロ・ビジャロボス『巣窟の祭典』と、フアン・カルロス・オネッティ『屍集めのフンタ』を読んでいる。どちらもとても好ましい印象。特にビジャロボスの表題作はすごくよかった。麻薬王の息子の少年のひとり語りで、一足でアフリカまで飛ぶそのダイナミクスさは、アフリカという以外何も共通点はないけれども先月に見たミゲル・ゴメスの『熱波』を思いださせたりもした。『熱波』は全然乗れなかったのだけど。ユーモアと残虐さ。好ましい同居。
電源が3%になって消費電力でどうのこうのというメッセージが現れたのでこれで終える。と打ってから更新するまでに1%まで来たので電源につないだ。
book
2013年8月6日
燃える平原 (叢書 アンデスの風)
レミヒオがおれの前から退いたとき、麻袋に刺しておいた皮針は、月のこうこうとした光をうけてきらりときらめいた。どうしてだかわからねえが、その長い針は、不意におれのココロをとらえた。だもんでレミヒオ・トリコがそばを通るとき、おれは針をさっと抜きとって、まようことなくやっこさんのヘソのすぐわきのところにぐっと刺しこんでやった。はいるところまでぎゅっと刺しこんで、そのまま手をはなした。
しばらくするとレミヒオは、腹痛におそわれたときみてえに体をふたつに折りまげた。そしてけいれんを起こしながら、すこしずつ膝を折り、地面にすわりこんじまった。顔からは血の気が失せ、その目に怯えの色がうかんだ。
やつは手斧をふりかざしておれにおそいかかりてえとでもいうように、一瞬立ちあがるそぶりをみせたが、あきらめたのか、何をしていいのかわからなくなっちまったのか、とにかく手斧をはなして、またうずくまっちまった。
そして体の調子がよくねえときみてえに、その瞳にはだんだん暗い影がさしはじめた。あんなさびしげな目は、ひさしく見てなかったもんで、やっこさんがひどくかわいそうになっちまった。それで、ヘソのところから針を抜いて、もうちょっと上んとこ、心臓のありそうなあたりに、針を刺しこんでやった。心臓はたしかにそこにあったみてえだ。やっこんさん、首を刎ねられたニワトリみてえに、二、三度身をふるわせたきり、しずかになった。
おれがレミヒオに話しかけたときには、すでに死んでたんだろう。
「なあ、レミヒオよ、悪いけど、おれはオディロンを殺ってねえぜ。アルカラセの連中がやったんだ。そりゃ、やつが殺されたとき、おれも近くにいたけど、おれが殺ったんじゃねえよ。(…)連中はとつぜんオディロンにおそいかかって、ナイフを抜いて、兄貴をそれこそめった切りにしちまった。オディロンはそうやって殺されたんだ。これでわかってくれたとおもうけど、兄さんを殺したのはおれじゃねえ。おれはぜんぜん関係ねえんだ」
死んじまったレミヒオ・トリコに、そう言ってやった。(P27-28)
短編集。先日読んだ『ペドロ・パラモ』とこの短編集がルルフォの作品のすべてなので、全部読んじゃったことに。
別段メキシコにはまっているわけでもないのだけれども、カルロス・フエンテスの『澄みわたる大地』を先月末に読んで今日からはセルヒオ・ピトルの『愛のパレード』を読み始めたのでメキシコの中をうろうろしていることにはなるのだけど(そのあいだにアルゼンチンのルイサ・バレンスエラ『武器の交換』を読んだけどこれは全然楽しめなかった。アルベルト・ルイ=サンチェス『空気の名前』も駄目だったし、斎藤文子さんが訳したものは苦手なのかもしれない)、メキシコ都市小説の原点と言われる『澄みわたる大地』、そして30ページぐらい読んだ感じではその流れの先にあるのかもしれないっぽい『愛のパレード』とはルルフォの描く世界はまるで異なっている。同じメキシコなのか、というぐらい違う。ルルフォの世界には都市的な洗練などまったくなく、冒頭の「おれたちのもらった土地」は、まったくの荒涼の乾ききった土地を埃まみれの顔をしたぶっきらぼうな言葉遣いの粗野な男たちが重い足取りで歩き続けるというだけの話(なのにやたらに面白い)だけど、全体にそういう感じ。読んでいるだけで喉が乾いてくるほどに(夏なので)、埃っぽくて、乾いている。この世界にはコロナビールなど存在していないし、自身の死を恐れることはあっても他者の死は取るに足らないもののように扱われる。生きるための条件であるかのように、暴力がそこここで振るわれる。そこに大きな感情が伴う必然性はないらしい。読んでいても、何がどうしてそうなったみたいな疑問を抱く余地もなく、ああ、殺しちゃったんだね、そうですよね、という、もうそれでしかないという納得を平然とし続けるしかないような、そんな感覚に陥っていく。
どの短編も異様に充実していて、とてもよかった。
それにしても、『澄みわたる大地』に添付されている年表を読んだときにメキシコの歴史全然わからんなーと思って、今あらためてウィキペディアでメキシコ革命の流れを読んでみたのだけどやっぱりさっぱりわからない。勉強したい。(何のためになのかさっぱりわからないけど)
←
→