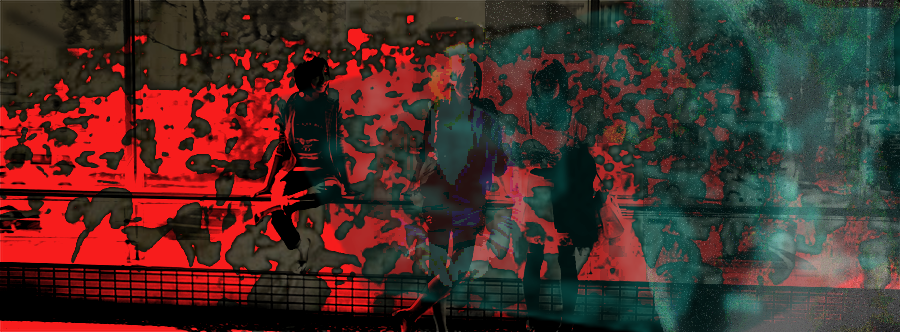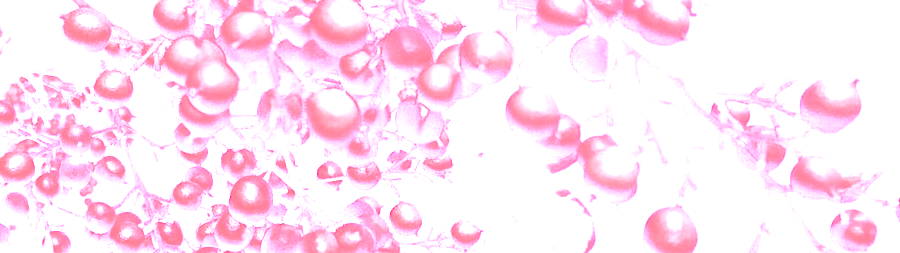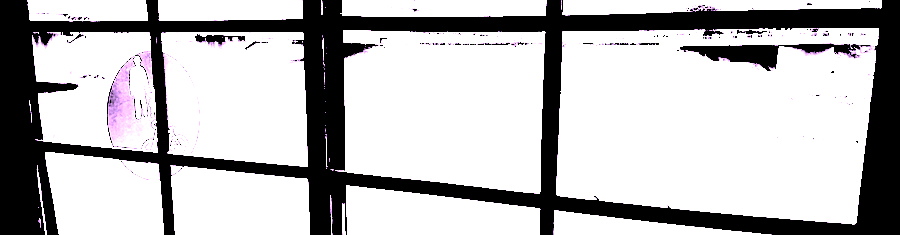text
2013年12月31日

23日に営業を終えた一週間後、私が本を読んでいることになどまるで構う様子もない母は、何度も、最近あった出来事等々を私に話しかけてくる。ストーブが焚かれた部屋はそれなりにあたたかく、外に面した窓ガラスだけでなく、廊下に面した扉のガラスも曇っている。父はダイニングテーブルで手帳を開いているのだか、年賀状を何かしているのか、わからないが何かしている。私に話しかけることに満足したらしい母はコタツで本を読みながら、眠そうな声をあげたので、うとうとしている。今日の午後に実家に着いてからの私は佐々木敦の『シチュエーションズ』を読んでいたが、それまでは電車の中の2時間、それからカフェでまた2時間、ボラーニョの『2666』を読んでいた。
そのカフェは、夏に田舎に帰ったときに寄り、父が温泉に入っているあいだに行ってこようと行ったが、満席で、待っていたらもう戻らなくてはという時間になったのでテイクアウトでジュース買って帰った、といういわくつきのカフェであり、同日朝にその姉妹店に行ったところでものすごくよかったのででは本店というところで希求していたのだけれども、今回はすんなりと入れた。
私はその場所をこのうえなく好きになったらしく、これだけの人気を得ながら、これだけの好ましい状況を維持させているものはなんなのか、その秘密を知りたくて、というのは半ば嘘で(ということは半ばは本気ということらしい)、好きになったから、この機会にもう一度行きたいと思っている。元旦はさすがにとは思うけれど、2日の昼過ぎなど、どうでしょうか?
『2666』は24日の朝に丸善で買い、行く先々で、少しずつ読み進めている。過剰な期待を抱いていた通り、過剰に楽しい。小説!という感じで大喜びで読んでいる。わざわざ読書用のノートを買ってあれこれ書き写したりメモしたりしながら読んでいる。今は第三部が終わり、第四部「犯罪の部」が始まるところだ。途方もなくワクワクするじゃないか。ワクワクするから、いつでも話しかけてこられる可能性のある母の覚醒中はやめて、静かに読むことに集中できる、母の睡眠中に読もうとして、今この家ではまだ開いていないということだった。
この家は、私は実家と言ったらいいのか田舎と言ったらいいのか扱いが難しい気がしているのだけど、祖母の家、というのが通りは一番よさそうなのだけど、今は普段は誰も住んでいなくて、そもそも、私が小ニぐらいのときに建て替えられて以降定住したのは祖母ですらなく、祖母の妹だか姉、つまり大叔母か大伯母だけで、祖母は建て替えが終わる前に亡くなったのだった。祖母の家だったら通りはいいけど実態は違い、大伯母か大叔母の家だったら実態は近かったけれど問いを誘発することを避けられず、大叔母か大伯母は、祖母のように慕っていたし、孫のように可愛がってもらっていたから、祖母といってもまるで差支えのない存在なのだけど、彼女がなぜ結婚しなかったかについてはよく知らず、戦争のため行きそびれた、という漠然としたことしか聞いたことがないのだが、かつて納戸にあり、いま岡山の私の家の隅のダンボールで眠り続けている世界文学全集は、彼女が買ったものらしかった。私は彼女が本を読んでいる姿はあまり見た記憶がないが、読書がとても好きだったということだった。私は世界文学全集は重すぎて、ダンテの『神曲』と、カフカのどれだったかと、を読んだぐらいで、あとは眠っていた。大伯母というか大叔母というか祖母みたいなその彼女は父が建て替えたその家に一人で住み、2階建てで全部で7つか8つ部屋のあるその家にたった一人で7年か8年か住み、私が高校生のときに脳卒中か何かで風呂場で倒れて以来、病院で寝たきりのまま生きている。言葉を用いて会話するような類のコミュニケーションはもはや取れないまま、ずっとそうしている。何年も見舞いにも行っていない気がする。
この実家というか田舎というかに来る前に、友人の家に2泊お世話になり、昨夜は鍋をして、くつろいだ。他人の家であり、昔からの友人一人ならまだしも、以前一度会ったことのあるだけの彼の彼女と二人暮らしの家であり、そういう中で、ああいったくつろぎを感じて眠り、すっきりと目を覚ます、風呂借ります、布団干します、コーヒーありがとう、皿洗います、トイレ借ります、洗濯だなんてそれじゃあお言葉に甘えます、そんなくつろぎの中で時間を過ごすことができるだなんて、私にはわりと、感動的な出来事だった。鍋をつつきながら、二人とあれこれと話していると、その団欒の中にいると、私は何度か、ほとんど泣きそうにすらなったものだった。
この数日は涙もろいのかもしれなかった。今日も、その素晴らしいカフェで本を読んでいたところ、一時間ぐらいが経過したときだろうか、店員の方が近づいてきて、よろしければ、みたいなことを言ってデスクライトみたいなやつを点けてくれた。最初から点けておけば、みたいな反論がありうるのはわかるけれども、私はその親切というか気配りに、何かほろりとやられそうになったものだった。「あのお客さんずっと本読んでるな、あ、あの電気つけたらもっと目に」というような考えが店員の方に浮かび、それでそろそろと近づいてきたのかと考えると、私はそれはとても好ましいものだと感じたものだった。
あるいは昨日だったのか、あれは一昨日だったのか、昨日か、ユーロスペースに行き鈴木卓爾の『楽隊のうさぎ』を見ながら、どこらへんからだろうか、主人公の男の子がちゃんと練習し始めるあたりからだろうか、違うな、ティンパニーの3年生が(あの3年生の存在が本当に素晴らしい!)彼に何やらをやらせたいと先生に相談して(あの先生というか宮崎将の表情が終始素晴らしい!)、それで全体練習をするくだりあたりからだろうか、あの3年生がリズムを叩きながら指導するあの感じからか、私の涙腺はどうかしたみたいに、少し刺激があったらすぐに泣いた。最後は、嗚咽するんじゃないかというぐらいに泣いていた。
中学の吹奏楽部の映画で泣かないわけがないので当然で、誰かが一生懸命であること、大きな声あるいは音が発生すること、その二つが揃うぐらいで私はたぶん涙腺ということで言えば決壊するような仕様だから、泣くのは当然なのだけど、だから、この手の題材のものを見るときに、泣いたかどうかはよかったかどうかの判断材料としては弱いことになるのだけど、でも映画の前で泣くことは私の中でわりと正義だからそれで手放しになってもまるで構いもしないのだけど、でもやっぱり『楽隊のうさぎ』に関してはそれだけではないように思っていて、というか誰かが一生懸命であること、大きな声あるいは音が発生すること、子供がすごくいいこと、その三つが揃ったらもうどうしようもないわけで、子供たちが、どのぐらいの素人度の子供たちなのかはわからないけれども、子供たちがことごとくに本当に信じられないぐらいにそれぞれがそれぞれにちゃんと存在を屹立させていて、どこを見ても、まったく見たことのない表情があるような気があって、そして途方もなく美しいことに彼らは撮影期間を通して本当に楽器を操る技術を成長させていて(成長の先の美しさと同時に、あるいはそれ以上に、最初に手に取る時のおぼつかなさが画面にしっかりと定着させられているということが感動的だった。握り方逆じゃん!というあの子が!というそれというか)、そして身体的にも成長していくという事件に遭遇し続けていて、私はその途方もない美しさに圧倒され、涙を流し続けていたような気が今している。
一年の最後にいいものを見られた。私は電車を乗り継ぎ、酒を買って友人の家に帰ると、ただいまと言った。
24日から3泊で彼女と奈良や京都を遊び、そのあとは友人と会って飲むばかりした。映画は昨日の『楽隊のうさぎ』のほかは、ジム・ジャームッシュの『オンリー・ラヴァーズ・レフト・アライヴ』を新宿武蔵野館で、ソフィア・コッポラの『ブリングリング』をシネマカリテで見ただけだった。年明けはカサヴェテスを見たいと思っている。
本を読むか、それ以外は友だちと会って飲むばかりした。私はその事柄、その時間がとてもうれしくて、友人というものの存在を希求していたことを、それは前から知ってはいたけれど、希求していたことを、ただただ実感するのだった。野放図に私は言葉を発し続けていたような気がした。そうすればビールも進んだし、胃の調子はそこそこだった。2週間分の胃に関する薬を医者から処方されているので、安心だ。それよりも、3泊目に京都のゲストハウスに泊まった翌朝からか、今年ずっと出ていなかったアトピーが顔限定で出たような感じがあり、最初の数日は持っていた保湿剤を塗ってしのいでいたのだけど、これはしんどくなったらたいへん気分を害すると思い、薬局でステロイド(強さのレベルはミディアム。顔に塗るのがよくないことはわかっているが、塗布範囲を限定的にすること、それから湿疹が収まったと判断したらすぐに塗布を中止すること)を買った。それを塗って、いくらか落ち着いた気がした。
奈良は二人とも中学生の修学旅行時以来だから初めてのようなものだったし、どんなイメージも持っていなかったのだけど、ひなびたところで、ひなびたところだけど行くに値するような魅力のある店は徒歩圏内にいくつもあり(徒歩圏内と言ってもずっと歩いていたから(地図上で)下から上で40分とかは徒歩圏内としているので遠いかもしれないけれども)、いい町だと思った。たくさんの個人商店があり、ろくでもなさそうな店もたくさんあり、これはきっと出店のハードルが低い、地価が安いのだろうなと思った。いい店はとてもよかった。
京都は喫茶店とか本屋とかに行った。東京でも本屋とかに行った。本屋はいつだって楽しかった。ガケ書房ではboidの樋口さんの映画評のやつと、たしかやはりboidから出ていた瀬戸なつきの嘘つきなんちゃらにまつわる小さい本と、荻窪の6次元の方の本を買った。6次元の方のやつを読んだ。「つなぎ場」みたいなことが書かれていて、つながる系の言葉に過敏に反応する私はもう絶対に苦手というか苦手なんだろうなとは思いながら、東京はカフェ化しているみたいな目次の言葉がちょっと気になって買ったのだけれども、やっぱり総じては苦手だった。考え方レベルではなるほどなるほどと思ったりも確かしていたのだけれども、たぶん言葉の使い方レベルの苦手さだと思うから、そういうことはすっ飛ばして意味内容を吟味して「ふむふむ」とか言うべきなんだろうなとは思うのだけど、やっぱり苦手意識を感じてしまうのだった。それにしても最近は店をやっている人の本をよく読んでいるけれど、B&Bの方のやつが断トツで面白かった。
そのB&Bには夕方ぐらいに行ってみたらイベント中で、半分しか入れず、半分までは入れたから御の字かもしれないけど(おんのじってこの漢字なのか。てっきりの恩の字だと思って、意味もそういう意味合いで使ってしまっているのだけど、もしかしたら違うのだろうか。現在このPCはインターネットにつながっていないため、テザリングすればいいのだけど今は億劫のため、調べるのが億劫なため)、向こう半分は小説とかが確か前行ったときはあるエリアだったからそちらに行けないのは残念なことではあったのだけれども佐々木敦の『シチュエーションズ』と松岡正剛の『知の編集術』とオリヴィエ・アサイヤスの自伝めいたものを買った。
松岡正剛のやつを読んだ。「編集ってなんだか大変そー」と思った。今わりとそういうことにはとても興味があるのかもしれなかった。何かを編集すること。それはたいへん出来たらいいなと思うことの一つだった。来年はそういうことをがんばるぞ、とか思うのだろうか。
一年、というものを区切りとして扱うことに対して私はバカらしいとずっと言っていたというか去年なんかはそういうたぐいの発言が散見されていた気がするのだけど、今年はわりとそういうひねくれたものがないみたいで、今年はこうだったら、来年はどうなることか、みたいなものがわりと素直にあるらしい。今、改めて自分が打鍵する音を聞いていたらこんな速さでタイピングできるなんて人間って捨てたものじゃないよな、と思った。人生というものが思ったよりずっと楽しい、と友人が言った。
book text
2013年12月18日

ヒップホップが引き続き私のなかで最も生々しいものとして響いているわけだけど、今のところ12月25日発売予定となっているFla$sbacksのfebbのソロアルバムがとびきりに楽しみであり、と思って改めて2Dclovicsというヒップホップ情報のサイトを見てみたところ、「12月25日発売」にも訂正線が引かれており、どうなったのだろうか。発売未定とあるけれども。いつなのか。そのサイトを見るとこの作品の発売延期具合がよくわかって愉快で、7月17日発売。9月4日発売。10月23日発売。10月30日発売。12月25日発売。それらすべてに訂正線である。どれだけ期待を高めてくるのだろうかと思う一方、何かたいへんな困難が立ちはだかっているのだろうかと心配にもなるほどの延期具合で、いったいいつ私はその音を聞くことができるのだろうか。
なんとなく、私は詩というものにはまるで明るくないし、詩を読むという行為は自分からはすごく遠くにあるものに感じてもいるので、それはどの程度遠いかといえば絵本を読みますというぐらいに私にとっては遠いものなので、詩というものがまるでわかりはしないのだけれども、ラテンアメリカの小説を読んでいると、それこそボラーニョの『野生の探偵たち』はずばりでそうだったけれども、あちらでは詩を読むというものが、詩作というものがいまだにそれなりの規模というか、それは言い換えると普通さというところで存在しているようにも見えて、本当にそうなのかどうかはわからないのだけれども、そういうふうに見えて、たしかに、それはラテンアメリカの記憶ではないけれども、思い出すのはデプレシャンの、デプレシャンのあれはなんだったか、『キングス&クイーン』だったかな、たぶんエマニュエル・サランジェという人が酒場かどこかで友人たちの前で何かを暗誦するみたいなのがあって、というか何かの詩を得意げに、そしてもっと言えば交互に暗誦するようなシーンって今までに何度も何度も映画の中で見ていて、日本でそんな光景ってこれまであった試しがあるのだろうかと思い、私たちの暮らしと詩というものがとても遠いものに思われているのだけれども、そういう中で、ヒップホップというものこそが、あるいはそれだけが、生活の中に詩がわりと普通にあるという文化圏のそれと、何か似ていたりはしないのだろうかと思ったり思わなかったりしているところだった。
何も言っていないのはよくわかっている。しかしここは野放図に、私が今年ずっとはまっているラテンアメリカ文学とヒップホップが根底というかむしろ表層というか、そういうところで結ばれているのだ、と言っておこうと思う。言っておこうと思うとか言って、言ったところで何もないのだけれども、言っておこうと思う。故のないことではないんだよと。
そういうところで、『街のものがたり―新世代ラッパーたちの証言』という何人かのラッパーのインタビューをまとめた本を最近読んだ。OMSBとかPUNPEEとか、あとOtogibanashi’sとか、今までに好んで聞いていた人たちの物語を聞くのは単純に楽しかったし、いろいろとすごくよかったのだけど、印象に残ったのは一度も聞いたことのない、聞いてみたけれど全然ピンと来なかったAKLOという人のインタビューで、友だちに話したら知っていたので結構有名みたいなのだけど、こんなことを言っていた。
アンダーグラウンド・ヒップホップを聴き出したのは、”ヒップホップってもっとカッコいいんじゃないか?”と思ったから。でもニューヨークに行ったら、アンダーグラウンド・ヒップホップに対しても”贅沢品なんじゃないか?”と違和感を抱くようになりました。なぜかっていうと、アンダーグラウンド・ヒップホップを支持している層は一部の白人と日本人なんですよ。DJ KLOCKさんがニューヨークにツアーで来たときにいっしょにライヴしたんですけど、客はナードな白人で”すげードラッギーだぁ!”とか言いながら頭振ってるんです。それを見て”俺はこんなヤツらのために音楽やってるんじゃない!”って感じたんですよ。(巻紗葉『街のものがたり―新世代ラッパーたちの証言』P19)
こうやって打ち込んでいるとカタカナの使い方がすごく嫌というか、自分とは違う使い方なので気持ちが悪いんだけれども、カッコいいとかヤツとか、気持ち悪いんだけれども、その「俺はこんなヤツらのために音楽やってるんじゃない!」というところだけが私の頭にはやけに痛烈に響いてきて、それはもう、何もかもに通じてそういうことは考えられるし、考えていいこと、考えたほうが長い目でみたときにはたぶんいいことだろうなと、「うわー」と思ったわけだった。そのあとにAKLOはラジオで掛かっているヒップホップを聞いてこれ流行ってるんなら取り入れていこうぜ、みたいなノリの連中に親近感を抱いて、説得力を感じて、ということを続けて語っていて、それは私にとってはすごく清々しいことのように思えるし、そこで彼が体現することにした自己礼賛型、この本で覚えた言葉を使うとセルフボーストのスタイルというのは、それ自体はすごく「いいね!」を押したい感じで、まあともかく、こんなヤツらのために音楽やってるんじゃない!はわかりやすいけれども、短絡的かもしれないけれども、金言だった。金言というほどでもないけれども、なんとなく「いいね!」と押したいというか刺さってくる類の言葉だった。では、どうするのか。兼ね合いの問題。
と、ここまで一昨日の晩に打って時間が遅くなったので切り上げて、その日から今日に至るまで胃が痛くて気持ちが悪く、それだけで私の人生はまるで惨憺たるものであるような気になってしまい、要は弱気の虫に食い散らかされて萎えているわけだけど今日は休みで外は雨で、おとといと同じ場所に座ってこうやって打鍵が再開される。日曜日の晩、それから昨日と、彼女以外の人間とまとまった量の会話をするという機会に恵まれ、それは私にとってとても楽しいことだった。人と話すことをわりと私の心身は欲しているのかもしれなかった。ただ、会話はいとも簡単にくだらないゴシップに堕する危険をはらんでいるため、そういったことには自覚的でありたい。自覚的であること。何においても。それはあざとさと表裏一体かもしれないが、大切な心構えであると、私は信じて疑わない。
その、続けざまの人間との会話の中でともに話題に上がったトピックとして本屋のことがあり、私は本がとても好きなので思うところは色々とあり、本屋さんも好きなのでいろいろと思うところがあり、あれこれ検索していたらちょうど先週ぐらいにB&Bの方が書いた『本の逆襲』という本が出ていたので矢も盾もたまらずに本屋に行き買ってきてあとたぶん10ページぐらいで読み終わるのだけれども、面白い。
と、ここまで打って、あと10ページなら今読んじゃえと思って読みきった。面白かった。
本の定義はどんどん拡張していっていること。それはいわゆる電子書籍によってということにはまるで限らずに。だれでも、あるいはどこでも本屋になれること。それはいわゆる書店の形態とはまるで限らずに。ということが色々と書かれていた。全体的にとても前向きな内容で好ましかった。
B&Bのこと。
そもそもぼくたちはイベントスペースを運営したいわけでも、飲み屋がやりたいわけでも、家具屋がやりたいわけでもありません。また、「古本はやらないのか」ということも訊かれますが、今のところ一時的な企画などを除き、本格的にやるつもりはありません。いつか「古本を扱うことで、新品の本がより売れるかもしれない」という考えに至ることがあればやるかもしれませんが、ぼくたちはあくまで、これからも成り立つ新刊書店のモデルを作るためにこそ、様々な試みをしているのです。(…)
ぼくたちはB&Bを通じて、その「本屋はメディア」を本気でやったらどういうことが可能か、という実験をしている最中です。新刊書店には、もっとできることがあるのではないか。(…)ひとつの街における情報や知的好奇心の媒介者となることで、本を売ることと相乗効果を生みながらできることを考えつつ、日々営業しています。(内沼晋太郎『本の逆襲』P153-158)
年末になると本屋について考えるようになるのか、去年の今頃も「本屋…」と考えていたところでB&Bに行ってみたのだけれども、私にとってはそこはけっこうピンとくる場所で、いいなと思っていくつか本を買って帰った記憶があるのだけど、今一度この年末も足を運んでみようと思った。楽しい本屋が岡山にもできるととてもいいなと夢想している。
先日初めて行った古本屋さんはわりと楽しくて、でも「これこそは今読みたかった本だ!」みたいな発見はなかったというか、発見というより自分のそのときの波長に合いそうな何かはよくわからず、それでもなんとなくアフォーダンスとか知りたいなーみたいなところからアフォーダンスの本を買った。彼女は蓮實重彦の『凡庸さについてお話させていただきます』を買っていた。
アフォーダンスのやつは思った以上に難しい内容で、難しいなーと思いながら読んでいるのだけど、盲人が足音と壁の反響音とか車の通りとか雲の厚みとか建物の途切れ具合とかを聞くというか知覚しているという話など、とても興味深いところも多々あり、それから平田オリザとの対話が面白かった。そのなかで著者がこういうことを言っていて、こういうことを言っちゃう人の書くことは真剣に読みたくなるなーというものだった。
役者がまばたきと首のうなずきをするときに、そのことの持っているすごみというのがあります。そういうことをみんな面白がるようになれるというのは、ちょっといいことだなと思います。なぜかというと、それはかなり他者をちゃんと見る根拠になるからだと思います。やつはどう歩くか、やつの唇はどうか、やつはどういう恋愛をしているか、そういうことを知ることも十分生きていく根拠となるはずで、僕は結構そういうことが好きなものですから、そういうことを百分の一でもわかって、それを会話にのせられることができれば楽しいと思います。(佐々木正人『知覚はおわらない アフォーダンスへの招待』P165)
生きていく根拠というのがとてもいい。
アフォーダンスが問題にしている事柄を読んでいると、どこか保坂和志に通じる感触があるような気がする。何が、というとよくわからないのだけど、人間が世界と地続きにある感じというか、アンディ・クラークの『現れる存在』とも通じるというか。楽しかったです。じゃなくてまだ読み終わっていないので、楽しいです。
最近読んだ本の中では『マテリアル・サスペンス』が群を抜いていて、衝撃的なほどだったのだけど、なかでも黒沢清との対談がすごくよかった。よかったというか、こんなに相思相愛の対談はなかなかお目に掛かれないのじゃないかというところでエキサイティングだった。黒沢さんの話しぶりがとても嬉しそう。
黒沢 鈴木さんに今回「踊り場」という指摘をいただいて、わが意をえたり、という思いでした。これまで誰も指摘しなかったし、自分もほとんど無意識でいたことでしたが、「踊り場」と言われた瞬間、「あぁ僕は本当に踊り場が好きだった」と思いました。実は気付かないようなところでも、踊り場を使っているのです。たとえば「アカルイミライ」で浅野忠信さんが警察につかまっている独房は、踊り場なのです。(…)
スタッフも「ここでやるんですか」と仰天しましたが、「絶対にここでやりたい。この踊り場はめちゃくちゃ面白いから」と言って、刑務所の独房に見立てて、踊り場を使いました。「LOFT」でもスライドを映写して、考古学の講義をしているような場面で踊り場を使っています。これもスタッフからは「こんなところで」と言われましたが、僕が「ここでやりたい」と言ってやりました。僕は踊り場フェチなのです。
鈴木 いや、そこまでひどいとは知りませんでした(笑)。
黒沢 隠していましたが(笑)、踊り場好きなのです。ご指摘いただいた「回路」の団地の踊り場もこのアングルに入りたいと強く言って、工事用の特別車両でキャメラを上げて撮りましたので、お金がかかりました。(…)それくらい、この位置からこの踊り場を撮りたかった。(鈴木了二『建築映画 マテリアル・サスペンス』P312-313)
こんなにも踊り場が意識的に撮られていたとは!そしてそれを見抜く鈴木了二の慧眼!というところでたいへん楽しかった。
『マテリアル・サスペンス』を読んで、エキサイティングな映画評論を読みたい、と書店に行ったのだけどどれがいいのかわからず、それでヒップホップの本とかアフォーダンスの本とか本屋の本とかを読んでいるのだけど、以前古本で買っていて読んでいなかった蓮實重彦のやつを今少しずつ読んでいる。
彼方を、向う側を、未知の領域を望見し、既知なる領域に支配している論理に従って征服の道へと踏み込み、未知を既知へと転換せしめる過程にその存在を賭けようとする怠惰な擬似冒険者ではなく、いま、ここにとどまり、既知と思われた領域の一点に未知の陥没地帯を現出せしめる反=冒険者。そんな存在が成就する死と境を接した身振りをここで「批評体験」と呼びたいと思うが(…)その体験は、「差異」を正当化する「排除」と「選別」の身振りからは気の遠くなるほど隔たった時空での「事件」であり、類似も、比較も、対立も、表象も機能しえない場に宙吊りにされたこの「事件」こそが、真の「前衛」体験なのである。(蓮實重彦『シネマの記憶装置』P74-76)
これはメカス論から引いた箇所なのだけど、相変わらず格好よすぎて痺れ狂う。面白くてエキサイティングな映画評論を読みたい。
休日で、雨が降っている。髪を切りに行く予定。
眼前で光を発するパソコンの画面、引用するために開いた本、黄色い煙草のパッケージ、それらが置かれた赤いこたつ机、顔を上げれば降る雨で小刻みに揺らいでいるように見える車の行き来やいくつかの木々を映す窓がある。生活の中にある様々な矩形は、すべてが書物のようであり、スクリーンのようだ。そう思ってみれば、この世界は(たとえ胃が痛くても)言葉が追いつかないほどに美しい。休日で、雨が降っている。本を読む。映画を見る。
cinema text
2013年12月6日
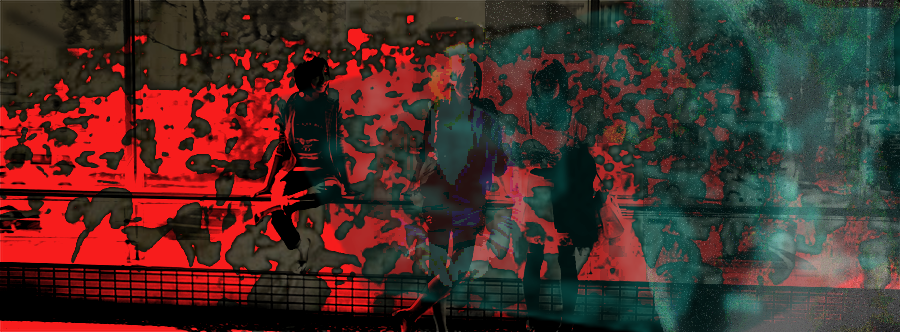
オマル・カベサスの『山は果てしなき緑の草原ではなく』を読み終え、それはサンディニスタによる闘争の1975年までのあれこれが描かれていて、それはそれですごく面白かったし、うわー山中でのゲリラ活動ってえげつないんでしょうねー猿とか食ったり病気の手術がむちゃくちゃだったり、と読み応えは非常にあったのだけど、描かれるのは1975年までで、読んでいる限りはまだまだソモサ王朝というか国家警備隊の脅威が強く国民にのしかかっているあたりで、そこからサンディニスタががんばってどんどん勢力拡大、いけるぞ打倒ソモサ、みたいな空気にはまだなっていないあたりで、そのあとの展開も読みたかったなという一抹の物足りなさはあって、訳者解説を読むとそのあとのことがなんとかというタイトルで書かれているらしいのだけど、未邦訳なので読みようもなく残の念はあるけれども総じていえば面白かった。
そういう、「山中でゲリラとかいいよね~」という流れであったからというわけではないけれども、私たちの店で上映会があり、山崎樹一郎の『ひかりのおと』と『つづきのヴォイス』を見た。『つづきのヴォイス』は岡山県北の真庭の山中で280年前に起こった農民たちによる一揆を題材にしたドキュメンタリーで、義民を顕彰する会の老人たちが様々の資料や証言にもとづきあれこれを話す姿を収めたものなのだけど、280年前を生きた不在の人物たちをめぐる語りのありようは、そういう楽しみ方がこの映画にとってふさわしいものなのかどうかはわからないにせよ、とても面白いものだった。なんせ、記憶は当然のことながら、確かな記録というものがそう豊富にはないようで、一揆を起こしあっけなく敗北を喫した農民たちがそのあとにどのような足どりを取ったのか、まるで定かではなく、そういう状況の中で、記録を信じてみたり、義民の末裔の言葉を信じてみたりと、まるで確固たる根拠を持ち得ないまま、その「どれが正しいのかはわからない」というエクスキューズは保持されながらも、あれこれと語られる。どの言葉も鵜呑みにはしてはならないという油断ならない言葉を聞き続けることの面白さ。特にそれまで個別に撮られていた老人三人が集まってあれこれを話し合う場面は面白かった。場を独占するデータサイエンティスト的な者、なかなか言葉を発する隙を見いだせない者。新たなデータの提示、そのデータを読み上げるそれまで輪に入れなかった者のいきいきした姿、「え、何そのデータ知らないんだけど」という感じを醸すデータサイエンティスト。総じてチャーミングな老人たちが映っていて、それを見続けるのは愉快な経験だった。
そういう、「山中でゲリラとか、一揆とかいいよね~」という流れであったからというわけではないのだけど、オリヴィエ・アサイヤスの『カルロス』3部作を見終えた。第一部から第二部の途中ぐらいまでの、カルロスが現役というか現場に出てどんぱちするところまでは本当に面白く、格好よく、カルロスは世界を本気でどうにかしたいのだなあという感心とともに見ていたのだけど、そのあとどんどん、ウィキペディアの言葉を借りるならば「金次第で誰の命令でも従う傭兵のような存在になった」カルロスに流れる時間はどんどん弛緩していき、それとともに映画自体も弛緩していくようだった。気づいたら体はぼっちゃりしているし、女を抱いてばかりいるし、やたら金持ちっぽくなっているし、病気にもなるし、だんだん「エキゾチックな国が好きなブルジョアの旅行記」みたいになっていく感じがして、それはそれで面白かった。この弛緩はこの題材においては宿命で、この弛緩を見せずに成り立たせようとしたら欺瞞になるのかもしれないと思いました。なのでとても好感が持てました。
それにしてもなんというか、そういう、「山中でゲリラとか、一揆とか、あるいはテロとか世界同時革命とかいいよね~」みたいなことはまるで思ってはいないのだけど、ここのところあまりに頻繁にそういうたぐいのものを見たり読んだりしているせいか、ナンバーガールの「MUKAI NIGHT」に「そろそろ変化がおとずれる、憂いの時代に突入か」という歌詞があるのを猫の鳴き声とともにいま思い出したところだけれども、なんだか秘密保護法案とかきな臭いことはいつの時代だってそうかもしれないけれども今もあれこれあるけれども、日本人の方々はいつかそういった、サンディニスタとか、真庭の農民とか、カルロスみたいな感じで銃とか鍬とかを持って立ち上がったりするのかな、するのかな、と思う。与党の偉い人が民衆の集会をテロと呼んじゃう時代だけれども、どうすんの、みんなどうすんの、なにかすんの、と思う。何かが起こるならば私はその様子をユーストリーム越しに見るのだろう。
そういう、「山中でゲリラとか、一揆とか、あるいはテロとか世界同時革命とかいいよね~」みたいなところとはまるで無関係に鈴木了二の『建築映画 マテリアル・サスペンス』を読んでいて、これがまたやたらに面白く、すごくワクワクしながら読んでいる。こことかとてもいい。
建築映画とは、建築サイドから見れば、映画によって隅々まで浸されて溺れてしまった建築であり、映画サイドから見れば、スクリーンに建築が突き刺さり、突き破ってしまった映画のことなのである。(…)この事態は要するに、建築的にも映画的にも、とりあえず「台無し」ということである。したがって台無しになったという自覚なくして建築映画は始まらない。台無し、それは基盤なき時代における基盤であり、それがすべての始まりだ。(P53)
すごく面白い。
そういうことも相まってか、ここのところは映画をよく見ていて、それは『マテリアル・サスペンス』に触発されてというところも実際に大いにあるだろうけれどもそれだけとは思われず、一つは『2666』を年末に読み始めるまでになんの本を読んだらいいのかがとうとうわからなくなったため、映画で時間を潰す、みたいなこともあるだろうし、もう一つにはせめて一年で100本は映画見たいと年初にたしか思っていたはずで、今何本なのかはわからないし、エバーノートを調べればものの1分でそれはわかるだろうけれども今はまだ知りたくはないのだけど、そういう100本見るぞみたいなところもあり、7月の夏休みに集中的に見て以降、岡山に戻って以降ほんとうに映画を見ていなかったので、年末で一気呵成だ!逆転だ!みたいななんかこう、数字合わせみたいな気分もあるのかもなとも思うし、あるいは寒くなって店は暇で気持ちと体力に余裕があるというのもあるだろうし、あれこれあるのだけど、まあそういうことで映画をよく見ている。雑駁に言って映画って面白いですね本当に、と思う、改めて。
この一週間ぐらいのあいだにも、山崎樹一郎『ひかりのおと』『つづきのヴォイス』、アサイヤス『カルロス』3部作の他に、小林啓一の『ももいろそらを』、アキ・カウリスマキとペドロ・コスタとビクトル・エリセとマノエル・デ・オリヴェイラの『ポルトガル、ここに誕生す~ギマランイス歴史地区』、ナンニ・モレッティ『ローマ法王の休日』、ロマン・ポランスキー『袋小路』を見た。
『ひかりのおと』は牛がしっかりと撮られていて、出産のシーンはもちろんこと、睡眠中の牛舎の様子とか、どの場面に出てくる牛もすごくよかった。ただ、持ち出される問題がとても多いためか、それを処理していく手つきが雑というのかわからないけれどもそれぞれの問題の解決があっさりというのか、ご都合主義というのか、牛に比べて人間はしっかり撮られていないような感じがあり、最後にはカタルシスめいたものがあって私も何やら感動をしてはいたのだけど、でもその感動は果たして適切なものなのだろうか、無理くり誘導されたものではないだろうかと思わないでもなかった。ただなんせ牛がよかったのでよかった。
『ももいろそらを』はたしか年の始めにアルドリッチの『合衆国最後の日』と『カリフォルニア・ドールズ』を見に大阪に行ったときに予告編で流れているのを見て、なんだかよさそうだなと思っていて、それでツタヤで見かけたから借りたのだけど、どういう評判なのかはまるで知らないけれどもこれがすごくよくて、女子高校生たちがちゃんと歩いて、ちゃんと会話をして、というのがちゃんと撮られている感じがして好感が持てた。インタビューを読んだら2035年の設定で主人公が過去を振り返るとかどうとかということで、あと過去の出来事を表現するためにモノクロにしたということらしく、そういえば冒頭に2035年みたいなことがあったような気がするけど始まってすぐに忘れていたのでよかったなと思っているのだけど、というかそういう作り手の意図みたいなものを先に知っていたら「それ僕は結構です」という気になっていただろうけれども、調べたら「被写界深度が浅い」というらしいまわりをぼやけさせた映像も、意図がどういうものかは聞きたくはないけれども私はすごくいいなと思って、なんせきれいだったし、まあなんせ女子高校生たちの演技が瑞々しく、心地よく、なんだかすごくよかったんだよなーこれほんとうに。と思いました。
『ポルトガル、ここの誕生す』は、エリセの工場のやつとオリヴェイラのがとてもよかったです。ペドロ・コスタはひたすらかっこいいなーと思いながらもけっこうしんどかったです。よかったです。
『ローマ法王の休日』は予告編のタッチと全く違っていい意味で裏切られました。「え~!?」と思いました。『袋小路』は、「ありゃりゃ~」と思いました。どれもとてもよかったです。
今年も残すところわずか。面白い映画をたくさん見るぞ、という思いを強くする一週間でした。
book cinema text
2013年11月29日

どうかしたのだろうかという小学生のように、私は11月下旬の今でも半袖ハーフパンツ姿で仕事をおこなっており、多くの方に「どうかしましたか?」と尋ねられているのだけれども、なんとなくその姿をやめられないでここまで来てしまった以上、寒くないといえば嘘にはなるけれども、ハーフパンツはいつ長ズボンにしてもいいのだけど長袖は執拗にまくらなければいけないので面倒であり、半袖でいける以上は行きたいのだけど、今日はどうにもその格好では寒さがきつく、少し間があいたらパーカーを羽織っていた。ここまで来てしまった以上、11月中はその姿で、と決めていたところをくじかれた格好だ。別に長袖長ズボンになっても構いはしないのだけれども、明日もきっととりあえずこの格好で店に向かう。
寒さはいくつかの物事に影響を与えるらしく、ここ10日間ぐらい、ガスコンロが補助なしにはつかなくなった。補助なしにというのは、ガスは出るからで、ライターを着火口というのか、火の吹くところにもっていき、ガスを出し、ボッ、となって手に炎が触れ、引く、ということをおこなっていたのだけど先日彼女が機転を利かせてチャッカマンを買ってきてくれたので今では楽につけられるようになった。ライターでつけることの最大のデメリットは、私の(直立時の)ライターに関する手癖が「火をつけたらすぐさまポッケにしまう」であるということで、何度もポッケにライターを入れ、次に着火するときに「あ、また」となってポッケから出さなければいけなくなった。悪癖だった。寒さのせいなのかはわからないけれどもそういう状態にガスコンロがなっていて、でもそれは終日の症状ではなく、店全体があたたまってくると、自発的に付くようになる。どういうことなのだろうか。それと関係があるかどうかは別として、ここのところiPhoneが残り20%ぐらいの電池の状態で触りだしたら急に消えて、再度電源をつけると「電池もうないですよ~」という人をバカにしたようなメッセージが出る、ということがいくらかある。今さっきもそうなった。33%だった。冬は世界をおかしくする。そういえば今年はまだなっていないけれど、去年の冬、パソコンになかなか充電できないことがあった。いくらあのケーブルというのかあれをさしても緑の充電し始めましたよライトがともらない。難儀した。今年はまだなっていない。
充電がどうとか、ガスコンロの火がつかないとか、そういう不便さを私は不便としてここに挙げたけれども、昨日読み始めたオマル・カベサスの『山は果てしなき緑の草原ではなく』を読んでいると、まあ、サンディニスタ解放戦線の戦士として山中でゲリラ活動をおこなっていたオマル君と比べたら、私の不便なんていうのは取るに足らないものなんだよな、オマル君たちフレンテの戦士たちを見習って、私もここはいっちょ、一所懸命がんばって生きるぞ、みたいな気になることはこれっぽっちもないのだけれども、私のこのぬくぬくとした生活はそれでよいとして、オマル君たちの活動はまた、非常に過酷で大変だったのだなあ、ということを思う。なお、「フレンテ」と知ったような言い方をしたけれども、そういう言い方はこの本で知ったばかりだった。Frente Sandinista de Liberación Nacionalのフレンテとのことだった。意味はわからない。戦線かな。
それはそれとして、この小説は小説というのかもわからないけれども、高校卒業後にフレンテに加入したオマル君がそのあと山中に行き、がんばった、というまったくの実体験を「俺はさ、あのときさ」みたいなトーンで語っていくもので、「君も今にわかるよ」みたいな書き方もたまに出てきて、書いているのか、何かの語りを採録したのかよくわからないけれど、たぶん書いたものだと思うのだけど、とりあえずなんにせよ、サンディニスタ解放戦線の人たちが打倒ソモサを目指してがんばっている状況がとてもよくわかって、すごく興味深い。献辞にも名のあるセルヒオ・ラミレスの『ただ影だけ』の記憶を手繰り寄せながら読んでいくとなお面白い。そっか、こういう人たちがあの酷い名前の兵士、マンコ・カパックなりなんなりだったわけだ、というあんばいで面白い。国家警備隊の手によって火山に落とされた兵士の話とか、どちらにも出てきて面白い。
昨日は、だから、休みだったので、よく寝て、起きて、本を読んで、うたた寝して、起きて、本を読んで、映画を見て、寝て、起きて、映画を見て、本を読んで、というような暮らしだったのだけど、起きたのが13時で、たしか21時ぐらいに一度寝てしまって起きて24時で、そのときの私の気分はひどいものだった。たった8時間しか私は活動できないのか、というバイタリティの低さみたいなもの、生きることに対する脆弱性のようなものをひどく感じ、気が滅入った。普段は10時前に起きて26時ごろに寝るような暮らしだったはずだから、16時間だから、その半分、8時間。なんてバカみたいなんだとひどく憤り、負けてなるものか、ニカラグアの山中でがんばっているオマル君のように私もがんばるぞ、という気には一つもならなかったけれども、さすがに惜しいという気のため24時から28時までは起きることにして映画を見たりした。
昨日読み終えた本。フェルナンド・バジェホ『崖っぷち』
昨日見終えた映画。ポール・トーマス・アンダーソン『ザ・マスター』、ヴェルナー・ヘルツォーク『ノスフェラトゥ』、オリヴィエ・アサイヤス『カルロス 第1部 野望篇』
『ザ・マスター』はホアキン・フェニックスの演技がとてもよかったです。あとフィリップ・シーモア・ホフマンの演技もとてもよかったです。絶えず攻撃にさらされるカルト宗教のマスターのフィリップさんが批判や非難に対してけっこうナイーブというか短気なところ、その脆弱性。誰よりもその宗教の力を信じているのは妻なんじゃないかというあの眼差しの強さ、家族でちっちゃく盛り上がる心もとなさ、そういったものがいい具合だった。
『ノスフェラトゥ』もまた「マスター」と呼ばれる男の話だった。ムルナウのやつは見たことがないのだけど、ヘルツォークはきっと景色を撮ることが好きなんだろうなと思いました。とても壮大でした。ネズミの大群がなんせすごかったです。広場で、たくさんの棺を運ぶ黒服の男たちの列を捉えるロングショットも格好良かった。その広場で人々が焚き火をしたりラッパを吹いたりバイオリンを弾いたり踊ったりしている中を白い顔した奥さんが練り歩くくだりもよかった。ラッパとかバイオリンとかの音楽はオフで、荘厳な雰囲気のBGMが流れているところがまた好ましかった。それまで弱々しい人だった奥さんがいつからか気丈で行動の人になるところもよかった。ペストは大変そうだったので来年はカミュの『ペスト』を読んでみたい。
『カルロス』は、アサイヤスは多分見るの初めてで、ずいぶん前、たぶん10年とか前に読んだ、10年にはなってないと思うけれども大学生のときに読んだ、下北のミスドで読んだ、梅本洋一の本でけっこう触れられていて(人違いでなければ)、見てみたいと思いながら見ないままここまで来てしまったのだけど、初めて見るアサイヤスは格好良かった。多言語が行き交う映画は楽しい。オマル君もがんばってるけど、カルロスも負けず劣らずがんばってるなーと思いました。抵抗の時なんでしょうか。週末に店で山崎樹一郎の上映会があり、新作のドキュメンタリー『つづきのヴォイス』が一揆の話なので、今は抵抗の時なので、楽しみです。見ている途中でビールを飲みたくなり、一時停止にしてビールを取ってきて再開させたら1分もしないうちに映画が終わったのでびっくりしました。2部も楽しみです。
『崖っぷち』はコロンビアの作家のバジェホさんの小説で、宗教や女性や国家、というか世界に対してありったけの罵詈雑言を吐き散らすような語りの小説で、まるで痛快という感じではなく、呪詛の言葉を延々と聞かされるこっちの身にもなってよ、という気にもなってくるのだけど、そのほとばしる憤怒の中でもおばあちゃんを筆頭に、あるいは死んでいく父と弟への愛情は隠さないあたりがなんだか健気で、切なくもなった。しばしば「いま、これを書いていること」への言及があって、特に植字工のお姉さんに向けたものが2箇所あったけれども、そういうあたりも面白かった。
理性の曇ったデマゴーグたちが「レイシスト」のレッテルを貼りかねないたった今の憂鬱な話題を終わらせるためにはっきりさせておこう。おれがニューヨークの黒人ジャンキーが憎いのは、連中が黒人であるからでもジャンキーであるからでもニューヨーク出身であるからでもない。連中の人間としての存在のためだ。ああいう奴らに存在する権利はない。少なくとも社会保障制度のおかげで生きている限り、しかもそのあいだおれたちコロンビア人が、寛大なるコロンビアによって与えられた恩恵のおかげであのクソの街で便器掃除をしなければならない限り、ああいう奴らに存在する権利はない。植字工のお姉さん。パラグラフや単語をひとつも削除しないでくれたまえ。(P188)
なんだか引用した箇所はそう面白くもなかったのだけれども、痛快ということもないけれども、全体の罵詈雑言はやっぱり、今あらためてパラパラと読んでいたら面白いというか気分がいいというか、気分はぜんぜんよくはないのだけど、よくもまあそこまで言うというところを突っ走っていて迫力がある。
いま『フェルナンド・バジェホ』で検索した中で2つ見た書評というか感想のブログで、ともにトーマス・ベルンハルトの名前が出ていた。ベルンハルトも罵倒芸とのことだった。『消去』はたしか、大学時代の同居人が読んでいた。罵倒芸だったのか。なんとなく納得する組み合わせだった。これもあれだったら来年読もう。来年。全部来年。今年はもう終わり。
book cinema text
2013年11月24日

クローネンバーグ的黒ゴマアイス大福を食いながら馬鹿笑いをした夜から何日が経ったのだろうか。私は過ぎる日を数える術をすっかり忘れたまま、何年かの時間を生きたらしかった。黒ゴマアイス大福は原型を留めることをすぐさまに放棄して、たちまちにグロテスクな表面を私たちにさらけ出したのだった。それを見てそれまで眠くなっていた私はすっかり目を覚まして、口に物を含みながらゲラゲラと笑ってみせたのだった。今その私の手の届くところにはセブンイレブンで当たったキリン一番搾りのロング缶があり、500ミリリットルの飲料を欲しているわけでもない中で、順調に残量を減らしていくのだった。その何日も前、あれはいったいどれだけ前の事だったのだろうか、今はいったい何日なのだろうか、今日、お前は誕生日だったね。28歳だ。お父さんはその頃、クウェートにいたよ。お前はそのメールを読み、横にいた彼女とともにクウェート!とひとしきり感嘆したのだった。お前はお前の父が自分と同じ年齢の時代があったことを想像しようとしたけれどそれはうまくできず、少なくともお前と同じ年のときにクウェートにいたという、確かに前に聞いたことはあった事実に今一度つきあたり、クウェート、と思うほかなかったのだった。お前はクウェートの地図上の場所を知らない。お前が今知っているのは、サン・ルイス・ポトシ、あるいはオアハカ、コアウイラ、ソノラ、ユカタンその他メキシコの州の名前と、そのおおよその位置取りについてだった。なぜお前がそれを知っているかといえばこのいくらかの期間で、ケンブリッジ版世界各国史シリーズの『メキシコの歴史』と、鈴木康久という外交官か何かの人が書いた『メキシコ現代史』を立て続けに読み、メキシコの歴史について学んだからだった。学んだと言っても結局お前がわかったことはソノラとオアハカ等の場所ぐらいであり、あとは「いろいろなことが起こったのだなあ」ということぐらいだったから、読んだことそれ自体が無駄と言っても過言だった。それなりに私は、メキシコで何が起きてきたのか、ひと通りはわかったような気がした。
とても面白かった箇所。『メキシコ現代史』はポルフィリオ・ディアス政権が出来たところから描かれるのだけど、いきなりフルスロットルで(文章がではなくメキシコが)、「他方メキシコ市では、最高裁長官だったホセ・マリア・イグレシアスがレルド大統領の選挙に不正があったとして自ら暫定大統領を名乗った。そのためメキシコ市は混乱したが、ディアスもグアナファト市で自ら暫定大統領の就任を発表した」
自称他称含め三人の大統領がいるなんて!というたいへんな愉快さ。結局ディアスがメキシコ市を取り、レルドは国外亡命、その後国会はディアスを大統領に指名するが、ディアスは腹心の将軍をいったん暫定大統領に据え、自らイグレシアス一派の討伐に出向き、やっつけ、大統領選挙を実施、唯一の立候補者だったディアスが正式に大統領の座につく、という流れ。1877年のことである。たいへん愉快でたいへん好ましい。
で、そのディアスの30年ほど続く政権を断ち切ったのがマデロで、マデロはアメリカのテキサスでサン・ルイス・ポトシ綱領を発表。自らが暫定大統領である、とそこには書かれている。なんかゴチャゴチャあってめでたくディアスを倒す。1910年のことである。
そこ以降の10年ぐらいはちょっとわけがわからなくて、マデロを暗殺して政権取った反革命のウエルタを打倒するぞっていうので北方のカランサとかビジャとかオブレゴンとかが革命軍としてがんばって、南方からもサパタとかが出てきて、カランサ政権になって、と思ったら昔の仲間は今は敵みたいな感じになったりして、さらに革命勢力が独自に革命紙幣を発行していたりして、何が何やらわけがわからずとてもすごい。読んでいてとてもいい。そのあとの、しばらく元革命家が大統領という時代が続くときは、どの大統領も「xxxはオアハカ州に生まれ、小学校を卒業したあとは不動産業をしていたが、革命軍に参加し、実績を上げ」という紹介になる具合が好ましい。いろいろ起こりすぎてどんどん忘れてしまったが、「メキシコぉ」という感じで二冊とも楽しく読むことができた。来たる『2666』に向けて、多少は準備になっていれば嬉しい。
このところ少しだけ映画を見ている。映画館で見たのは青山真治の『共喰い』ぐらいだけれども、これはもう何言っていいかわからなかったけど物凄かったのだけど、そのあと何を見たんだっけか、ベルトルッチの『暗殺の森』、オリヴェイラの『永遠の語らい』、クストリッツァの『アンダーグラウンド』を見た。先日『カフカと映画』を見てその訳者解説で名前を見た影響であのなんだっけ、陰気な映画を撮る人、ドイツの、ドイツじゃなかったっけ、オーストリアだっけ、オーストリアかそこらへんのあの、ハネケだ、ハネケの『カフカの「城」』も借りて見始めたのだけど10分かそこらで眠ってしまい、きっとこれは見ることはなく返すだろう。『暗殺の森』と『永遠の語らい』がとてもよかった。『暗殺の森』は「うわ~、ファシズム~」という感じでとてもよかったし、踊るところはなんせ美しかったし、森のシーンもとてもよかったし、妻のふてくされた表情もとてもいい。その妻であるところのステファニア・サンドレッリが出ていたことは後で知ったのだけど『永遠の語らい』も、これは2006年の2月、文芸座のオールナイトで見た以来で、今回で3回目になるけれども、とても、7年か!7年ぶりに見て、今回が一番面白く見られた。歴史学の教授の母親が娘に各地の歴史を語っていくところをこれまでは多分そんなに興味深くは見ていなかったのだけど、今回はなんでだかとてもよかった。4人の語らいの場面も、そしてクライマックスももちろん。今まででいちばん取り返しのつかなさみたいなものを実感しながら見ていた気がする。それにしても7年。
7年とか8年とか、簡単に、簡単な年月ではないけれども、経ってしまうのだなと、それを思う。今週は火曜日が休みだった。昼飯を食い、家の方向に戻っていく途中で城下公会堂の前を通ると、店の前の黒板に塚本功という文字が書かれていて、それはその夜におこなわれるライブの告知だった。その時までそのライブの存在を知らなかったのだけど、夜に予定もなかったので行くことにした。私は大学時代のいつだかの時期にネタンダーズをとても好んで聞いていた時期があり、なんのきっかけで知ったのかは今はわからないし、多分何かのイベントとかで他の目当てがあって行ったときに知ったとかが妥当かなと思うのだけど、ネタンダーズが好きで、塚本功のみずみずしいギターと声、特にスキャットする声をとても好んでいたのだけど、今、私のすべてが記録されていると言ったら過言でしかないエバーノートで検索をしてみたところ2004年10月、ネタンダーズのCDを買っていることがわかった。9年前だ。僕は19だった。いや、10月であれば18だった。予想通り、お台場だか新木場だかどっかであったローライフで見て知ったらしかった。たぶんそのイベントにはフリスコあたりを目当てに行ったのだろうと思われる。9年。18。いくつもの歳月。ローライフでネタンダーズの出番はたぶん一番最初とかの時間帯だった。ライブの頭で塚本は今日は気持ちのいい日ですねとかいい朝ですねとかそういったことを言って、では「悲しい出来事」という曲をやります、みたいに始めたのだったと思う。それでとても笑い、そのあとにたぶん、とても好ましい時間を過ごしたのだったろうと思う。
だから、そういう記憶を引き連れるためというよりは、あのギターをまた聞きたいという単純な欲求に従う格好で夜のライブを見に行ったのだった。それは素晴らしいライブだった。俺はたぶん、目を見開かせながら、少し口角を上げながら、うわーとか思いながらそのライブを見続けていた。ただただ格好良かった。一挙手一投足がセクシーで力強かった。だからそれはとてもいい夜だったんだ。と彼は言った。
彼の店は土曜日の今日、さすがにこれは回し切らんわ、という忙しさになった。ここのところは忙しくなってもまあなんとかなるよねという程度だったから、この日の忙しさは彼を面食らわせたし、ワーカーズハイのような状態にもさせた。忙しいとき、最近の彼の脳裏には「サン・ルイス・ポトシ」という言葉が繰り返し浮かぶようになっていて、この日も彼はその都市名を、ただの音の連なりとして頭の中でループさせながら働いていた。サン・ルイス・ポトシ、サン・ルイス・ポトシ、サパタ、サパティスタ!サパティスタ民族解放軍を支援しているNGOの人のところに泊めてもらいました、と、この水木、行商で店に来ていたノックの帽子屋のノックさんが言った。彼は世界のけっこうな各地を旅行して帽子の生地等を買っている。チアパス州のサンクリストバルを訪れたときのことだと言った。サパティスタの人ではなかったそうだが、目出し帽はかぶっていたと言っていた気がする。なんだかすごい経験をしているなと思った。サパティスタ民族解放軍、EZLNという省略形を見るたびに、サパティスタのSはどこに行っているんだよ!と私は怒気を含んだ声で叫ぶことに毎度しているということはないのだけど、今「あれ、解放戦線だっけ」と思ってググったときに、「Ejército Zapatista de Liberación Nacional」のことだったと知った。Zだったのねー、というところだった。
メキシコの歴史を学んだのち、いくつか小説を読んでから年末に『2666』に向かう予定で、先日買ったバジェホの『崖っぷち』を読み始めた。クソ死神めが!みたいなトーンの小説らしい。これはコロンビアの小説だ。今日、Amazonで注文したオマル・カベサスの『山は果てしなき緑の草原ではなく』が届いた。これは中古で895円からあり、1200円でプライムマークが付いているやつがあり、それって送料無料ってこと?というところからとても悩んだ挙げ句、なんで送料無料がそんなに魅力的なのかはわからないにせよ、悩んだ挙げ句、勢いに任せて新品、2730円で買った。がんばれ、応援しているぞ、現代企画室、の現れということだった。1994年初版第1刷、2000部発行、とある。それが新品で届く。20年近く経って未だに2000にも満たないのか、そしてそれがまだ新品としてあるのか、と思うとなんというかすごい。買ったら「一時的に在庫切れ; 入荷時期は未定です。」になった。私が世界に与えた影響がこのように可視化されるのは好ましい。ざまあみやがれ!入荷時期は未定だこの野郎!一時的とか言うけどどれだけの一時なのかわかったもんじゃあるまい!と誰にでもなく啖呵を切りたい。これはニカラグアの小説だ。サンディニスタ!
book cinema text
2013年11月9日

とても久しぶりにウディ・アレンの『ラジオ・デイズ』を見て、相変わらずとてもラブリーで好ましい映画だと、終始ニコニコとしながら画面に見入っていたのだけれども、この映画を初めて見たとき、私は滂沱してけっこうなところ動揺し狼狽したのだったと、それを思い出すと、あのときのあの状況はなんだったのだろうかと不思議にすら思うわけで、例えばラジオの夫婦で相談みたいなコーナーに両親が出演したらというシーンの、愛してます、それ以上どうしろと?という妻の言葉に、あるいは部屋で音楽を聞きながら踊る娘を父親と伯父が優しく見守り、一緒に踊り、コーラスを担当するあの親密さに、私は激しく感動したのだったけれど、今見てもそれらはとても好ましいシーンであることには変わりはないのだけれども、泣くということもせず、うろたえるということもなく、すんなりと、いいシーンだねで流れる。何もそれが惜しいわけではなく、ただあのときのその感動を思い出すだけだった。2005年の4月20日、その日はたぶん授業はない日で、だから私は昼間に家で映画を見て、多く泣き、そのあとにゼミに出席するために家を出たのだった。余韻を引きずりながら学校までチャリだか原付きだかで向かったのだった。それをただ思い出す。
そういったものごとを思い出していると、ふいに車で246を走っていたときの、なんでもないロードサイドの風景が思い出されて、その道を再び走りたくなる。大学時代の同居人が車を持っていたこともありしばしば運転する機会があったのだけど、そんなに多くあの道を走った記憶はないのだけれども、なぜだか、あの道を思い出す。どこに向かっていたのだろうか。車を走らせて映画館なりに行く理由もないし、今となっては目的も同乗者がどういった人たちだったのかもわからないけれども、あの道を走った。また走りたいと今わたしは思うけれど、レンタカーを借りて走ったとしても、同じような気分を経験することはないだろう。それはよく分かっている。何も取り返せないということはよく分かっている。ただ何か、今わたしは無性に、あの道をまた走りたいと思っている。具体的な記憶で言えば辻堂や江ノ島、そこから鎌倉への道の方がよほどあるけれども、もっと何か漠然とした走行を246で今、私はしたいと思っている。年末にでもおこなうだろうか。決してしないだろうということもよく分かっている。
この春頃から、ほとんど禁欲的とも言える姿勢でラテンアメリカの小説を読み続けてきて、そろそろ、今年の締めくくりとしての、そしてラテンアメリカ縛りのしめくくりとしての『2666』に突入しようと思っているのだけれども、まだそれを読み始めるには早いし、できればその読書は年末年始の休みの時期におこないたいと思っているのでまだ早いし、だからといって次に読みたいラテンアメリカの小説が今あるかといえば特に思い浮かばないということがあり、ここに来て大変な迷いが生じてしまっている。
最近はチリ人作家ホルヘ・エドワーズがキューバに代理大使としておもむいた3ヶ月を記した『ペルソナ・ノン・グラータ』を読み終えた。徹底した盗聴や誰が密告者なのかまるでわからないキューバ公安組織のえげつなさや、1971年という、アジェンデ政権発足後、そしてピノチェト及び軍部によるクーデター勃発以前の微妙な時期にチリ人が感じていたこれどうなるんだろうかなあ感、革命キューバの現状を見ていると社会主義路線とかいってもうまくやんないとこれ悲惨だよなあ感、ゆくゆくは血が流れることになるかもしれないよなあ感、フィデル・カストロの無神経さと繊細さ、無能さと有能さ、そういったところが見られて面白かった。特にキューバを去る直前にエドワーズとカストロのあいだでおこなわれた対話の緊迫感と、そしてそこにまさかの展開で生じる親密さは、素晴らしく読み応えがあった。
また、小説以外はラテンアメリカで縛ってはいないということもあり、夏前に買い、面白く読めないという理由で最初の方で放棄していたペーター=アンドレ・アルトの『カフカと映画』も読み終えた。これはカフカの叙述のスタイル等々に映画が激しく影響を及ぼしているということを各種資料から読み解く感じの批評だったのだけど、最後まで面白かったりたいして面白くなかったりしたのだけど、『城』とムルナウの『吸血鬼ノスフェラトゥ』の共通点を「驚き」と言って推測するくだりなんかは、何が驚きなのかもわからなかったし、そこをこじつけてみて何が生まれるのかもわからなかったりしたのだけど、カフカが身振りや手振りに執着して心理学的な要因を排した表層的な叙述をする、運動の力学を重視するみたいなところは「そうだよなー」みたいなところで面白かったのだけど、これを読んでいたら俄然、カフカを再び読みたくなったし、なんというか、動きのある小説、歩きまわる小説、身振りが見える小説を読みたくなり、それはカフカでもよかったし登場人物が動き続けるという意味ではドストエフスキーのどの作品でもよかったし、あるいは、読んでないからわからないけどローラン・ビネの『HHhH プラハ、1942年』はやはり読みたいし、スパイとか関係しそうだからきっと動きまわるだろうという推測も成り立っているし、また、スパイといえば最近買ったコンラッドの『密偵』も面白そうだし、と、要は締めの『2666』を前にして、いま私はラテンアメリカ外の小説をとても読みたくなってしまっているという事実があり、それにとても困惑している。困惑しているというか、読みたいぞ、というときめきを与えてくれる、まだ見ぬラテンアメリカ小説の選択肢がいま浮かばなくて、どうしたものかとなっている。先日古本屋で買ったボルヘスには予想通り手が伸びない。ボルヘスが私を拒絶しているのか、逆なのか。
そういった大変な迷いの中で今日は本屋に行き、フェルナンド・バジェホの『崖っぷち』を買った。これは松籟社の「想像するラテンアメリカ」シリーズの小説で、内容の良し悪しは当然知らないのだけどこのシリーズは敬遠していた。その理由は本当にたったひとつで、ハードカバーでなくてソフトカバーだからだった。やっぱりハードカバーでしょ、というところだった。
とは言え、そうも言っていられない状況になってしまった今、なってしまった今というか、本屋のラテンアメリカ文学コーナーを見ればもちろんまだ読んでいない小説はいくらでもあるのだけれども、どうにもプイグとかコルタサルとかフエンテスとかはそれぞれ一冊ずつは読んでいるけれどもそれ以上に読みたいとは今の気分は感じないし、現代企画室のラテンアメリカ文学選集はなんでだかジメッとしていそうなイメージで食指が動かされないし、と思っていたのだけど、いまふとラテンアメリカ文学選集のページを見たところ、「都会を離れニカラグアの解放ゲリラに身を投じた青年をまちうけたものは?果てしなく続く緑と、泥と、孤独の中で這いずり回る男たちの、想像もつかない地獄を描く。」という説明書きを見て、それとても面白そう!とにわかに活気づいた。オマル・カベサスという人の『山は果てしなき緑の草原ではなく』というタイトルのものだった。これ次いってみよう。また、その下にあったホセ・マリア・アルゲダスの『深い川』は夏に古本屋で買っていて、いまだ読む気が起きずに読んでいなかったのだけど、「アンデス山中で、白人に生まれながらインディオの間で育った少年の目に、先住民差別の現実はどう映ったか。待望久しいインディへニスモ文学の最高峰。」という説明書きを読んだら読んでみたい気になった。まだまだあるじゃないか、ラテンアメリカ、というのが今の偽りのない気持ちだ。簡単だ。
今日はまた、それと同時に、もう『2666』に向けていくしかないよね、みたいな気持ちから、『2666』はメキシコが主な舞台と聞いているので、メキシコの歴史をよく知っていた方がいいのかなというところでケンブリッジ版世界各国史シリーズ『メキシコの歴史』を買った。読み始めたのだけど、革命期のあたりのことがよく知りたくて、というかフエンテスの『澄みわたる大地』に挟まっていた年表でその時分の歴史を見たときに、「なんだこれは、何が起きているのかさっぱりわからない!」となったこともあり(セルヒオ・ラミレスの『ただ影だけ』のニカラグアなんかは、なんとなく動きというか色々な勢力の移り変わりがシンプルなような気がして(もしかしたら複雑なのかもしれないけれども)「なーる」とか思えていたので、メキシコの「年表を見てもいったい何がどうなっているのか、誰が何をしたいのかまるでわからない」という感じは衝撃的ですらあった)、革命期のあたりの歴史をよく知りたいなと思って買ったのだけど、読み始めたのだけど、紀元前8000年ぐらいのところから記述が始まり、今はやっと西暦1000年ぐらい。各地でいろいろな文明ができていたらしい、ということが勉強できました。勉強できましたとかちょっと斜に構えた薄笑いの感じで書いているけれども、なんでだか妙に胸をときめかせながら読んでいる。文明!みたいな気分だ。
これを読んでもうちょっと最近のことにフォーカスして知りたいなと思ったら鈴木康久という方が著している『メキシコ現代史』というのがあるということが今わかったので、そちらを読んでみようと思う。(それにしてもこの『メキシコ現代史』、Amazonで見たらフォーマットが2つあって、一つは3150円のやつ、もう一つは1200円のやつで、後者をクリックしてみると【ハ゛ーケ゛ンフ゛ック】というふうになっているのだけど、こういう割引の扱いができたこと自体が「へー」なんだけど、それ以上にこの綴りのいびつさがなんかもういいのかAmazonという感じでソワソワさせる。というところでもういいだろと思ってその【ハ゛ーケ゛ンフ゛ック】のやつを今注文した)そういった下調べをして「よし、メキシコ」みたいな武装モードになっていざ『2666』読んでみたら、まったく勉強必要なかった、みたいなことになったらなったで面白い。
メキシコ……
つい先日の朝、テキーラの瓶を見ながら彼女がつぶやいた。「プロダクトインメキシコ」 私は、メキシコ…と思いiPodから流していた音楽を変えた。それはメキシコ、メキシコ、と歌っていた。それを聞いた彼女は、「あの映画のやつみたい、黒人の奴隷の人と歯医者が組んで懸賞金を狙う…」と言った。メキシコ!私は思った。それはまさに、その黒人の奴隷の人と歯医者が組んで懸賞金を狙う映画を作ったタランティーノの『デス・プルーフ』のサントラから流した曲だった。たった一曲で映画作家が浮かび上がるというこの尋常ならざる事態に私はおののき打ち震えながら、あの、六本木で友人と見た『グラインドハウス』の上映、細い足が振り落とされた次の刹那に起こった映画館中に響き渡る拍手を思い出した。あれは、私の映画体験というか映画館体験において最も幸福な時間だった。ブラボー、ブラボーと、私は他の客と一緒に手を打ち鳴らしながら、流れ続ける涙を頬に感じながら、胸中で叫んだのだった。そしてまた、渋谷の映画館で見た『デス・プルーフ』のことも。二度目の鑑賞とあって余裕もあった私は、このバカ素晴らしい映画をバカ楽しく見ようとフロントでビールを買って臨んだ。そのビールが予告編が終わるまでに飲み終えられたこと。あるいはまた、同居人と海老名のシネコンに行って見た三度目のそれ。夜の死んだショッピングモール。『デス・プルーフ』の上映にまつわる様々な場面を私は思い出し、それは私をシンプルに幸せな気分にさせた。何かに熱狂すること。熱狂ということの喜びと大切さを今、私は『デス・プルーフ』の記憶を通じて、あるいは何時間も編み物をし続ける、暇があれば編み物本を読み編み図を見て何かを考えこむ、YouTubeで編み物動画をサーフィンする彼女の姿を通じて、あるいは『2666』に向けて足を踏み出そうとする、躊躇する、武者震いする自分の姿を見て、改めて思う。ちょっと読む前から『2666』に期待し過ぎているというか神格化し過ぎている気がする。よくない。
text
2013年11月5日
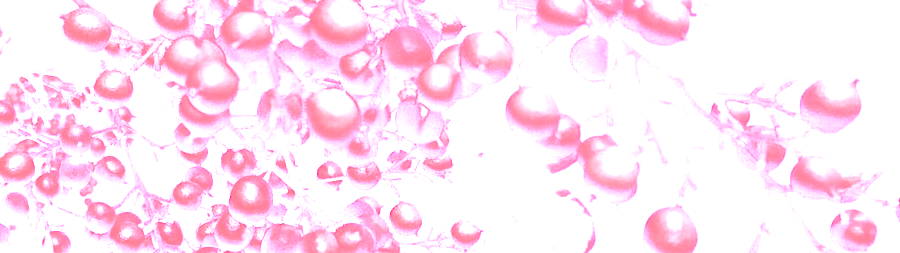
古本をあまり買わないのは私の読書行為はカバーのついた本を読み、読み終えたらカバーを外す、本棚に収める、までが入っているというところが大きくて、だから基本的にはカバーのついていないAmazonで買うことはなくて、どこかの本屋で買ってカバーをつけてもらうという流れがあるのだけど、それ以外にも古本屋を利用しない理由としては買ったところで著者なり出版社なりにお金が回らない、それはきっといいことではないだろうという認識があるためというのがあって、一冊売れたところでの影響などたかが知れているのはそれはそうだろうけれども、私は少しでもそれを作った人たちに何かしらの還元をおこなえるのならばおこないたいのでそうしている。だから古本屋で買う本というのはノーマークで、偶然見つけて、そこで偶然見かけなかった限りは買わなかっただろうという場合にだいたい限られていて、そこで買うのは、サンキュー、古本屋さん、出会わせてくれて、というところがある。
そういう気分は持ちながらも、珍しく、一週間のあいだで二度も古本を買うということをおこなった。一つ目は最近出来た古本屋で、そこはサブカルなものが好きなんだろうなあという色合いのお店で、色があるというのは好みの別はあれいいことだなと思いながら、あまり好みのものは置いていないと思いながら、なんとなく中原昌也の自伝と暴力温泉芸者のCDと高橋源一郎の小説を買った。二度目は昨日の朝に家の近所の公園でマーケット的なものが催されていて、それは愉快な催しだなと思ったし、人見知りながらもちゃんと知った人に出くわせば「あ、おはようございます」ぐらいは言って、以前同じ催しに行ったときに知った人に出くわして挨拶をし続ける状況に辟易というかしんどいと思っていたのが嘘のように、朝の爽やかさに乗せられる格好でそれなりに爽やかな気分を維持しながら挨拶することができたのだった。そこで古本屋も出ていて、一つは面白いと思えるものが置いていなく、並ぶ本を見ていてもけっこう残念な気分になるというか、なんというか、何が並んでいたのだったか忘れたけれど、ある種のブックオフ的な品揃えに見えたというか、少し前に話題になったような本の、古本とか古書とかいうよりは中古品といった方がニュアンスがわかりやすいような気がするのだけど、それは例えば村上春樹の岬がどうのこうのみたいなタイトルだったと思ったけど今検索したら岬なんていう文字はどこにも入っていなかったのだけど、それが印象的というか決定的というか、村上春樹を置くのがダメというわけでは全然ないのだけど、というか、だからここで村上春樹の名を挙げるのはフェアじゃないような気もするのだけど、なんだかとても、あーはいはい、という気持ちになったというか、あの本はたぶんあの日、誰かが買うのだろう、絶対誰かが買うはずだ、それは「中古」で、いくぶん安く手に入るからだ、という、確信めいたものが、あーはいはいを助長させたというか、ともかく、古本屋は、何を置くかということも当然大事だろうけれども、何は置かないかということもすごく大事というか、あーそれ置いちゃう、というのを感じてしまうと一気にだるい心地になるというか、それはもちろん、商売でやっているのだから売れる本を置くのは大事だとは思うのだけど、いや、古本屋であればその商売上、何を売りたいのか、何を売る店だと認知されたいのか、みたいなのがある方が商売上もやっぱりいいのではないかと思うのだけど、なぜならばあの日あの場所で村上春樹の中古本を買った人は、その店がなんという名前で、どこに行けば買えるかを知ろうとすることは絶対にないと思うからで、一方でもう一つ出ていた古本屋では、私たちはそこで何冊か買ったのだけど、コンラッドの『密偵』だったかな、そんな感じのやつとボルヘスの『夢の本』だったかそんなタイトルのやつと、あとなんだったか、とにかく何冊か買ったのだけど、私はそこで本を買ってから、のちに検索してどういう古本屋なのか、そこでは他に何を買えるのかを調べることになった。それは商売上、客の動きとしては悪くない動きではないだろうか。ということだった。
それにしても、古本屋とか先日あったというか毎月やっているらしい古本市とか、覗くといつも思うのだけど古本屋の人たちは幻想小説というのか耽美小説というかそのあたり全然わからないのだけどそういった類の小説がすごく好きだよね、という印象を受ける。サドとか澁澤龍彦とかバタイユとか、わからないけれどもなんかそういう感じ大好きだよねといつも思う。べつだん強く興味をそそられないけれど別に嫌だとかは思わないのだけど、外国文学っていったら幻想とか耽美とかそういうものでしょみたいな空気があったりするのだろうか。中原昌也とかを買った古本屋でも、外国の小説はほとんどなかったにも関わらず『ソドムの百二十日』以下そのたぐいのものはあって、ちょっとモヤモヤするところがあった。べつだん強く興味をそそられないけれど別に嫌だとかは思わないのだけど、どうも、なんだか、ファッションとしてのそういう類の小説という部分があるようにどうしても感じてしまって、そう感じてしまうと一気に気持ちが悪い。
なんでもそうだけどファッションとしてやってるでしょーそれ、みたいなものが透けて見えてくると気持ちが悪いもので、結局、ファッションとして、外皮に装飾を施す行為として何かをやっているように見えるものに感じるのは、そのコンテンツそのものを本当に信じてはいないのではないかという疑念であり、それは古本屋の品揃えに限らず、何かしらに対する発言だってそうだし、催されるイベントにしたってそうだし、なんだってそうだ。本当に信じないと、のめり込まないと、大好きだと、絶対にこれは良いものだと、確固たる姿勢で言えなければいけないなどとはまるで思わないのだけど、信じてなどいないものを不器用に装飾して提示されても薄ら寒さしか覚えない。信じていなければいけないなどとはまるで思わないというのは、信じていなくても全然いいからせめて信じきっているような華麗な嘘をついてほしいということで、ほしいというか、うまく嘘をついたらいいのにな、というところで、往々にして、信じていない人は全然うまく信じているふりをすることができない。ここのところ、そういう、目の前のコンテンツの力を根本的に全然信じられてないんだろうなー、ただの利用する対象ぐらいの感じなんだろうなー、みたいな気分になることがあり、なんだかなー、それ、いったい誰が幸せになるの、と思うのだった。
ファッションなんて犬にでも食わせとけ、というところだった。
book text
2013年10月26日

iOS7へのアップデートをしようと思って、以前やろうとしたらうまくいかなかったので特に気にしないまま過ごしていたのだけど、前日に人と話していた際にその話になり、パソコンにつないでやったよ、と言われたので、そういうやり方があるのか、と知り、それを実行するためにパソコンにiPhoneをつないでいざアップデートしようとしたところ、OS Mavericksというのが出て、それへのアップグレードが無償でできるよ、ということが知らされたのでそれも併せておこなったのが二日ほど前の話で、そうしてみると全然詳しくないので何がなんなのかうまくわかっていないのだけど私の使っているMacはMacBookAirはMBAは何かが、メモリーが?4GBのやつで、これまではあらゆるアプリを閉じているときの残りのメモリー?メモリーで合ってるんだよね、メモリーが2GBぐらいだったのだけど、アップグレードをしてみたら1GB未満で、chromeでも立ち上げた日には簡単に100MBを下回り、今見たら52.9MBという状況で、これはとても少ないように思えるのだけれどもそのあたりについてはいかがでしょうか、と誰に聞くわけでもなく聞いた。台風と前線の接近により一日中雨だった。前線というのが、ヤンボーマーボーの天気予報を見ていた時代から今に至るまで、なんのことかわからないでいる。27年ほど生きてみたけれど、いまだに、あるいはいよいよ、ますます、世界は未知で満ちている。それはそれで悪くないことだと思い、何か偉い経営者とかの話でも聞いてみた方がいいのではないかと今日丸善に行った際にそういった経営コーナー的なところに立ち寄って、どういう本があるのだろうか、何が今の私に導きの手を差し伸べてくれるのだろうかと本棚を眺め回していたのだけど、今の私は何を読んだらいわゆる「学び」であったり「気づき」であったりを得られるのかわからなくて、多分、学びや気づきという語に対してわざわざ鍵括弧を付けないでは済ませられない、「うへえ…」みたいな忌避感を持って臨む限り、そういったものは得られないのだろう。いやそんなこともないというか、そういう紋切り型とか思考停止的なものに対する警戒感はいつだって持っていたいというか、だってそうでしょう、学びとか気づきとか、言葉を侮辱するなというか、なんかこう、そういうのあるでしょう、と苛立ちが頭をもたげてくるのでこれっきりにしたいところなのだけど、だってそうでしょうと打つとshing02のどれかの曲を思い出す。それを聞いていたのは高校生の終わりの頃だったように思う。音楽や、たぶん特に音楽だと思うのだけど、音楽のことを考えるといつも高校生のときに戻るというか、高校生のときにそんなにライブに行っていたようにも思えないけれども、ああそれは高校生のときに行ったわ、みたいなことがよくあって、先だっても人にdownyのアルバムを貸したところから、そういえばdownyを見に新宿のロフトに行った夜があったということが思い出されたのだった。その夜はdownyとブルーハーブの2マンだった。ブルーハーブを、存在は知っていたのか、知らなかったのか、私の耳はまるで格好いいものとしては聞かなくて、ペラペラよく喋る、ぐらいに思っていたのだと思う。私は学ランを着てロフトの白と黒の格子の床、あれはステージがそうなんだっけ、フロアもそうなんだっけ、忘れた。格子の床。学ランを着て、鞄はどこかに置いて、私はそのライブを見たのだった。それを思い出した。それを先だって思い出したのだけど、一方で、先日人から「どんな映画が好きなんですか?」と問われたときには何も思い出さないということがあり、私はやや愕然としたというか、こうやって私の頭から固有名詞が一つずつ消えていくのだろうかという恐れのような感情を抱いた。昔であればぽんぽんぽんと何人もの映画監督、いくつもの作品タイトルが口をついたように思うのだけど、いま私は失語症に陥ったかのように、言葉を発することができないのだった。たぶん覚えやすいからなのだろう、アンゲロプロスという語は咄嗟に思いつくのだけど、それに続かない。運命のつくりかた?それも全然間違っていないのだけど、そんなにすぐに出すタイトルだっただろうか。どんどん、遠のいていく世界がある。かつての、ゴダールのどれかを見ている時に生徒より先に「感情教育!」と声をあげた私は、消えつつあるのか。それを惜しむ気持ちもあれば、それはそれでそういう時期であるという気持ちも一方であり、5年前、あるいは6年とか7年とかなのかな、それぐらい前の、大学生の時分の、見られる限り映画を見ようとしていた青年に「なあ信じられるか?5年か6年か7年後のお前は本屋行って著名な経営者の言葉を聞きたいとか言ってるんだぜ。蓮實とかゴダールとかメカスとか、いや、そういうのはそういうので全然欲してるんですけど、でも経営とかってどういうことなのかなとかってやっぱり読んでみたくて、みたいなことオドオドしながら言ってるんだぜ」と言ったとき、彼は何を思うのだろうか。「ジュノ・ディアスの『こうしてお前は彼女にフラれる』、フリオ・コルタサルの『かくも激しく甘きニカラグア』を読んだ。今日は経営本はいいのがわからないのでパスしてやっと届いたホルヘ・エドワーズの『ペルソナ・ノン・グラータ』を買った。」どうだろう、と私は5,6,7年前の青年に問うこともできる。まだ大丈夫そうだとも思わないか?まだ小説とか、うしろ二つは小説じゃないけど、なんかわかんないけど文化的なものに対する渇望というか熱心な接し方には変わりはないだろ?だったら経営の本とか読もうとしても、そのぐらいは許してやってもいいんじゃないか?現実との折り合いの付け方。悪くないんじゃない。それはそれで。そう問いたい。うん、まあ、そうかもね、と5,6,7年前の私だって答えてくれるだろうか。答えてしまっているだろうか。それで、だから本を読んでいる。ドミニカ、ニカラグア、そしてキューバ。私は勝手に中米めぐりをしているなと思い込んでいたのだけど、本来的には中央アメリカに該当するのはニカラグアだけで、西インド諸島を構成する大アンティル諸島を構成するキューバとドミニカは入らないらしい。広義の、ということにすれば入るとのことだった。今ウィキペディアが教えてくれた。ジュノ・ディアスはすこぶる面白かった。わりと本当に切ないじゃないか、と思いながら、結構のところ胸を締め付けられながら読んだ。その短編群の中では少し異質というか、子供時代の出来事が書かれている「インビエルノ」の、家族が狭いアパートに閉じ込められる閉塞感と、ある雪の夜の散歩の情景が悲しく美しかった。いや、どの短編もすごくよかった。フリオ・コルタサルは『石蹴り遊び』とかがたぶんとても有名なアルゼンチンの人だけどなぜか食わず嫌いというか読む気が起こらなくて、これはセルヒオ・ラミレスの『ただ影だけ』の舞台になっているニカラグアについてのエッセイというかそういった文章なので、ニカラグアという国への興味から読んだというか、夏休みに吉祥寺の古書店百年で買って、やっと読んだというところなのだけど、長く続いたソモサ王朝の独裁をサンディニスタ解放戦線が1979年とかに打倒した翌年、80年からコルタサルが死ぬ前年83年までに書かれてたぶんスペインとかの新聞に掲載された文章で構成されたニカラグアを応援しようぞという本なのだけど、ニカラグアですごいことが起こっているぜ、これはもうなんかすごいことだぜ、というトーンが、次第次第に暗く、けっこうやばいぜニカラグア、となっていく様が興味深いというか何かの推移を物語っている感じがして面白い。面白いとか書くとコルタサルから「ほらここにもファーストフード野郎」とか指された挙げ句に説教されそうだけど、それはいいとして、コルタサルは革命後のニカラグアをすごく賞賛していて、同時にカストロ率いる革命キューバに対しても肯定的な立場を取っているのだけど、革命後のキューバがやばい状況だったことはいくらか前に読んだレイナルド・アレナスの『夜になるまえに』でも描かれていたし、たぶん標準的な国際世論でも「あれはやばい」みたいな感じなんじゃないのかなとおもうのだけど、知らないけど、ニカラグアというかサンディニスタに対する評価というのはどういうものなのだろうか。歴史はそのあとにサンディニスタ大失敗、という結果になったことを教えてくれるけれど、それもこれもコルタサルが言うようにソモサ残党及びそれを支援するアメリカのちょっかいがなければ何かが美しくなされたのだろうか。それともキューバみたいにあれはやばいみたいなことになったのだろうか。コルタサルの文章を読んでいると、革命後にサンディニスタがおこなった、おこなおうとしていたことはとても素晴らしそうに見えるのだけど、そんなシンプルなものだったのだろうか。一方で、今日読み始めたホルヘ・エドワーズの『ペルソナ・ノン・グラータ』はチリ人の著者が外交官時代にチリ大使としてキューバに滞在した1979年末から数ヶ月のことが書かれているっぽいのだけど(これ間違えた。1970年12月から71年3月。だいぶ間違えた。)、ここで描かれるキューバはわりと「あれはやばい」寄りの感じっぽく、カストロは疲れた顔をして演説している。砂糖黍が目標の量取れなかったじゃないか!と国民に対して憤怒している。「そりゃ無理に決まってるだろ」みたいなことがアレナスの自伝にもあったような気がした。様々な人の視点から歴史を見るというのは面白そうですね。そういうこともあって、今日休憩時間に本を買ったあとに行ったコーヒー屋さんでは、コロンビアとニカラグアの二択だったので迷わずニカラグアのコーヒーを飲んだ。おいしかった。その前に古書市をやっているところに出くわしたので、そこで見つけた蓮實重彦の『反=日本語論』のハードカバーを買った。文庫では持っているということはお前もすでに知っているだろう。お前はその本をキャンパス内のサブウェイで読みながら、不覚にも涙を流して、まるで素晴らしい映画を見た時のような涙のこみ上げ方じゃないか!こんな泣き方は今まで読書でしたことがなかった!ビバ、蓮美!とか思って感激したのだったろう。俺は今でもそれを覚えていて、それが強く残っていて、だからわざわざ、必要もないのに今日また買ったんだよ。どうだろう、5,6,7年前の私、このことに免じて今の私を許してくれはしないだろうか。
book text
2013年10月21日
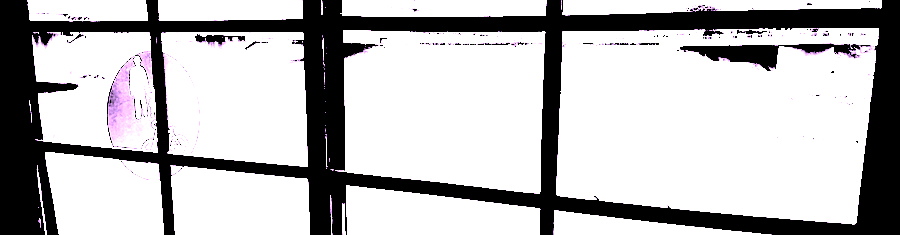
かつてスターバックスに行った夜にレジで「これどうぞ」と言われてカップの上でドリップする商品のサンプルか何かをいただく機会があり、その時だったかその時でなかったか忘れたけれどスターバックス、パーソナルドリップ、オリガミ、いずれのアルファベットの単語の横にもレジスタードトレードマークを意味する丸に囲まれたRが付されており、このペースで世界に登録商標が増え続けた場合、私たちはいつの日かまともに会話するだけで何かしら請求されるようになるのではないか、という話を今晩彼女として、そのときに私たちが武器にするのは言い淀みや吃音であるといった結論に至ったわけではなかったが、どこを引いても似たようなものが見つかるのでそれは本当にどこでもいいのだけど、例えば「その短い合間に女の前腕を撫でながら、二人の間で一節一節を際立たせるようにして話すその姿は、言葉を積み重ねていけば痩せこけた顔を少しはごまかすことができる、女がありきたりの質問をしてこないかぎりは大事な何かを救い出せる、そんなことでも考えているようだった」というような文章は、バス停の前のカフェというのか酒場というのか何かそういった類の店の店主の視点から描かれている文章であって、あるカップルの行為を見つめる店主がずいぶん勝手に妄想を膨らませてそんなことを思っているというわけなのだけど、ここにはどんな躊躇も、思考の吃りも感じられず、嬉々として何か、「文学」的とでもいうのか、そういった世界に安心して身を委ねているような気がどうしてもしてしまって、フアン・カルロス・オネッティの『別れ』はだから、一つも面白く読めないままに終わってしまった。このウルグアイ生まれの作家のものは、先月か先々月に読んだ『屍集めのフンタ』も全然楽しく読めなかったのだけど、ホルヘ・エドワーズの『ペルソナ・ノン・グラータ』を買いに行ったら在庫がなくて、それで代わりにというか、水声社の「フィクションのエル・ドラード」シリーズの第4弾ということで、出ていたんだ、というのを店頭で知り、どうだろうという懸念はありながら、このシリーズは追っていきたいような気でいるので買ったのだけど、懸念はそのままに的中し、私はオネッティの小説は今後は読まないようにするべきだという結論に至った。オネッティの文章は私にはすごく気持ちが悪くて、どこまで人の思考みたいなものにずかずか無遠慮に入っていけば気が済むのだろう、無礼だ、みたいな気になるというか、要すると「うるせーよ」と思ってしまうので、そういった人間にオネッティの読者になる資格はきっとない。バルガス=リョサを始め多くの作家がオネッティを「すごい」と言うらしいのだから、きっとすごい作家なのだろう。表題作とあと短編2つを収めたこの作品集の中で、唯一、本当にたぶん唯一、私がいいねボタンを押したのは「他方、青年といえば、極度の臆病者、そして皮肉屋だったが、ある冬の日の夕方、恐怖と風邪、やましい心とあの世と三十八度の熱に怯えて眠るバルテーのベッドへ近づき、用心深く、それでいてはっきりと、こう呟いた。「二つお許し下さい。私を共同経営者にすること、すでに公証人とも話はついています。嫌なら私は出ていきます。薬局は店仕舞い、これで商売も終わりです」」というくだりで、「バルテー弱り目に祟り目www」と思った。そのため今日は「どうしていつも、うまくいかないのだろう……。」と帯文にあるジュノ・ディアスの『こうしてお前は彼女にフラれる』を買って素敵なカフェ的な場所で読んでいたのだけど、買う時はなんだかそう乗り気でなく、いくつかの場所でやたら面白いと目にした『HHhH (プラハ、1942年)』を読んでみたいというような、ラテンアメリカから私を引っ張りだそうとする磁力を感じたりもしていたのだけど、「まあとりあえず2666読むまでは、年内は、小説についてはラテンアメリカ縛り継続で…」という内なる声に従って買ったのだけど、読んでみたらやっぱり面白いもので、4編ほど読んだけれどもどれも充実していた。「アルマはメイソン・グロスの学生で、ソニック・ユースを聞きマンガを読むオルタナ系のラティーナだ」とか、別になんていうことのない一文だけど、もうそれで十分という気になってくる。この短い「アルマ」という一編もまた、すごくいい。「なあ、これはおれの小説の一部だよ」とか、笑わないではいられないけれども、笑うその笑みもこわばりを覚えてしまう。とてもいい。ジュノ・ディアスの文章も軽やかで好ましいけれども、私がそれを読む向かいで彼女が読んでいた『スローターハウス5』の、「So it goes.」、そういうものだと何度も書くヴォネガットのありようを、まあなんというか、私の人生にもインストールしたいし、オネッティに欠けているのもそういうものだの精神なんじゃないかと、たいそう立派な作家の肩を叩いて私は言ってやりたい。今度は私が「うるせーよ」と言われる番だろう。うるせーよ、本読めねーよ、と思って私はジュノ・ディアスを途中で切り上げてカフェを出たのだけど、横のテーブルの若い女性お二人がたいへん賑やかに話をされていて、びっくりするぐらいに大きな声というか、耳に入り始めると全部持っていかれる程度には大きな声だったので読書どころではなくなって、本を閉じ、試しに「新潮のクレストブックスシリーズは始まって15年なんだって。長いね。なんかもっと最近なのかと思ってた、長くてその半分ぐらいの感覚。読んだことあるのは数学のやつとなんか忘れ物の駅のやつだけかな、あとオスカーワオと」と、若い女性のボリュームを自分も体験してみようと思って同じぐらいの大きさで発話してみたのだけど、その感想としては「やっぱり過剰に大きい」というもので、とてもじゃないけど、恥ずかしくて続けられなかった。「今日はよく話したねー」みたいな満足の声というものがあるけれど、あれはもしかしたらどれだけ多くの言葉を発したかという以上に、会話という運動の中でどれだけカロリーを消費できたか、が競われているのかもしれないと感じたのは、そのときだった。帰りの車ではそのことを話しながら、寄ったマクドナルドで購入したフライドポテトを食べた。いくらか前にSIMI LABの何かのyoutube動画を見ていたら、マクドナルドの添加物感がたまらない、死んでも死体も腐らなくて済みそう、みたいな会話がたしかなされていて、それを思い出したのだけど、そういう添加物ライフを謳歌みたいなものと正反対をいくであろう岡山の北の方、真庭市は勝山に店を構えるパン屋さんタルマーリーの方の本『田舎のパン屋が見つけた「腐る経済」』を最近読んだ。一度か二度は食べたことがあって、おいしくて、でも店には行ったことがなかったのだけど、本屋に行ったときに出ているのを見つけ、ただの岡山の人が出しましたという本であれば買うこともなかっただろうけれど、冒頭でレーニンの言葉を確か引いていて、なんだろう、ちょっと面白そう、と思って買ったのだった。わざわざ買った経緯と理由を言い訳がましく書くのはただ岡山の人が出した本だから買ったというふうに思われたら、いやあすっかり岡山に染まっちゃって、などと指をさされそうで嫌だなという奇妙な防衛意識からで、でもまあ多分、関係ない土地の、まったく聞いたことのない店の本だったら手にとってないんだろうなとは思うのでなんとも言えないところなのだけど、でもまあその本は、思った以上にとても面白かった。パンについても、「なんという…!」というこだわりというか実践が知れ、「うわーなんかもうパンの世界とか一切知らないけどこれはきっとたぶんものすごいことされてるわ~…」という思いをいだいた。ほとんど畏怖ぐらいにすごいなあと感じました。私はいったい何を実践できるのだろうと、そういうことを考えだすとわりと気が塞ぐというか、半端な自己嫌悪に陥るので自戒というか自重しないとと思うのだけど、とりあえずのところ思ったのはゲスなところに引き下げてという感じが否めないけどやっぱりテキストというのはこれからの時代すごい力になるはずですよねということで、いいものを作っています、いいものを売っています、いい場所を提供してます、それ自体はそれぞれに素晴らしいことですねと思うのだけど、だから、選んでくれますよね?という姿勢ではダメで、それならまだいいけれど、なのに、なんで来てくれないんですか?みたいなことを口走り始めたらもう最悪で、何かの信念を持っている人ほどそういういいもの作ってるのに売れないのは時代のせいとかお前のせいみたいなことを言う人が見受けられるような気がして、自己満足したいのか他人に認められたいのかわからないというか、社会とか他人に呪詛の言葉を吐いてそれでお腹が膨れるなら、口座に金が充当されるならそれもいいけどそうじゃないので、信念を持っていいものを作ってメイクマネーして生活を立てたいならばちゃんと伝える努力もしなきゃと私はいつも思っていて、この本を読んで「うわーそれ超行くっすわー、食べたいっすわー」と思わせられ、改めてそれを思った。ただそれとて手法として取り入れればいいというものでもなく、まず内実というか、信念とか何やらがあってこそなんだろうから、それは決して「うまいことをやる」というのが先に立つものではなく、まず何か信念というか実践というかそういった何かがあって、それをストーリーに仕立てて価値をちゃんと伝えるみたいな、その情報までパックして価値を高めるみたいな、書いていてどんどん気持ちが悪くなってきたというか吐き気がしてきたというかビールを煽りたくなるというか指が腐ってきたというかなんだけど、まあなんかそんな感じだよねーということを、それは再認という形というか補強という形だけど思ったのでいい読書だったのだと思うのだけど私の生きる場所は岡山ではなくてラテンアメリカなので話を戻すと『売女の人殺し』は最後まで本当に面白く、どれも面白く、特に印象に強く残ったのは「ブーバ」という作品で、「中盤にいた二人のディフェンダーがその場に釘付けになったように見えたんだ。俺は相手右サイドバックにぴたりと背後につかれたまま走り続けた。ブーバも同じく相手左サイドバックにマークされたままペナルティエリアに近づいてきた。そのときあいつがフェイントをかけてセンタリングを上げた。俺はこのボールには届かないだろうと思いつつエリア内に入っていったが、相手センターバックがボケッと突っ立っていたというか、急に気分が悪くなったみたいだったのと、ボールが変な動きをしたせいもあって、確かなことは、俺は奇跡みたいにエリア内でボールをキープして、突進してきたキーパーと俺の左背後にいた相手右サイドバックが反則覚悟で当たるべきか迷っているあいだに、簡単にシュートを放ってゴールを決め、俺たちが試合に勝ったってことだ」とあるようにサッカーが扱われているのだけど、サッカーの動きのある描写と、マンションでのスタティック(かつたいへんダイナミック)な描写、それらを回想する現在の描写の連携がなんかこう、たまらない類のものだったのだろう。そのことは「俺たちは、何年ものあいだ互いに音信不通だった。それがついこのあいだ、史上初めてチャンピオンズリーグを制覇したチームを懐かしく振り返るという趣旨のテレビ番組が作られた」というなんということのない箇所でほとんど涙が出そうになったことが証明している。とにかくボラーニョコレクションのこれからの刊行が楽しみなのだけど、年二冊ずつという予定らしく、しかも次はすでに読んでいる『通話』の改訳版ということなので、まあでも、今『通話』は人に貸しているということもあるし、「せっかくなので」みたいなところでこれも買って再び読むような気がしているが、年二冊ということはボラーニョコレクション全部読んだら『2666』行こうみたいなことをやっていたら何年も後になってしまうということで、やはり今年最後の一冊みたいなところで読むべきだろうかと、なんとなくそろそろラテンアメリカ縛りは終わりでいいような気もしてきた、つまり下火な気分が出てきたということもあるので、そろそろ、というところだけど、『売女の人殺し』に挟まれているボラーニョコレクションのアナウンスのチラシに煙草をくわえながらレンズを見つめるボラーニョの写真があって、「roberto bolano」で画像検索していろいろ見てみてもその印象は揺るがないのだけど、ボラーニョの顔はわりと佐々木敦に似ている気がする。『HHhH (プラハ、1942年)』で検索したら最初の方に佐々木敦の書評のページがヒットして、今は早稲田で教えられているのか、そして教授なのか、と知る。かつて私は毎週とても楽しみにして「ポップメディア史」という講義を聞いていた。大きい教室はオメガ館とかいったっけ。アルファ館だっけ。そういうことはどんどん忘れていってしまう。
cinema text
2013年10月17日

「「「「10月の天王山、3連戦最後の一日は一日中といって過言ではない程度に忙しく、その中でも作業の楽しさというのか、運動の喜びというのか、何かそういったたぐいのポジティブな気分を維持したまま私は労働することができたらしく、閉店後の店の外の席に座って呆けた顔でビールを飲んでいた。材質的なものに非常に疎いので何かわからないのだけど籐椅子的な雰囲気のその椅子に体育座りで腰掛け、ビールを飲んでいた。昨日ほどではなかったが星がいくつもまたたいていた。向こう岸や向こうの橋を間断なくというほどではなかったが車が通りすぎていった。その椅子からでは目が届かない地点で魚が何度か飛び跳ねていた。店の前の堤防沿いの道は車が通れない細い道なので、本来は走ってはいけない原付きに轢かれる危険性はあるにせよ基本的に車両との事故に遭う可能性は低く、また、洪水が起きてしまう可能性はあるにせよ基本的に水の事故に遭う可能性も低く、総じて安全な地点であると言えた。洪水、FLOODSと題された長編に続くとされている濱口竜介の『不気味なものの肌に触れる』を昨夜やっと見た。」とここまで書いて夜はビールの一杯の影響により断絶を余儀なくされ、向かいのソファで丸まるようにして眠る彼女を起こし家に帰ったのだったが、その翌日である今日の火曜日は雨降りということもあってかひたすらに暇な日中だったため、体力が十分に余っているらしく普段であれば昼寝に興じるところを、起きたままこのように打鍵することを選んだということだった。そのためコーヒーを淹れ、煙草を吹かしながら、外の雨音を聞きながらここに今いる。いつもより少し挽き目を細かくしてみたコーヒーは苦く香りもよく、これはこれでいいと思いつつも、この苦味は中煎りのこの豆ではなく深煎りの豆に担わせるべき苦味だとも感じられるため肯んずばかりでもいられない。連休中に限った話でもないけれども特に連休中はそういった傾向が顕著になるけれども、営業後の夜な夜なにフェイスブックでも開こうものならば、今日は誰それとどこそこに行ってかくかくしかじかを食ってあれを満喫、みたいな投稿がおびただしく並ぶため、いくらスクロールしてもそういった喜びの報告が視界から消えることがないため、あまり見すぎると健康によくないということはよくよくわかっているのだけれども、連休は私たちには連戦以外なにものでもないため、喜びといったものはマネーとして還元されるばかりで、行為の中の美しさを競うすべもない。その連戦中の唯一の報告可能な出来事は先述の通りに濱口竜介の『不気味なものの肌に触れる』を見た、ということであり、リリース直後にダウンロードしていたものの、見るタイミングを逸し続けていたところ、読んでいた蓮實重彦の『表層批評宣言』の中に「不気味」という語を目撃し、それは「ここで遭遇することになるものは、喪失だの崩壊だのと違ってそれ自身が充実しきった過剰であり、程よい感傷で湿った郷愁や未来への楽天的な信仰によっては処理しきれぬ不気味なる何ものか、得体の知れぬ怪物に似た絶対的な畸形性にほかならぬ」というように書かれていて、このあたりの章は私にもわかりやすく俄然面白く読んでいたのだが、後半、装置だとか風景だとかが語られ始めると次第に手に負えなくなり、ま、表層ってことで、ぐらいの感覚で読み終えることになったのだけれども、ともかく、この本の135ページ目で遭遇した「不気味」に触発され、そういえば、そろそろ、ということで日曜の晩、カレーをコトコトと仕込みながら、店のソファに座って洪水と題された長編に続くとされている中編、『不気味なものの肌に触れる』を見たのだった。毒されきっていることは自覚のうえで書くけれど、その50分ちょっとのあいだ画面に映し出されるものはことごとくが充実した過剰であり、ただただ、予兆としての不気味さというか不気味さとしての予兆のようなものが緊張感を一瞬も途切らすことなく持続し、いつ終わってもいいし、いつまでも終わらなくていいという満たされた宙吊り感の中、終わった。そこで提起されるのは事件としての徹底したアクション」とここまで書いて、そうだ、店のブログを書こう、となって中断され今に至った。あと20分で休憩時間が終わる。気づいたら外が暮れてきた。夜の部が始まる。雨は降り止んでいないことが外を歩く人がさす傘でわかる。傘は橋の光に下から照らされて『アカルイミライ』のくらげのように明るんでいる。『FLOODS』では、川にいったいどんな事件が起きるのだろうか。『不気味なものの肌に触れる』を見ている限り、阿部和重の『シンセミア』のような、どうしようもない規模の悲惨と破綻が待ち受けているようにしか思えないし、あるいは何も起きないような、そして絶えず何かが起き続けているように錯覚させる事件、あるいは一般には事件とは称されないような出来事が、運動があるのだろうか。その手が、その肌に、届かない、というそれだけが、すり抜けるというそれだけが、こんなにエキサイティングでスリリングな経験として浮上するのだと、その映画は言う。「まるで子供が暇つぶしに戯れる謎遊びのように、問題を、解答によって埋められる瞬間をむなしく待ちつつ「知の空間」にぽかりと口をひろげた過渡的空白だぐらいにしか考えようとはしない」思考には一つの満足も与えようとしないこの予兆と現在の映画を、」とここまで書いたところで営業時間になり、夜も驚くほどに暇で、数えるほどで、天気の悪い日はここまで落ち込むものかと驚きながら、連休で疲れていたのでこれもまあありだろうと納得して夜が更けていった。珍しくお客さんと遅い時間まで話し込むというおこないをし、閉めたあとは打鍵するつもりだったけれど遅くなったこともありビールを2缶飲んですぐに家に帰ってボラーニョの『売女の人殺し』を、その中のちょうど「売女と人殺し」を読んでから眠りに落ちた。その短編のような悪夢は見ることなく健やかに眠った。だから今日は水曜日で今はまた休憩時間になっている。この日記を書き始めて2日か3日が経ったということだった。長く書き継がれる日記。一方で一時間かそこらでささっと、ひどく軽いタッチで書いた店のブログは更新後一日の今の時点で、ここからはそう伸びないだろうけれども90のいいねをつけていていいねと思う。店のブログはいつも簡単に数十のいいねをつけるのでいいですねと思って、一方でこちらはついても10とか、一つもつかないこともあるから比べるべくもないのだけど、同じ書き手でここまで違うのだねと、すこしばかりの羨ましさにも似た感情を抱かないといえば嘘になる。いや別に羨んでもないけれど、はいはいあっそう、お店というのはずいぶん気楽ですね、みたいなよくわからない僻みの感情が芽生えるというのか。その店も昨日は一日中暇であり、報いを受けたんだ、お前は報いを、と店を指さして笑う自分がいたりいなかったりするというかいないのだけど、事業税納付の督促状というのがずいぶん前から届いており、それは黄色い封筒に入っていて否が応でも見るよねという格好で届けられたけれど、昨日やっと開封して、納付しないと差し押さえだって辞さないですよ、と脅し文句が書かれていた。払わなければならない。事業税は飲食業だとたしか所得の5%だったっけ、そんな具合の水準だったはずで、所得税で10%だったか15%だったか20%だったか抜かれて事業税でまた5%取られて消費税も今後は払う必要がたぶんあって、一体どれだけ抜かれるというか納めなければいけないのかと思うと、売上なんていうものは見て喜んだり悲しんだりしない方が健康だと思わないでもない。ひどい報いを受けることになるからだ。一方で数多く差し伸べられる手をことごとくにすり抜ける染谷将太の、ドッペルゲンガーのように存在する石田法嗣の、草原を駆け抜けたあとに撃ち抜かれ倒れる渋川清彦の、対峙する相手に依らず性的な香りを漂わせ続ける瀬戸夏実の、絶えず訝しげな視線を遠方に向ける村上淳の、常に音もなく現れ危険な戯れに興じる水越朝弓の、それぞれにまったく不気味なあり様や身振りで次々と画面に現れる人物たちは、その後に待ち受けているとしか思えない破綻や悲惨を、これは報いだなどと悲観的に受け取ることなく、その怪物めいた、幽霊めいたあり様を崩すことなくきっと通り過ぎて行くのだろうと見えるのだが」とここまで書いたところで休憩時間が終わり、夜の営業が始まり、もっとも幽霊めいていたのはほとんどセリフもなかった河井青葉だったようにも思えるが、昼はわりにちゃんと忙しかった店も急激な寒さのせいか、今宵とてわりに暇であったために私は彼女とアルバイトの方に向けてボークとインフィールドフライについて説明し、インフィールドフライの説明のあとに、かつて稲葉が、またそれより何年も前に秋山がおこなった頭脳的なフライ処理の模様を、少しばかりの興奮を持って伝えたのだったし、その後にはボラーニョの続きを読むことすらし、それは「いい知らせと悪い知らせがある。いいほうは、死後の生(またはそのようなもの)が存在するということ。悪いほうは、ジャン=クロード・ヴィルヌーヴが死姦趣味だったことだ」と始められる「帰還」という一編で、国際的なファッションデザイナーと一人の幽霊とのあいだに素晴らしい親密さが生じる模様を描いたもので、それは完全に心温まると言ってしまって差支えのない類のものだった。見ることも、触れることもできない存在との邂逅、いくぶんかの葛藤を経て生まれる親交、と韻を踏んでみたのは他でもない、ここのところ聞いた中でももっとも怪物的な、畸形的なヒップホップがOMSBの『Mr. “All Bad” Jordan』で、それがあまりによかったというか、異様というか異形というかとても心温まるものだったため、検索していたら見つけたOMSBによる2012年のアメリカのヒップホップ15選をなぞっていろいろ聞いてみるぞという気分になったからで、今日はLil Ugly Mane『Mista Thug Isolation』とKendrick Lamar『good kid, m.A.A.d city』を買った。Lil Ugly ManeはOMSBのコメントでは「汚ねぇしクソドロドロだし、この界隈では一番キチガイだと思う」とされているもので、休憩時間に聞きながらウトウトしていたら確かにドロドロした夢を見たような気になれる、とても心温まるものだった。このドロドロ感は今とても嬉しいものであるためこれから何度も聞くことになりそうな気配があるし、今はケンドリック・ラマーを聞いていて、ケンドリック・ラマーはフジロックで「今一番かっこいいラッパーだと思いますよ」と後輩の方が言っていたので喜び勇んで聞きに行ったところ、大味な、翌日後輩の方が言った言い方でいうと「メジャーヒップホップっぽい」ステージで、あーなんかそれは別にいいかなーという感じだったのだけど、後輩の方はまた、「アルバムはもっとアンダーグラウンドな感じなんですけどね」とも教えてくれていたので、いつか聞いてみたいと思っていて今のタイミングになったけれど、まだ数曲しか聞いてないけど「いやほんと、こっちのほうがライブより100倍かっこいいよ!」と早くも快哉を叫びたい。かっこいい。Lil Ugly Maneはバンドキャンプで買ったのだけど、ケンドリック・ラマーは初めてAmazon MP3を使って買った。itunesストアはもう1年とか前からDRMフリーで販売しているらしいのだけど、なんでだかずっと「はいはいitunesはDRMついてるんでしょ、じゃあ極力使いませんよ!」みたいな、DRMがついていたら実際どうなのかとかもほとんど理解せずに文句を言っている気分が抜けないため、今もitunesストアではなぜか買い物したくなくて、今回はそれでAmazon MP3を使ってみた次第だった。まあ本当に、どうでもいい話だ。きわめて寒いし頭が、ふいに何かが飛来したような痛みをさっきから何度か覚えているのだけど夜がもったいないのでビールを飲む。
←
→