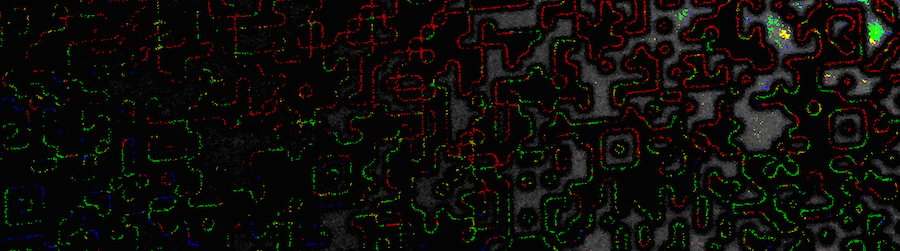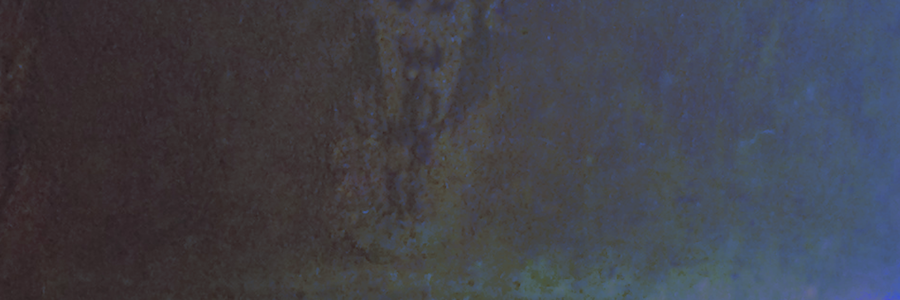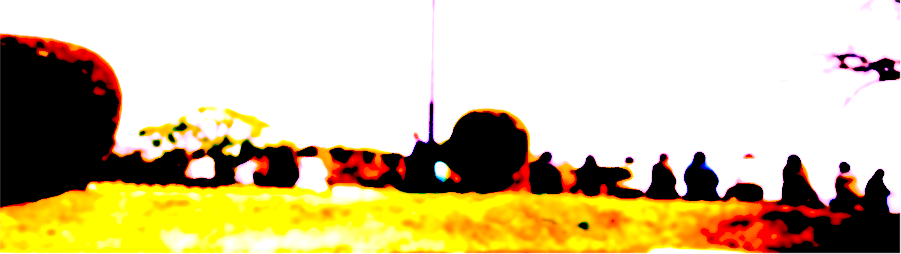book text
2014年6月25日
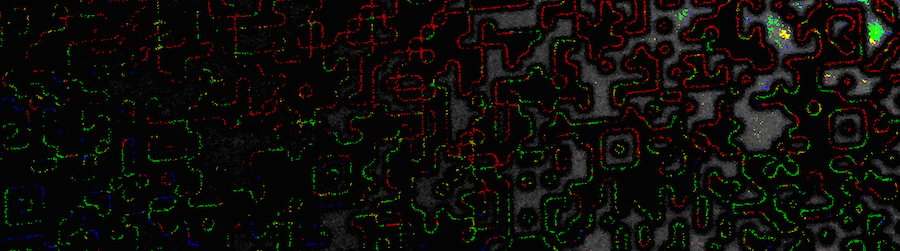
ギアナ高地はコロンビア、ベネズエラ、ガイアナ、スリナム、フランス領ギアナ、ブラジルにまたがってあると書かれているけれども地図を見た限りだとコロンビアはかすっている程度で、ブラジル北部とその他あれこれ、というところがだいたいというところのようだが、先日テレビをつけていたところギアナ高地を歩く人の姿が映しだされ、それはたいへん壮大な光景で、テレビというのもそう悪くないものであるどころか時によってはとてもいい、と思うきっかけの一つにもなったわけだったし、その数日後、日曜日の晩、夜7時からは鉄腕ダッシュが、8時からはイッテQが続けてある日本テレビは、とてもよいのではないか、素晴らしくよいのではないか、とすら思ってしまったほどだった。鉄腕ダッシュでは最高のラーメンを作るために最高の麺を作るために最高の小麦を作るために荒れた土地を耕すという段階が映され、イッテQではバヌアツ共和国の真っ赤なマルム火山が映された。マルム火山はちょっととんでもない赤さであり、私は諸手をあげて「ブラボー」と叫んだと、のちにその場に居合わせていた父母によって聞かされた。そういうこともあってか、昨日からジャレド・ダイアモンドの『銃・病原菌・鉄』を読み始めて、本屋に行った際に何文庫かわからないので探しようがない、と思った私はamazonアプリを立ち上げて「銃 細菌」で検索をしたのだが、ちゃんと教えてくれた。たいへんありがたい融通の利き方だった。
昨日から、だから、『銃・病原菌・鉄』を読み始めて、最近は惰性で本を読んでいるというか、適当に読んでいる感じがとても強かったため、それは生活の状況がそうだから仕方がない、みたいな言い訳をしたくもなるらしいけれども、でもたしかに今は何もない私、誰でもない私、みたいな宙ぶらりんで、早く、早く、みたいな焦りがある、ということはよく理解はできるけれども、でも実際に時間がないのかと言われればここ数十年のあいだで一番あるというぐらいに時間はいくらでもあるのだし、であるならば丁寧な読書をしてもいいのではないか、適当な読書をするのはその焦りみたいなところに押しつけておいてその実はただ怠惰に、早く、何冊も本を読んじゃおう、読んじゃうぞ、みたいな気持ちの現れなのではないか、という疑念も十分に成立するものであり、そういうところで『銃・病原菌・鉄』についてはちゃんと読むぞ、みたいなところで先月ぐらいに「本はこうやって読んだらいいよ」みたいな内容が書かれているブログで紹介されていたパラグラフごとに要約を書きながら読んでいこう、みたいな読み方を実践してみているわけで、ここらへん素直だなと思うのだけど、だからパラグラフごとに今は要約を書きながら読んでいるので時間はかかるのだけど、ここで思い出してほしい、私はいま時間だけはひたすらにあるのだ、ということを、という感じで、ノートを何枚も埋めながら読んでいる。
第一章は人類誕生から最終氷河期が終わる1万3000年前ぐらいまでを扱っていたのだけど、それを読んでいると、人類歴の長さ的にはアフリカ完全にチャンピオンというかすげーなーみたいなところがあり、なんせ500万年前だったか700万年前だったか、そういうところからずっとおられるみたいで、アメリカ大陸とか1万年前とかだから、アフリカのこの圧勝感はんぱないなー、と思って、人類とか、そういうことを考えていたせいだろうか。昨夜は人類が滅亡するところだったらしかった。
周りの人たちが次々と、気づいたらなんか変になって、体の一部を膨張させて破裂して死ぬ、という光景を何度となく見た。この調子で俺も死ぬ、今日死ぬ、ということがよくわかった。知り合いが子供を二人連れて海沿いの道を北部へ向かって歩いていた。少しばかり清々しい表情をしていたように思う。屋敷に集まっていた人たちの中にはここぞとばかりに私怨を晴らそうと凶行に出る者もあった。それはもしかしたらしょうがないことだった。屋敷も静かになった。パソコンだったかスマホだったかを見ると、何かのスレッドにメッセージがあれこれと書かれていた。もうほんと終わるんだなと、それはずいぶん静かな午後になってきた。家族は別々の部屋にいた。いたというか、一緒にいたけれど、ある段階で別々の部屋に移った。スマホの電源が残り19%だったところで落ちて、iPhoneちゃんはこういう日にもそれやらかしますかー、と思って、充電をしようかとも思ったのだけど、いやもう死ぬのにフェイスブック見るのもなーと思って電源落ちたままにした。なんだか喉に異変を感じた。これは死ぬ予兆なのか、と思った。死ぬことに対しては圧倒的な恐怖感があった。怖すぎるしまだ全然死にたくなかったなと思った。
という夢を見た。本当に怖かったので起きたのは8時前という早い時間で、わーこんな時間に起きちゃったし怖かったし夢で本当によかったと思って母が淹れてくれた茶を飲んだ。そのあとベッドに座っていたら寝ていた。映画は引き続き見ていないで私はビールを二つ飲んだ。そこまでやっていた作業はもはやはかどらなくなり、それはひたすらなリストアップの作業だったし、私はいったいいつ、新しい仕事を始めることができるのだろうと考えると気分は緊張したり塞いだりおちこんだりもしたけれど、私はげんきです、みたいなことになった。ビールを二つ飲んで、十分に酔っ払って、早く寝るつもりがまったく寝る機会がないのですでに3時半で、あと1時間半でキックオフなので私もそろそろストレッチを始めた方がいいのかもしれないと焦りを覚え始めた。先日どこかを歩いていたらルサンチマンの塊みたいな顔つきをした男が闊歩していて近づかなかった。
book text
2014年6月19日
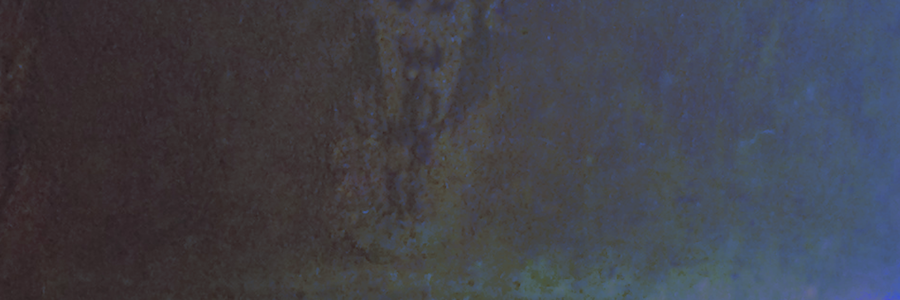
5球続けてだったか、6球続けてだったか、宮西の投じた直球なりなんなりを今成はファールにし、そのうちの2球が審判に当たった。一度はひどく強く喉の下のあたりに直撃したように見え、しかし実況や解説者がそれに言及することはなかった。今成は最終的にショートゴロでその打席を終えた。ゴロを捕った大引がそのまま2塁を踏んだか、セカンドの中島に放ったか、そのどちらかだった。先発の上沢が降りてからの日ハムはピンチ続きであり、誰が登板してもピンチを迎え、ようやく抑えたり、抑えられなかったりしていた。しかしダグアウトで戦況を見つめる上沢の顔はどれだけのピンチになっても妙に楽しげであり、それを見た私まで楽しい気持ちになってしまうほどだった。武田久のDNAを引き継いでいるのか、クローザーの増井はここのところいつでも塁を賑わせているように認識しているのだけれども、今日も簡単に危機的な状況を招き、どうにか同点で勘弁してもらう、というふうで試合は終わりそうな気配を見せず、私はテレビを消し、本を開いた。
先日人からいただいた小説で、作者の名前もタイトルも知ろうとしないまま読み進めていて、舞台は1950年とかのアメリカ、背がとても低く歯抜けで目が悪く吐血がち、ちょっとした異変にもビクビクしてどもりがち、とうてい信用できそうにない女に自分の素性と目的を簡単に晒してしまう、という特徴を持った殺し屋(腕利き)が、職業が物語る通りだけれども、人を殺そうとしている、という話だ。なんというか、出てくる女の様相もそうなのだけど、翻訳の言葉を荒くしていったらすごくなんというか「現代の……差別用語とされる……当時の状況を鑑み……芸術作品……原文のまま……」な感じにすごい勢いでなりそうな、何もかもが欠損している、という小説で、普通のミステリーを読むつもりで読み始めたのだけど、何かどこかおかしいことになっている気がしている。なんせ職務が遂行されそうな気配もない。
と、ここまで打ったところで放棄して眠ったのが昨夜のことであり、今日その小説は読み終えられ、解説を読んでいるとそれはジム・トンプスンの『サヴェッジ・ナイト』という小説だったということが発覚した。主人公は標的の住む小さな町に紛れ込んで情婦を作るわけだけど、ちゃんと町人らしく見えるように教師学校に行って授業を受けたりする、午後は斡旋されたパン工場で働いた、彼はいっしょうけんめいパンを作った、どうしてそこまでの、という熱意を持って業務に取り組んだ、その熱意の半分でも本来の任務に向けることができれば、彼はこれまでたくさんそうしてきたようにスムースに仕事を全うできただろう。ひどい、どうしようもない展開になっていく。それは非常に愉快なことだったし、読後感は清々しさすら覚えるようだった。私は満足して本を閉じた。
と、ここまで打ったあとにベランダに出て煙草を吸うと、私は黄色のアメリカンスピリットを吸っているのだけど、まるでなんか甘いフレーバーのついた細いやつとかあるじゃないですか、ああいうのを吸ったときのような奇妙な甘みが唇に残って、なんなんだ、これは、と愕然とした。それが少し前に飲み終えたコーヒーの影響であることは明らかで、なぜならそれ以外に要因が見当たらないからなのだけど、だから明らかで、それにしたって、こんな甘みは予期していなかったことだった。
今日、長い散歩みたいな物件探しの町歩きの途中に寄ったコーヒー屋さんで買った豆だった。なんの気なしに「じゃあこれで」と指さすと、値段これですけどと言われ、驚きひるみ100gのところを50gにしてもらって、というその豆は去年のカップ・オブ・エクセレンス3位というもので、先ほどがんばって丁寧に淹れて飲んでみたところ、飲んだことのないような味で、なんなんだこれは、というところだった。説明書きに「青リンゴ」とあったのだけれども本当にその通りの味がして、すごい、と思った。コーヒーじゃない飲み物を飲んでいるようだったし、馬鹿舌なのか、手放しで「美味しい!」とはなれなかった。難しい味でした。
そういうわけなので今日は散歩をし続ける日として記憶された、つまり何の成果もなかったし、いくらか食器を買った、素敵なカフェがあった、というところだったのだけれども12,3キロほど歩いたし、先日書いた通りにFIFAワールドカップのサッカーの試合をテレビで見るという流行りはすぐに廃れたので、今日も早く寝て、明日に備えたい。何一つ用事がない日々を生きるということは思いのほかに難しいもので、何を根拠に目を覚ましたらいいのかがわからないから長いあいだ眠ってしまい、一日が腐る。気がついたら人生も腐るだろうけれども、町は変わるところもあれば、十年を越えても変わらないところもある。意想外なものが変わっていないと、それは意想外なのだから当然のリアクションなのだけれども、えーまだあったの、と思ってびっくりする。あのろくでもない焼肉屋がいまだに健在とは、というところだ。町というか商売は不思議だ。
煙草を吸ってベランダから戻ってきた私は一目散に台所に向かい、金麦を取った。唇にまとわりつく奇妙な甘みを洗い流すためだった。すると3時間前のことが思い出された、というよりはほとんど3時間前のその時間の中に戻ったような感覚になった。家に帰ってきてテレビをつけるとちょうど試合終了のタイミングで、今日は大谷が8回を投げて1安打無失点という快投を見せたようだった。ダラダラと続いた昨日の試合で敗戦投手となったアンソニー・カーターが4点リードの9回のマウンドに上がり、ランナー2人を出しながらもなんとか抑えた。木こりのような容貌の大男カーターは、写真を見たこともないけれども『森の生活』のヘンリー・デイヴィッド・ソローを彷彿とさせた。ウィキペディアを見てみたらソローは全然そんなふうではなく、むしろエイブラハム・リンカーンのようだった。リンカーンの画像検索の中にソローが紛れ込んでいても、どうしたんだろう、ぐらいしか思わないかもしれなかった。しかしアンソニー・カーターは9回を無事に抑えた。
cinema text
2014年6月14日

映画を見ようと思って出かけたらどうやら近くで今晩エグザイルのライブがあるようで、たくさんの若い人々がエグザイルと書いたTシャツを着て首にタオルを巻いており、今日もまた、開場と同時にたくさんのグッズが売れるのだろう、ということがわかった。音源を売るのではなく、ライブで収益をあげる、みたいなことを初めて読んだのはクリス・アンダーソンの『フリー』においてだったかそれ以前だったか、それは忘れたけれども、フリーミアムモデルだとそういう感じになるよ、みたいなことが書かれていたような気がおぼろげながらするのだけど、エグザイルの状況を見ていると、ライブ及びグッズ販売は確かに大きな収益源になるのだろうなということがよく実感されたけれども、一方でエグザイルのような知名度がない音楽家の方々はどうなのだろうと考えたとき、と考えたのち、私は映画館の中に吸い込まれてウェス・アンダーソンの『グランド・ブダペスト・ホテル』を見たわけだけど、節々に「いいね!」とは思いながらも最後までそう乗ることなく終わってしまっていささか物足りない気でいたところ、エンドクレジットが流れていく様子を見ていたらぼろぼろと涙がこぼれていくのを知覚したのだった。音楽とアニメーションの愉快で楽しい調子に、うれしい、心揺さぶられる思いが強くしたのだった。
先日、京都に行った際に寄った恵文社の古本コーナーで見かけたので買ったウィリアム・サローヤンの『ママ・アイラブユー』がやっぱりすごくよくて、だから、ウェス・アンダーソンには、今作はシュテファン・ツヴァイクにインスパイアされてとあったけれど、次回作はウィリアム・サローヤン作品を下敷きにして撮ってほしいと思った。途方もなくチャーミングな映画ができそうな気がする。
ここのところは映画をまったく見ておらず、最後に見たのが先月の24日だったから、20日も見ていなかったことになった。24日は『デス・プルーフ』を見にバウスシアターに行った。ビールを買い込み、友人たちとそれを見た。たくさん笑い、泣き、勇気をもらった気になり、予定通りにかかと落としが決まった瞬間に喝采を送った。それは素晴らしい時間であり、そのまま友人の家に行った私たちは、今度は家で、もう一度見たのだった。そしてそれはやはり同じように素晴らしかったし、スタントマン・マイクがやたら美味そうにナチョスを食うシーンで一時停止され、友人は即席でナチョスを作ったのだった。そういった一日を美しいと形容しない場合、人生において美しい一日など存在するのだろうか、というような美しい一日だった。
しかしそれから先は私は映画をまったく見ておらず、なぜなら私のこの日々はバケーションではなく求職中のそれだからであり、実家に帰ってきてからは物件探しや内見等をおこなって日々を過ごしている。あまり焦らない方がいいとは思っているのだが、収入がない状態を続けていくような勇気も私にはないから、できたら早く店を作りたいと思っているが、いろいろなことをわかっていない私は物件を見たところでここから店を作るためにはどれだけの費用が掛かって、というようなことをまるでわかることができず、そして明確な物件のイメージも持っておらず、うろたえるばかりだった。やりたいことははっきりとわかっているけれども、物件や内装のイメージがないためつまずいている感があり、悩ましく思っている。飲食店開業の本などを手にとってみるのだけれども、そしてそれは参考というかなるほどということにはなるのだけど、そこにはたいがいの場合「夢」という言葉が出てくる。それが気に障る。これは夢ではない。と私は思う。やりたいことをするための舞台設計でしかない。夢などではない。
FIFAワールドカップが開幕して数日が経った。にわかサッカーファンになるというのは予感としては十分にあったことだったが、まさか、昨日の夜中から朝方までの2試合を見、明日は7時に起きてイングランド対イタリアを見て、そのあと日本対コートジボワールだぞ、みたいな感覚にまでなるとは思ってもいなかった。せいぜい日本代表の試合は、見るぞ、がんばれ、がんばれがんばれ、ぐらいだと思っていたので、わー4時のスペイン対オランダまで1時間空くのかー、仮眠してのぞもうかな、みたいなことを言って結局起きたまま試合を見て、うわーオランダ容赦ないなー、なんかちょっとなぜか泣きそうになってきた、みたいな妙な感情まで発生させるとは、思いもよらなかったことだ。明日は早い。今日は12時には寝ようと思っている。なんてまさかこんな、なんなんだこの、この感じは、とおののいている。数日で飽きると思っているが、どうだろうか。
物件がなかなか決まらない場合はアルバイトでも始めようか、と今は思っているが何をして働こうか、と今は思っている。なんにせよ開業資金というか貯金は目減りしていくだけだし高い住民税の通知も今日届いた。実際に開店に向けて動き出してからは、お金のことばかりを考えている気がする。これまでもお金のことはよく考えていたけれども今は脳裡にこびりついてはがれないような様子で、常にお金のことを考えている気がする。貯金額ではとうていできそうにないということが徐々にわかってきた感もあり、でももしかしたらできたりするというかできるぐらいのものをやるのが身の丈に合っているかなとも思いつつ、よくわからないのだけれども、借り入れを検討し始め、日本政策金融公庫にもちょっと行ってみた。貸してくれるといいのだけどと思いながら、借り入れをすることを考えていると夜よく眠れなくなる、という日が一晩だけあった。ただ、まだ救いはあって、「借り入れ」という言葉で考えている分にはそこまで悪くない。これを「借金」という言葉で考えだすとなんだかぞっとしてくる。同じことなのに不思議なものだ。だから結局すべての場面のそこここにサインがあって、私はそれを拾い上げながら涙を流したり、強く強く息を吐いたりするわけだった。人生を再び駆動させること。私にできるだろうか。昨夜の中継で初めてアディショナルタイムという言葉を知ったのだが、もうロスタイムとは呼ばないのだろうか。2010年、日本サッカー協会の審判委員会がロスタイムとは呼ばないことに決めたらしい。人生には空費時間なんてない、ということらしい。強くそう思う。
cinema text
2014年5月11日
強い風が家のベランダの向こうに広がる森というかいくつかの大木の葉をゆっさゆっさと揺らし、集まった太い持続音が私の耳に届く晩がいくつかあったが、その風が吹き始める数日前には雲が空をいくらか暗くさせ、降らないままでいてくれるだろうかとそこに集まった数十人は頭上の空を見やり一様に懸念の思いを抱いたものだったが結局は杞憂に終わり、友人の結婚式はつつがなくとりおこなわれた。
そこで私は初めて人前結婚式というものを見たのだったが、とても好ましいものだった。チャペルに通されたときには、片言の牧師によって祝福されるというあの茶番を演じるのだろうか、あの二人でさえも、と思っていたのでそうではない形式の結婚式が目の前でおこなわれ、それは清々しく好ましいものだった。一方であの茶番としか言いようのない片言牧師とて、そう悪いことばかりではないのかもしれない、というのはのちに人々と話している際に思い知らされたことだった。曰く、日本人牧師による挙式は、逆にガチにキリスト教色が出てしまって、それは多くの非キリスト教信者ではない日本人の男女にとって望むところではないのではないか、とのことだった。一理あると思った。
披露宴というかパーティーは、乾杯の挨拶とそれに付随する形のいくらかのスピーチというものを任されていたので、それが終わるまでは気が気でないというか、緊張しいなので話している途中でえづいたりしたらどうしようと不安に思っていたが、以前も一度友人代表スピーチ的なことはしており、そのときは話し始めたらペラペラと話せたものだから、まあそうなるかなとは思っていたのだが、それでも、ここのところは気のおけない友人と話している最中でさえも吐き気に襲われ、ちょっとトイレ、などと言って席を外しえづく、みたいなことがいくらかあったから、それがスピーチ場面に適用されないとは言い切れない、ということで不安は不安ではあった。結果としては想定外に声が震えるということが序盤にあったものの、全体としてはつつがなくとりおこなわれた。カメラが向けば、私の顔はいつだってこわばるのだった。カメラの前で素直な顔でいられた試しが生きている限り一度もない。
小学校時代の友人の結婚式だった。親しい人の結婚式は、本当にこんなにいいものはないなと、わりとシンプルな性格なのか本当にそう思えて、今回も本当に二人をもう完全にというか全面的に祝福しますわという祝福モードに街は包まれ、多くの参列者たちは選手団に大きな歓声を送った。赤いジャケットを着た選手たちも晴れやかな顔で手を振りそれに応えた。私はそんな瞬間があれば、それは根拠に、希望の、もっと言えば生きる、と、そのように、感じた。うれしかった。
小学校時代の友人で、新郎側の友人でもっとも多かったのは高校時代の友人の方々であり、私はわりと面識があったり遊んだことがあったりする人があったので、アウェーな気分に陥ることがなく安心だった。友人からは、中学3年生のときにナンバーガールの1stを録音したMDを誕生日プレゼントにもらったことがあった。それまでオリコンランキングに入る音楽以外に音楽があることすらほとんど認識せずにJポップを聞いていた私にとって、その音楽は衝撃以外の何ものでもなかった。だからそれは間違いなく私の人生を変えたし、何かを決定づける出来事だった。だからその友人は、私の人生にとって大変な重要人物だったし、高校時代の人たちの幾人かも、彼の何かしらによって大きな影響を被ってきたと言った。そういうことが十年後あるいは十数年後にこうやって振り返られることは、とてもいいことのように思えた。だから私はそう話したことのない彼の高校時代の友人二人と二次会までのあいだの時間を喫茶店に行って過ごし、喧々諤々と話をしたのだった。プレシャスな時間だったし、人生にとってこんなにうれしいことは、そう、という大げさなことすら思った。
二次会もとてもよく、そのあとに仲の良い友人と飲みに行き、総じて本当にいい一日を過ごした後の私はただの暇人であり、散歩をよくおこなった。3駅分、5キロぐらいを歩いてゆき、途中で喫茶店に寄ったり、ということをおこなって電車に乗って家に帰った。散歩前、家で映画をいくつか見た。『秋刀魚の味』と『嘘つきみーくんと壊れたまーちゃん』、『夏時間の庭』、『桐島、部活やめたってよ』を見た。いずれもよかった。『秋刀魚の味』はどうも初めてではなかったが、途中からは初めてとしか思えない気分で見た。岩下志麻の、あの顔の、おぞましいほどにゆっくりした動きにドキッとし、無数の矩形だけによって繋がれた画面の連鎖にぞっとした。みーくんもまーちゃんもチャーミングだった。そして夏時間の庭。本当に、びっくりするほどによくて、庭に座る人々のあの笑顔というか破顔というか、笑っちゃったあの感じの素晴らしさ。暗い部屋に座る老婆の影の美しさ、強さ。遺産相続という話もなんだかすごくいいものに思え、そして最後のあの子どもたち。なんて最高なんだ!!!!と思って立て続けに見た桐島、封切り時に2度見に行って以来、DVDで見るのは初めてだったのだけど、さすがにある程度冷静に見られるかと思っていたけれどやっぱりダメだった。ちょうど真ん中ぐらいだろうか、どこでだったか、今の酔っ払った頭ではうまく記憶を取り出せないのだけど途中で涙腺が崩壊し、鼻水を垂らしまくりながら最後まで見ることになった。やっぱり途方もなくすごい映画だと思う。
だから、というかそういうこともあって、カントの『実践理性批判』を買って読み始めたはいいけれど、進まない。理解しているのかしていないのかわからないというかしていないのだけど、驚くほど進まず、いくらかがんばって文字を追うのだけど、気がついたら手にはiPhoneが握られていて、2ちゃんのまとめサイトとかをサーフィンしている、2時間経った、みたいな夜がいくらかあった気がした。今は先月から読んでいるけれどこれもまた進まないヴァージニア・ウルフの『歳月』を読むことにした。登場人物がうまく把握できないながらも、少しずつ、歳月が経つにつれ、なんとなく輪郭が浮かんできたというか、人に生命が宿ってきたように思うし、章の最初にある風景描写はどれもすごくよくて、風や太陽が主人公となるということはやっぱり小説にとってというか読む私にとって、すごく楽しいことだった。今は少しずつ楽しい。
そういったこともあり昨夜は吉祥寺のバウスシアターにいき、牧野貴の『Phantom Nebula』を見た。いくつもの像が、光と轟音の中から浮き上がり、消えていった。銃剣を持ったインディアンの隊列が画面中央から下に向かって行進していく様子や、波打ち際で組み合う二人が倒れ、と思ったらエクソシスト的にがーっと後退していく様子、人面が何かに飲み込まれ変形していく様子が観察された。それは、残酷な自由をこれでもかと享受する時間だった。そのことに私はうろたえ、驚いたことに感動して涙を幾筋が流しさえしたのだった。それは残酷な自由だった。何が見えてもいいという圧倒的な自由。画面を見るということの本来的な難しさを突きつけてくる自由。自分が見たものが一緒に同じ画面に向かっているはずの何十人もの人とはまったく共有できないかもしれないということを前提に初めて手にする自由。どこを見るのか、そこに何を見るのか、すべてを自分で背負い込むしかないというような自由。自由とはかくも、という時間だった。
しかし端的に、すごく面白かった。牧野貴の映画はどれを見てもそう思うけど単純に面白くて、不思議なことだ。何を見てもいいから、とんでもないものが目の中に現れてくるから、しかも絶えず現れてくるから、こちら次第でいかようにも、だからなのだろうか。
その前に日中はK’sシネマでボリビアの映画を見たのだった。何が上映されるのかも知らずに映画館に行き、何が上映されるのか結局知らないまま上映が始まったのだけど、そこで見た『叛乱者たち』はどうも最新作とのことで、目玉の作品だったのかもしれなかった。人はすごく多かった。ホルヘ・サンヒネス、ウカマウ集団。そう面白くなかった。え、ボリビア、こんなにクオリティ高い映像を撮るの!?というところで面食らったところもあったのかもしれなかった。映像が目的ではなく、歴史を紹介するための手段にしかなっていないような気がしたのかもしれなかった。他のやつはどうなんだろうか。少し気になるが、どうなんだろうか。
今日もよく歩いた。表参道駅からぐるっと代々木公園のあいだを通って結局渋谷駅にゆき、そこからぐるっと表参道をかすめて神山町というのかな、アップリンクがあるあたりまで歩き、渋谷まで、という行程をあとで地図で測ってみたところ10kmくらいはそれだけで歩いたらしかった。昼から酒を飲むことをおこない、それはこのうえなく好ましい時間だった。夏時間の庭。帰ったのは結局終電間近だった。大宮から家までも、5キロほど、電車はまだあったけれどラーメンを食うことでその手段をなくして、歩くことにした。夜道は怖かったし、明らかに時空を超えただろ今、という道を消失する瞬間がありぞっとした。
text
2014年5月4日

先月か先々月に久方ぶりに見たハーモニー・コリンの『スプリング・ブレイカーズ』が意想外なことにあまりピンと来なくて、あの夏、映画館で見たときに私のうちに生じたあの熱狂はいったいなんだったのだろうと狐につままれたような感じになったのだけれども、映画館でなければ発生しないマジックがあるということだろうかというところだった。やはり冒頭のあの無根拠な楽天、圧倒的な物質としての体また体の放出みたいなアドレナリン全開の様子は、併せて流されるあの調子のいい音楽を大きな音で聞くことによって初めてちゃんとした、というよりも見事な、というか圧倒的な効果を生むということだろうか。あとはあの馬鹿げた画面を大人数で共有しているぞ、というシチュエーションの喜びというかアホらしさによるところも大きいのかもしれない。
そういうことなので今の私はスプリングブレイクの最中であり、ろくでもない高速バスに乗ったのは4月の最終日だったかもしれなかった。
3列独立シート。ギリギリで取った予約のためか私は最前列の真ん中の席に座らされ、消灯時間になると仮眠に入る運転手の一人が、現在運転中の運転手に向かって「起きてこなかったら起こしてください」と告げ、さらに「じゃ、寝ちゃわないように」と冗談めかしていい、それを受けた運転中の運転手は「あ、はい、気をつけます」と応じた。気をつけますじゃないよ!と私はいくらかの不安を覚えながらそういえばと思いだしシートベルトを締めたのだけれども、運転手稼業は本当に責任重大で、どれだけの俸給でおこなわれているのかわからないけれども、それは大学時代からバスに乗るたびにいつも思っていたことだけれども、彼らにはたくさんの俸給を与えてほしいよな、と思うのだった。
それを実現するためには高速バスの乗車料金を上げなければいけず、そうなるともはや新幹線とそう変わらない値段になり、そうなるともはや高速バスを利用するメリットがほとんどなくなる、という事態があったりするのかもしれない。痛し痒しだね。
そういうわけで運転席と客席のあいだにカーテンが引かれた。メレディス・モンクを聞きながら、眠られずに目を開けているとカーテンの上に無数の光が現れては消え、それらはある地点からぐっとスピードを上げてあっという間に通り過ぎたり、上に、横に、変な踊りを踊りながら消えたりと、長いあいだ見ていても飽きない光景だった。牧野貴の映画を、再び見たくなった。
到着予定時刻よりもいくらか早い6時すぎには新宿駅西口に着き降ろされ、小雨の降る中で喫煙所で煙草を吸っていると清掃員が三人ほど勢いよくやってきて、掃除をするから喫煙所の外で吸うように人々を促した。喫煙所の外に、簡易の灰皿が置かれた。そこに立っていると、喫煙所内に残された傘などのゴミがどんどんと外に放られ、足元を脅かされるふうだったのでまた一歩横にずれた。小雨が降っていた。6時過ぎ、それでもたくさんの人がすでにこれからという一日を生き始めているという情景を見ながら、一人、一人の顔であれば、私は彼らを肯定することができるのかもしれない、と思った。思い込みでしかないだろうか。何かに属して自信を持ったり役割を演じたりする顔ではなく、ただの一人である、何者でもないその顔であれば、なんとか肯定できるような気がその朝には確かにしたのだった。
7時までうろうろとしながらどうにかやり過ごし、開店したばかりのベルクに入ってモーニングとビールを頼んだ。やはり美味しかったし、初めてベルクで椅子に座るということができた。
無性に、ナヌークのノートがほしいという気分になり、ネットで取扱店を見ると大宮のエキュート内のスミスとあり、そこが9時半オープンだったので、新宿から鈍行で大宮に行ったり、エキュート内のプロントが経営しているっぽいカフェ・バーみたいなところで時間を潰したりして9時半すぎのスミスに行くと取り扱いがないとのことだった。なぜか諦めきれず、浦和のパルコにあるスミスに電話し、ない、と言われた。私は何かさも知ったように今ナヌークだとかスミスだとか打っているが、実のところは何も知らないのであり、デルフォニックスという名前はなんとなくは聞いたことがあったぐらいで、そもそもステーショナリーという言葉ですらおぼつかなく、駅?という感じがどうしてもしてしまうから、認識の構造を作り直さなければいけないのかもしれないし、ナヌークもスミスも、調べている中でそのときに初めて知った名称ということだった。あのノートがほしい、から始まった、ということだった。諦めて東急ハンズでろくでもないノートを買った。そのあと高島屋にあるジュンク堂で本を買った。岩井克人の『資本主義から市民主義へ』というやつだった。
それらを持ち、24時間営業をしている古い喫茶店に行って、ソーセージの盛合せとビールを2杯。ベルクで買ったベルクの本を読んだ。たくさんの名言というか、いやー、いいことおっしゃる、ということが書かれていて、たくさんメモを取った。店を出て実家に向かったのは13時ぐらいだった。この喫茶店はどうもだいぶ老舗の雰囲気があるのだけど、なんで24時間もやってるんだろうといつも思うけれど、年末に帰ったときに初めて存在に気づき、それから何度か来ていて、メニューがやたらに豊富で、完全に喫茶の枠を超えているというか方向性がよくわからない、という感じが好ましい。私はソーセージとビールで、右隣に座っていたご婦人はアメリカンを飲み、左隣りの若い、白々しい、妙なハイテンションの、ろくでもないとも初々しいとも言えるカップルというか男女はオムライスと豆腐丼なるものを食べていて、豆腐丼については「熱い、熱い」と女が連呼していた。このえうなく楽しそうに「全体的に熱い」と言っていた。
家に帰ったとてやることもなく、ソファで昼寝をした。起きれば暗くなっていた。夕飯を食べ、日をまたぐかまたがないかぐらいで眠り、翌朝8時には目を覚ました。勝手に8時に起きる、ということは私にとってはありえないことなので、「わお」といささか過度のリアクションの声を上げた。
8時に起きたとて、やることがないことには何も変わりなく、ご飯と納豆という朝ごはんを食べ、しばらく無為の時間を過ごし、10時前には大宮になんとなく出、美味しいコーヒーが飲める、と教わった店に行って確かに美味しいコーヒーをいただき、でもそこは長い時間を過ごすところではなかったのですぐにスタバに移り、なんとなくそこで過ごしていた。旅行や帰省のたびに思うけれども時間をやり過ごそうとすると本当に金が掛かる。
どうしたものか、と思い、思いついた友人に何をしているのかとメールをしたところコーヒーゼリーを食べるところで、とあり、それではここは一つどうだろうか、と尋ねると、それでは3時ごろにベルクで、ということになり、やったー、と思い新宿に出た。ルミネエストだし、みたいなところで性懲りもなくスミスに行った。ナヌークのノートがあったけれど買わなかった。ベルクではビールを3杯か4杯飲んで、ジャーマンブランチとソーセージを食べた。ベルクは、本当に素晴らしい場所だと毎度のことながら思った。一人の人間が一人の顔のままで入り、何ものにも脅かされることなく一人の顔のままで出ていける稀有な場所だと、毎度のことながら感動した。たいへん楽しい会話をおこなえたので満足して大宮に帰った。夕飯を食べ、10時過ぎには寝た。
8時ごろ起き、今日も今日とて何もやることがない、と思いながら時間が過ぎていくに任せ、美味しいコーヒーが飲める、と教わった店で美味しいコーヒーをいただいた。数日後に迫った友人の結婚式に着るスーツを持ってきておらず、買おうかと思っていたのだがどうせ着る機会などないのだからともったいなくなり同じ背丈の友人に借りることにして、代々木公園のあたりにいるよ、とのことだったので、でも受け渡しは夜の予定だったのだけど、何もやることがないから代々木公園なる場所に行ってみるか、と思い新宿まで出た。新宿からぐるっと歩いて、ビールを飲みながら参宮橋の方まで行き、代々木公園の入り口があったので最寄りのコンビニでビールを2缶買って公園に入り、緑の中でたくさんの人々が思い思いに過ごしているようで、まともに公園の中を歩くのは初めてだったので、とても素敵な場所というか素敵というよりはもっと、生きる根拠になりうるような場所だと思いとても心地がよかった。ビールを飲みながら『資本主義から市民主義へ』を読み、少し眠くなったので橋をわたって向う側に行ったら何かが催されており、ブラジル、ペルー、アルゼンチン、パラグアイ、メキシコ、といった国々の料理を供する屋台がたくさんあって、でも人がたくさんあって、どの場所にも行列ができていたので行列の少ないところでビールを買ったりタコスみたいなものを買ったり串焼きみたいなものを買ったりしてうろうろした。友人が、早い時間でも大丈夫、と言ってくれたので言われた場所にいき、スーツを受け取った。俺もう眠いぞ、と思っていたので助かった。
家に帰り、夕飯を食べて9時過ぎに布団に入り、本を読んでいるうちに寝ていた。目を覚ました。もう朝かな、という感覚で目を覚ました。時計を見たら1時にもなっていなくて、MLBの試合情報を見たら2時からとあったのでそれを見ることにして、この日記を書き、今さっき試合が始まり、やや高めに入ったストレートか何かを2番打者が右中間にぼやぼやと打ち上げ、と思ったらスタンドインしたので驚いた。そんな打球にはとうてい思えなかったのでびっくりした。
book
2014年5月4日
お望みなのは、コーヒーですか?――スターバックスからアメリカを知る
大学生最後の一年間ぐらい、スターバックスでアルバイトをしていた。漠然と抱いていた「偽善」というイメージ自体は最後までなくなりはしなかったけれども、この上なくフェアな職場で、働く環境としてはすごく好きだった。いやほんと、この店をもっとよくしていきたいよね、と、ただの学生バイトの身でありながら思っていたし、同じ立場でそう思っている人が実際にたくさんいたから、なんかこう、終わったあとに飲み屋に行って「この店を」とか話したりして、「うわ、偽善の内側に俺は今」と思いながらも、とか思うのはもしかしたら偽悪かもしれなくて、まあ、こうやって打鍵しているとこっ恥ずかしい気になって赤面及び頬が緩む感じがあるのだけれども、なんかこう、楽しかったんですよね、スタバ、というところだった。最後の日は大号泣、という。今考えてもなんともこう。
それが2007年とか2008年とかだったから、ちょうどスタバの業績不振が騒がれているころで、ということはこの本を読むまでは一つも知らなくて、そしてスタバのブランドが陳腐化されていき、客層は平均年収8万ドルの富裕層及びクリエイティブ・クラスから平均年収5万ドルへと落ち着き、という流れもこの本を読むまでは一つも知らなかった。そして当初は「ビジネスピープル、旅行好きの人々、本を買うのが好きな、「まともな稼ぎのある人々」」を明確にターゲットにしていたということも。
僕の中でのスタバのイメージはずっと変わらなくて、盛り上がりも衰えもあまり感じたことはなくて、特別な存在でも悪の権化的な存在でもなく、なんかまあどこにでもあって、キレイで、落ち着けるかどうかはわからないけれどもイヤホンさえ挿せば本は読めるしパソコンを開いても問題ないし、という便利で使い勝手のいい場所だ。圧倒的にプレディクタブル。
プレディクタブル(予期可能性。この単語なかなか覚えられない)。これは本当に長所で、「真正なものを消費する。人びとは一見このことを支持しそうだが、そうでもないのだ。人びとは真正さを犠牲にしてでも、汚れ一つない、なじみ深い場所を求める」や「外に出て皆がいる公共の場所に行きたいけれど、絶対に安全で予期可能な環境でなければ嫌だ、という願望を人々は誰しも持っている」とあるけれども、だからこれは本当に長所で、いや本当に長所だよなーと思うので、現在の僕はスタバかサイゼリアぐらいにしか行かない。プレディクタブルっていうのは場所にとってはすごく大切な要素だと思う。少なくとも僕のような、選択という行為のコストを高く見積もり、安全性に重きを置くような人間にとっては、何も考えずに行けるのは極めて楽だ。(極めて楽って打ってみたけれど、わ、極楽、と思ったのだけどそういうつもりというか極楽だとは思ってはいないというか別にそんなこといちいち言う必要はないのだけど。)
だから、本書では、スタバという企業は、というか総じて大企業というものは、ポストニードの経済秩序のなかで鍵となる概念だという「約束」をフル活用していますよ、「約束」は「幻」と言い換えてもいいですよ、要はあらゆることがフェイクなんですよ、という話だったと思う。それはオルデンバーグが言うのとはかけ離れたものであるにも関わらずサードプレイスを自称する点、ディスカバーどころかみんな知ってるアラニス・モリセットなのにディスカバリーミュージックと言っちゃう点、やってないわけではないじゃないですかというエコへの取り組み、いやリトルガイズを支援してますよ豆買ってますよ少しですけどというグローバリゼーションへの取り組み等、いろいろとあるみたいだし、まったく知らなかったことがここにはとにかく書かれていたので、へ~、スタバ、黒いなあ腹、とニヤニヤしながら読みもしたのだけど、僕はどうしても、いいじゃんそれで、と思ってしまうのだった。営利企業なんだから、しょうがないでしょ、利潤の最大化目指すでしょ、と思ってしまうのだった。
著者とて別にスタバを断罪しているわけではなくて、スタバ(あるいは大企業)を選んでいる皆さん、スタバに幻想を抱いてませんか、実態をお教えしますよ、こんな感じですよ、どうですか、まだ好きですか、そうですか、それならまあ、というぐらいのスタンスだとは思うのだけど、ご多分にもれず大変意識の低い人間で申し訳ないのだけれども、まあ、それならそれですわ、大した期待はしていなかったけれど想像以上に色々なことが中身ないんだね、スタバは、という印象を抱いたぐらいだった。僕はこれからもスタバに行く。便利で、安全だから。それだけ。というところだった。
いや、しかし、腹、本当に黒いんだろうかスタバ。本当はもっと色々しっかりやりたいんだけど、株価とかあるので、売って売って売りまくらなければならないので、膨張したボリュームを必死で維持しなければならないので、というところなんじゃないだろうか。全部、しょうがないじゃん、と思ってしまう。環境問題への取り組みの章の最後にも、「エコが大衆化しステイタスづくりに役立たないとすると、劇的な改革をやったって注目なんてされない。ならば、なぜ思い切ったことをやる必要があるのか?なぜ急いで真面目にやらなければならないのか?」とあるけれども、いやほんとそこだよねーと思うのだけど、こういうのはスタバとか大企業とかの責任というよりは、社会の意識みたいなものが「このレベルまで取り組まなきゃアウトでしょ」みたいなふうになるか「そんな取り組み超クールですねー」みたいなふうになる以外に、つまり鞭をちらつかせるか飴を舐めさせるか以外に企業をモチベートすることはできないのではないかと思っちゃうのだけど、そういうものでもないのかな。僕はもしかしたら今一度CSRというものについて考えてみたほうがいいのかもしれない。企業の社会的責任だなんて、そんなもの、と思ってしまっている節がある。自営業者としてもこの態度はよくないかもしれない。
そういうわけで総じて楽しく読んだのだけど、シュルツさんが創業者だとばかり思っていた僕にとっては、ボールドウィンさんらが始めたスターバックスを「この小さなシアトルの会社をビッグにするのだと心に決めた」シュルツさんがスタバに入り込み、そして拡大路線を取り、いったん辞めて自分で新たな店をやり、と思ったらボールドウィンさんらの経営が不振に陥ったところで一気に攻め込み、そして、という流れがたまらなく面白かった。
人の店を見て「この小さな会社をビッグにするのだと心に決める」って、なんて厚かましい男なんだろう!今自分たちの店に人がやってきて「君らの店、いいね。俺も参加して、店でっかくしたいんだけど、どう?」とか言われたら頭おかしいのかと思うだろうなと想像するとシュルツさんの行動力というか厚かましさには度肝を抜かれる。そしてどんどん本物からそんなに本物でないものへと移行していくこのグダグダというか「あーそれダメな路線だー」という感じ、インディーズでスリーピースで無骨な音鳴らしてたのに、どうしてその曲にストリングスが、みたいなあの感じ、メンバー増えてその人シンセって、どうしたの、っていうか誰ですか、っていうあの感じ。小さなものが大きくなっていく過程でどんどん削ぎ落とされていく真正さのようなものが、読んでいて「うわ~……」となって楽しかったです。
「ボールドウィンらが重視した真正さへの探究心を、原型とはかけ離れた品を買い求めることが真正なものの追求だという観念とすり替えれば、かれらは皆スターバックスの愛好者となるとシュルツは踏んだのだった(P38)」
「効率は真正さに勝るものだった。しかしスターバックスは効率の追求に加えて、本物志向の演出を止めようとしなかった。本物志向のイメージこそがアピールであり、かれらが売り出す感情的価値の核心だったからである(P45)」
それにしても装幀のこのふんわりした感じと値段のギャップは愉快というか、ターゲットとしてふんわりスタバファンみたいなものも考えられているのかもしれないけど、あ、スタバ、とか思って手に取ってもこの値段じゃ買わないでしょ、二段組じゃ買わないでしょ、と思った。「誰がターゲットなのか意識すること!」
あと「ほんのさわり」とか「すべからく」とかが誤用だったよねという使い方で使われている箇所がいくつか目についたのだけど、岩波ってそういうところすごく堅牢そうだと思っていたのだけど、そうでもないのかな。
引き続きアイライクスターバックスです。
book
2014年4月20日
疎外と叛逆ーーガルシア・マルケスとバルガス・ジョサの対話
『鼻持ちならないガウチョ』所収の講演録の中でボラーニョに「老マッチョ二人組」と呼ばれているお二人だけど、今現在の僕にとってはどちらもそんなに積極的に読みたい作家ではない。
ガルシア・マルケスは『百年の孤独』は二度読むほどにはとても好きだし『コレラの時代の愛』や『わが悲しき娼婦たちの思い出』やノンフィクションの『誘拐の知らせ』とかも好きなんだけれども、いろいろとラテンアメリカの小説を読んでいく中で、今はマジックリアリズム的なものよりも正面から政治や歴史を書いているものの方が楽しいところがあるので当分はいいかなと思っているし、バルガス・ジョサ(リョサと言いたい!ジョサ慣れない!というかなんで今さらジョサなんだ水声社。正しいのはわかるけど、アマゾンとかでもいたずらに著者名が分かれちゃうしなんか色々な面でどうなんだろう水声社。今さら誰もカート・コベインなんて言わないだろう!)はこの一年ぐらいで4つ読んだのかな、『都会と犬ども』と『フリアとシナリオライター』と『アンデスのリトゥーマ』、『緑の家』、どれもそこそこに面白かったのだけど、まさにマッチョという印象で、すごい頑固そうというか、村上春樹とかリチャード・パワーズを読むときに感じるものだけど、作者の中に完全なる正解がありそうでそれが押しつけられている感じが息苦しい、みたいなところがあり、いつか『世界終末戦争に死を』とか読んでみたいものもあるけれど、よほど色々に余裕があるときだなと思っている、というそんな位置づけ。
そんな曖昧な位置づけならばなぜ手に取ったのかと問われても「なんとなく」か「水声社だし、応援したいし」ぐらいしか答えられないのだけど、対談およびインタビューはとても面白いものだった(バルガス・ジョサのガルシア・マルケス論はそう面白くなかった)。訳者解説で「ガルシア・マルケス研究でしばしば引用される文献」とあったけれど、そのせいか、節々で既視感のある発言に遭遇した。この対談がソースだったのか、みたいなところも含めて面白かった。
『百年の孤独』で一躍時の人となったタイミングのガルシア・マルケスにバルガス・ジョサがインタビューする体の対話。前書きで「対照的な気質」とあるけれど本当に温度感の違う二人で、エキサイティングともまた違う、微妙な噛み合わなさがとてもよかった。
「あの家では、ペトラ叔母が亡くなった部屋も、ラサロ叔父が亡くなった部屋も、空き部屋になっていました。そのせいか、夜になると、家には生きている人より死人の方が多くなって、普通に歩くことすらできなかったほどです」とか「叔母というのは(…)大変に活発な女で、ある時突然死衣を縫い始めたものですから、「ねえ、なぜ死衣なんか縫うの?」と私は訊きました。すると彼女は、「あのね、私もう死ぬのよ」と答えたのです。それで針仕事を続け、縫い終わると横になって本当に死にました」とか、さらっとこういう発言が出てくるのを見ているとガルシア・マルケスっていうのは本当にマコンドみたいな人なんだなあというのがわかってとてもいい。
また、そんな調子のガルシア・マルケスと、それを認めない感じのバルガス・ジョサのすれ違いというかほとんどガルシア・マルケスの発言全部無視、自説固持、みたいなところも面白い。
「簡単には信じられない非現実的な逸話が併存する小説が現れる…… ともかく、あなたの小説には、詩的、あるいは幻視的とでも言えばいいのか、一見ありえないような挿話が……」「いやいや、『百年の孤独』における私はリアリズム作家ですよ、だってラテンアメリカではすべてが起こりうるし……」「『百年の孤独』を読んでいて驚いたのは、多くの登場人物が同じ名前を持ち、何度も同じ名前が出てくること……」「父と同じ名前の人なんて、ここにだっていくらでもいるでしょう。(…)さっきも言ったとおり、物事は説明なしにそのまま受け入れないと……」「わかりました。(…)あなたの本には、空想や溢れんばかりの想像力……」
だから空想や想像力じゃないんだって!という感じがとにかくよかったです。ボルヘス批判も興味深かった。
また、「ラテンアメリカ文学のマドンナ的存在」だっというエレナ・ポニアトウスカによるバルガス・ジョサへのインタビュー、これもとてもよかった。
まずポニアトウスカによるインタビュー序文的なやつ。
「ある時ふと考えてみると、男であれ女であれ、真に興味をかきたてられる人物は、情熱をかけて仕事に打ち込んでいる者だけである、という事実に気づかされたことがある。(…)しっかり据えて仕事に臨まない者たち、広く浅くの態度を取る者たちは、遅かれ早かれ疲労と倦怠を免れず(自分でも満足できない仕事に他人が満足するはずはない)、すべてが徒労にすぎないような印象を与えることになる。」
いやーもうほんと、すいません、と思いました。いやーもうほんと、ほんとすいません、と思いました。
それからバルガス・ジョサの規律好きみたいなところ。
「僕はその時々のインスピレーションで執筆するようなタイプじゃないから、これは重要なんだ。性格の問題だろうね、銀行員と同じように、毎日決まった時間規則的に仕事をしないと僕はダメだね」
そしてその規則正しい日に立ちあがる美しい時間について。
「僕にとって美しい日と言うのか、素晴らしい日、わかるかな? 爽快な日とは、机に向かって座ったまま八時、九時までずっと書いていられる日さ。そういう時はすらすらと文章が出てくるからね……(…)そんな日はよく眠れるよ。気分がいいし、幸せとは少し違うけれど、ともかく、世界と仲直りしたような気持ちになる。(…)
和解したように気持ちがいいんだ、わかる?」
なんかこう、とても低い次元での共感だろうけれども、わかるなーとなりました。ノーベル賞作家に向かってこんなこと言うのもあれなんですけど、マリオ、その感じ、俺もわかるよ、わかる、と言いたいと思いました。
しかしこのインタビューの中で何よりもいいのはポニアトウスカのあれこれで、過剰な食い下がりと、意味というか意図不明のインタビュアー注。
食い下がりは「幸せ?」という問いから始まり、執筆している時間は幸せだし、それを中断されると不機嫌になる、と答えるバルガス・ジョサに対し、「でもね、マリオ、人間らしい生活というのも必要じゃない?」と食い下がり、家庭と子供の必要性を説く。「あなた、もう二十九歳でしょう、マリオ」「それじゃ、子供は欲しくないの?」「(いらないという答えに対し)そんなバカなことを!」と。
そして意図不明の注。「(微笑…… バルガス・ジョサの微笑は優しい…… 聞き手の唇、あるいは心に残りそうな微笑…… )」「(再び微笑。こんなふうに微笑むことのできる人はいつまでも歳を取らず、ずっと若いままだろう、そんな気がする)」こんなの初めて見たよ。
このときポニアトウスカは33歳。どんな人なのか、バルガス・ジョサとどんな関係だったのか、まるで知らないけれどもこれはもうエレナはマリオに首ったけだったのかな?とつい下世話な想像が膨らんでしまう、素晴らしいインタビューだと思う。
そうこうしていたらガルシア・マルケスが亡くなったとのこと。200歳ぐらいまでは平気で生きるのかと思っていたので驚いた。
book
2014年4月20日
HHhH (プラハ、1942年) (海外文学セレクション)
「この平明で曇りのないスタイルは、こけおどしのたぐいを避け、あくまでも自然な語りの背後に留まろうとしているようにみえる。こうして読者は一種、陶酔状態のなかで、いつしか語られている事実の時空に運ばれ、ハイドリヒの乗るオープンカーを待ちかまえている二人の若者の熱い内部に文字どおり滑りこんでいく。計画を頓挫させる予期せぬ出来事、弾の出ないピストル、的から外れて車の一部だけを吹き飛ばす爆弾、襲いかかる追跡の手。これらの細部はどれも確かな考証に支えられているから、読者の記憶からけっして消え去ることはないだろう。(P386)」
訳者解説にあるバルガス=リョサのコメントだけれども、これはなんというか全然違うんじゃないのか、と思ってしまう。
「いつしか語られている事実の時空に運ばれ」というけれど、ここまでの入念かつ執拗な教育によって読者はいつ「僕」が出てきてもオーケーですよという体勢になっているから、「語られている事実の時空に」完全に運ばれるということは決してなくて、むしろ完全に運ばれてはいけないとすら思わされている節があるわけだし、実際、バルガス=リョサが挙げている場面にしても、ガブチークの短機関銃から弾が出ず、それに代わってクビシュが鞄から爆弾を取り出した、というまさにここという場面ですらもすぐに脱臼させ、「これほど完璧に<歴史>の声が響く作品にお目にかかるのはおそらく初めて」という、最近読んでいる小説の話を持ち出してくる。この中断を見てしまえば、著者は「二人の若者の熱い内部に文字どおり滑りこんで」ほしくなんかないようにどうしたって思えてしまう。
それからもう一点。「読者の記憶からけっして消え去ることはないだろう」という根拠:「これらの細部はどれも確かな考証に支えられているから」
うそだ!と思う。小説の場面が読者の記憶にこびりつくとしたら、それはただその小説の語りが充実しているから、というそれだけなんじゃないか。「確かな考証に支えられているから」記憶に残ると言ってしまったら、考証が不確かな歴史小説の場面は記憶に残らないことになるけれども、そんなことって全然ないんじゃないの、と思う。何かの支えがなければ自立できないなんて、むしろこの発言は小説というジャンルに対する見くびりなんじゃないか、とまで思ってしまう。
(そんなふうに違和を覚えながら、特に意図的にそうしたわけではなかったのだけどガルシア=マルケスとバルガス=リョサの対話、『疎外と叛逆』を読んだら、1965年のインタビューで「文学作品の大原則は、そこに描かれた現実が自立した世界として、誰の手を借りることもなく、それ自体として生命を持つことだよ。それ自体が生きた現実でなければいけない……」と発言していた。言ってること逆じゃないの、先生!となった。それにしても『疎外と叛逆』は水声社からのやつで、水声社はどうも「リョサ」ではなく「ジョサ」を通したいみたいなのだけど、そっちが読み方として正しいらしいというのも聞いたことがあるけれども、こんなにリョサに慣れちゃっているのに、私たち、一体どうしたらいいの!となっている)
ということで別段嫌いなわけじゃないし読んでいきたい作家だなとも思っている、けれど一方であんまり信用できない気もするな、と漠然と思っているバルガス=リョサあるいはジョサのコメントがなんだかすごく癪に障ったので噛み付くことから始めたのだけれども、この作品を知ったのは去年のいつだかに丸善で面陳されてるのを見た時で、珍しいことにポップが添えられていたので印象に残った。
確か「高橋さん」という書店員の方によるものだったと思うけれども、まあとにかくすごいですよ、みたいなことが書かれていたから「いいね丸善、いいね高橋さん、ポップとか俺大賛成だよ」と思って気にはなっていて、いつかのときに丸善ではなくジュンク堂に行ったらまったく同じポップが貼り付けられていたから、「なんだよ、丸善岡山店の高橋さんかと思ったら、違うのかよ!がっかりだよ!」となった。落胆はしつつ、読みたいなとは気にしつつ、でもその時の僕は「年内の小説はラテンアメリカのみ」という自主的な縛りの中にあったので買うわけにもいかず、それから半年以上が過ぎただろうか。やっと出番が回ってきたのでジュンク堂で買ったわけだった。
そんな経緯で読んだ『HHhH』は総じてエキサイティングな小説だった。
書かれようとする場面は事あるごとに疑問に付される。「歴史上の人物の声を我がものとしようとするあまり、その声は作者自身の声に似てしまう」語り手は何度でも何度でも手を止める。「読者の記憶に侵入するためには、まずは文学に変換しなければならない」そう言いながらも、その変換の作業がなかなかはかどらない。こんな姿に変換していいのか。これは身勝手な創作ではないか。こんなことを言わせてしまっていいのか。こんなことをさせてしまっていいのか。「ずっと前に死んでしまって、もう自己弁護もできない人を操り人形のように動かすことほど破廉恥なことがあるだろうか!」歴史的な正しさのようなものは常に宙吊りにされ、読んでいる側としてもその時間の中に没入することなんて許されず、常に語り手の存在を意識させられ続ける。
そうなってくると実に厄介なもので、エクスキューズなく描写が進んでいくとき、読んでいてちょっと没入しかけたとき、ふとこちらの頭に「あれ、今、これ、大丈夫?」みたいな余計な考えがもたげて来る。「なんなのこれ?やっぱり創ってるんじゃない!」と叫ぶナターシャの声が頭に響く。
「十分にありうる。でも、ありうるということと、まぎれもない事実であることは違う。くどくどうるさいって?僕がこういうことを言い出すと、たいていは偏執的だと思われる。みんな、何が問題なのかわかっていない」
その偏執に、語り手はどこまで忠実にいられたのか。どこかで折り合いをつけたのか。あるいは勇気をもって突き破ったのか。
クライマックスをなす水責めとそれに抵抗するガブチークたちの場面。書かれている場面がそれを書き進めている日付とともに進行していく模様はだいぶやばくて、2008年と1942年が、メトロノームの針のように左に、右に、頭を揺さぶってくる。だんだんわけがわからなくなっていく。ここだけはバルガス=リョサに同調するけれど、このやり口は確かにある種の「陶酔状態」に読者を導く。素晴らしく効果を上げていると思う。壮大で感動的でダイナミックで大好きな場面だ。
一方で、ここまで来ちゃうと、その日付、本当に正確なんですか?みたいなことまで言いたくなる自分もいて、6月2日にそれ書いて、翌日にそこ書いて、そうしてみたら2日に書いた分が少し違うような気がして修正とかしたり、してないですか?してる場合、すました顔してそのまま2日扱いですか?その修正については言及なしでオーケーですか?みたいな、知らないけど、意地悪だしほとんど重箱の隅つつきみたいなことを言っているのはわかっているけれど、そういうことを思ってしまった。その部分ですらも、「やっぱり創ってるんじゃない?」と。作者は自身の作為をどこまで許しているのだろうかというか。
そんなふうな考えにとらわれていると、段々と、いや、たしかにこの手法すごいいいし面白いんですけど単純に小説の題材として面白いし、実際なにもくどくど考えずに読んだら面白いし、普通に小説な感じでよくないですか?という本末転倒のところまで思ったりして。小説はもっと図々しく、野放図で、恥知らずでもいいんじゃないかというか。それを言ったら作者は「君まったくわかってないよね…… 一冊かけてあなた一体なに読んできたわけ?」とすごく嫌な顔をするだろうけれども。
いや、なんだかこんなふうに書いてくるとあまり楽しく読んでいなかったように見えるような気がするのだけど実際はとても楽しかったのだったし、歴史を小説として扱う作者の真摯で倫理的な姿勢(本当によく思うけれども、真摯さと偏執はいつだってほとんど同じものなんじゃないか)は胸に響くものがあった。とにかく徹頭徹尾、これは歴史と作者とのあいだに横たわる距離を巡る格闘の物語だと思う。
「或る絶対的/絶望的な距離(それは具体的なものだけではなく、非=当事者性とでも呼ぶべき認識とかかわっている)と、その距離を越えて発言しようとする意志とが共に表現されている。(…)
距離を何らかの仕方で縮めようとするのではなく(それは結局、どこまでいっても不可能なことだ)、むしろ距離を丸ごと受け止めることによって、この映画を完成させた、ということが重要なのだ。」
これは書評で『HHhH』を絶賛してもいた佐々木敦の『シチュエーションズ』から引いたのだけど、まったく同じ意志がこの小説にはみなぎっていたと思う。とにかくとてもよかったです。それにしてもデビュー作でこれを書いたローラン・ビネは、次にいったいどんなものを書いてくるのだろうか。
最後に面白かったというか愉快だったところ。
「え? <類人猿作戦>の秘密って、この程度のものなのか?」
いやほんとこれ、びっくりしたというかあっけにとられた。
それからモラヴェッツが3人、ズデニェクが2人登場してきたり、「ただでさえガブチークとクビシュという二人の主人公が陽気で、楽観的で、勇敢で、人から好かれる性格なのに、さらにそこに似たような性格の人物を登場させているのだから」というあたり。厄介だけどもうなんかほんとそれどうしようもないよね~と。
book
2014年4月8日
鄙の宿 (ゼーバルト・コレクション)
いかに踊れるか、というところが問題だと思うのだけど、この作家論で取り上げられている作家たち、ヘーベル、ルソー、メーリケ、ケラー、ヴァルザー、そして画家のトリップ、について、ルソーはもちろん存在は知っているし新潮文庫で出ている『孤独な散歩者の夢想』だけは読んだことがあるのだけど、それ以外については一つの作品に触れたこともないし、解説によればどの人もドイツ語圏では有名な方らしいけれども名前も一切知らなかった。一切知らない作家について書かれたものを読むというのは少なくとも今回の僕にとってはなかなかに難しいもので、取っ掛かりのリズムみたいなものが見いだせないためにまるで入っていけないというか、興味わかんなー、というところが大半で、要はなかなか踊れません、というところだった。
その中で例外が二編あって、それはルソーとヴァルザーのところだった。
ルソーについての文章は僕の中ではわりと「これこれ、これぞゼーバルトに鳴らしてほしい音」みたいなところがあるもので、時には名前を変えて潜むことまで強いられるような暮らしをしていたのかという、これまでまるで知らなかったルソーの伝記的な記述も僕にはとても面白かったし、なにせそのルソーの人生には広範で頻繁な移動が含まれているという点も、踊るということでは踊りやすいところがあったのだと思うのだけど、それよりも何よりもいいのは、ゼーバルトがビール湖に浮かぶサン・ピエール島を丘の上から見渡した時からほとんどちょうど200年前にルソーがその島に逃げ着いたこと、かつての修道院の建物が今ではホテルとレストランになっており、ルソーが暮らした二つ隣の部屋にゼーバルトが泊まったこと。保存されているらしいルソーの部屋で過ごした数時間のあいだ、「私はと言えば、ルソーの部屋にいて、過ぎ去った時代へと連れ戻されたかのような心地であった」とゼーバルトは書いている、「それは幻想ではあったが、遠いエンジンの音ひとつしない、百年か二百年前に世界中をひたしていたのと変わらぬ静けさが島をひたしていただけに、その幻想には容易に入り込めた」と。
この感じだ。ゼーバルト自身の体験の記憶と、彼がひもとく書物や資料からの記憶が響き合って奏でられる音楽、この感じが僕を踊らせるのだ。ゼーバルトが見た景色、歩いた道のりが、あれよあれよと書物や歴史に侵食されていくその瞬間のグルーヴこそが、僕を踊らせる。実に気持ちよく、体をくねくねさせながらおこなうヘンテコな踊りを踊らせる。僕はたぶんそうやって踊りたくてゼーバルトを読みたいと思っている。
このとき以来私は、空間も時間も超えて一切がいかに繋がりあっているかを、ゆっくりと学んでいったのだった。プロセインの作家クライストの人生と、トゥーンの醸造所で事務員をしたと自称するスイスの散文作家の人生とが。ヴァン湖の湖面に響くピストルの音のこだまと、ヘリザウの精神病院の窓からの眺めとが。ヴァルザーの散歩と私自身の遠出が、誕生の日と死去の日が、幸福と不幸が、自然の歴史と産業の歴史が、故国の歴史と亡命の歴史が。(P147)
ゼーバルトという書き手の姿が見えて、そして次の刹那、不気味なほどに一切がいかに繋がりあっているかを示されるとき、僕の足はステップを踏む。
そういう点ではヴァルザー論もまさにそれで、なんせヴァルザーのある写真はゼーバルトに「反射的にいつも私の祖父、ヨーゼフ・エーゲルホーファーを思い出させる」のだ。「彼が着ている三つ揃いのスーツの生地や、柔らかいシャツの襟や、タイピンや、手の甲に浮いた老人性のしみや、きれいに切り揃えられたごま塩の口髭や、両眼のしずかな表情」までもが、あるいは「帽子を手に持って歩いた」り「晴れた夏の日でもきまって傘と雨合羽を散歩に携えていった」という習慣までもが祖父を想起させる。そして祖父の写真とヴァルザーの写真が並べられる。二人は同じ年、1956年に亡くなっている。なんという不気味なダンスだろう。
こうした相似や、交錯や、偶然は、なにを意味しているのだろう。ただの記憶の判じ絵、ただの自己欺瞞や錯覚にすぎないのだろうか。それとも人間関係の混沌のなかにひそんでいて、生者も死者もひとしく包摂する、私たちの理解を超えたある秩序の体系が、こうしたかたちで表れているのだろうか。(P125)
あるいはまた、ヴァルザーの小説とゼーバルトの小説が驚くような一致を見せる瞬間。月光降り注ぐボーデン湖を渡る情景。茶づくめの身なりをした婦人との出会い、喪の行路。
私は常日頃、自分が心を惹かれる作家に対して自分の作品のなかで敬意を表すというか、かぶっていた帽子を少し持ちあげて彼らに挨拶するようなつもりで、その作家の作品から美しいイメージや特別な二言三言を借り受けてきた。しかしながら、すでに身罷った作家仲間を追憶するための標を付すことと、自分が彼岸から挨拶されているような感覚をどうしても拭えないこととは、天と地ほども違う。(P127)
実に戦慄的で実にダンサブルだ。
ところでここで引かれたゼーバルトの小説というのは先日読み返した『移民たち』の中の「アンブロース・アーデルヴァルト」で、彼は晩年精神病院に入り、「思考の能力、想起の能力を根こそぎ、二度と戻らぬまでに消したがっていた」ために率先して電気ショック療法を受けて朽ちていったという恐ろしいエピソードを持つ人だけど、ゼーバルトの描くあるいは取り上げる人物たちは本当にどいつもこいつも、何か「消失」への願望があるというか、「驚くべき精妙さをもって人生を回避する行動障害」とゼーバルトは書くけれど、存在から逃れたいような衝動を持った人たちばかりだ。
ヴァルザー。
彼らは書くことによって非個人化をなしとげ、書くことによって自分を過去から切り離した。彼らが理想とするのは、完全な記憶喪失の状態だった。ヴァルザーの文章はどれもその前の文章を忘れさせるという役目しか持っていない、とベンヤミンが指摘しているが、現実にも、家族の記憶をまだ描いていた『ダンナー兄弟姉妹』後すぐに記憶の流れはじりじりと細くなっていって、ついには忘却の海に注いでしまう。(P134)
ルソー。
彼自身、なによりも望んだのは、頭のなかで回りつづける車輪を止めることだった。にもかかわらず書くことにしがみついたとすれば、それはもっぱら、ジャン・スタロバンスキーが言うように、ペンが手からぽろりと落ち、和解と回帰の無言の抱擁のうちに真に本質的なことが語られるであろう、というその瞬間を招きよせんがためだった。そこまでヒロイックではなにせよ間違いなく言えることは、物を書くとは、次から次へと続けずにはいられない強迫的行為だということだろう。その証拠に、思考の病に陥った人間のうちでもっとも治癒しにくいのがおそらく作家なのだ。ルソーは若い頃だけでなく晩年パリでも楽譜を写す仕事に励んだが、それは雲のように四六時中脳裡に湧き上がる想念を払いのけるための、残された数少ない手段のひとつだった。でもなければ思考の装置を止めることがいかに困難であるかは、ビール湖に浮かぶ島での、彼言うところの幸福な日々についての描写が証している。(P54)
書き続けることで思考の装置を止めること。僕なんかもブログをだらだらと書くこと、打鍵を続けることはわりとセラピーみたいなところがあって、内容なんてなんだっていいからとにかく言葉を打ち続けて白紙を文字で埋めていくことによってデトックス、みたいな、止まれ、消え失せろ雑念、煩悩、みたいなところがあるのでとても「はい、わかりますよその衝動みたいなやつ」と思うのだけど、僕なんかじゃまったくわかりえないレベルのそうとうなあれなんだろうなーと。だってルソーはさらにガラスになりたい節すらあるんだぜ、と。
ルソーはこう語る、「ベッヒャーが断言するところでは、動植物の灰のなかには溶けるとガラスになる土が含まれており、その土からは、いかなる美しい磁器にもまさる美しい花瓶を作ることができる。ベッヒャーは極秘の方法によって実験をおこない、それにより人間がガラスからできており、ほかのすべての動物と同様にふたたびガラスに戻ることができると核心した。(…)」(P57)
ところでヴァルザー論を読んでいたら彼の小説をとても読んでみたくなった。
次から次へとすばやく移り換わっていくのがつねなのだ、ヴァルザーにおいては。場面はまばたきひとつの間しか続かず、作品の登場人物にも束の間の命しか恵まれていない。<鉛筆書きの領域>だけにも、何百人が住んでいる(…)。
登場した刹那はめざましい存在感があるのに、よく見ようと目を凝らすと消え失せている。私には彼らがいつも、ちらちら震える光暈に取り巻かれていて輪郭が定めがたい、初期の映画の訳者であるような気がしてならない。夜頃の夢に脳裡を過ぎていく人びとのように、彼らはヴァルザーの断片的な物語や胚芽のような長編を通り過ぎていって、宿泊簿に記帳もせず、到着したと思うまもなく旅立って、二度とふたたび姿を見せないのだ。(P132)
こんな小説読んでみたい。幸い邦訳が出ているみたいなので、いつかチャレンジしてみよう。ヴァルザー論には踊れたけれど、ヴァルザーその人の書く小説に僕は踊れるだろうか。
cinema text
2014年4月4日
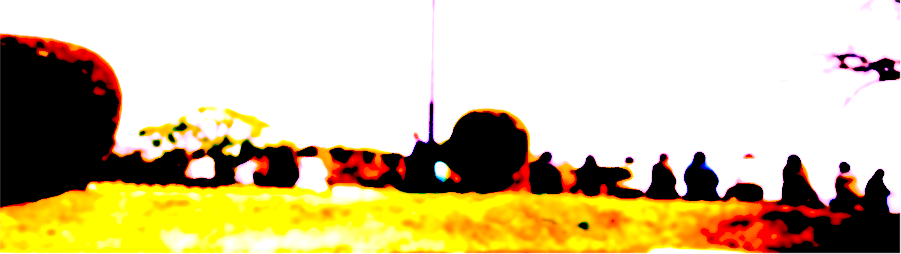
昨夜たいへん美味しい鍋を食いながらジョージ・A・ロメロの『ゾンビ』のあとに続けて見たジム・ジャームッシュの『リミッツ・オブ・コントロール』はやけに心地がよくて、映画館で見たときは大部分をうとうとして過ごしてしまい、今回も最後の方で少し意識が飛びかけていたけれど、全体を通してやけに心地がよくて、それはなんだったのだろうと考えみると、一応の筋書きとしては殺し屋が指令を受けて人を殺しに行くというお話になるけれども、それにとらわれずに画面を見てみれば、なんのことはない、ヴァケーションの映画じゃないか、ということなんじゃないかと今日たいへん忙しくていつものように朦朧としながら労働しながらはたと気がついたのだった。殺し屋であるところの男はスペインのあれはバルセロナなのかしら、におもむき、変な形のマンションに滞在し、連日美術館に行き、毎日決まったようにカフェに行き、座っていると人が来て少しいい話をしてくれてそれに耳を傾け、快適な列車で移動し、仮庵に泊まり、フラメンコを堪能し、またカフェに行き、カフェに行き、カフェに行き。アメリカから来たギャングなの?と好奇の目を向ける子どもたちに問われたときにノーと言うが、それは本当にノーなのであり、ギャングじゃなくてサイトシーイングですよ、というのが正答だ。としか思えないほど、男の行程は穏やかで、安らぎに満ちているように見える。この映画はそういう気分で見ればいいんじゃないかな、とたいへん忙しくていつものように朦朧としながら労働しながら私はそれに思い至ったのだった。
今日も今日とて、夜は店を閉めた。
啓蟄という言葉を知ったのは去年のことだったと思うけれども、まさに、という具合で春になって一気に忙しくなり、花見時期のこの一週間というのはゴールデン・ウィークにも負けないぐらいのバカみたいな忙しさに見舞われるため、あ、無理です、となってギブアップする、そんな日々だ。がんばれないほどはがんばらない、という方向を、今になって。春になった。今日は半袖で過ごした。時間貧乏であるがゆえか、金というよりは時間がもったいなくてここのところ千円カットを利用している。一時間も一時間半も美容院にいるよりも、十分十五分で済むこちらの方が性に合っているのかもしれないしどうせ髪型にこだわりなどないのだから、そもそもそうするべきだったのかもしれないと今になって。昨日はじゃあ8mmでと言ってただの坊主にしてもらった。お互いに簡単そうだった
ここ一ヶ月ぐらいで見た映画。
リミッツ・オブ・コントロール(ジム・ジャームッシュ)
ゾンビ(ジョージ・A・ロメロ)
コンボイ(サム・ペキンパー)
スプリング・ブレイカーズ(ハーモニー・コリン)
偽りなき者(トマス・ヴィンターベア)
悪徳(ロバート・アルドリッチ)
ハタリ!(ハワード・ホークス)
親密さ(濱口竜介)@オーディトリウム渋谷
永遠に君を愛す(濱口竜介)@オーディトリウム渋谷
天の許し給うものすべて(ダグラス・サーク)
アメリカン・ハッスル(デヴィッド・O・ラッセル)@TOHO岡南
なみのこえ 気仙沼(濱口竜介、酒井耕)@moyau
なみのおと(濱口竜介、酒井耕)@moyau
『親密さ』を見に行ったのは三月半ばの金曜日のことで、その日は6時ぐらいに店を上がらせてもらい、7時半ぐらいの新幹線に乗り渋谷へ向かい、少しだけ時間があったのでスタバで本を読み、12時からのオールナイトを見、6時半ぐらいの新幹線に乗って岡山に帰って土曜日の営業をしたのだった。むちゃくちゃなスケジュールだったし土曜日の営業はしんどかったけれども、それだけのことをする甲斐のある時間だったし、多くのことはここでは書かないし、見る前に読んでもまったく問題ないんじゃないこれはということは店の方に書いたのだけど、やっぱりこの映画は私にとってはあまりにアクチュアルだった。ストラグル、という言葉がずっと頭の中で回っている。ストラグルグルグルという状態だ。どれだけの人が今度の上映を見に来てくれるだろうか。そしてどれだけの人に響くのだろうか。全然わからないし、いろいろと不安だ。
今日も今日とて店を閉めて、6時に、7時半にやっと昼飯を食い、二人で11時過ぎまで延々と仕込をしていた。昨日休みだったのに、今日の時点ですでに体が重くて金を数える腕すら重い。ビールの小瓶を2本飲んだらやたらに酔っ払って、3本目の今は何がなんだかわからない。本を読んだ。ボラーニョの『鼻持ちならないガウチョ』とゼーバルトの『鄙の宿』をここ数日で読み終えた。3月もなんとかノルマ的に思っている5冊を読了して、これでこの3ヶ月は毎月ちょうど5冊ずつという、なんとも言えないアジャストな感じであるのだけど、3月に関しては岡田利規2冊とボラーニョはともに200ページに満たないものなので、なんというか別に狙ったわけじゃないにしてもこすい感じのアジャストな感じになっている気がしてならない。大長編にでも挑もうか。次に何を読もうか、まるで何も浮かばない。
人生。人生。人生。人生。よだれみたいになってビールが口の端からこぼれていった。雨降ってる。増税。
←
→