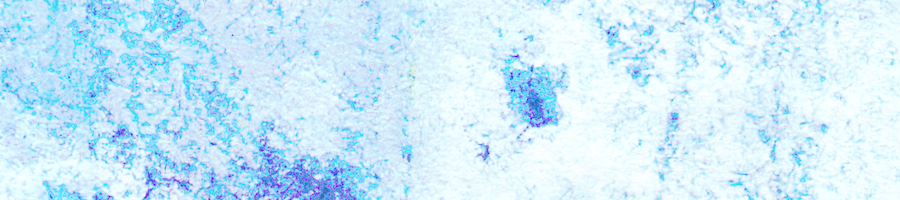book
2014年4月2日
鼻持ちならないガウチョ (ボラーニョ・コレクション)
実際のところ、ラテンアメリカ文学とは、ボルヘスでもマセドニオ・フェルナンデスでもオネッティでもビオイ=カサーレスでもコルタサルでもルルフォでもレブエルタスでもなければ、ガルシア=マルケスとバルガス=リョサの老マッチョ二人組でもない。ラテンアメリカ文学とは、イサベル・アジェンデ、ルイス・セプルベダ、アンヘレス・マストレッタ、セルヒオ・ラミレス、トマス・エロイ・マルティネス、アギラール=カミンだかコミン、そしていまここでは思い出せないその他大勢の著名人たちのことである。(P153-153)
聴衆たちを大笑いさせたという講演録「クトゥルフ神話」はこんな感じでたくさんの人名が出てくるわけだけど、知らない名前もたくさんある中ではどんな皮肉を込めてボラーニョが話しているのかはあまりわからないから大笑いの感覚なんてまるでないのだけれども、僕がなんでラテンアメリカ文学にこんなに肩入れしているというかワクワクを持続させているのだろうと考えた時、その理由の一端がこの講演録を読んでいる時にわかった気になって、それは、ラテンアメリカの人名が好きなのだ、という実に簡単なことだった。おびただしい数のカタカナの固有名詞を見ているだけでなんだか胸がときめいてくる。ボルヘス!フェルナンデス!オネッティ!カサーレス!コルタサル!ルルフォ!ルルフォ!ルルフォ!という具合だ。
そういうこともあってか、巻頭の「ジム」なんかは、火吹きの男を見るジムを語り手が見ている場面なんかはすごくいいのだけど、いかんせん出てくる人名はアメリカ人のジムたった一つであるせいか、たった3ページの掌編ということもあり、「まあそっか」ぐらいのところで終わってしまったのかもしれない。
いやそれは嘘だ。やっぱりそのシーンはすごく美しいものだったし、一つの記憶を呼び起こした。
それはいつだかのフジロックの夜のことで、オアシスで(それはフェス会場の中の憩いのオアシスであり、決して倦怠の砂漠の中の恐怖のオアシスなどではなかった)僕らは大道芸を見ていた。レッドマーキーや岩盤のところから届いてくるビートや重低音の中で、若いパフォーマーが一生懸命大道芸をやっていて、たぶん四人とか五人で見ていた僕らは僕らなりに「いいよね、がんばってるよね」という気分で見ていた。僕らは二十歳そこそこで、人生や未来のことなんて楽観的にしか考えていないか、あるいはほとんど考えてすらいなかった。そういう若い僕らの中で、友人の友人ということでこのとき一緒に来ていた人がいて、その人は一人だけ30過ぎか前か、いずれにせよそのぐらいの年齢だった。彼はバンドをやっていて、そのかたわらで自分の店だったのか雇われ店長だったのか正確なところは覚えていないけれどもバーの類の店に立っていた。彼はその年のうちにバンドで結果が出なければ教師になる、という決定をしていた。しかし結果とはなんだったのだろう。一度だけ、ライブを見に新宿の小さなライブハウスに行ったことがあったが、ドラムとギターのインストバンドで、すごく格好良かった。ライブを見たのはフジロックの前だったか後だったかはっきりとは覚えていないけれど、とにかくその夜、様々な音や光にあふれたその夜、僕らは大道芸を見ていて、ハラハラしながら見守ったり成功すれば喝采を送ったり僕らなりに感動したりして、そういうことをひと通りおこなったあと、そばにいた彼が腕を組んで立ち尽くしたまま滂沱していることにみな気づいた。それは茶化すことのできるような泣き方ではなかったし、若かった僕らは、さりとてその気分を十全にわかることなどできず、彼が涙を流したままパフォーマーに歩み寄り、投げ銭用の帽子に大きなお札を入れているのを見ていたのだった。彼はパフォーマーに何か話しかけていた。握手もしていたかもしれない。大道芸を見終えると、僕らは早々とキャンプサイトに帰ることにしてみなで歩いていたのだけど、先ほどの光景を見てから僕は何か考えるようなモードに入り込んでしまい、先に帰ってて、と言って友人たちと別れた。コーヒーを買い、どこかに腰掛けて煙草を吸った。それは何か考えるようなモードのためといった風でありながら実際のところはただのポーズでしかなくて、本当はただ、コーヒーと煙草の一人の時間を少し過ごしたかっただけだった。
という感じで僕なりにボラーニョ風みたいなタッチっぽい感じで書いてみたのだけど、しかしボラーニョ風というかボラーニョのスタイルというか、ボラーニョのコアみたいなものというか、ボラーニョをボラーニョたらしめている要素っていったいなんなのだろうか。何か泣きたくなるような寂寞としたもののような気もするけれども、そうじゃない気もするし、アクションというか身体の見事な運動という感じでもないし素晴らしい長広舌とかでもないし情景描写の妙といったものでもないし。僕を、そして多くの人を惹き付けているボラーニョのボラーニョらしさとはいったいなんなのだろうか。これまで邦訳されてきたものはどれも読んだけれどもよくわかっていない。なんとなく、触れてくるよね、心の襞に、みたいな感じだろうか。これが一番そんな感じがする。そんな感じがすると言っても何もわかったことにはなっていない。解説の青山南の、「彼の文章世界にやけに印象に残るシーンが多いのは、「聖母マリアが姿を表したときのような」瞬間がいくつも散りばめられているからだろう」という言い方はなんだかうまいことまとめるなあというか本当にそうかもなあという気がした。素晴らしい瞬間がいくつも本当に散りばめられている。
ただ、「ジム」の次の表題作「鼻持ちならないガウチョ」は、「その晩、彼は店に集まったガウチョたちに話しかけた。おれたちは記憶を失いかけている気がするよ、と連中に言った。ま、それはそれで結構なことだ。ガウチョたちは初めて彼の言うことを彼よりもよく理解しているかのように彼を見つめた」とか、なんか触れてくるよね、心の襞に、みたいな感じでいいなと思うところもあったのだけど僕はボルヘスほとんど読んだことがないのでどんなふうに響き合っているのかとかよくわからないし、あまりこういう老人の話は惹かれないのか、全体としては「そっかー」ぐらいのものだった。(これまでボルヘスは『創造者』を読んだことがあるだけで、これはチンプンカンプンだった記憶があってそれ以来避け続けているのだけど、今度『伝奇集』読んでみようという気になったのは収穫というかなんというか)
表題作が僕にとってそんな感じだったので、これはまさかまずいかなーあんまり楽しめなかったりして、と懸念していたのだけど、それに続く「鼠警察」は、読み始めてすぐに「ぼくたち一族」とか「上司の何匹か」といった表現が出てきて、まあなんかあれなのかな、匹っていうのは警察を鼠扱いしているみたいな感じの言い方なのかな、とか思っていたら本当に鼠の話じゃないか!となってまず愕然として、僕はこの作品のネタ元のカフカの「歌姫ヨゼフィーネ、あるいは二十日鼠族」はたぶん読んだことがないか読んでいても忘れているので、鼠かよ!なんで鼠の話を書くんですか!ボラーニョさん!という感じでかなりびっくり仰天して、わーこれはマジでそんな鼠のお話ですかー、寓話ですかー、という感じでかなりさっきの懸念ふくらむという状態だったのだけど、どんどんどんどん、いや本当に面白い、ということになっていった。リアリティっていうのはどんなものが材料でもこんなに確固たるものとして生じるものなんだなということを実感。
完全に『2666』のサンタテレサの連続殺人事件と通じるというか同じもので、変死体が上がっていくごとに緊迫感がどんどん高まって、いよいよモンスターと対面したときのあの、恐怖を巡るセリフは本当に恐ろしかった。
「お前は間違ってるよ。あの女は死ぬほど怖がってた、と彼は、まるでぼくたちがこの世のものでない存在に取り囲まれていて、その存在から丁重に同意を得ようとするかのように、両脇にぼんやりと目をやりながら言った。彼女の聴衆は、自分では気づいていなかったが死ぬほど怖がっていた。だがホセフィーナは怖くて死ぬどころではなかった。日ごと恐怖の真ん中で死に、恐怖のなかで蘇った。(P69)」
何がそんなに怖いのかわからないけどこのセリフは本当に怖いなーと。
そして「アルバロ・ルーセロットの旅」。これも本当に好き。これが一番よかった。やっぱり何かとボラーニョが描く小説家とか詩人が出てくる話は好きなんだろうなと思う。『野生の探偵たち』も『2666』も『通話』の「センシニ」も。あとは今思い出せないけどそういう類の話は何だかすごく惹かれる。小説の中に固有名詞なり書誌的な記述が入ってくることが楽しいのかもしれない。この作品の中にちょうど、プルーストの『失われた時を求めて』をバカンスのあいだ読んだ、読んだことがあるとこれまで周りに言ってきたため、というくだりがあるけれど、ポスト・ボラーニョ世代の旗手みたいな扱いらしいアレハンドロ・サンブラの「盆栽」にもまったく同じ挿話があり、『失われた時を求めて』というのはチリにおいては「読んでるよ」と嘘をつき、嘘を本当にするべく読まれるためにあるみたいじゃないか。そしてそれはなんだかすごく素敵なことじゃないか。
「フリオがエミリアについた最初の嘘は、マルセル・プルーストを読んだことがあるというものだった。読んだ本のことで嘘をつくことはあまりなかったが、あの二度目の夜、何かが始まりつつあることが、その何かがどれだけの期間続くにせよ大切なものになることが二人にわかったあの夜、フリオはくつろいだ調子の声で、ああ、プルーストは読んだことがある、十七歳の夏、キンテーロで、と言った。(…)
その同じ夜、エミリアはフリオに初めての嘘をつき、その嘘もまた、マルセル・プルーストを読んだことがあるというものだった。(…)つい去年のことよ、五ヶ月くらいかかった、だってほら、大学の授業で忙しくしてたから。それでも全七巻を読破してみようと思って、それがわたしの読書人生でいちばん大切な数か月になったの。」
「それぞれを『失われた時を求めて』を読んだこと――というより読んでいないこと――へ結びつけていたあの打ち明けがたい秘密のせいで、二人はプルーストを読むのを後回しにしていた。二人とも、今回一緒に読むことが、まさしく待ち望んでいた再読であるかのように装わなくてはならなかったので、特に記憶に残りそうな数多い断章のどれかにさしかかると、声を上ずらせたり、いかにも勝手知ったる場面であるかのごとく、感情あらわに見つめ合ったりした。フリオに至っては、あるとき、今度こそプルーストを本当に読んでいる気がする、とまで言ってのけ、それに対しエミリアは、かすかに悲しげに手を握って応えるのだった。
彼らは聡明だったので、有名だとわかっているエピソードは飛ばして読んだ。みんなはここで感動してるから、自分は別のここで感動しよう、と。読み始める前、念には念をということで、『失われた時を求めて』を読んだ者にとって、その読書体験を振り返ることがいかに難しいかを確かめ合った。読んだあとでもまだ読みかけのように思える類の本ね、とエミリアが言った。いつまでも再読を続けることになる類の本さ、とフリオが言った。」
それはさておき、この小説の最後の、小説家と映画作家の対面の場面。「鼠警察」にしても「アルバロ・ルーセロットの旅」にしても、対面とはこんなにも誰かにとって恐ろしいものなのか、という対面。すごくいい。しかしルーセロットの行動は非難されてしかるべきなのだろうか。ここなんかは残酷というよりはよっぽど親密な情景として読んでしまっていたので、そのあとに死んでしまいたいとまで言わせていることにびっくりした。
モリーニは、ホテルの掃除用具が詰め込まれている屋根裏部屋にいた。窓を開け放ち、ホテルを取り囲む庭園と、黒い格子越しに部分的に見えている民家の庭に見とれているようだった。ルーセロットは近づいて背中を軽く叩いた。そのときのモリーニは先ほどよりもひときわ華奢で、背も低く見えた。少しのあいだ、二人は黙って二つの庭を交互に見つめていた。(P97)
それからシモーヌとの関係もとてもいい。ボラーニョのこういう感じがやっぱり好きなんだと思う。通じ合う瞬間というか。
シモーヌに電話をかけ、状況を説明し、金を貸してほしいと頼んだ。するとシモーヌは唐突に、ぽん引きはいないのと言うので、ルーセロットは、借金を申し込んでいるのだと、利子を三〇パーセントつけて返すつもりだと答えたが、その後二人は笑い出し、シモーヌは、何もせずに、ホテルから動かないで、車を貸してくれる友達が見つかり次第、ニ、三時間で迎えに行くからと言った。彼女は何度かあなたと言い、ルーセロットも返事をするときに同じ言葉を口にしたが、その言葉をこれほど甘く感じたことはなかった。(P98)
そのあとの「二つのカトリック物語」も楽しく読んだ。「文学+病気=病気」はよくわからなかった。総じて結局とてもよかったし、もっともっと読みたいです。ボラーニョコレクション、引き続き楽しみ。
book
2014年3月30日
ラテンアメリカ傑作短編集: 中南米スペイン語圏文学史を辿る
来たるべき『2666』に向けて一年間ラテンアメリカ小説縛りで読書をおこなうということを経験した身としてはその地の傑作短編集と銘打たれたものを読まないという選択肢はないわけで、読んだわけでした。
よかったのはエステバン・エチェベリーアの「屠場」、バルドメロ・リリョ「十二番ゲート」、リカルド・ハイメス・フレイレ「インディオの裁き」、リノ・ノバス・カルボ「ラモン・イェンディアの夜」、アルトゥーロ・ウスラル・ピエトリ「雨」、マリア・ルイサ・ボンバル「新しい島々」といったところで、特に巻頭の「屠場」は、ラテンアメリカ最初の短編とも言われる作品とのことだけれども、それはわりと僕の中のラテンアメリカってこれだよね~やっぱり、みたいなものと合致するものでもあった。
「四十九頭の牛はそれぞれの皮の上に並べられていた。二百人ほどの人間が牛の動脈から出た血でどろどろとなった地面に足を踏み入れた」
そんな屠場における真っ赤っ赤な狂宴の模様はたいそう禍々しくバカバカしく、子供の首が唐突にちょん切られるくだりに限らず、にぎやかでいいなあと思いながら読んだ。
「十二番ゲート」はたぶんページを折ってあるこの箇所がよかった。
「むなしく朝から夜まで、耐え難い十四時間も、厳しい労働の中で、蛇のように身をくねらせながら、激しく厨房に襲いかかってきた。店の奥底で彼のように労働を強いられた何世代もの人間が、終わることなくこなし続けてきた尽きることのないオーダーに気合いを入れて向き合ってきた。
しかし、この手強く絶え間ない戦いは活力あふれた若者を急速に老いぼれに変えていった。狭く湿った陰気な厨房の中で、背は曲がり筋肉はゆるみ、檜を前に震える癇の強い子馬のように、年老いた店員たちは毎朝店への通勤路を歩いていると腹のそこからこみ上げてくる吐き気に堪え切れず何度も何度もえづいた。目からぼろぼろと涙がこぼれ、それでも吐き気はおさまろうとしなかった」
大変だよね、労働、というところか。
「インディオの裁き」
なぜかというか誤植で本文の上にある作品名は「インディオの嘆き」となっているのだけど、裁きも嘆きも大差ないか、と思って読んでいたらけっこう大差あった、という作品だった。これ虐げてきて今や虐げられる側となった旅人は怖かっただろうなあと思いました。「突然、山の頂から放たれた巨大な石が、うなりをあげて彼らの近くを転げ落ちていった。その後、次から次へと……」とか。たいへん怖そう。
あとこういうところが好み。
「こうも言えるかもしれない。尾根や四つ辻を呪いが伝わっていくのだと。」
こういう感じが好きなので「新しい島々」もそういったところに「いいね!」となって、「一晩中、風は同じ調子で唸りながらパンパを縦横無尽に駆け巡った。時に家を取り囲み、窓や扉の隙間から滑り込んでは蚊帳のネットを激しく揺らしていた」という書き出しからしてグッときて、こういう文章を読むとムージルの『特性のない男』の冒頭部分を思い出すけれど、無人称的なカメラって僕は好きなのだろう。ウルフの『灯台へ』の第二部とかの無人の屋敷とか。いいよねーと思う。
あとこの作品を読んでいると節々で、特に前半だけど、というかだんだんつまらなくなっていったのだけど、冒頭の風とか女の弾くピアノの音が聞こえてきたあたりとか、読んでいると僕も小説を書きたいなあと思う気分になって、小説を書きたいぞ、と僕に思わせる文章はたぶん僕はとても面白く読んでいる証の一つだと思っているので、たいそうい面白がっていたのだろう。だんだんどうでもよくなっていったんだけど。
「ラモン・イェンディアの夜」はカーチェイスの疾走感すごいし最後救われないよね、というところ。「雨」は年老いた夫婦に宝物、主に子供、というところで『うたうひと』の民話語りを思い出し。
まあなんかそんな感じでなんかいい加減な書き方をしているなーと我ながら思いながら書いてきたのだけど実際のところ全体を通したら全然ワクワクみたいなものはなくて、「ラテンアメリカ!」と叫びたくなるようなあの高まりは全然なくて、僕はスペイン語も英語も解さない日本人なので白水社とか現代企画室とか水声社とかそういう素敵な出版社が出しているようなものぐらいでしかラテンアメリカの小説というのは知らないので、どうなのかわからないのだけど、ここで取り上げられている作家たちはどの程度ほんとうに重要な作家たちなのだろう。知っている名前はそれこそオラシオ・キロガぐらいしかないし、キロガとて読んだことはないのだけど、他はまるっきり聞いたことも見たこともないのだけど、どうなのだろう。まあでもあとがきに「作品は主として私が留学したイリノイ大学大学院博士課程ラテンアメリカ文学専攻の学生を対象にした推薦図書の中から選んだもの」とあるから、きっと立派な作品なんだろう。
この短編集は副題に「文学史を辿るとある通り年代順に並んでいて、「屠場」が1838年で最後のやつが1964年だけど、むしろそれ以降のラテンアメリカの作家たちの短編集を読んでみたい。去年読んだ『巣窟の祭典』のビジャロボスとか『盆栽/木々の私生活』のサンブラとか、そういう若い作家たちの、今こういう人たちが熱いんですよーという短編集を読んでみたい。
book
2014年3月26日
わたしたちに許された特別な時間の終わり (新潮文庫)
2006年3月にスーパーデラックスで見て以来、「三月の5日間」は僕にとってもっともアクチュアルな表現というか作品であり続けて、それ以降も何度も(何度もというほどではないというか二度。2007年の六本木クロッシングのときと2010年の鳥取、鳥の演劇祭のとき)舞台で見、DVDでも見、小説も読み、している(戯曲はまだ読んだことがない。こちらも近々)。
今回数年ぶりに小説を再読しようと思ったのは少し前に『エンジョイ・アワー・フリータイム』を読んでやっぱりいいよね岡田さんとなったからで、もともと持っていたのだけどお客さんに貸し出しをしたら数年も返ってこない、何度も督促の電話をしているのに返してくれない、電話にも出てくれなくなった、本当にうんざりする、というところで手元になかったので、しぶしぶAmazonで注文したのだった。ハードカバーで持っていたものを文庫版で買うというのも妥協のような気がして嫌だったのでマーケットプレイスで500円ぐらいのやつを買った。新品同様、状態はとても良しだった。
そういうわけで久しぶりに、しかしこれが不思議なことに、僕の過去をなんでも記録しているはずのエバーノートにはどこにも「わたしたちに許された特別な時間の終わり」というキーワードに反応してくれるノートがなくて、もしや「私たち」にしたのかなとか「残された」だと勘違いしていたのかなという説もあったので「許された特別な時間の終わり」とか「特別な時間の終わり」とかで絞って検索してみても同様で、どうやらこの小説、「三月の5日間」と「わたしの場所の複数」を収めた『わたしたちに許された特別な時間の終わり』を買った、そして読んだ、ということは一度もブログやツイッター等で書いていないらしかった。そのため、いつが初読なのかわからないのだけど、間違いなく数年ぶりなのだけど、読んだ。図らずも、ちょうど二人が5日間を過ごした渋谷のラブホテルを出、別れた日かな、今日、という日に読んだ。3月20日がブッシュというかアメリカがイラクへ宣告したタイムアウト(タイムアウト。許された特別な時間の終わり)の日のようだから、そこから計算すると多分ちょうどその日ぐらいだった。だから何というわけではいささかもないけれども、それは僕に何かを思わせるには十分な符合だった。
で、その再読は相変わらず激しくアクチュアルだったし、もっとも大切な作品という位置づけは変わらなかった。先日、濱口竜介の『親密さ』を再見し、今日、この小説についてあれこれ考えたのちスターバックスの店内から窓の外を眺めながら□□□の「いつかどこかで」を聞いて、ともにそれは私に涙を流させたのだけど、この二つの作品と「三月の5日間」は、どこかで響き合っているような気がするのは僕の都合のいい捉え方でしかないだろうか。
何度も何度もこの作品に触れ、その都度、今回もやはり、僕がもっとも打ちのめされるというかアクチュアルぅ~というか本当にもう大切で大切で仕方ありませんと思うのは二人がこの特別な時間を5日間限定にしようと決めたというあたりのところで、実際にこの小説には何度も奇跡という言葉が出てくるけれども、本当に奇跡のような、美しいとしか言いようのない会話が描かれている。
「男のほうが--でも別に俺と、これからもそしていつまでも、みたいになろうとか、思わないでしょ?--と女に言った。男は--や、ほんと率直に、うん、って言っていいからさ、だってお互い様なんだし、言おうよ--と言った。うん、うん、と女は言った。涙の出ない偽の涙腺がぱかっと開いたようなすがすがしさがした。一度、二人のそのときのうんという声が、もちろん単なる偶然だったのだが、完全にぴったり重なりあったときがあって、それは奇跡の一種に思えた。あまりにぴったりと合わさりすぎたので、二人ともそれについて冗談めかして言及したりもできなかった。だからそれについては何事もなかったようにやり過ごされていった。それから男はまた話しはじめた--別にね、今の俺らのこういう関係が、ここから先たとえば、いつまでも系にはならないわけじゃない?でも、俺思うんだけどさ、いつまでも系の方が関係としてランクが上だとか、ランクが上だったら二人はいつまでも系になって、そうじゃないからこの関係はそうはならなかったとか、なれなかったとか、そういうことじゃ絶対にないじゃない。分かるでしょ?--女は分かるよと言った--うん、でもそれってすごいラッキーっていうか、この五日間一緒に過ごした相手がたまたまそういうこと分かる人だったっていうのはね、スペシャルなことだよなあって思うんだよね。そういうことみんなが分かるわけじゃ別にないからさ、ほんと、超スペシャルなことだと思うんだよ。超スペシャルとか言って、ただやってただけだろお前ら、って話もあるけど--(P67-68)」
分かるでしょ?分かるよ。このシンプルなやり取りが生み出す途方もない親密さに僕は毎度、本当に毎度、涙腺がぱかっと開いたようなすがすがしさを感じて僕の場合にはそういう親密な瞬間、ジャストな瞬間を目撃するといつだってすがすがしさが涙腺へと直結するのでちゃんと落涙する感じになって、落涙するのだけど、この瞬間は本当に本当に美しいと思う。
それは『親密さ』で言えば、妹が兄に「あなたのその言葉を聞いて、私はこれからも生きていけるような気がします」というようなことを言ったあの瞬間の、その「これからも生きていけるような」感じ。その瞬間さえあればなんとか生きていけるような感じ。人生にそういう瞬間以上に素晴らしい瞬間なんてないんじゃないかと思えるような、そういう感じ。「フリータイム」でもあったけれども、それは本当に、生きていくことの根拠、希望の根拠になるような、そんな感じだ。
何か、この二人が見せる最強の親密さは、世界を構成する秩序をどろっと溶かして無効にするような意志というか力を感じる。世界。ここでいう世界は、イラク戦争を含めた普段はカッコつきで「世界」としか思わないような世界で、渋谷のラブホテルの二人という極めて小さなユニットの小さなお話が一気にその世界を射程に捉えるダイナミクスにも、僕は毎度心を揺さぶられるというか鷲掴みにされる。
さっき秩序と書いたけれどもここで無効にされようとしている秩序は人間と人間の関係のあり方ともう一つ、「時間」もあって、それもまた、僕をなんだかものすごい気分にさせるところだ。
「いつの間にか私たちには、時間という感覚から遠ざかるようなあの感じが訪れていた--時間が私たちのことを、常に先に先に送り出していって、もう少しだけゆっくりしていたいと思っても聞き入れてくれないから、普段の私たちは基本的にはもうそれをすっかりあきらめてるところのもの、それが特別に今だけ許されている気がするときのあの感覚だ--それが体の中に少しずつ、あるいはいつのまにか、やってきていた。私たちは率先して自分たちがそうなるよう、積極的に仕向けて、そして実際そうなっていった。(…)
私たちはもちろんどちらも電話を持っていた。でも電源はすでに切っていて、私も彼も自分のデイパックの脇のメッシュのポケットに入れてしまっていた。さらにそのデイパック自体も、ベッドから一番遠い壁のところまで持っていき、見たくもないし存在すらしていてほしくないもののようにそこに置き、そうすることで時間を、自分たちの領域の外まで追いやってしまって、自分たちが、時間ってなんだっけ?くらいのところまでいきやすくするようにした。今になって私は、今があれから何日経ったのか、今の日付はいつなのか、そんなこと分からなくなってしまいたい、という気持ちでいた自分のことを、冷静に俯瞰できる。そしてあのときは、そういう気持ちでいることが特別に許されていたのだということが、よく分かる。私たちは窓も時計もない、テレビも見ずに済む、子供の夢のような部屋にいたのだ。セックスして、そのあとまったりする。いつのまにか寝て、どちらが先に寝たのかどちらにも分からないような幸福な奇跡の中で、私たちは短く眠る。(…)もちろん時計も太陽もない世界での話だから、あれが二日間だったのか、三日間だったのか、丸一日くらいでしかなかったのか、正確なことなんか分からない。そのときの私たちは、分からなくなることができていたのだ。(P53-55)」
時間という概念を消失させようとすること。それと同時に、携帯端末を通して否応なく関係しようと働きかけてくる世界(職場とか友人とか)とも切り離されること。すごくアナーキーな実践だし、なんかこう毎度、すごいはい!と思う。
たぶん僕にとって最も近い経験は、それは窓はなくとも太陽の真下だから時間の推移は自然のもとでよくわかるからだいぶ異なりはするのだけど、2007年の、大学最後の年に行ったフジロックでのことで、初日の晩に携帯を落として失くして落し物センターみたいなところにあるということは把握していたのだけれども最終夜まで取りに行かずに携帯なしで過ごした四日間だか三日間に当たるだろうなと思いだした。自然と偶然だけに身を任せるような時間の過ごし方で、その年のフジロックはそれまでで一番充実した気分だったんだ、ということを思い出した。
で、僕は今回これを二回連続で立て続けに読んでみたのだけど、それまで、この作品で描かれているものは最高の奇跡で、最高にジャストな瞬間で、最高に特別に許された時間だよね、というところで楽天的な感動をしていたのだけど、遅まきながら今回初めて気がついたことがあって、それはこの奇跡はいささかも楽天的なものではなくて、ほとんど綱渡りぐらいのもので、恐れのようなものが背後にずっとあったということだった。変質への恐れ、それから、モードをコントロールしようとする意志、というのがこんなにみなぎっていたのか、ということに初めて気がついた。上記の「自分たちが、時間ってなんだっけ?くらいのところまでいきやすくするようにした」とかもそういう恐れ及び意志の現れだし、それ以外にもたくさんというかオブセッションみたいにたくさんあった。
「自分そのものについての話は絶対にしないというようなことが、いつのまにか二人のあいだでなんとなくのルールのようなものとして諒解されていることの奇跡、みたいなことを感じていた。それが奇跡だということを、あえて口に出して言ったりは、絶対にしないでおこうと固く思っていた。バカみたいだけど、言ってしまうことでなにか変質してしまうのを、恐れていたからだった。(P46)」
「でも実はこのとき私は、不思議に思うことでそのモードが消えてしまったり元に戻ったりするのではないかと、少し心配していた。だから不思議に思っていることに、必要以上に自分で気付かないように、していた。(P57)」
「そしてもっとも厄介なもの、憂愁みたいなものを私のほうにおびき寄せてきた。その先の私はそのことから逃れられなかった。でもあまり気に留めないよう、最大限の努力はした。(P60)」
「このまま電車に乗ってしまって渋谷を離れたら、今感じているこの渋谷--知ってるのに知らない街--みたいなモードが自分の中から消えるだろうし、そしたらもう二度と、これは戻ってこないだろうと、正しく予感していたので、女はもう少しこれを引きずっていたかったから、まだ離れたくなかった。(P70)」
奇跡の維持のために二人が随所でストラグルしていたということが、今回になって初めて、やっと、なんだか、やっぱりこの作品はすごいもんだ、というものを僕に与えた。そしてまた、ストラグルのあとに「だけどしばらくそうしているうちに、この感じは意識すると簡単に消えちゃうとか、そういう脆いものではどうやらなさそうだ、ということが分かってきて、それからはもう、そのことにそんなにナーバスじゃなくなっていった。私はこの五日間を、最後までこのモードの中で過ごすことができた。とてもラッキーだった。たぶん私の人生でこれだけラッキーなことは、もうない。(P57)」という安堵と噛み締めが続くから、本当に感動的だ。
と、ここまでもっぱら「三月の5日間」についてだけウダウダと書いてきたけれども「わたしの場所の複数」も相当にやっぱり面白くて、次にどんなものがカメラに映し出されるのかわからないドキドキ感とか、描写の精緻さというか、身体・心情ともに映し出すカメラの画素数の高さ、小説のテンションみたいなものでいったらこちらの方が完成度は高いと思うし、そこで取り上げられるエピソードもどれも魅力的で、この作品について書き出したらまた長くなりそうな気がするのでもうやめる。
いずれにせよ、「三月の5日間」は引き続き、僕の中でもっともアクチュアルでもっとも大切な作品ランク1位を維持し続けるだろう。『市民ケーン』があれこれのランキングで1位に置かれるのを見て「え、引き続き?」みたいな感じを受けるときがあるけれど、「三月の5日間」は僕にとって間違いなくそれのようだ。大好きです。
book
2014年3月20日
サードプレイス―― コミュニティの核になる「とびきり居心地よい場所」
少し前、夜の11時ぐらいに来られたお客さんが「カウンターはないんですか?」と言われ、うちの店は僕らと向かい合う形式のカウンターは撤去しているので「ないんです」とお伝えすると、いくらか逡巡したあと、「今日は人とお話がしたかったので」と言って帰られた。僕はその逡巡の時間と、そのあとに彼がくだした決定(それは少し気まずいものであったはずだ)を心底肯定したいと思って、いいと思います、そういうのすごく賛成です、今自分にとってもっとも必要な時間を過ごすべきだと思います、それに妥協や遠慮は要らないはずだと思うんです、と思って少し感動したあと、人はこんなふうにコミュニケーションを渇望するものなのだなと、何か身につまされるような気になった。
僕自身は、よく知らない人とコミュニケーションを取るハードルがすごく高く設定されているためか、バーとか小さな居酒屋に行って店の人と話をしたりみたいな過ごし方ってまるで想像できなくて、いったい何を話したらいいのかわからないし、話が続かなかったらどうしようという恐怖の方が大きいし、だからといって表面を撫で続けるようななんの内容もなさそうな会話にもまったく意義を見いだせないから、わからないのだけど、そういう時間を必要とする人がいるということに何か、ずしんと来るものがあり、思い返せば、考えてみれば、そういえば、そういう店、本書でいうところの「インフォーマルな公共生活」を営むための僕にとってのそういう店が、岡山にもかつてあったのだった、ということを思い出した。二つあった。そこに行くと僕は店の人と話したり、あるいは一人で本を読んだり、店の人に「この人」とかいって紹介される人と話をしたり、それで顔見知り的な関係になって店で会ったら挨拶をし合う仲になったり、というのがあったのだなあ、友達的な人もその場所でできた、そしてそれは、苦しいサラリーマン生活、見も知らぬ岡山生活を支える間違いない安全弁だったのだなと、思い至るわけだった。だからさっき書いたことは半分は撤回しなくてはならなくて、かつて僕にはそういう欲求があった、でも今現在は僕にとってはそれはハードルが高すぎるのでしんどい、ということだった。
サードプレイスという言葉を初めて知ったのはスタバでバイトをしていた大学時代で、スタッフ証みたいなやつか小さい手帳みたいなやつに印刷されていたスターバックスのビジョンか何かに「サードプレイスを提供する」という文言があって、僕はおおいに「そうだ、それはいいぞ、そいつはいいぞ」という気でいた。だからこの本を読むまでの僕にとってはサードプレイスと言えばスタバ的な場所だ。
「かつて場所があったところに、今わたしたちが見出すのは<非場所>だ。本物の場所では、ヒトが人間である。彼または彼女は、ユニークな個性をもった一個の人間だ。非場所では、個性など意味がなく、人はたんなる顧客や買い物客(…)にすぎない。非場所では人は一個の人間であることも、そうなることもできない。個性は意味をなさないばかりか、妨げにもなるからだ(P327)」と実に否定的に本書では書かれているけれど、僕にとってのサードプレイス=スタバは完璧に肯定的な意味でこれに該当して、何ものでもなくなれる場所、誰も自分を誰かだと知らず、誰の目も気にしなくていい場所、という感じだった。
サードプレイスで過ごす時間、エンジョイ・アワー・フリータイムは僕にとっても切実というかほとんど死活問題で、そのために第一でも第二でもない第三の場所が必要であるという点においては著者と意見が合致するのだけど、本書で著者が主張するサードプレイスは、定義が「個々人の、定期的で自発的でインフォーマルな、お楽しみの集いのために場を提供する、さまざまな公共の場所の総称(P59)」となっているように「お楽しみの集い」がなければならず、「談話がないところに生命はないのだ(P313)」と断言するように徹頭徹尾コミュニケーションの発生を要件としていて、そういう点には僕はもう本当に「勘弁してください……」とげんなりする他なかった。
本書を手に取ったのは年末に読んだ堀部篤史の『街を変える小さな店』でちらっと言及されていて(しかしなぜだろうか、恵文社一乗寺店の店長という肩書がそうさせるのか、なんとなく敬称であるところの「さん」をつけないといけないような気になってくるのはなぜだろうか。著者名に敬称とか要らないとずっと思っているのだけど、これは『本の逆襲』でも感じたけれども商店主だとそうなるのか、敬称をつけた方がいいような気になる。この僕が勝手に感じている圧力みたいなものはなんなのか。)、サードプレイスって、職業柄、興味あるよね、と思って買ったのだけど、読み始めてすぐに雲行きの怪しさを感じ取りつつも読んでいったのだけど、もう本当にげんなりする他なかったし、ずっと反発をしながら読むことになった。
途中で挟まれている写真のページで著者の写っているものもあったけれど、それを見るとわりと納得で、もうなんかすっごいザ・アメリカンな感じのおじいさんで、ビールジョッキを高々と掲げてアメリカンなジョークを飛ばしてそうで、そりゃこういうことを書くわけだよなと偏見とともに納得したのだけど、あまりに「コミュニケーションこそが至高」という態度が強すぎて、明るすぎて、健全すぎて、こわかった。
76ページで記される会話のルールとか難しすぎるし、「内輪の人間たちが意外なメンバーを受け入れたときの喜びは、排他的な場所で新参者を厳格な審査に合格させたときの喜びにも劣らない(P88)」とか、いったい何のゲームをやっていらっしゃるんですか……そんな場所ではリラックスなんて絶対にできないんですけど……そういうの何よりもストレスフルなんですけど……それってとびきり心地よくない場所なんですけど……と消沈するほかなかった。
また、第12章の「男女とサードプレイス」は、なんかあの写真のおじいさんを見たらさもありなんというかこれも完全に偏見なんだけど、女性蔑視が甚だしすぎやしませんか……なんなんですか、何様のつもりなんですか……マッチョすぎやしませんか……と唖然とするほかなかった。(そのあたりのことはことごとく解説で批判されていて、こんなに清々しい、おもねらない解説なんてめったに読めないよな、という気持ちのいいものだった。「本書ではオルデンバーグがあまりにもノスタルジーに浸かっているために違和感を覚える読者がかなりいると予想される」とか「著者の女性に対する認識が「古い」としか言いようがないと思う」とか。)
なんかこの本全体が、ひとりよがりな話をでかい声でし続ける輩に与えられる「ボア」という称号を地で行っているような気がして、「サードプレイスっていうのはこんなにいいものでな、昔はそういうところがたくさんあってな、しかし嘆かわしいことに今では本物のサードプレイスなんてどこにも……」的な与太話を延々と聞かされている気分だった。
だから共感とかそういうものは求めずに、パブの歴史とかコーヒー・ハウスの歴史(小林章夫の『コーヒー・ハウス』も読んだけれど、本書の簡潔な説明で十分に要点は学べると思った)とかそういう歴史を粛々と学んで「へえ~」と思えたらいいや、と気分をシフトさせて読んでいたのだけど、一つだけ共感というか「いいね!」と思ったのはフランスのカフェとビストロのところで、「歩道のカフェの永続的な魅力を説明しようとした人びとが確信しているように、その秘密は公と私のユニークな融合にある。そしてその融合が促される場所は、とくにテラス席だ。「それは適度な親しみと不干渉を結びつける」とサンシュ・ド・グラモンは言い、このような環境のなかに人はいつまでもとどまって満足している、と指摘する(P250)」や「ビストロでは(…)他者との交流を求める圧力はまったくない(P251)」とあって、孤立とか一人でいることとかを糾弾しまくっている著者は本当にこれに対して賛意を持っているのか、物足りなく思っていないのか、と疑いは抱くのだけど、僕にとってはそういう、親しみと不干渉が融合し、他者との交流を求める圧力がない場所こそがいいよねと思っているし、自分たちの店もそういう場所になりたいと思ってずっとやっている。というところでこの箇所にだけは「いいね!」を押した。結局、僕が求めているもの、実現したいものは、著者のいうサードプレイスが社交とイコールであるならば、第四の場所、フォースプレイスということなのかもしれない、と思ったわけだった。
最後に。これは1989年の本だから当然インターネット以前に書かれているわけだけど(しかしなぜこのタイミングで邦訳されたのだろう。訳者解説もほしかった)、職場でも家庭でもなく、「形式ばらない気軽な帰属によって生じるお手軽版の友情や意気投合(P130)」やインフォーマルな公共生活、つまるところ弱い紐帯的なものと言ってもいいと思うのだけど、そういうものは現代ではある程度、どうなんだろう、SNSやネットによって補完されているところがないだろうか、ということをずっとうっすらと考えていた。ネット上にこそそういうフラットな、気兼ねのない息抜き場としての役割を見出している人たちもたくさん今はいるだろうし、僕にもいくらかそういうところがあるような気がするのだけど、著者は現代っ子のそういう意見に対してはなんて言うのだろうか。絶対に一蹴されるだろうと思う。
book
2014年3月20日
エンジョイ・アワー・フリータイム
フィクションがほしい、フィクションが!圧倒的なフィクションが!と思ったために行った丸善は、元々は『ラテンアメリカ傑作短編集』と『映画はどこにある インディペンデント映画の新しい波』を買うつもりで、「フィクション!」の欲求はラテンアメリカの短編たちによってもたらされるつもりでいて、『映画はどこにある』のある棚に向かっている途中、というかそのほんの手前、戯曲のコーナーをなんとなしに見たら岡田利規のこれがあり、読んでみたい気はなんとなくしていたというか読んでみたかったような気はあったというか読んでみたいと思ったことは何度もあったような記憶があったし、それでなくても「エンジョイ・アワー・フリータイム」という語の並びの響きは好きで、個人のブログはおろか、店のブログにおいてすらもそういった語を打ち込んだことがあったわけだったし、だから、というわけでもなく何か(それは多分、岡田利規なら今の僕にすごく刺さる言葉を与えてくれるはずだというような予感)に引き寄せられるようにして本を手に取りページをめくると序文があり、その最後に「それから、わたしにはどうにかして現実を肯定しようとする傾向がある」とあり、それで「あ、はい、買います」となった。現実を肯定しようとする傾向。
それでその夜は、たいへん安く、そして明るく、広く、使い勝手がいいためにここのところ何度か利用しているサイゼリヤに行ってたいへん安い赤ワインを飲みながら(フィクション!のラテンアメリカではなくこれを)読み、今また、サイゼリヤにやってきてこれを打鍵しているということになっている。サイゼリヤをとても気に入ったのかもしれなかった。平日水曜、夜の0時前の店内は今までもそうであったように3割か2割か1割程度の入りで、僕は4人がけのボックス席に座って、通路を挟んだ椅子とソファの席では若い男性二人がたぶん意中の女性の話をしていて、視界の中に入るもう一組である若い女性四人は、と打っていたところで先ほどの男性二人が席を立ってレジに向かった。大学生だとなんとなく思っていたら安そうな黒いコートと黒い鞄とその下がスーツなので若いサラリーマンだったらしく、それで視界の中に入るもう一組である若い、と言ってもたぶん僕とそう年齢が変わらない程度の若さの、だから三十前くらい、もしかしたら越しているかもしれない、女性の年齢なんてまるでわからないのだけど、女性四人はときおり激しい笑い声を上げたり手を打ち叩いたりして楽しげで、路線の名前とかが出ていたから旅行の計画でも練っているのかもしれないし、「泣いていいんだよ」というおどけた声も聞こえてきたからそのときは恋愛の話に花か何かを咲かせていたのかもしれない。今はイヤホンをつけてしまったために会話は聞こえないが、僕の座るいくらか後方にも人がいたような記憶があった。
ビールを頼もうか、赤ワインを飲んだらさすがに(弱いので)酔っ払ってこういう打鍵的な運動をできなくなる気がするのでそれではビールを頼もうか、でもビールも、どうだろうと思っていてそれじゃあサイゼリヤらしくドリンクバーなるものを頼むべきか、セットだったら170円、単品だったら280円、なんとなくだけれども単品でドリンクバーだけの客って店員にとってどうというか安い客だと、ここはお前のオフィスじゃないんだぞ、という気持ちを起こさせるんじゃないかとか要らぬ心配をしてしまうところもあって、でも考えてみたらここで働いている若かったり若くなかったりする店員にとって一人の客の注文の仕方、利用の仕方なんてたぶん本当にどうでもいいことで安いからどうとか高いからどうとか、むしろここでものすごく金を使っていく人を見たら逆に訝しく思われたりすら、とか要らぬ憶測が働いて何も頼めないまま10分ほどが経ったところでさっき帰った男性二人がこの時点ではまだ帰っていなかったのでボタンをプッシュすることによって店員を呼び寄せて「プリンとティラミスの盛合せ」と言っていて、自分が飲食業をやっているせいなのか、そういうのを聞くたびに「単語かよ」と、「文章として完結させろよ」と、「体言止めのつもりなのかよ」と、でも実際に自分で注文してみるとけっこう単語しかいけないというか、でも最後に「で、はい、お願いします」ぐらいは言えるからやっぱりそれがあるとないのではまったくの別物だからちゃんと「で、はい、お願いします」ぐらいは言った方がコミュニケーション的にいいと思うんですけどコミュニケーション求めてないっていう説はそりゃそうなんだけど求めるとか求めないとかの次元の前にそういうのあると思うんですけどどうでしょうというのがあるのだけど、ともかくその「プリンとティラミスの盛合せ」を聞き、それは、たしかに、素晴らしいチョイスかもしれない、と僕も思い、そういった甘味とドリンクバーを注文するという合わせ技を演じればいいのだ、とこれまでまるで考えていなかった選択肢があることを知り、もうそれしかないと思ったわけだったけど、無性に「プリンとティラミスの盛合せ」が食べたくなってしまったとは言え通路を挟んで横に先ほど「プリンとティラミスの盛合せ」を頼んだ男性二人がいる状況を考えると安易に注文するわけにもいかなくて、というのも、いくら僕が小声で、聞こえないように「プリンとティラミスの盛合せ」と言ってみたところで店員はとてもハキハキと明朗に「ご注文を繰り返させていただきます。プリンとティラミスの盛合せとドリンクバーでよろしかったですか。ドリンクバーはあちらにございますのでご自由にご利用下さい」とリピートと案内を大きな声でするから通路を挟んで向こうの男性二人にも筒抜けだろうし、よしんばそのやり取り小さな声でおこなわれたとしても、注文品がやってきたときに店員が「プリンとティラミスの盛合せです。ご注文は以上でおそろいでしょうか」とやっぱりハキハキと持ってくるだろう。それを通路を挟んで向こうの男性二人にもし聞かれたら「あいつ絶対俺らの聞いて無性にプリンとティラミスの盛合せを食べたくなりやがった」と言い合いニヤニヤされると思うととてもじゃないけれど頼めやしなかった。そこでわりと妥協になったのだけど「自家製クリームコーヒーゼリー」にして、ドリンクバーでは冷たい紅茶を入れて戻ってきたわけだけどリプトンのマークがあった紅茶はさっぱりしているのでグビグビと飲めてしまいすでになくなってしまったからまた立ち上がりドリンクバーに向かわなければならないのだし、そうなるとドリンクバーに行くためには旅行の計画か恋愛の話に花を咲かせている女性四人のボックス席の横を通らなければならなくて、すかさずおかわりにいく男である僕という姿をそこで晒さなければならなくて、そのときには「あいつたった今アイスティーらしき飲料をグラスに満たしてたのに、またドリンクバー行ったね。しかもグラスに入っている飲料の色を見る限り再びアイスティー。よっぽど好きなんだね、アイスティー」などと揶揄されるのが落ちでしかないだろうし、そうなったときにはチラチラとボックス席に一人座る僕は見られ、「あいつサイゼでマック開いてドヤ顔ですか」など「アイスティーを高速でおかわり」の範疇を超えた中傷すらされかねず、それに気づいた僕は今の居心地のよさを奪われ、そそくさとマックをしまって出て行かなくてはならないだろう。
しかも、というところでこれ打ち始めてたぶん今15分ぐらいは経っているのだけどまだ「自家製クリームコーヒーゼリー」がやってこず、「自家製クリーム」とは言ってもそれを今作っているとはとうてい思えないし、これはオーダーが通っていないのではないかという疑念がもたげてきて、それならばそのオーダー未遂に乗じる形で「であれば、プリンとティラミスの盛合せに変更していただけますか」ということもできるチャンスが今到来、と思っていたところ、本当にそのタイミングで今、「たいへんお待たせいたしました。自家製コーヒーゼリーでございます。ご注文は以上でおそろいでしょうか」がやってきて、「あれ、自家製クリームコーヒーゼリーじゃなくて自家製コーヒーゼリーなの?」といっしゅん思いこそすれどそれは口にするほどのことではないので何も言わず、とりあえずやってきた「自家製クリームコーヒーゼリー」あるいは「自家製コーヒーゼリー」を食べようと皿に目を向けたところ、皿の上に乗ったガラスのボウルの中にバニラアイスの乗ったコーヒーゼリー(角切りではなくゼラチンで固めて終わり)という状態なのだけど、だからこの場合の「クリーム」はきっとバニラアイスのことであろうとは思うのだけど、でも一方で、コーヒーゼリーと言えばコーヒーゼリーにコーヒーフレッシュを掛けて混ぜるみたいな風潮があると思うのだけど、そのご多分に漏れずボウルのわき、皿の上にコーヒーフレッシュがちょこんと置かれていて、それは「メロディアン」と書かれた、花の絵柄のコーヒーフレッシュなのだけど、「え、まさかクリームってこのメロディアン?であるならば、この自家製っていったいどれに掛かってるの?メロディアン絶対自家製じゃないでしょ?メロディアンは業者が、というか今調べてみたら「ポーションタイプのコーヒーフレッシュはその代表的な成果であり、当社はこの分野の先駆者であると同時に、トップメーカーでもあります」という昭和33年創業のメロディアン株式会社の商品でしょ?であるならばこの「自家製クリーム」ってどういうことなの?というかここでいう「クリーム」はおそらく「バニラアイス」であることぐらいは俺だって忖度してやるぐらいはできるから意地悪なこと言ってるのはわかるんだけどなんで明らかにバニラアイス以上にクリーム的なフレッシュを置いて人の目を惑わすの?なんで「いや、ここでいうクリームはアイスのことで、横にあるクリーム的なフレッシュとは関係なくてアイスのことで、アイスとコーヒーゼリーは自家製で、それで総称して自家製クリームコーヒーゼリーなんですよね、メロディアンのフレッシュはこの場合の自家製とは関係ない添え物でしかないんですよね」とかまで考慮するよう客に求めるの?」的な煩悶というか混乱が生じ、今そうやっているうちにコーヒーゼリーを食べ終えた。
『エンジョイ』と『フリータイム』は大学時代に劇場で見ていて、『ホットペッパー、クーラー、そしてお別れの挨拶』は残念ながら未見で今回初めて触れることになった。『エンジョイ』を劇場で見た時は、ニュース映像(たしか。フランスの暴動か何かが出てきたような記憶)の使い方とかに対して「うーん、よくわからないなあ」等、いまいちピンと来なかった記憶があるのだけど、『フリータイム』は抜群に感動して、等々あるのだけど、今回戯曲として3つを読んでみて、方法論とかは僕はよくわからないし、「おっもしれーなー」ぐらいしかないのだけど、扱うモチーフが、こんなにも近いところにあったのか、ということで驚いた。
どれも労働というか働き方の問題というかあり様が取り上げられていて、フリーター、(多分)事務職の社員(もしかしたら契約社員)、契約社員と、グラデーションはあれど、わりと詰む可能性あるよね、人生、いつでも、みたいな感触と近くにいる人たちが描かれている(感触、という言い方をしたのはじゃあ正社員なら安泰なのかっていう問いで、そうじゃないだろ、終身雇用とか(笑)、みたいな感覚が今僕にはあるからで)。そういうことすら感知せずに「いいなあ、面白いなあ、ぐっとくるなあ」などと受け取っていたのだから、「どうせ俺はちゃんと就職してわりといい待遇で働いてみたいになるんでしょ、わりと高学歴ゆえに」というポジションに座っていた大学生は気楽なものだけど、今回こうやって読んでみて、人ごとではないというか、以前よりもよっぽどアクチュアルなものとして読むことになったのは、かつてそれらに触れた大学生のときと違い、会社に入り、辞め、自営業者になり、という労働者として6年ぐらいの時間を経験したからなのだろうか。
いくつものぐっとくる、プレシャスな瞬間がある。
店員 (その三十分を、気分が「こうやってる時間をこのまま今日はもう少し続けてみよう」って思ったときとかは、延長して一時間とか一時間半とか満喫しちゃってもたぶん大丈夫で、職場に行って「あ、私今日、ファミレスが駅前にありますよねいつも三十分くらいあそこで自分の時間って大切なので過ごすっていう日課はどうしても不可欠なんでやるんですけど、それを今日はもう少し続けてみようって思って、それで続けて来てそのぶん遅刻して今来ました」って言ったら「あ、そのくらいのことはいいと思うよ、ていうかそういうのって正直、ここだけの話大切だからそういうことしてたほうが絶対いいと思うよ三十分でじゅうぶんって思うのとかって違うと思うよ」とかって普通に許されちゃう場合ってありそう)(P84)
女(嘘) や、でもそんなに客となーなーみたいになっちゃいけないみたいなのは、そのほうが私もいいと思いますけど、こういうところはファミレスだし所詮、
店員(嘘) あ、はいその「所詮」って部分が相当大事だと思ってて、あ、分かってるなあっていうそういうお客さんというかお客様は助かります、(P89)
女 でも三十分で、結構だいじょうぶでっていうか、うん、そういう面はあって、その三十分は日記っていうのかどうか、前の日に自分に起きたこととか、それと関連して考えたこととかについて、ノートに、普通の大学ノートで横線の罫線のついた、そこにペンとかで書く時間にあてていて、ときどき三十分が、そう、ときどきでいつもそうなるわけじゃないですけど三十分がほとんど、永遠、(ウケて)、うん、でもそう、永遠! におおむね等しくなることがあるっていうことを私は知ってて、そういう経験をしたことがある、確かに知ってて/るってことが私のなにかになってて、なにかにというのは、希望の根拠、になって/なってるんです、だから三十分で私は大丈夫なんです全然それ以上要らないんだと思っていて、全然自分的にはフリータイムを三十分で満喫って感じなんです、よねー。(P100)
女優1 二人でいるとなんかもう、それだけでほんといいと思う、とか言うと、言葉としてはすごい普通だけど、でもほんとそう思う、
女優1 「言葉としてはすごい普通」とか言って、でも、私が今自分では相当すごいと思ってる、そういう言葉で言えるような他の気持ちと較べものに、一緒にしないでよみたいな自分の気持ちの状態は、普通の程度の言葉なんかじゃ表せないって自分では思うけど、でも、今までその言葉を使ってきた歴代の人の気持ちも、実はみんな、どれも今の私のみたいにほんとうはすごいもので、てそれぞれ思ってたかもしれなくて、だったら今のこの私の気持ちも、もしかしたら、二人でいるとそれだけでもういいと思う、ていう普通の言い方で、じゅうぶん言えてる、てことになるのかもしれないけど、(P183)
ところで去年読んだ『遡行 —変形していくための演劇論』で、「これまでの僕は主にフリーター、つまり「負け組」のことを描いていたので、それはわりと大きな変化だと言っていいと思う。(…)僕自身の問題であり僕らの世代の問題であるところのものを、外の世代に対してぶつけていこうっていう意識、つまりはまあ当事者意識があったのだ。けれども今はもう、僕は『三月の5日間』や『エンジョイ』に出てくる彼らと自分とが同じだ、と思うことはできない。単純に年をとったというのもあるけど、自分が演劇のつくり手としてなんだかよくわからないがずいぶんと認められてしまったというのもある。「負け組」の若者にアイデンティファイするのが、だんだん本当のことじゃなくて、ふり、になってきた。だからそれはもうやめた」ということが書かれていて、僕は『三月の5日間』をスーパーデラックスで見て以来、完全に岡田利規に帰依しているというか、もう全部信じます、岡田さん、という人間なのだけど、岡田さんのこういう誠実なスタンスものすごく好き。
book cinema text
2014年3月11日
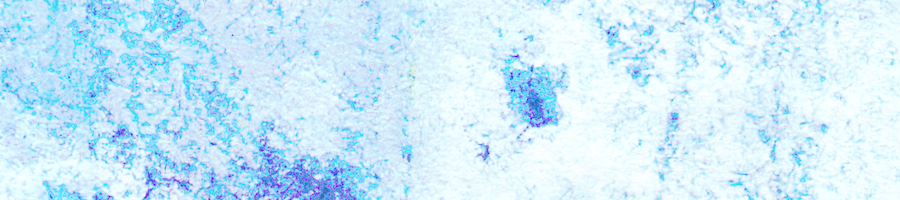
現在読んでいる本はレイ・オルデンバーグの『サードプレイス―― コミュニティの核になる「とびきり居心地よい場所」』で、昨日の営業終了後、本屋に行き岡田利規の『エンジョイ・アワー・フリータイム』、野々山真輝帆編の『ラテンアメリカ傑作短編集: 中南米スペイン語圏文学史を辿る』、『映画はどこにある インディペンデント映画の新しい波』を買った。
『サードプレイス』はサードプレイスって大切だよね的な考え方があったりするというか商売柄というのかそういうことを考えたい的なところもあったりなかったりしたために読んでいるのだけれども本当に反発ばかりしながら読むような感じになっていて、「うるせー!」と何度思ったことか、というところで、それが別にストレスだからというわけではないにせよフィクションがほしい、フィクションが!圧倒的なフィクションが!と思ったため丸善に行き、元々は『ラテンアメリカ傑作短編集』と『映画はどこにある』を買うつもりで行ったのだけど、その『映画はどこにある』のある棚に向かっている途中、というかそのほんの手前、戯曲のコーナーをなんとなしに見たら岡田利規のそれがあり、読んでみたい気はなんとなくしていたというか読んでみたかったような気はあったというか読んでみたいと思ったことは何度かあったような記憶があったし、それでなくても「エンジョイ・アワー・フリータイム」という語の並びの響きは好きで、このブログはおろか、店のブログにおいてすらもそういった語を打ち込んだことがあったわけだったし、だから、というわけでもなく何かに引き寄せられるようにして本を手に取りページをめくると序文があり、その最後に「それから、わたしにはどうにかして現実を肯定しようとする傾向がある」とあり、それで「あ、はい、買います」となった。
それを昨夜、スターバックスに行き、それからサイゼリアに行き、最後にマクドナルドに行くという資本主義の虜みたいな形のはしごをした昨夜、読んだわけだった。「ホットペッパー、クーラー、そしてお別れの挨拶」は舞台を見たことはなくて、だから初めて作品に触れたのだったけれども、面白かった。私たちも後を追いますというあたりとか、そういうあたりに、ドキドキした。労働。「フリータイム」はスーパーデラックスで、大学卒業を控えた時期に見ていて、それもすごくよくて、もうほんとやっぱり大好きだよ岡田さん、あんた!と思ったあとに近くのカフェ的なところで茶をしばいていたら岡田さんが客として入ってこられたのでドキドキしながら話しかけて購入したばかりの『三月の5日間』のDVDにサインをしてもらったというなんというか甘酸っぱい記憶が重なるのだけれども、読んでみたらやっぱりすごく好きで、
店員 (その三十分を、気分が「こうやってる時間をこのまま今日はもう少し続けてみよう」って思ったときとかは、延長して一時間とか一時間半とか満喫しちゃってもたぶん大丈夫で、職場に行って「あ、私今日、ファミレスが駅前にありますよねいつも三十分くらいあそこで自分の時間って大切なので過ごすっていう日課はどうしても不可欠なんでやるんですけど、それを今日はもう少し続けてみようって思って、それで続けて来てそのぶん遅刻して今来ました」って言ったら「あ、そのくらいのことはいいと思うよ、ていうかそういうのって正直、ここだけの話大切だからそういうことしてたほうが絶対いいと思うよ三十分でじゅうぶんって思うのとかって違うと思うよ」とかって普通に許されちゃう場合ってありそう)
とか
女(嘘) や、でもそんなに客となーなーみたいになっちゃいけないみたいなのは、そのほうが私もいいと思いますけど、こういうところはファミレスだし所詮、
店員(嘘) あ、はいその「所詮」って部分が相当大事だと思ってて、あ、分かってるなあっていうそういうお客さんというかお客様は助かります、
とか
女 でも三十分で、結構だいじょうぶでっていうか、うん、そういう面はあって、その三十分は日記っていうのかどうか、前の日に自分に起きたこととか、それと関連して考えたこととかについて、ノートに、普通の大学ノートで横線の罫線のついた、そこにペンとかで書く時間にあてていて、ときどき三十分が、そう、ときどきでいつもそうなるわけじゃないですけど三十分がほとんど、永遠、(ウケて)、うん、でもそう、永遠! におおむね等しくなることがあるっていうことを私は知ってて、そういう経験をしたことがある、確かに知ってて/るってことが私のなにかになってて、なにかにというのは、希望の根拠、になって/なってるんです、だから三十分で私は大丈夫なんです全然それ以上要らないんだと思っていて、全然自分的にはフリータイムを三十分で満喫って感じなんです、よねー。
とか、本当にすごくよくて、希望の根拠、よっぽど、『サードプレイス』よりもこっちの方がサードプレイス論としていいんじゃないのかっていうか私にとって響くものであるということでしかないけれどもそういうことを思って、サンクトゥム・サンクトルム、私はそういうことを思っていて、フィクションが!と言って買って『ラテンアメリカ傑作短編集』は冒頭のエステバン・エチェベリーアの「屠場」だけ(スターバックスで)読んだのだけれども、確かに、「フリータイム」をサイゼリアで読んだということは悪くない選定だったようなところがあり最近私はサイゼリアはとてもいい時間を私に提供してくれるような気がしつつあるのでいつだって思うけれども資本というものは侮れないし、そういう場所を軽蔑したり下に見たりすれば事足りるというわけでは全然ないわけで、糞くだらないサードプレイスもどきよりもよっぽど誰かにとっては大切な場所になりうるわけで、サイゼリアが大切かといえばまだそんな段階には全然来ていないけれども、いずれにせよ「屠場」を読んだのはスターバックスで、真っ赤な、50頭の牛が屠殺される情景、その肉を民衆が取り合う情景、暴走した牛によって子供の首が飛んでしまう情景、そういうものを見て私はおれの精神は正常ではないというあの『無分別』を、というよりはグァテマラの、マヤ民族の被った歴史を思い出さないわけではないけれども、子供の首が刎ねられ、民衆たちは(スターバックスで)真っ赤に染まっていた、というのがその夜の全貌だった。野蛮このうえない、という感想を書きながら、私の目は喜んでいなかっただろうか。おれの精神は正常ではない、それならばどうするのか、ということへの究極的な解決案としてゼーバルトの、アンブロース叔父、積極的に電気ショック療法を受けて壊れていったアンブロース叔父のそれ、「思考の能力、想起の能力を根こそぎ、二度と戻らぬまでに消したがっていたのですよ」、はあまりに薄ら寒く、あまりに重く、カーブする線路に横たわり砕け死んだ教師のそれよりもよほど薄ら寒い自殺方法だけれども、BYOFバーでデボチカをトルチョックしてスタージャ(あるいはスターバックス)に入ることに比べれば私にとってはそう悪くない洗濯というか休みが近くなればタオルが枚数が足りなくなるような気がして今日も緑とピンクと青のタオルというか食器拭きを見比べて呆然と立ち尽くす時間を5分ほど、使ってしまったのもありそれは嘘だったはずだけれども缶コーヒーは飲んだ朝からお腹を下して30分ほど、使ってしまったことは昨日だったか今日だったか定かではない。それで朝の準備が遅れれば本当にろくでもなかったというところで、ここ数日の夜は待ちに待ったSIM LABの新作を数曲ずつ聞きながら、カラフルにしてソリッドなサウンドのそれを数曲ずつ聞きながら、最高だよあんたたち、と思うのだった。
それにしてもSIM LABの2nd、OMSBがツイッターでitunesストアランキングで何位で嬉しいんだけどフィジカルで買ってくれると嬉しいですみたいなことを書いていたのもあり、DVDもついているというのもあり、DVD以上にOMSBのその発言に促されて「お、それならフィジカルで買うよ、そっちのが嬉しいんだったら」という気になったのでAmazonで買ったのだけど、買って、届いて、最初にしたことがitunesへのインポート、そこからiPodとiPhoneへ、というこのなんともやるせない作業、それはそれで全然いいんだけど、なんともやるせないこの作業。特典DVDはまだ見ていないのだけどジョン・カーペンターの『ゼイリブ』みたいなシーンがあるという噂を聞き、見るのを楽しみにしている。(ゼイリブに対する思い入れとかまるでないけど。いや、思い出はある。友人の家に行ったらそれがテレビで流れていたのだった。それを思い出す。どの駅なのかもまるで思い出せないけれど、それを思い出す)
ということでここで唐突に2013年のベスト企画の音楽編になるのだけど、3月なのだけど、
5lack × olive oil
vanadian effect
flashbacks
omsb
f.s.blumm & nils frahm
bill orcutt
captain murphy
kid fresino
kendrick lamar
otogibanashi’s
ここらへんだった。私の頭の中には新譜も何もないので発売がいつなのかとかはまるで関係していないのだけど一位はvanadeian effectに捧げたい。何度聞いても興奮した。2013年の気分、ということであればそれで、2014年の気分、ということであればいつだって頭の中に現れるのはOMSBだ。アゲンストアゲンストアゲンストアゲンスト、と頭の中で何度も叫ばれている。フラッシュバックスもとても本当によかった。サグというのが実際のところどういうものを指すのかは私はわかっていないのであれなのだけどヴァナディアンもオムスビもフラッシュバックスもサグというところでいいよねというところだった。いいよねというか、端的に言って鼓舞された。どつかれた。弱いので私は一撃で倒れたまま立ち上がれないでいるし店で流していたものではF.S.Blummとニルス・フラームのやつが最も好まれた。F.S.ブルムは個人名義のアルバムもよく流れていて、いいよね、この人、とずっと思っていたら日本にツアーで来るらしく、岡山の会場は私たちの店になったのでとても嬉しかった。こういうのって本当に嬉しいよねと思う。
三月。
の5日間。それからエンジョイ、フリータイム、とチェルフィッチュは大学在学中に見たのはその3つなのだけど、昨日読んだ「ホットペッパー~」にしても、いずれも労働の問題が描かれていた。労働。あるいは非労働。というか、人生のある一片を描くことが、労働あるいは労働の不在みたいなものと直結してしまう人間というか人間の人生というか人生ってなんかすごいなと今日あらためて思ったのは今日だったか昨日だったか忘れたけれども、やぶさかではないけれども、労働をすること自体はやぶさかではないけれども、それほどの重要事であるということがなんというか改めて驚いたというか、労働、だから私たちの人生、私たち。
『なみのおと』を見たのは先週のことで、『なみのこえ 気仙沼』と併せて上映された。それらを見た。どれも本当にいいのだけれども、やっぱり私は『なみのおと』の最後の新地町の姉妹のやつが感動し続けて(つまり鼻水を流し続けて)、口のあたりがずっと冷たかったのだけれども、あの姉妹の見せる表情、カメラの前とはとうてい思えないあの満面の笑み、離れて暮らす姉妹ゆえなのか、なされる会話があまりに新鮮(というのは彼女たちにとって)であることが奇跡のようで、姉の口から世界が、地球が語られるときのあの躍動、二人のあいだにあるあの率直さ、親密さ、それらすべてがあまりに掛け替えがなかった。という話はなか卯でおこなわれた。
「そうですね。『なみのおと』の場合は、実際に一度話を聞いて、それを改めてキャメラの前で話をしてもらうというかたちを取りました。同じようなことを一度話してはいるものの、正確には同じ話ではないし、その場で初めて出てくる話もある。ただ、そのことは、たとえばインタビュイーがうっかり漏らしてしまう生々しさを撮るということが一番の目的ではなかったんです。キャメラの前で、ある種の空々しさに耐えながら話してもらうことが、とても重要なことだと思ってました。」とインタビューの記事であった。空々しさに耐えながら。先日震災を扱ったドキュメンタリーがやらせだったのがどうというのが話題になっていて、演出の範囲がどうの、という作り手の弁明があって、それに対するはてブとかのコメントを見たら「そもそもドキュメンタリーに演出とか」みたいなリアクションが散見されたのだけれども、なんかこう、いろいろあるよねと思った。『なみのおと』のいくつもの顔たちの前でも、同じことが言われるのだろうか。ガレキ。ゼーバルト。
ともかく現在読んでいる本はレイ・オルデンバーグの『サードプレイス』で、それから昨日の営業終了後、本屋に行き買った岡田利規の『エンジョイ・アワー・フリータイム』、野々山真輝帆編の『ラテンアメリカ傑作短編集』を並行して読みつつあるようなところがあり、『映画はどこにある インディペンデント映画の新しい波』もリュックの中に入っている。今年のルール、初めて読む本、昔読んですごくよかった本、を順番に読む、というものが3月、完璧に崩れた。このあたりにおれの精神は正常ではないとは言い切れない部分があるわけだったし煙草を吸いすぎているのか吐き気がさっきからしていてえづくなのかえずくなのかわからないし検索する義務も感じないし解決したいという気持ちも湧かないながらもちゃんと生きている。
book
2014年3月4日
密偵 (岩波文庫)
絶えず裏切りを念頭におかねばならぬスパイは、どのような情況下であれ、他者の言葉から二重、三重の意味を読みとかねばならず、相手が味方であってもそれを怠ってはならない。スパイにとって情報収集とともに重要な作業とは、誰がスパイなのかを明確に知ることなのだから。そして、スパイは特異な存在である自己を社会においては常に平凡な存在として仮構していなくてはならず、同時にその特異な才能を発揮しつづけてもいなければならない。つまりスパイは自分が他者の眼にどう移っているのかという問いをくり返し発動させ、そこで得た回答を幾度も吟味しておく必要がある。だから優秀なスパイとは、より多くの眼と耳、もしくは複数の意識を、絶えず連動させつつバランスよく統御し得る者だといえる。確かにこれらはとりわけスパイにのみ当てはまる条件ではない。しかしスパイは、こうした情況を極めて苛酷に、絶対的な体験として生きているということを忘れてはならないだろう。
と書かれた阿部和重の『インディヴィジュアル・プロジェクション』を読んで、そういえば以前古書市みたいなやつでスパイっぽいタイトルのやつを買ったよな、と思い出し、コンラッドの『密偵』を読むことにしたのだった。ヒッチコックの『サボタージュ』の原作らしい。
1857年生まれのポーランド出身のイギリス人、海洋文学を得意とした、『闇の奥』という作品はフランシス・フォード・コッポラの『地獄の黙示録』の原案となった、ということがウィキペディアによると知れたコンラッドに関しては大学生の時分にゼミの課題読書として『ロード・ジム』を読んだことがあるだけで、それもどんな小説だったのかきれいさっぱり忘れてしまったので、どんなものを書く作家なのかはまるで見当もつかなかったのだけど、タイトルがタイトルなので、クールに決めたスパイが暗躍して様々な事件が惹起され、何もかもが間一髪、高いテンションで持続されるサスペンス、次のページを繰るのが楽しみすぎて、もうこんな時間だけど、眠れない!「警察! 大使館! ひぇー!」みたいな気分で読めたらいいなと思って読み始めたものの、△の異名を持つ密偵ヴァーロック氏からして、冴えないデブのおっさん、ちょっと歩いたら汗だくで息切れ、みたいな感じだからどうなっちゃうんだろう、と懸念を抱いてはいたのだけど、大使館でヴァーロックにグリニッジ天文台の爆破を指示するウラジミル氏の発言がなかなかによかった。
世論になんらかの影響力をもつような爆弾攻撃は、いまや復讐だのテロリズムだのといった意図を超えなければならない。ひたすら純粋に破壊的でなければならない。他に何か目的があるのではなどと露ほども疑われることなく、ただひたすら純粋に破壊的でなければならない。(P48)
ローラーなんかかけたって、「ああ、あれはただの階級憎悪さ」なんてうそぶかれるにきまっている。しかし、あまりばかばかしくて理解することも説明することもできず、ほとんど考えられないような、じじつ気違いじみた、破壊的狂暴性を帯びた行為に対しては何と言うべきだろうね?(…)攻撃には、いわれなき冒瀆のあらゆる衝撃的無意味さがなくてはならぬ爆弾があんたらの表現手段なんだから、もし純粋な数学に爆弾を投ずることができるならほんとに強烈なんだがね。(P50)
ただひたすら純粋に破壊的。衝撃的無意味さ。というあたりがなんとも言えずいい。
そういうことなのでまあどうだろうなと思って読み進めてはいたのだけど、指示を受けたあとのヴァーロックは太った体をだらしなく弛緩させて物思いに沈むばかりでキビキビとした諜報活動などこれっぽっちも描かれないし、何よりも鬱陶しいのは語り手の評論家気質で、たくさんありすぎてどこを引けばいいのかわからないのだけど、とうとう憤激したらしくノートに「ここにあるのは行為や場面ではなく書き手の傲慢な想像だけだ。評論に付き合っている暇はない!」とバカみたいなメモを取っていて、その箇所はここだった。
ヴァーロック夫人は根本的情報を求めてこの束の間の人生をいっときたりとも無駄にすることはしなかった。これはどこから見ても分別ある態度と思われる一種経済的な処世術であり、なにがしか得な態度でもあった。明らかに、人さまのことをあまり深く知り過ぎないというのは結構なことではなかろうか。(P243)
今こうやって引用しながら読んでみても「うるせーよ!」の一言で済ませたくなるような書きっぷりだ。何度読み返してみても「うるせーよ!」と思う。
だからもう、これダメだな、全然おもしろくない、と半ば読書を放棄しようかと思っていたのだけど、そのたった2ページあとの、「スティーヴィーは、打たれるということがどんなことかを知っていた。経験からそのことを知っていた。それはいけない世界だ。いけない、いけない!」でなんか面白いな思い抜き書きし、さらに次のページ、やはりスティーヴィー、「そして、事実、それらをついに得た。彼はすぐに立ち止まって、それを言葉にした。「哀れな民衆にとって悪い世の中だ」」をまた抜き書きし、その抜き書き部分に対して「このあたりとつじょ面白い」とメモを残し、少し持ち直した。
そうこうしていると第9章に辿り着き、283ページあたりからの警視監がやヒート警部がやってくるところを、ヴァーロック夫人側の視点から描くところはこれまでのつまらなさが嘘のようにたいへんスリリングで息を呑んだ。事情がわからないながらに共謀する感じ、夫不在時に交わされるヒート警部との会話、浮き上がってくる事実、そしてなんせ、ドアを隔て、とぎれとぎれに聞こえてくる警部と夫の会話、ドア越しに知らされてしまう真実。イギリス文学を代表するような作家らしいコンラッドに対してこんなことを言うのも気が引けるけれども、店舗兼住宅という舞台装置を見事に活用した、すべてがうまくはまっている見事な場面だと思った。
さらに第9章の続きから夫殺害までを描く第11章も同様に凄まじく面白く、ここは特にヴァーロックの人間の屑っぷりがたまらなかった。事故とは言え、自身の企ての結果として妻の弟を木っ端微塵に死なせておきながら、その死を知り悲嘆にくれるというよりは抜け殻のようになっている妻に対する感情や発言として、まあ見事な屑っぷりを見せてくれる。
彼は肉を切り分け、パンを切り、テーブルの脇に立ったまま夕食をむさぼりながら、ときどき妻のほうへちらりと視線を投げた。彼女がいつまでもじっとしたまま動こうとしないので食の楽しみも台無しだった。(P336)
食の楽しみって!という驚き。
これはまたやけに厳しい受けとめ方をしているもんだな、と彼は考えた。(P338)
お前が軽すぎるんだろ!という。
さらにそういう軽薄なヴァーロックに同調するような語り手。
「さあ、もう寝なさい。おまえに必要なのは思い切り泣くことだ」
この意見は、人間誰しも異論なく認めるところという以外、べつにどこといって褒められたものではなかった。女の感情は、空に漂う水蒸気ほどにも実体のないものであるかのごとく、驟雨となって降れば終わり、という事実はあまねく理解されているところだ。(P348)
人間誰しも異論なく認める。という事実はあまねく理解。というあたりが本当に人を見下している感じでもはや愉快。(とは言えこういう女性蔑視的なことをさらりと書いちゃう感覚はもしかしたら時代的なものなのかもしれないのでなんとも言われないのだけど)
さらには悲嘆に暮れる妻に責任をなすりつける始末。
「おまえ、しっかりしなくちゃだめだよ。ちゃんと頭を使わなきゃ。警察をそばに引き寄せたのはおまえなんだぞ。まあいい、そのことはもう言うまい」と彼は寛大につづけた。(P357)
寛大に、と形容する語り手もまた。
挙げ句…
「こっちへおいで」と彼は一種独特の調子で言ったが、それは、聞きようによっては獣性の口調と思われないが、ヴァーロック夫人には求愛の声音としてお馴染みの口調であった。(P378)
この「メイクラブ、しようよ」の一言でぷっつりきた妻によってこのろくでもない男は殺されるわけだけど、もう見事なまでの屑オンパレードで、読んでいて痛快というほどだった。
この小説のクライマックスとなる後半部分を僕はだいぶ楽しみながら読んでいたらしくて、さらに第12章の、やはり同じ舞台、店舗兼住宅におけるヴァーロック夫人と伊達男オシポンのあれこれもすごく面白くて、ヴァーロック夫人の強烈な変わりっぷり、それにたじろぐというか様々な恐怖を覚えるオシポン、という光景がすごくよかった。
苦痛の叫び声をあげてよろめきながら、気が狂いそうなドア・ベルの鳴る中で、両腕が、ひきつった抱擁にしめつけられて、脇に釘付けにされたのを感じた。と同時に耳もとで女の冷たい唇が虫の這うように動いて言葉になった。(…)なんとしても彼を離さなかった。彼女の手は、彼の屈強な背中で指と指とをからませて、離れないようにがっちりと組み合わされていた。(P414)
しかし、駆け寄ったさいに彼女とぶつかって倒してしまった。いまや彼女が脚にからみつくのを感じた彼は、恐怖が頂点に達して逆上したような状態になり、妄想をいだき、譫妄状態特有の症状があらわれた。彼ははっきりと蛇身を見たのだ。彼は女が蛇のようにからみついてきて、どうしても振りほどくことができない。(P421)
このあたりのヴァーロック夫人はほんとうに妖怪みたいで恐ろしい。
こんなふうに妖怪じみた女に迫られ続ければ、その果ての伊達男の妄想もやむない。
彼はスペインかイタリアのどことも知れぬ寒村で、屈辱的な恐怖にとらえられて暮らしている自分自身の姿を見た。そうしてやがてある晴れた朝、ヴァーロック氏と同じように胸にナイフを突き立てられて死んでいるところを警察に発見される……(P422)
殺されることよりも、「屈辱的な恐怖にとらえられて暮らしている」という状態が本当に恐ろしい。
そういうわけでつまらないつまらないと思いながら最後になって面白い面白いとなって読んだわけだけど、面白かったのでなんでもいいのだけど、この小説は読む前に期待していたようなスパイのあれこれではいささかもなくて、いみじくも警視監が言ったように「ある観点からすれば、われわれはここで家庭劇を眼前にしているわけですよ」というわけだった。
面白かったのでそれはなんでもいい。だけどこの主張したがりで説教くさい、他人にはまるで興味なくて自分の話だけとにかくまくしたてたいよくいるおっさんのような独善的の語り手と一冊分付き合ったあとでは、コンラッドの他の小説も読んでみよう、というふうにはならなかった。
book cinema text
2014年2月27日
コンラッドの『密偵』を読んでいる。秋ごろに買って、スパイとかって、楽しいよね、と阿部和重の『インディヴィジュアル・プロジェクション』を読み思ったため、手に取った。これがなかなか進まない。コンラッドというか語り手の評論家気質が邪魔で、私は行為を読みたい。行為を見たい。読書が停滞する。そうやって2月が終わろうとしている。停滞の2月が終わろうとしている。何もかもが停滞している。
先ほど今月読んだ本の感想をまとめてアップした。
読書感想文 カート・ヴォネガット/スローターハウス5
読書感想文 伊藤計劃、円城塔/屍者の帝国
読書感想文 W.G.ゼーバルト/移民たち
読書感想文 阿部和重/インディヴィジュアル・プロジェクション
読書も停滞しているし、書くことも停滞している。ここでもまったく書いていなかったし、店のブログも今月は書いていない。「今月は書いていない」。書かない月など始めてから今までなかったのに、とうとう書かない月ができてしまおうとしている。今更あせって何かを更新する気にもなれない。何もかもが停滞している。
映画を見ることも停滞している。ここ1ヶ月ほどで見た映画。
スローターハウス5(ジョージ・ロイ・ヒル)
なみのこえ 新地町(濱口竜介、酒井耕)@moyau
うたうひと(濱口竜介、酒井耕)@moyau
横道世之介(沖田修一)
ウルフ・オブ・ウォールストリート(マーティン・スコセッシ)@TOHO岡南
ザ・フューチャー(ミランダ・ジュライ)
君と歩く世界(ジャック・オディアール)
殺し(ベルナルド・ベルトルッチ)
夜の人々(ニコラス・レイ)
アントワーヌとコレット(フランソワ・トリュフォー)
刑事ベラミー(クロード・シャブロル)
先月に比べるとツタヤディスカスの回転が明らかに悪くなっていて、こんなようでは月額1980円を払っていられないことになる。その中で映画館で見た『ウルフ・オブ・ウォールストリート』は抜群に素晴らしく、ディカプリオを筆頭とした人々の熱演というか怪演というか力演というか、本当に素晴らしい熱量を感じさせる映画だった。これを見てからときおり胸をこぶしで叩いて「オッオッ」とやって鼓舞することにしている。たいへん鼓舞された素晴らしいハイテンション映画だった。それを見た同じ夜、『横道世之介』を見た。これもまたものすごく素晴らしかった。世之介役の方ももちろん素晴らしかったのだけど、大学の入学式で知り合ったなんとかという男の彼の節々がまったくたまらなく、合宿の夜の風呂の場面なんかは3度ぐらいくり返し見て、そのたびに笑った。このあたりは脚本を書いている前田司郎の力量なのだろうか。とてもよかった。セリフに限らず、コスチュームプレイものとしてもとてもいいものだと思った。ちゃんと映画館で見ればよかった。しかし映画館で見る理由はその時は見つけられなかった。それは残念なことだった。
週末は店で濱口竜介/酒井耕の東北記録映画三部作の上映会第一週があり、『うたうひと』は忙しい週末の閉店後の疲れがどっと来たのかうとうとしてしまい、節々で見るおばあちゃんたちの素晴らしい顔つきやなめらかな唄い口に感動しながら、うとうとしてしまった。一方、そのあとの『なみのこえ』は度し難く面白いというか、非の打ち所の見つからない面白さというか、途方もなく面白くて、終わったあとに彼女と一風堂に行ってラーメンを食いながらあれこれと話した。どの対話をとっても抜群に面白い。
役場の元上司と部下の役場的紋切り型にほとんど終始するような対話ですら、あそこで与えられた枠組みの中においてはとてつもなく面白いものになるから不思議だ。最後の図書館での対話は、最初に見た時は、聞き手の濱口監督の存在が威圧的というか、ものすごい暴力装置として機能していそうな気がして、そればかりに気を取られていたのだけど、今回見たら、やっぱりどうしても暴力装置だよなという印象の中で、むしろそこで追い詰められていく話し手が、ある瞬間からグルーヴを獲得する、ある瞬間でほとんど女優として生まれ変わる、そんな変異の対話としてものすごいエキサイティングなものに見え、その見え方が作り手にとって本意かどうかはわからないのだけれども、ものすごいエキサイティングなものに見えた。それはもう、すごかった。すごみを獲得していた。
月の初め頃だったか、もう忘れた、N’夙川BOYSのライブを見にペッパーランドに行った。特別に好きなバンドではないし、ツイッターでフォローしている方がつい最近「高校生の時だったら熱狂していたのだろう」みたいなことを、好意的な書き方で言っていて、まったく、その通り、と思ったのだけど、でも好きなバンドではあるし、好きな曲はいくつもあるしというのでライブを見に行ったのだけど、いいライブだったし、いいライブだったとどれだけでも思いたいのだけれども、そこでライブを見る私はずっと苦しかった。上着を脱ぎもせず、壁にもたれ、前方の少年少女たちがワイワイと手をあげ声をあげる様子とともにステージを見、どこか遠い出来事を見るような感じ。昔、高校生の頃、ナンバーガールのライブを見ながら、自分もそうだったのだけれども、と思いながらも、もう自分にはあんなふうに楽しむことはできないという諦めもあり、でも今の見方こそが自分にとってはナチュラルなものなのではないかという気持ちもありながら、でも、場は圧倒的に楽しさの中にあり、その楽しさと相容れない私の狭さを、どのように扱ったらいいのか考えあぐね、苦しい。
それから数週間がたっただろうか。店の本棚に置いている蓮實重彦の『映画時評』を高校生のお客さんが借りて行った。映画好きなんです、大学、東京、比較芸術学を学びます、映画、たくさん見ます、蓮實重彦、数冊しか読んだことないです。
がんばれ、楽しめ、途方もなく楽しめ、美しい、青年よ、君はうつくしい、僕は君を本当に応援する、君が味わうであろう虚しさも苦しみも含め全部肯定して全部応援したいなぜならその振る舞いが僕自身を僕自身の人生を慰めることにもつながるだろうから、というスタンス自体が打算の産物でありでも賢くあろうとしたら打算とはどうしたって付き合うことになろうから、それもまた仕方がないことだよ、仕方がない、そろそろ30になろうとしているうだつのあがらない男など、仕方がないなどと言う以外に脳のない男など、死んだほうがいいのだろうか、少なくとも17か18の君から見たら死んだほうがいいように映るだろうしわりとその意見には賛成だしこんなふうな虚しさが仮に続くのであるならばそれを選ぶことはしかし、しかし僕のような勇気のかけらも持ち合わせない人間には決して出来ないということだけはわかっているビールを、ビールをといっても金麦を3本飲み、コンラッドを読み進める気にもなれず今月の読了本は4冊か、ひどい、などとくだらないことを言い捨てるしか私にはできないし柿の種がどんどんなくなろうが、休日は本当にあっという間に過ぎ去って何も今日もできなかったという後悔を残すため、私に与えるためだけに休日というものはそもそも存在しているのだろうかと疑い出したらキリはないかもしれないがそう思いたくもなるようなこの体たらくであり、何もかも進まない、停滞し続ける2月、それが2月で終わるとは到底思えない、絶対にこの状態は続くしそれは大いに私を参らせることは今の今からどれだけわかっていようが外を音を立てて雨が降ろうが明日は仕事であり、仕事は大切であり、つまらない悩み事しか私にはないのだから、つまらなく生きることしかどうやらできない。いかなる笑顔にも応じる気はない。
book
2014年2月27日
インディヴィジュアル・プロジェクション (新潮文庫)
「暴力的なことに惹かれているふしがある」とつぶやき、「SASやスペツナズの隊員は単独行動で何人まで殺さずに処理可能なのだろうか」と愉快そうに問い、「ファッショナブルに暴力性を身にまとう渋谷の若者たちに魅せられていたのかもしれない。あるいは、恥じらう素振りもみせずに自身の欲望を世間にむけて剥き出しにしているかのような人々を見て、強く勇気づけられた」と漏らす語り手にできる精一杯のがんばりは、ゴミ箱に打ち捨てられたフィルム断片を映写中の映画のフィルムに混入させ、「オヌマ・バージョン」を作って映写することぐらいで、町中のちょっとした喧嘩ぐらいはしてみせてもマンションへの侵入時や映画館の倒壊時など肝心なところでは自身で手を下すこともできずただ呆然としたり嘔吐をしたり足に一発撃ち込まれて入院をする羽目になるのだから、「映写技師だけを尊敬しろ!」などという叫びはむなしく響き渡るだけで誰の耳にも入らない。個人的な映写、それが複数の意識の統御を目指すものであれ、多重人格の狂気からの脱出を目指すものであれ、映写機の後ろに構える映写技師をわざわざ振り返って見る物好きなどまずおらず、観客の目を奪うのはいつだってスクリーンに投影されている画面の連なりだろう。
数年ぶりに、そして多分三度目の読書となった阿部和重の『インディヴィジュアル・プロジェクション』は、読むごとに面白さを増すようで、今回も一晩でぐんぐんと引きこまれるというのか飲みこまれて読んでしまった。
毎回何を考えて読んでいたのかは覚えていないけれど、今回は、あるのかないのかわからないプルトニウム爆弾を巡ってのあれこれやからアルドリッチの『キッスで殺せ』を思い出しながら読んでいたら、最後に映画館が炎上する様子は海辺のロッジの炎上そのもののようだし、その際に「何も告げずに去っていった」ムラナカとアラキの二人が「互いに身体を支え合いながら」という姿は、まるっきりマイク・ハマーとヴェルダのようだった。
また、何度読んでも面白くて笑ってしまうのは「彼氏とうまくいってないから心に隙間ができちゃっただと? このおれをタンポンだとでも思っているのか!」を筆頭とするエクスクラメーションマークが使用される文章で、本当にバカバカしいなあと思いながらたいへん愉快。あとなぜかヒラサワの姿を考えるときにFla$hBackSのラッパーfebbの姿で考えていた。ヒラサワはボウリングが得意。
それから、もっとも目を引いたのはカヤマの存在だった。暴力を志向しながらもろくに実践することもできない語り手が投影するもっとも理想的な人物はカヤマなのではないか。ファッショナブルに、純粋に、シンプルに暴力を体現するスマートボーイ。ちょうどこれを読んだ晩に、たいへん暴力的なものに僕も惹かれるようなところがあったためか、だから、「理想的な人物」というのは何も語り手にとってではなく僕にとってなのかもしれないが、だからこういう読み方自体、大変に個人的な投影でしかないわけだけど、暴力というのは時にたいへん魅力的だと思っていた晩、それを体現するすべを僕は持たないと嘆いていた晩、できることといえば道端にごろんと転がってじたばたするとか、壁を思い切り蹴って足首を痛めるとか、吸い終えていない煙草を路上に投げつけるとか、本当にそれぐらいであることを全くもって悲しく苛立たしく感じていた晩、僕の理想はカヤマのありようだった。そしてそれは、まるっきりこの人とつながった。だいぶ長いが。
このろくでもない国はそんなものだらけですけれど。それからしばらくして、彼はアマルフィターノをじっと見つめて言った。何もかもが悪いほうへ向かってます、もうお気づきでしょう、先生。アマルフィターノは、何を指すか分からないように、細かいことには触れず、状況は芳しくないようだと答えた。手にしたものがそのままだめになっていく、とマルコ・アントニオ・ゲーラは言った。政治家たちは政治のやり方が分かっちゃいない。中流の連中はアメリカに行くことしか考えちゃいない。そしてマキラドーラで働こうとここにやってくる人間は日に日に増えている。僕が何をするつもりかお分かりですか? いや、とアマルフィターノは答えた。いくつかに火をつけてやるんです。いくつかの何に? とアマルフィターノは訊いた。いくつかのマキラドーラですよ。何てことを、とアマルフィターノは言った。それに軍隊を出動させたいですね。通りに、いや通りじゃなくて幹線道路に、腹を空かせた連中がこれ以上やってこれないようにね。幹線道路に検問所を置くのかな? とアマルフィターノは言った。まあそんなところです。今考えられる唯一の解決策ですから。ほかにも解決策はありそうだが、とアマルフィターノは言った。人々は敬意というものをすっかりなくしてしまいました、とマルコ・アントニオ・ゲーラは言った。他人に対する敬意も、そして自分自身に対する敬意もです。アマルフィターノはカウンターに目を遣った。三人のウェイターが横目で二人のテーブルをうかがいながら、声をひそめて話をしていた。出たほうがよさそうだ、とアマルフィターノは言った。マルコ・アントニオ・ゲーラはウェイターたちの方を見ると、手で卑猥なサインを作ってみせ、笑った。アマルフィターノは彼の腕を掴んで駐車場まで引きずっていった。日はすでに暮れていて、店名が意味する足の長い一匹の蚊をかたどった巨大なネオンサインが、鉄枠の上で輝いていた。ここの連中は君に敵意を抱いているようだ、とアマルフィターノは言った。ご心配なく、先生、とマルコ・アントニオ・ゲーラは言った。こちらは武装していますから。
僕には分かります、あなたのことが、とマルコ・アントニオ・ゲーラは言った。つまり、僕の思い違いでなければ、あなたのことを理解しているつもりです。あなたは僕に似ていて、僕はあなたに似ている。あなたも僕も、落ち着けない。二人とも窒息しそうな環境に身を置いているんです。何も起きていないかのように振る舞っているけれど、実は何かが起きている。何が起きているか? 窒息しそうなんですよ、まったく。あなたはあなたなりに憂さ晴らしをしている。僕は僕で、ふっかけてやるんです。あるいはふっかけられてもいい。でもただふっかければいいというわけでもない。凄絶な修羅場にならなくては。秘密を教えましょう。僕はときどき、夜、外に出かけて、あなたには想像もつかないような酒場に行きます。そこでおかまのふりをするんです。ただしそんじょそこらのおかまとは違う。洗練されていて、人を小馬鹿にするような、皮肉屋のおかま、ソノラでもっとも不潔な豚小屋に咲くヒナギクです。もちろん、僕自身はこれっぽっちもおかまなんかじゃありません。そのことは亡き母の墓にかけて誓えます。それでも構わずおかまのふりをする。うぬぼれた、金持ちの、あらゆる人間を見下す男娼です。すると、起こるべきことが起こる。ハゲタカがニ、三羽、声をかけてきて僕を外に連れ出そうとする。そこから修羅場が始まる。こっちは分かっているけれど構いはしない。向こうが痛い目を見るときもある。とくに僕がピストルを持っているときはそうです。でなけりゃ痛い目を見るのはこっちです。どっちだって構わない。僕にはそういったどうしようもない発散の場が必要なんです。友人たち、僕と同じ世代の、もう大学を出た数少ない友人たちにときどき言われます。気をつけろ、お前は時限爆弾だ、マゾヒストだとね。一番親しかった友人には、そんなことできるのは君みたいな人間だけだと言われました。面倒なことに巻き込まれてもつねに助けてくれる父親がいるからだと。でもそれはたまたまです。親父に何かを頼んだことなんて一度もない。実は僕に友達なんかいません。いないほうがいいんです。少なくともメキシコ人の友人なんかいないほうがいい。メキシコ人はみんな腐ってる。ご存じでしたか? 一人残らず。ここじゃ誰も救われない。共和国大統領からあの道化のマルコス副司令官まで。もし僕がマルコス副司令官だったら、何をすると思います? 自分の全軍勢を投じてチアパスのどんな町でもいいから総攻撃を仕掛けます。強力な守備隊がいればいつだってね。そして哀れなインディオたちを犠牲にするんです。それから、たぶんマイアミに行って暮らします。どんな音楽が好きですか? とアマルフィターノは尋ねた。クラシック音楽です。ヴィヴァルディ、チマローザ、バッハ。では、普段どんな本を読んでいますか? 昔は何でも読みました。ものすごい量をです。今読むのは詩だけです。汚れていないのは詩だけなんです。詩だけは商売の手が及ばないところにあるんです。お分かりいただけるでしょうか? 詩だけが、といってもすべての詩というわけじゃない、それははっきりしていますが、詩だけが健全な糧であって、腐ってはいないのです。
それぞれP216からと、P226からで、ボラーニョの『2666』、アマルフィターノの章の終わりかけからだ。ゲーラのこの魅力的な姿を読んだときに、どの作品かわからないがドストエフスキーの人物にもこういうスマートバイオレンスボーイってとてもいたような感じがあるし、そして最後の詩こそが、詩だけが、と言ってしまうあたり、スマートであると同時にこのうえなくキュートだなと思ったのだけど、『インディヴィジュアル・プロジェクション』のカヤマの、酒場での長広舌は、やはり酒場でのゲーラの長広舌とリンクしてこのうえなく愉快だった。そしてこれを引用するために開いた『2666』は、やっぱりものすごく面白かった。
錯乱する語り手。先日読んで阿部和重を想起することになったオラシオ・カステジャーノス・モヤの『無分別』ともやっぱり響き合っていて、切迫というのはいつだってバカバカしいものだということを教えてくれる。
book
2014年2月27日
移民たち (ゼーバルト・コレクション)
年末に読んだ素晴らしくエキサイティングな映画論『建築映画 マテリアル・サスペンス』の刊行特集のページに、著者の鈴木了二と美術家の岡崎乾二郎が対談をしているものがあって、そこで「ガレキ映画」というものについて話をしているのだけど、最近ヴォネガットの原作を読んで、そして改めてジョージ・ロイ・ヒルの映画を見た『スローターハウス5』が少し取り上げられているのだけど、それはともかく、「私にとって<都会>とは、瓦礫の山に焼け焦げた壁、むこうにぽっかり空が見える窓の穴のことだった」と書くゼーバルトの作品は、まさに「ガレキ小説」と呼びたくなるようなものだ。
ただし、この『移民たち』という小説というか散文作品と言われるものを読んでいると、ゼーバルトの場合は、それこそヴォネガットが『スローターハウス5』で端的に描いたように、ビリー・ピルグリムらが難儀して歩き、茹で上がった死体を拾い出す、空爆後のドレスデンに横たわるようなガレキの光景が描かれるわけではなくて、かつて栄え、そして今やすっかりダメになってしまって久しいいくつものいくつもの廃墟の光景を通してガレキ小説たらんとしているように見える。
本当に、ここに収められている4編の作品を読んでいると、嫌になるほどに廃墟ばかりだ。ほとんど、ゼーバルトが歩きさえすればすべての都市は廃墟になるのではないか、調査と称してやってきたゼーバルトの影によって都市は廃墟化するのではないか、ゼーバルトは都市からしたらとんでもない死神なのではないか、などと無茶なことを言いたくなるほどに、ここでは廃墟しか映されない。
ともかくたちまち知れたのは、この昔日の伝説の海水浴場が、いまや世界のどの国どの場所を訪れても言えることではありながら、救いようもなく落ちぶれ、車の波や、ブティック街や、あらゆる方法で蔓延していく破壊の欲望によってみごとに台無しになっていたことだった。十九世紀後半に建てられた鋸壁や小塔のあるネオゴシック様式の城館風の別荘や、スイスの山小屋風、東洋風の別荘などはほぼ例外なく打ち捨てられ、落魄の様相をしめしていた。(P127)
おりから夜が明けはじめ、私は窓外を過ぎていくそっくりおなじ形をした家の列に眼を瞠ったのだが、その家並みは都心に近づけば近づくほど、だんだんと荒んでいくような印象があった。モス・サイドとヒュームではひとつの通り全体が窓も扉もすべて板で塞がれていたし、一区画がごっそり取り壊されている場所もあった。そうしてできた荒れ野原のむこう、およそ一マイルほど先に、十九世紀の栄光の都市が遠望できたーー巨大なヴィクトリア朝風の事務所ビルや倉庫ビルが林立し、いまなおいかにも豪壮な印象を与え、しかしその実、私もほどなく知ることになるのだがほぼ完全に空洞と化した都市が。(P163)
廃墟と化すのは何も都市に限った話でもない。ゼーバルトの作品においては広大な屋敷は必ずと言っていいほど朽ち果てかけているし、老人たちはすっかり何の意欲もなくして多くが自死を選ぶ。
薄ら寒い二つのエピソード。
読んで読んで読み抜いたのです、アルテンベルクを、トラークルを、ウィトゲンシュタインを、フリーデルを、ハーゼンクレーファーを、トラーを、トゥホルスキーを、クラウス・マンを、オシエツキーを、ベンヤミンを、ケストラーを、ツヴァイクを。つまりどの人をとっても、ほとんどが自殺したか、自殺の淵まで行った作家たちでした。パウルの抜き書き帳を見れば、こうした作家の生涯に対するすさまじいまでの思い入れがわかります。引用は何百ページに及んでいて、(…)そしてくり返しくり返し自殺の話が出てくるのです。(P64)
アンブロースが治療にしたがったのは、そうではなかった。じつはある一念のゆえでした。あなたの大叔父さんは、思考の能力、想起の能力を根こそぎ、二度と戻らぬまでに消したがっていたのですよ。(P124)
ゼーバルトの小説は時たま読みたくなるというか、「そういえばゼーバルト読みたいなあ」という気が頭の端でチラチラし続けているような状態がいつでもあって、今回もそういうモードになったために久しぶりに手に取ってみたのだけれども、彼の文章を読む喜びは、僕の記憶違いでなければ、どこまでも静かで、スタティックに見える文章が、度し難いほどダイナミックに動いていく、だけどやっぱり表面は静か、静謐といって差し支えないほどに静か、というあの感触を味わうことで、それは具体的に言えば語り手の文章が、話し相手の言葉に、あるいは様々な資料の文章に滑らかかつ決定的に侵されていく、その侵入を語り手が全面的に招き、そして任せてしまうあの言ってみれば野放図な感じだと思っていて、『移民たち』においても様々な人物の昔語りが、手記が、どんどんとページを侵食していくわけだし、訳者あとがきによれば「アンブロースの<日記>のなかに一九一一年版の『ブリタニカ百科事典』の記述がまるごと引用されている」とあるぐらいだから、大変にでたらめなことをやっていることがわかりニヤついてしまいはするのだけど、僕の記憶していたようなあのダイナミックさが僕にとってのゼーバルトの真骨頂であるとするなら、『移民たち』はそこまでダイナミックな感じは受けず、わりと本当に静かに進んでいくもので、それぞれの話はそれぞれに本当に面白いのだけど、そういう点ではどこか物足りないところがあった。
実際、いつ以来の再読なのかもわからない再読をして、驚いたことにどの話も本当に覚えていなくて、まったく初めて読むものとして読んでいて、記憶力の弱さというのは便利といえば便利だとは思いつつも本当に自分の覚えていなさにびっくりしたのだけど、初めて読んだときもそこまでグイグイと持っていかれはしなかったのかなと思ったのは、折ってあるページの少なさも物語っているように思った。
数少ない折り目のついたページの一つが146ページで、これはアンブロースの日記の部分なのだけど、イルカの群れに取り囲まれた情景や、モスクで祈りを捧げている農夫の足裏など、美しいと思われる描写があり、それでページを折ったのかなと思ったら、このページの終わりかけ「そこで十二歳ばかりの苦行修行僧(ダルヴィーシュ)を見かけた」とあり、そこか!となった。お前は、これだけ美しいもろもろの中で、痛ましいもろもろの中で、充実したもろもろの中で、「ダルヴィッシュって、苦行修行僧って意味だったのか」という点でページを折ったのか!となった。
今だったら、僕はこのあたりのページを折りたい。
アーラム夫人は(…)たたき起こされた驚きと私の風采を面白がる気持ちをいっしょくたにした質問をひとつ、こう発して、ふたりのあいだの沈黙を破った。で、あなたはどこから湧いて出てきたんでしょ? そう言ってたちまち、こんなトランクを下げて祝日の金曜のこんなとんでもない時間に門口に立ってるなんて、そりゃあ外国人ーー彼女は<外人(エイリアン)>ということばを使ったーーに決まってるわよね、と自分の問いにみずから答えてみせた。だがそれからいわくありげににこりと微笑み、さっさと背中をむけたので、私はそれを付いてきてよいというサインと受けとめて、敷居をまたいだ。(P164)
ゼーバルトの文章とは思えない嬉しい親密さ。
やがて夕闇がしのびよってくると、目覚まし時計の針が蛍光を発しはじめ、それが私の子ども時分から慣れ親しんできたおだやかな黄緑色で、夜中にこの光を見ると、いわれもなく護られているような心地になった。そのせいなのだろうか、(…)ティーメーカー、便利でおかしなあの装置こそが、夜闇に光り、朝はひくくコポコポと音を立て、そして昼はただそこにある、それだけで私を生きのびさせてくれたような気がする。(P166)
目覚まし時計の針の蛍光に護れている感覚、僕にもあった、目覚まし時計を買いたい、と思った。
この肖像は、先祖たちの長い長い列、焼かれて灰になって、それでも痛めつけられた紙のなかでなお亡霊として彷徨いつづけている、灰色の顔をした先祖たちの長い列から浮かび上がってきたのだと。(P175)
この小説全体を一文で言い直すと、この文章になるのではないか。
船はゆっくりとこの水路を滑っていったのだ。港が近くなると、家々の黒いスレート葺きの屋根をはるかに凌駕する巨大船が、両わきの家並みのあいだを抜けていった。冬は濃霧をぬって近づいてきて、忽然と姿をあらわし、音もなく前を通りすぎて、たちまち白い霧のむこうに消えていった。アウラッハは語った、あれはわたしにとって、眼にするいわくいいがたい、なぜともわからぬが深く胸を揺さぶられる光景でした、と。(P180)
少し前に見たヴェルナー・ヘルツォークの『ノスフェラトゥ』でペストとネズミとドラキュラ伯爵を運ぶ巨大船が水路を入っていくところがあってそれを思い出した。水路に巨大船という光景は目の前で見たら物凄いのだろうな。
僕はこの作品をゼーバルトの最高傑作と思う気はさらさらないし、他のやつもどんどん再読したいと思っているところなのだけど、それでも、いくつもの死、廃墟、ガレキ、残酷に作用する過去の記憶、目の前の生の痛み、それらが静かに紡がれていく様を読むことは、やはり幸せな、充実したことだったし、その幸福は惨めさともたやすく通じ合うもので、その体験は貴重なことだと言って間違いなかった。
読み終えたのは休日の夜だった。どうしようもない休日の晩、ほとんどの時間をコタツで眠って過ごし、やっと外に出て、その日はじめての食事を0時半、駅前のマクドナルドで食べ、食べ終えてから大通りを挟んで向かいにあるサイゼリアに行ってデカンタに入った赤ワインをこぼしながら飲み、煌々と照り映える光のしたで読み終えた。思考の能力、想起の能力を根こそぎ、二度と戻らぬまでに消したがっていたのですよ。この言葉が頭にこびりつき、それなりに酔っ払った僕は廃墟のように静まり返った岡山の町をふらふらと、星も見えないろくでもない空を見上げながら家に帰ったのです、と彼は語った。思考の能力、想起の能力を根こそぎ消すこと。アンブロースのような実行に移す度胸もない僕は、こうやって虚しさをどうにか美化しながら、ろくでもない生を生き続けるのでしょう、少なくともその夜はそう思っていました、と。
←
→