text
2012年5月7日
ゴールデンウィークがやっと終わって、経営的にはこれ以上ないほどにというかこれ以上はないんだろうなという水準でゴールデンなウィークだったというかゴールデンウィークのゴールデンというのは金のことなのねというのが身にしみてわかったウィークだったのだけど体や気持ちの疲弊の方がより強く、と短絡的には思ってしまうけれど少し視線を先に伸ばしてみればこのウィークに助けられたということになるだろうなということは重々にわかってはいるのだけどそれでも渦中にあるときは怯えとともに始まる日々だったしひたすらに、それは完全に「さばく」という作業に終始し、ゴールデンなウィークでも現在のうちはそうなるのねということがよくわかったのだけど客足がすっかり夜には途絶えて、という夜とてやることはひたすらに仕込み、仕込み、仕込みであり怖いのは明日、だからがむしゃらに食事を制作し続けなければいけないという強迫にやられて気持ちも足腰も肩も、全部が疲れて、悲惨だった。
ゴールデンなウィークに限らず忙しい日に思うのは恐れであり、それは怒濤に来続ける人々をうまくさばくことができるのだろうかという不安もあるし、それとはまた別に、店はいつだってさばかれる存在としてあるわけで、こちらとしてはもはやさばく対象となってしまった人々を十全に満足させることができるのだろうか、二度目はあるのだろうか、という不安でもある。後者は未来に対する不安ということになる。もはや、飲食店である以上、店に踏み入れてしまった人からはどれだけまずい飯を出そうともお金はもらえるわけで、だから問題はその先であって、人がぎょうさん来て、お金をぎょうさんいただいて、その額を見て満足した顔をしているような飲食の人はたぶん間違っていて、そのお金を見たときに本来覚えるべき感覚は不安でなければならないんじゃないかと今は思っている。たくさん人が、つまりチャンスが来た。そのたくさんの人たちを満足させられなかったとしたら、それは将来的に見たときに店にとって損失と呼べるのではないだろうかと、そう考えていて、だからいつもより多いお金を見たときに感じるというかまっさきに去来するのは大丈夫だったろうか、我々のこの日のおこないは、ということだ。ということは理想であり、私は未熟なのであーよかった、お金たくさん、ありがたや、疲れた、という思考になる。まあどうでもいい。
全部どうでもいい。全部とは言わないけれども大方はどうでもいい。唾棄すべき無内容な馬鹿笑いも、ネガティブな部分で同調して溜飲を下げることも、全部くだらない。なんにもなければいい。人間に関わることの全てが私にとってはなんというか容量オーバーというか、みんなよくやってるなと思う。感心する。尊敬する。何にも興味が惹きつけられない。どうでもいい。映画や小説を私がどうしようもなく欲するのも結局、無菌室のなかに入りたいだけなのかもしれない。誰かが制作したものを安全な場所で眺めながら、インスタントな感動や動揺を得て、それがあればいいのかもしれない。そこで得られる感動も動揺も、本当に安全なものだ。この作品で人生を変えられた、みたいなことを言う人がいるけれども私の人生は小説や映画では変わらなくて、せいぜいのところが「あーいま俺茫然自失」と思いながら茫然自失のポーズを15分きめるとか、1日や2日、長くて1週間とか思い出しては感動したり動揺したりするぐらいで、人生のスパンで考えればあっという間にそんなあれこれは過ぎ去って、私は元通りの私として軽薄に振る舞い続ける。とても安全で、何にも脅かされなくて、私は、そんな無菌室でゆったり、何かにひたったつもりでいられればそれで満足なのかもしれない。私の生など、驚くほどに、嫌になるほどに軽いもので、ウィスキー飲んで、ダルビッシュの投球を見て、飽きてソリティアやって、寝て、起きて、私には何も残ってなくて、そもそも何もなくて、がらんどうで、からっぽで、バカがバカの顔して何も楽しめないまま死ぬまで生きて、それだけでお腹いっぱい。悲しい。誰にも同情も何もされたくない。それならこんな文章書かずにキーボードから指を外せ。くだらない。それならわざわざブログに更新してツイッターでそれを知らせてなんていうくだらなさの極地みたいな行動せずに目をつむってろ。なんの自意識なんだよ全部。何を発露して何を知ってもらいたいんだよ。苦々しい。「苦々しい。」って、なんでわざわざそんなこと打つんだよ。誰からの何を期待しているんだよ。頼むから黙っていてくれ。「頼むから黙っていてくれ。」頼むから黙っていてくれ。混乱したふり。全部ポーズ。コントロールA、コントロールC、ダッシュボード、新規投稿、コントロールV、「5月、ゴールデンウィーク、金」、公開。
cinema
2012年5月3日
 車から降りた若い女が迎えた男に引き上げられて窓から建物の中に入る。そこで3人だけの上映が行われる。というところから「やくたたず」あるいは「除外された人」というタイトルの映画が始まる。このときの車のエンジン音と、画面には映されていないけれど足元に水たまりでもできているらしくぴちゃぴちゃと鳴る音が妙に印象的に耳に響いて、それだけでなんとなくこれからの2時間への期待が高まった。
車から降りた若い女が迎えた男に引き上げられて窓から建物の中に入る。そこで3人だけの上映が行われる。というところから「やくたたず」あるいは「除外された人」というタイトルの映画が始まる。このときの車のエンジン音と、画面には映されていないけれど足元に水たまりでもできているらしくぴちゃぴちゃと鳴る音が妙に印象的に耳に響いて、それだけでなんとなくこれからの2時間への期待が高まった。
教室での音楽の授業、3人の子どもがつかまる汽車の流れ、ハモりだす3人、煙草に火をつける暗室、地下室らしき場所で酒を飲む老人と子ども等、少年時代を映したいくつかのシーンがとてもよかった。また、老人のダンスパーティーのくるくる、交わされる色目遣い、外に出ての殴り合いの喧嘩、この人たちは50年前からずっと青春を生き続けているのだろうなという顔つきが、画面全体に幸福感を与えていた。グルジアの街は音楽で満ち溢れていた。
ただ、これらは冒頭20分ぐらいのことで、窓から伝書鳩を飛ばす様子や、数十年前の話なのにフランスの駅の人々がイヤホンをして歩いている光景や、撮影現場やフィルム編集の手つきや、老いてなお気品をたたえるビュル・オジェの姿やラストシーンはよかったけれど、そう目をみはるようなショットもなかったし、全体に特にまあどっちでもいいかなというのが正直なところだった。
予告編とかつて見た『月曜日に乾杯!』の記憶から、なかなか好きなように映画は撮れないけれどそれでもなんだか陽気に生きています、からっとした色恋と素晴らしい友情と鳴り止まない音楽とともに、みたいな多幸感あふれるものを勝手に期待していたのだけど、思いのほかに低いトーンが持続していく映画だった。
それにしても、前も同じこと書いた気がするけど、『CUT』から始まり、『ヒューゴの不思議な発明』、まだ見てないけど『アーティスト』、そして本作と、映画に関する映画が同じ年に矢継ぎ早に上映されていく感じっていったいなんなんだろう。いよいよ、何かが終わろうとしているのだろうかというような無駄な勘ぐりをしてしまう。
・『汽車はふたたび故郷へ』公開 オタール・イオセリアーニ インタヴュー | nobodymag
・汽車はふたたび故郷へ インタビュー: オタール・イオセリアーニ 「映画は時間の中で流れる芸術」 – 映画.com
・2012-04-09 – 『建築と日常』編集者日記
・『Chantrapas』 – maplecat-eveの日記
text
2012年4月27日
保坂和志の『カフカ式練習帳』が出ていたことが知れて、買わなきゃ、読まなきゃ、という気になっているのだけど小説はまずピンチョンの『逆光』読んでからだなと思っていたところなので、どうしようか迷うところだけどだけど保坂和志の新しい小説なんて一刻も早く読まないと、と妙に気が焦る。今日は休みだった。いつもより早くに起きて店に向かい、今まで使っていなかったというか借りていなかった地下室を5月から借りて客席にするので知り合いの建築士の人にお願いして大工さんを呼んでもらって邪魔な柱を移動してもらったり、プロジェクターの吊り下げ台を作って取り付けてもらったりをして昼になり、それから車で倉敷方面に出てホームセンターやリサイクルショップに行き家具や電球等を購入して帰ってきたらもう夜で、体があまりに疲れてその疲れがまったく抜けないような状態になっていたので初めて整体に行って体をほぐしてもらった。左の肩と背中のだるさがひどくて、夜になるとだんだんと重くなってもう嫌だという気分になるのだけど今日のような休みの日でもそれがありしんどかった。それが解消されたかといえばどうかわからないし今こうやって打鍵していると左腕がしんどい。フライパン、ということだけなのかはよくわからないけれど職業病だね、よく来られるよ飲食の方は、と整体の先生が言っていた。
倉敷に行く途中においしいパンを買おうと寄ったUNIONという店で、お客さんとオーナーとおぼしき方の会話を聞いていたら今年の出店は少人数で、云々、フジロック、という言葉が聞こえ、買うときにフジロックに出店されているんですかと尋ねると今年で4年目になるという。オレンジコートの奥の方でコーヒーを売っているらしい。最初、パン屋さんでフジロックで、というところでまさかヘブンのやたらおいしいパンとホットワインを出す、毎年お世話になっていたというかパンと一緒に幸福を噛みしめていたあのパン屋さんかなと思ったけれどもそれは違ったみたいで、オレンジの奥のコーヒーは利用したことがなかった。今年もフジにはいかないだろう。10年続いたものが2年途絶える。それが何年になるのか。何年になるのか。
どうも、不意に聞こえてしまったフジロックという言葉に私は大いに動揺してしまったらしくそのあとしばらくなんとなくうつむいた気分が持続した。自分の人生を生きる。組織にもカレンダーにもお客さんにも支配されない、自分で支配する人生を生きたいと、格好だけはいいことを先日店のアカウントでつぶやいたりはしてみたものの、現実としてあるのはやはり、どうにも、いろいろ現実的なことだ。多くを休んだらお客さんが離れていってしまう、それはすなわち生活に完全に直結する、という恐怖がどうしてもつきまとう。それを振り払うためには多くを休んでみる必要があるのだけど、それだけの勇気を私たちは持てるのだろうか。今の段階ではそれはできないような気がしている。なんせ怖い。
同じ事は広告というか雑誌等の掲載にも現れていて、本当であるならば口コミ等で広げていきたいというか広げていくのが一番健康的で、たぶん継続的で、いいことなのだろうとはわかっているし、なんせカフェであり、ワヤワヤと忙しい空間にお客さんは来たいわけではない。だから私たちとしても雑誌に掲載してもらって短期的にわっとお客さんが来ることがいいことなのかどうかはよくわからないというか、本当はよくないことなんじゃないかとすら思っているのだけど、どうしても、では、そうしなかったとき一体どれだけのお客さんが来るのか、もしかしたらあっという間に忘れ去られてしまうのではないか、と考えると、お誘いがあればじゃあお願いしますと乗る流れになっている。あちらからで、無料掲載の話だけなのだけど、岡山の地域誌というのはすごく強くて、載れば大きな影響があるということがこの一年足らずのあいだで身にしみてわかった今、なんというか、どういう身の振り方がもっともよいのか、今一度考えないといけないような気はしている。
自分の人生を自分で支配する、ということの一つのささやかな実践として、最近は週一で休みを作っているのだけどそれにプラスアルファする形で火曜日に半休を作って見に行きたいライブを見に行くということをしてきた。実にささやかで、しかし逡巡は消えない。必要なのは勇気なのか、それとも人員なのか。肉体的な極度の疲労もあいまって、それを常にといっていいほど考えている。
ライブはgrouperとenの二組のやつで、grouperはもともとアルバムを二つ持っていて、なんで買ったのだったか、ドローンとかノイズとかに興味が集中しているときにどこかのサイトで知って、それで買ったやつだと思うのだけど、どこか遠い場所で密やかに奏でられていると思っていた音楽を岡山なんていう文化のぶの字もないのかあるのか知らないけれどなんていうかだいたいスルーされてしまうような土地で聞けるというのは幸福な体験で、それは逃せないと行った。どちらのライブもドローンで、平日の夜に座り心地のいい椅子に座って聞くそれらはどこまでも気持ちよかった。スーパー8で撮られた粗く光に満ちた映像をバックに美麗と評されるキラキラドローンを紡ぐenと、静かなで微かで妙なる感じの、すごく低空飛行な感じでどこまでも続くのかいつ途切れるのかわからないスリリングな演奏をするgrouperとで、すごく充実したものを聞くことができた。という満足感がライブ後にそれぞれのCDとTシャツ2枚を買うという珍しい行動に私たちを走らせた。経済。
自分が好きだったり敬意を持っていたりするものをビジネスにしていくということについては何も思わないし、むしろ積極的にそうするべきじゃないかと今の私は考えているというか、映画にせよなんにせよ、いかに広くにリーチするか、いかにマネタイズするか、いかにサステイナブルな状況を構築するかっていうことをうさんくさいカタカナ語をどれだけ使おうとももっと真剣に考えたほうがいいんじゃないかと思っているのだけど、そうではなく、ビジネスありきで文化的な何かを利用しようとする人種にはへどが出る。そんな資格ないよほんと。見てるだけで胸がむかつくから消えてくれよ。
Grouper – Hold the Way

Grouper – She Loves Me That Way
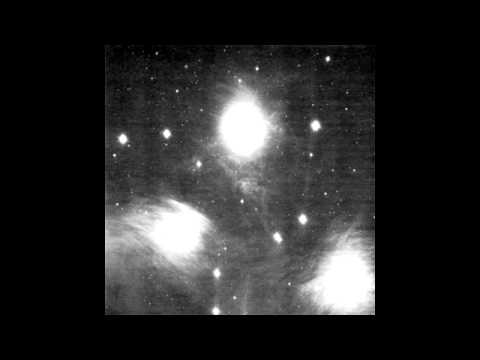
En -The Sea Saw Swell

text
2012年4月20日
部屋が暑い。部屋というか、正確には店であるけれど、夜にピナ・バウシュの映画を見に行って帰ってきて(という言い方がすでにおかしい)、いつだって夕飯ジプシーの私たちは店でご飯を食べて、それからずっと何かしらをおこなっている。休日には入り口の前に本日お休みですの看板を出しているのだけれども、前を通る人たちがこの人たちはなんだろうという顔をしていくのがどうしても気になるので2階に移った。いつまで出ることになるのか、こたつの席に座って、寒いから暖房をつけているのだけど暖房が効きすぎて体が火照っている。ビールの影響もあるのかもしれない。500円で売られる原価180円のビール。原価率36%。二度に渡って「び~る」と変換されて腹が立った。google日本語入力を使っているのだけれども、よくないのだろうか。たまにストレスがある。そのため2本目のび~るを厨房から今とってきた。
今日は週に1度設けている休みの日に当たり、昨夜間違えて二人して店で寝てしまったためにわりと早く起きられたので近くの喫茶店でモーニングを食べたあと県立美術館で催されているベン・シャーン展を見に行った。ベン・シャーン展は注目されているのかされていないのか知らないけれど美術館の前を通るといつもとてももはや静謐と呼んでもよさそうな静かな空気が流れていて、誰もいないんじゃないか、学芸員すら、という空気が醸しだされているのだが、入ってみるとちらほらとは人がいたので少し安心した。でもちらほらには変わりなかった。たぶん、岡山の美術館が盛り上がるのは先日までやっていた長谷川等伯であったり、昨年の夏ぐらいだったかにやっていた琳派と若冲の展示だったりなんじゃないだろうか。その字面には喜び勇んで向かう人たちには、今回の「ベン・シャーン クロスメディア・アーティスト―写真、絵画、グラフィック・アート」という文字の並びはそう訴求しないのかもしれないし、美術館の看板というのか、外から見える情報としてもまさに「ベン・シャーン クロスメディア・アーティスト―写真、絵画、グラフィック・アート」しかなくて、つまり一つの好悪の判断となる代表作的な作品のサンプルが表示されているわけでもなく実にシンプルであっけないものであることも、この閑散を呼ぶ一つの原因となっているんじゃないだろうか。そんな感じのやつね、と思える視覚的情報がないというのはけっこう、いろいろなものを遠ざける気がする。実際わたしも何かの展示をやっていると気づかずに通りすぎたことが何度かあった。
ピナ・バウシュもそうなのだけど私はアート的な教養がまったく欠如しているのでベン・シャーンという人は名前すら一度も聞いたことがなく、どのぐらい有名でどんな感じで評価されているのかは当然まるでわからず、最初のドレフュス事件等を扱った社会的らしい絵画もなんだか別に面白いとも思わずこれはつまらないまま終わってしまうかもなと案じていたところ二部の、説明によるとより抽象的なものに向かっていったとかなんとかの作品群を見てすっかり面白くなった。常にどんよりと深い青とか緑の空の中で赤い線が鮮やかに浮き出ていて、小麦とかレンガ塀とかフェティッシュな悦びに淫していそうな細部に目を見張ったし、何より、ソースとなった写真をわきに置く展示方法によって一枚の絵画が複数の写真をもとに構成されているという成り立ちがよくわかって、それがとても面白かった。
一番面白かったのは「縄跳びをする少女」で、背中を向ける少年の写真、舗装された道で縄跳びをする少女の写真、廃墟めいたレンガ壁とその手前に茂る花々の写真がひとつのフレームに収められて、特に廃墟手前にあった花がにレンガ壁の内壁に移植されている様子が、次元が組み違っておかしなかことになっているような目眩めいた感覚を与えて私をとても興奮させた。その他「解放」の浮遊感と壊れた家の壁紙であるとか、「至福」の綿密な小麦であるとか、タイトルわからないけど腕のやつとか、いろいろと面白かった。けれどだいたいにおいて私はいつもこうなるのだけどいくつかの作品を集中して見たら疲れてしまって、3部4部はすごく適当に見ることになった。いつも思うけれど、一日の一時間とか二時間の中で数十点の絵画を見るなんていうのがそもそも間違いなんじゃないかと今日も思って、半券提示で500円で再入場とか、そういうことをやってくれるとすごく嬉しいのだけど、人に渡されたりしたら困るというような問題なんだろうか。
休日を心底満足できる形で私は過ごしたことがなくて、今日も朝から喫茶店、美術館、それから行ってみたかったところで昼飯、タリーズで読書、美容院で散髪、そのあと映画、というわりとめいっぱいのコースを過ごしてもまだ、やはり、全然、何も、何も満たされないような感覚で、それはほとんど後悔と呼んでも差し支えないような感覚で、すごくよくない。それを少しでも埋め合わせるような心持ちでこうやって夜な夜な、カタカタと打鍵を繰り返してみせるが、これとて、なんの救いにもならない。バカがバカなことを書いているとしか思えない。私はどうやったら満足できるのか。満足したことはあったのか。あったのだろうし、というか、あったのだろうかと問うてしまうことは自分の人生に対していささか礼を失していると言わざるをえないと頭では十分にわかっているつもりなのだけど、果たしてそんなことはあったのだろうか、まるで記憶にないと、私はくだらない不満をこうやって並べ続ける。そういう人生なのかもしれない。
cinema
2012年4月20日
 気分が乗ってないから笑えないと困惑する少女に普段笑っている笑いとは違うの、感情はいらないの、真剣に笑うの、と言って手を握って、走り回りながら大声で笑う年配ダンサーと少女。稽古を見つめながら否応なく体が動いてしまう指導者たち。キャメルの煙を吐き出しながら子供たちを厳しかったり柔らかかったりする顔で見つめるピナ・パウシュ。服を脱ぐなんて恥ずかしいと言っていた少年が舞台で見せるブリーフ姿と自信に満ちた表情。それに対する女の子の見せる若々しい媚態。練習の途中でしゃくりあげながら泣いたガリガリの女の子の、練習時とはまるで違う、完璧に自分のものにしたように見えるおどろおどろしく生々しい歩き、凛とした視線、肩を、あるいは髪をなであげるしぐさ。集団で前方に走りだす椅子のざわめき。舞台裏のちょっとした笑顔。
気分が乗ってないから笑えないと困惑する少女に普段笑っている笑いとは違うの、感情はいらないの、真剣に笑うの、と言って手を握って、走り回りながら大声で笑う年配ダンサーと少女。稽古を見つめながら否応なく体が動いてしまう指導者たち。キャメルの煙を吐き出しながら子供たちを厳しかったり柔らかかったりする顔で見つめるピナ・パウシュ。服を脱ぐなんて恥ずかしいと言っていた少年が舞台で見せるブリーフ姿と自信に満ちた表情。それに対する女の子の見せる若々しい媚態。練習の途中でしゃくりあげながら泣いたガリガリの女の子の、練習時とはまるで違う、完璧に自分のものにしたように見えるおどろおどろしく生々しい歩き、凛とした視線、肩を、あるいは髪をなであげるしぐさ。集団で前方に走りだす椅子のざわめき。舞台裏のちょっとした笑顔。
とにかくすべてがみずみずしく、88分間、異常に長続きする涙の衝動をこらえたり決壊させたりしながら、私は幸福で仕方がなかった。幸福で、親密で、成長とはこうあるものだと、私は、もう、いろいろなものを放棄してでもこういう映画を全力で支持したい。美しかった。人間は美しいし体はもっと美しい。少年少女を過ぎていく時間は切実で、はかなくて、なんとまあ、本当に、偉大なものだと、羨望や嫉妬にも似たまなざしで私は彼らを見続けた。
どうも、若い人たちが体を使って何かに取り組むものであったり稽古の場面というのが大好きらしい。真剣さと無防備な表情のギャップに弱いのかもしれない。ワイズマンの『パリ、オペラ座のすべて』であるとかフィクションだけどアルトマンの『バレエ・カンパニー』であるとか、合唱だけどマリー=クロード・トレユの『合唱ができるまで』であるとか、もはや『ウォーターボーイズ』や『フラガール』もそこに入ってきていいと思うけれど、若い人たちが一生懸命がんばったり笑顔を弾けさせたり歯がゆさに泣いたりしてくれれば、私はもうそれだけで映画を全肯定できる。たぶん、特にアントワーヌ・ドワネルもののジャン=ピエール・レオーに向けている私の視線はこれとほぼイコールなんじゃないかと思う。人間ってすばらしい。その素晴らしい人間をうつしだす映画ってたまらなくすばらしい。そういうことなんじゃないかと。
ダンス等にさっぱり疎いのでピナ・バウシュというダンサーがどれだけの人なのかさっぱり知らないのだけど、誰かに似ているなと思ったらヒッチコックの『レベッカ』に出ていたいじわるメイドのフローレンス・ベイツに似ていた。と思って画像を見比べたらそうでもないかなとも思ったけれど鼻が似ているかもしれない。あまりにどうでもいいけど。
text
2012年4月16日
店は観光地といえば観光地というか日本三大庭園のすぐそばである以上いちおうやはり観光地にあると言っていいとは思うのだけどそういう絡みというか、すぐそばで桜カーニバルという名称の、要は桜がたくさん見られますよ、屋台も出るので好きにやってくださいね、ブルーシート、というカーニバルというかカーニバルっていったいなんのことだったのか、その意味が溶解するような用法だと思うけれどそういったことがこの2週間ほど催されていて、晴れた日や土日はたくさんの人々がそこにやってきてシートに寝そべるか座るかしながらビールを飲んだり何かを食べたりしていたらしく、朝、店に行く前の時間に散歩がてら後楽園の外苑をぐるっと歩いてそのカーニバルが催されている土手道も歩いてきた。土手の上に立つ桜の木は傾いで斜面すれすれまで枝およびたくさん咲かせた花を下ろしていて、前には川らしきものが流れていて、その向こう側が後楽園だった。後楽園の園内の桜の木もいい咲きっぷりを見せていた。朝にも関わらず場所取りの人たちが居座っていて、中にはスーツを着る者の姿もあった。仕事で花見というのを気楽なもんだとは一切思わないというか私だったら辟易というか仕事の一環で飲み会らしきものが催されたらいろいろと激しくうんざりするだろうから一切それを気楽だとは思わないけれども、組織としては気楽なもんだなと、やはりこれも一概には思えないけれどまあ、それ土日やればいいんじゃないの、とも思ったけれど私だったら会社の飲み会らしきものが事もあろうか土日に催されたら代休を要求したくてもできない、みたいな空気に屈してなんともいえない憤りだけを貯めこんでいくだろうから、もしかしたらそれは次善策としては十分かもしれない。
いずれにしても、人々はそこで飲み食いをおこない、話に窮したら桜がきれいである旨を相手に伝え、私は今にぎやかな場所にいるのでイヤホンをしている。

桜のカーニバルは観光地に店を構える私たちにも大いに影響を与えるもので、土日に限らずたくさん人が来た。いらした、と書くべきだろうか。いらした、と書くことは何かに対する迎合なんじゃないのかという余計な気を回してしまうのだけれどもそんなことはおそらくはないのだろう。いらした。たくさんの人が。方が、と書くべきだろうか。方が、と書くことは何かに対する迎合なんじゃないのかという余計な気を回してしまうのだけれどもおそらくそんなことはないのだろう。どうでもいい。方がいらして、たくさんお金をもらった。それはとてもありがたいことだった。14時間であるとか、それ以上であるとかの時間、腰を下ろすことが20分だとかそのぐらいだったということが何度もあり、夜ご飯を食べるのが閉店したあとになる、ということが何度かあった。その絡みかどうかはわからないのだけれども昨日の夕飯はミックスナッツであり、今日の夕飯は一風堂でのラーメンとなった。一風堂では何を店員に聞かれても単語でしか答えない男が横に座っていた。声の調子だけを聞けば決してつっけんどんではないのだけれども、いくつかは最後まで何かを言い切ったらどうなんだろうと思わずにいられなかった。彼に合っているのは一風堂でなくて松やであり、彼が対するべきは人間ではなく発券機だ。
その、2週間ほど忙しかったためというだけではなくこのところの私は時間がない時間がない時間がないということばかりに気を取られていてそういうことに気を取られているから余計に時間が削られる。時間がないスパイラルに陥る。一生懸命生きているような気がする。たいへんがんばっているような気がする。だけど非常な焦りというか、追い立てられるような気分になって、昨夜も閉店後に仕込みを始めてそのまま店で寝るというような真似をして、本も読まない、映画も見ない、そんな生活を望んでいるわけでもない。一時的な繁忙であることはどれだけ承知してみても、時間がないという強迫観念を退けられるわけではなかった。体が本当にしんどく、気持ちもそれに劣らないしんどさにあった。たくさんのことがどうでもよくなった。私には何もないような気がしなかったけれど、時間はないし、友だちもいないよなということはここのところずっと考えていることで、飲みに行く友だちもいなければ愚痴を聞かせる友だちもいなければ言うべき愚痴も持たなければ友だちの作り方なんて、まったく忘れてしまった。どこに行って、何を、いったい誰と話したらいいのか、そんなことはまったくわからない。そもそも、お客さんを見ていても思うのだけれどもよくもまああれだけみな話すことがあるものだと感心するとともに自分の話すことのなさに愕然ともする。何をあんなに話しているのだろうか。よほどそれは有意義なものなのだろうか。私にはそのあたりがまったくわからない。様々なことをこの何年か十何年かのあいだに切り捨てていって、今の私があって、そして何も話すべきものを持たない。私はこうやって、にぎやかな場所にわざわざ出向くという行動がよくわからないけれども、こうやって、イヤホンで音楽を聞いて、ディスプレイに向かって、指は打鍵して、文字がこうやって映しだされていって、世界がこの中だけで完結するような状態になって、そんな状態がいちばんしっくり来るのかもしれない。それ以外の世界なんて汚らわしく、余計で、私を傷つけ、罵り、殴りつけてくる、それだけなのではないだろうか。厭世観に酔う年齢ではもはやないことは重々に承知しながらこんなことを言っているのだからおめでたいものだし、友だちがいないと言いながら私は数百の友だちに向けてフェイスブック等で「カタカタしていないと気が休まらないためまたブログを更新した。不毛なことこのうえない」というようなコメントでもつけて更新を知らせるのだろうし、それに「いいね!」がつけばそれはそれでなんとなく嬉しくなってみたりもするのだろう。くだらない。あまりにくだらない。
弱気なことばかりを書いていても何も生まれないことはわかっていたのだけれども本当にあまりに何も生まなかった。ブログなんて形はやめて増田で書くべきなのかもしれない。フェイスブックも、ツイッターも、ブログも、あまりに私に紐付きすぎていて、私は私とは関係のないところで、せめてネット上でぐらい、生きたい、と思うこともあるけれどどこでも本名を晒してやっているのはもはやそういう線引きは無意味だと判断したうえでなのだけれども、それにしたってこんな暗い文章、本名のもとで書かれワールドワイドウェブに投げられる必然なんてどこにもないのに。ほんとうに、何をやらしても私はくだらない男だ。ということが判明したのでよかったです。
book
2012年4月13日
佐々木俊尚『「当事者」の時代』を読んだ。
「当事者」の時代 (光文社新書)
いつの頃からか佐々木俊尚信者になっていて、最近は全然追えていないけれどかつては毎朝のツイートを読むことが習慣かつ楽しみだったし、今でも週一のメルマガを読むために毎月1000円を払っているほどで、自分でもいったい何のつもりなのかさっぱりわからない。最近は以前ほどの興味はないのだけど、それでも新刊が出たなら早く読むぞ、ということになっている流れに従って読んだ。
あとがきによると小熊英二『1968』、加藤典洋『敗戦後論』、原研哉『白』に強く影響を受けて書かれたという本書は「<マイノリティ憑依>というアウトサイドからの視点と、<夜回り共同体>という徹底的なインサイドからの視点の両極端に断絶してしまって」「この極端に乖離した二つの視点からの応酬のみで」成り立ってしまっているという日本の言論の成り立ちを、著者の新聞記者時代の経験談、「異邦人」としての戦後の在日朝鮮人、6、70年代の学生運動、古くからの日本人の宗教観、世界初のトーキー映画『ジャズ・シンガー』に宿るユダヤ人問題等、だいぶレンジの広い話題を横断しながら分析していくというものだった。
その日本に巣食っている言論の状況に対して著者は「今こそ、当事者としての立ち位置を取り戻さなければいけない」と熱っぽく語っていて、その処方箋は「メディアの空間に脚を踏み入れる者が、インサイダーの共同体にからめとられるのではなく、そして幻想の弱者に憑依するのでもなく、つねに自分の立ち位置を確認しつづけること。完全な<加害者>でもなく、完全な<被害者>でもなく、その間の宙ぶらりんのグレーな状態を保ちつづけること」とのこと。至極まっとうで、まあ、なんか、そうだよな、と思った。新聞記者時代の経験から書かれた一章、二章が特に面白かった。
思い出すことが二つあって、ひとつは震災直後のタイムラインで、誰もが深刻なツイートをしているなかで年下の知り合いが友だちとご飯食べてきた楽しかったぴょんぴょん的なツイートをしているのを見て、これはなんか場違いというかちょっとどうなんだと思って今はそういうのはやめといた方がいいんじゃないのというダイレクトメッセージを送った私で、もうひとつは最近は見ないというかミクシィならではの現象だったのかもしれないけれど殺人事件の記事に対して加害者に信じがたいほどの強さの憎悪コメントをぶちまけるたくさんの人々で、どちらについても、いったいお前は誰なんだ、誰の言葉を代弁しているんだ、と思っていたのだが、あれこそがまさに憑依だったんだなと。私は被災者に憑依することで単純にいま自分が見たくないものを排除しようとして、ミクシィの人々は被害者遺族に憑依してどれだけ罵っても反撃できないサバルタンとしての殺人犯を糾弾し日頃の鬱憤か何かを晴らそうとしていた、ということだったのだと思う。マイノリティ憑依というのはたしかに便利で無敵でだからこそ非常な暴力装置として機能する。これはよくよく注意しないといけないなと、そう思いました。
それで、当事者としての立ち位置を取り戻せということだったのだけど、当事者としての立ち位置の難しさということはやはり震災のときに強く感じたものだった。同じ国の地続きの場所でどうしようもなく大変なことが起きていて、でもそのことを私が知れるのはパソコンのディスプレイを通してだけで、西日本に住んでいる身としては生活になんの変化もなくて、圧倒的な日常が続いていて、そういう状況のなかでどんな当事者意識を持って、どんな振る舞いが可能なのか、悩んだとは言わないまでも困難さを感じていたことを覚えている。実際あのころ、震災の非当事者という当事者性を引き受けて体現できていた人なんてどこにもいなかったような気がする。誰もが「被災国日本の国民である自分は震災の当事者である」というような顔をしていて、本当に、本当にそれをあなたはちゃんと心底で感じられているのですかと私は問いただしたかった。自分だけがこんなにぼんやりとした恥知らずな人間なのかと、そこまでは思わなかったけれど、一枚岩のような「国民」のみなさんの言動は私を大いに戸惑わせた。
当事者性を獲得する最後の手段のような感覚だったのか、数万円分の金銭および物資の寄付をしたものの、結局それで得られたのはちょっとした免罪符だけでしかなくて、偽装の当事者性すら得られないまま震災は自分のなかでどんどん薄くなっていった。店を始めてから震災後の移住者の方々と知り合う機会が何度もあったけれども、この人たちと自分には決定的な断絶があるように感じ続けていた。そんな中で今年の3月11日の午後に感じた奇妙な緊張と泣きそうな感覚は、あれは一体なんだったのだろうか。一体なんのつもりなのだろうか。
それはいいとして、本書は面白かったは面白かったのだけど、たぶん私が佐々木俊尚という人に求めているのはこういうものではないんだろうなというのはよくわかった。『「キュレーション」の時代』や『2011年新聞・テレビ消滅』や、あるいはメルマガで書いているような、現状の分析から来たるべき未来を投射するものを読んでマジっすか、そんなことになっちゃうんすか、それはちょっと楽しみかも、という感じでワクワクさせてもらいたいだけなんだろうなと。
それと気にかかったのが、準引用みたいなものだとは思うし書き方の問題でしかないといえばそうなのだけど、たとえば津村喬の『われらの内なる差別』が書かれた経緯を語るところで「早稲田のキャンパスの近くにある下宿の四畳半は、日が暮れてだんだんと薄暗くなってくる。続行しているバリケード封鎖のことを気にしつつ、次の一行をぼんやりと考えていると、李智成の短い遺書の向こう側に、なにか真っ暗な大きな空間がぽっかりと口を開けているように津村は感じた」云々というような描写がされて、こういう感じに登場人物の心象風景が描かれる文章がところどころに入ってくるのだけど、これってまさに憑依してるんじゃないの、というのが違和感として付きまとった。当然、これらは本書で言っているマイノリティ憑依というものとは異なる文脈に属するものではあるとは思うけど、なんだか、そういうところに接近してしまう危険性をはらんではいないかと感じた。何かからの引用ならちゃんと引用として書けばいいのになと。どうなんだろ。そういうもんなんだろうか。
関係ないけどNUMBER GIRLの「TEENAGE CASUALTIES」が私は好きです。「どこかの誰かが被害者 どこかの誰かが加害者」という歌詞に揺さぶられて今の私の何かが形成されているような感すらある。

cinema
2012年4月5日

昨夜バスター・キートンの『キートンの大列車追跡』を見た。先日見た『キートンの探偵学入門』も抜群に面白かったのだけど、キートンのとんでもないアクションと壮大な機械装置が融合するとこんなにもとんでもないことになってしまうのかと文字通り目を見張った。眠いのなんて完全にどこかに消えてひたすらに画面に見入った。
本作は機関士に扮するキートンが北軍の列車強盗の連中を追いかけて恋人を取り戻し南軍を救うヒーローになるという顛末の話だけど、ひたすらに横移動で撮られていく機関車のスピードと猛々しさと、その画面の中であっちに行ったりこっちに行ったりちょこまかとハードに動きつづけるキートンのアクションがとにかくすごくて、線路に横たえられた木材をぎりぎりのタイミングでのけるところに限らず、ほんとうにほんの一歩間違えれば死ぬんじゃないの、という危険な行為を70分間おこない続けている。そしておびただしい数の兵士たち、馬たち、大砲、燃える橋から落下する機関車。全編に漲るスペクタルの様相は喜劇という言葉の枠を軽々と飛び越えて、ただただ、なんだかもう、とんでもない。(言葉にならないので見てください)
それにしても機関車のこのスピード感はなんなんだろう。私に滂沱の涙を流させた大傑作、『アンストッパブル』(トニー・スコット)の素晴らしい列車が屁のようにすら見えてくるほど速く、ヴィヴィッドで、このうえなく危険で愉快な乗り物だった。先日から引っ張っているジョン・フォードの『アパッチ砦』の馬もそうだけど、速さというのは撮影やCGの技術の発達とは全然比例しないのかもしれない。
サイレントを見ていると、自分でも信じられないほどに無邪気に笑える。アミール・ナデリの『CUT』でのシネフィル東京の上映会で観客の人たちが実に健やかに笑っているのを見て、さすがにこんなことはないだろうとちょっと気持ち悪く思っていたのだけど、サイレントを、というかバスター・キートンを見ている時の私はまさにあの健やかさで笑っている。不思議なことだ。
・『キートンの大列車追跡』 1/4 ‐ ニコニコ動画(原宿)
・Sherlock Jr. (1924)(『キートンの探偵学入門)
http://video.google.com/videoplay?docid=-8074699069179823154
これほしい。けど高い。
バスター・キートン自伝―わが素晴らしきドタバタ喜劇の世界 (リュミエール叢書)
book
2012年4月3日
「新潮」を買って柴崎友香の『わたしがいなかった街で』を読んだ。やはり柴崎の『寝ても覚めても』目当てで「文藝」を買って以来だから、どうも柴崎友香の新作はわりと一刻も早く読みたいらしい。雑誌名の括弧は「」なのか、『』なのか、どっちなんだろう。
今作も度し難く素晴らしかった。
わたしがいなかった街で
柴崎の小説はどこらへんからだったか、たぶん『主題歌』あたりからぐんぐんと不穏な空気が立ち込めるようになって、読むたびにはっとさせられていたのだけど、宇宙人襲来の『ドリーマーズ』、ドッペルゲンガーの『寝ても覚めても』に続いて、今作はテレビやiphoneのディスプレイやあるいは電話から異次元の世界がこちら側に浸潤してくるような、いっそう怖ろしい話になっていた。と書くとジャンルものを書く小説家というように響きそうだが、実際に描かれてるのあくまでも文化系女子が生きるゆるやかで時々ちょっとした起伏のある日常(という言葉を使っていいのか悩むというか作中で明確に日常とはそういうもんじゃないと書かれているからそれを裏切る使い方ではあるのだけど)で、だからいっそうたちが悪い。
たぶん『また会う日まで』だったんじゃないかと思うのだけど、男友達だかと電話で話しながらともに同じテレビ番組を見て、何かを言葉を交わして、という場面があって、遠く離れた場所で電話回線でつながりながら同じ映像を見るという、その人と人との同期の仕方にひどく感動してうろたえたような覚えがあって、今作のテレビや電話というのもその延長線上にあるようにも思えるのだけど、手触りがあまりに違う。
主人公の「私」は部屋にいるあいだほとんど垂れ流しというような状態で戦争のドキュメンタリーを見続けていて、あるいは通勤中にはiPhoneで海野十三という小説家の『敗戦日記』の空襲の場面を読んでいて、生活の描写と地続きにどこかの町の戦争の映像が描写され、あるいは東京や大阪の風景を見ながらかつてそこにあったと思しき空襲を想像する様が描かれる。何もない、ほとんど空虚といっていいような日常がふいに割れて、どこかの、いつかの、わたしがいなかった街でおこなわれていた戦争の時間がわっと入り込んでくる。テレビやiPhoneの液晶画面が、地理や時間を超越した世界の入り口というか裂け目というか、覗き込んではいけないぽっかりと開いた深い深い穴のように機能して、クローネンバーグの『ビデオローム』や黒沢清の『回路』や、鈴木光司/中田秀夫の『リング』に連なるような、ほとんどホラーのような結構を小説に与えている。今にも貞子が這いでてきそうな予感がつきまとう。
また、「わたし」の世界はどんどん融解していき、電話で概要を聞いているだけのはずの友人の一日がまるで自分の目で見ているような描かれ方で書かれるし、しまいにはその友人が出会った葛井夏という若い女の生活や思考にまでなんの障壁もなくカメラは侵入していき、最後には「わたし」は小説から降りてしまう。しかもなんの救いもないようなどんな出口も見えないような状態で。
どこか、岡田利規の「三月の5日間」(これは戦争と現代の生活を見事に結びつけたというか、いま我々に持てるのはこの距離感において他ないんだよなという点においても共通するのだけど)や「わたしの場所の複数」を想起させるような、一人称が軽々と三人称の視点を獲得していく感じが私はものすごく好きで、「もっとこい、どんとこい」というような高揚した気分で読んだのだけど、それにしても、新作のたびに思うけれども、柴崎さんは毎度とんでもないところに向かっていく。『寝ても覚めても』を読んだとき、前のブログで「この人は次いったいどこに向かうのだろうか。行きついてしまったように見えるから、畏怖と興奮とともに心配になる」とお節介ながらという注釈は加えながらも書いていたのだけど、ほとんど同じことを今回も思った。
「私」が放棄された中で描かれるラストの、クライマックスと言っていいだろうけれども、高速バスから見る「棚田と海と、その向こうに燃えながら沈んでゆく太陽」の場面はほとんど厳粛ともいえるような美しさで、涙を流していたおばちゃんはたぶんロメールの『緑の光線』のマリー・リヴィエールに違いないのだろう。
それにしても、葛井夏が中井を経由して獲得する、気になったら聞けばいい、話しかけたくなったら話しかければいいという実践は、たぶんこの作家に通底しているショートカットな処世術で、それは本当に、素晴らしく素晴らしいものだといつも思う。
以下ページ折ったところ。
夜、パソコンを開いて、随分会っていない知人たちのブログを辿ってみた。ソーシャルネットワークサービスというものに、しかも複数登録している人も多くて、それぞれの場所で、知人同士が、知人と誰かが、やりとりしている。このあいだたは楽しかった、その店はおいしくない、おやすみー。
知らない人のこういうやりとりを見ていると会ったこともないその人に一方的な親しみを感じるようになったりするが、知っている人の書き込みは、彼らといっしょにいた時間からどんどんと離れていく自分を実感させる。なぜみんな、こんなふうに気楽に、素早く、なにかを伝えることができるんだろう、と思う。(…)長らく会っていない人たちが毎日いろいろな経験をし、誰かと次々に言葉を交わし合うのを見ていると、わたしにとって、知っている人さえもテレビみたいに画面の向こう側の、自分には関わることのできないところへ移動していくように感じてしまう。
日が長くなってまだ薄闇で、暑くも寒くもなく弱い風が吹き、そのような空気の中を一人で自由にただ歩けるということは、もしかしたらこの時間が自分の人生の幸福で、これ以上のスペシャルなことは怒らないし望んでもいないのではないかと考えながら、しかしそう言うとたいていの人には平穏な日常こそが素晴らしいという意味にとられるかもしれないが、自分は「日常」があらかじめ確かにそこにあるものだとは思えないし、たとえば仕事に行ってごはんを食べて眠るというような日々のことだとも思っていないし、それぞれに具体的で別のものがそこにあるのを一つの言葉でまとめることができなくて、「日常」という言葉を自分自身が使うこともない。
入江さんがルワンダに行こうとして死んだことを知ったときに、わたしにとってはルワンダという場所が存在し始めた。地図に書いてある名前ではなく、こことつながった場所として、歩いて行けばいつか辿り着く、同じ時間を生きている場所として、存在するようになった
前はこういうところに来ると、連絡を取り合わなくても誰か知っている人がいたのに、と思う。絶対誰かいるだろうという安心みたいなものがあった。それがいつ頃までだったのか。気がつけば「前」に京都に来たのがいつだったのかもすぐには思い出せない。同じような場所で同じような人たちがいるつもりでも、人は少しずつ入れ替わって、今はもう苦手なこの人しかいない
周囲の評判のよさと、怒っているときのその人の態度は、「裏表」ではなかった。彼は、自分が正しいと信じることに基づいて振る舞い、努力して自分の状況を作り上げてきた自信があり、その正しさに当てはまらない夏の言動が理科出来ず、もっとよくなる方法を助言しているだけなのに、と当惑しているのだった。(…)彼は、怒るたびに萎縮していく夏の態度を見て、いっそう腹立ちをぶつけるようになった。友だちに告げ口をしたからおれの評判が悪くなった、人を納得させられないような中途半端な考えながら最初からしゃべるな、と言われたのには、夏はいくらなんでもおかしいと思い、距離を置いたほうがいいんじゃないかと告げたら、今までなく激高して、自分はこんなに頑張ってきたのに無駄にするのか、おれはほんとうはこんな人間じゃない、穏やかに生きていきたいのに、おまえが怒らすようなことばっかりするからこんな汚い感情を持たなくてはならない、と壁をがんがんたたきながら泣きだした(…)あれが暴力と呼ばれるものの入り口なんだと、そうわかった瞬間に、泣きたくなった。楽しかったことも壁にあいた穴もいっぺんに浮かんで来ると同時に、今までに感じたことのないかなしさが体中に広がった。
錦糸町で、住んでいたマンションから駅へ歩いて行く途中に、公園があった。四角い、硬い地面の公園で、桜の時期には屋台が出るのが楽しみだった。公園をぐるりと囲む桜はきれいで、あの時期はほんとうにすばらしい。海野さんの日記で、あの公園が空襲のあとの仮埋葬地だったことを知った。一万人以上が何年か埋められていたあの公園では、桜が咲く前に引っ越したので私は見ていないが、今年も桜は咲いて屋台が出て提灯がついて大勢の人がやってきた。
日常という言葉に当てはまるものがどこかにあったとして、それは穏やかとか退屈とか昨日と同じような生活とかいうところにあるものではなくて、破壊された街の瓦礫の中で道端で倒れたまま放置されている死体を横目に歩いて行ったあの親子、ナパーム弾が降ってくる下で見上げる飛行機、ジャングルで負傷兵を運ぶ担架を持った兵士が足を滑らせて崩れ落ちる瞬間、そういうものを目撃したときに、その向こうに一瞬だけ見えそうになる世界なんじゃないかと思う。
しかし、それは、当たり前のことがなくなったときにその大切さに気がつくというような箴言とはまた別のことだ。いつも、自分がなんで他の人ではなくこの体の中に入っていて、今ここにいるのかと、不思議に思うというよりは、どこかでなにか間違えている気がしてしまうことのほうに関係があるのかもしれない。自分がここに存在していること自体が、夢みたいなものなんじゃないかと、感じること。
どたどた、と音がして、昇太がやってきた。「砂羽ちゃん、あのー、えーっと」昇太は続きをなかなか言わなかった。なんなのよ、とうしろで有子が急かす声が聞こえた。「あのね、ぼくね、砂羽ちゃんと、いっしょに生きていきたいです」
真っ白い天井には、向かいの家に停めてある自動車のフロントガラスに反射した光が映っていた。百日紅のい枝葉と花が薄い灰色になって投影され、細かいところまでくっきりと正確に再現されて、揺れていた。
母親は、栗まんじゅうの端をちぎって子供に与えた。夏の友人たちは、それを横目に見て、「でかっ」「やばっ」「どこで売ってるんやろ」とささやき合った。夏は、前に並ぶ家族たちのほうへ一歩、二歩、近寄った。「衝撃の大きさですね、それ」急に話しかけられた母親は、一瞬ぽかんとしてから、返答した。「…‥‥ああ、そうでしょう? 驚きますよね」(…)「クズイちゃん、そんなキャラやった?」「学習してん」得意げな表情を浮かべつつ、夏は、今度中井に会ったらお礼を言おうと考えていた。
・2012-03-12 – 偽日記@はてな
・2012-03-09 – 『建築と日常』編集者日記
・2012-03-13 – 『建築と日常』編集者日記
text
2012年3月30日
里芋を薄味で煮ておいた。少ししょっぱくなったかもしれないので扱いに注意したい。薄味で煮ておけば、片栗粉をまぶして揚げ出しにも簡単にできるし、炒め物に使ってもいいし、煮物に流用したっていいわけで重宝する上に、なんせ、忙しい朝の時間で里芋の皮を剥く作業はできるだけやりたくないから休みの日の夜にやってしまうことは正解のはずだった。そもそもは、ストックのなくなったオムライスの仕込みをしに休日の夜にわざわざ店に来たのであり、8割方終わったので帰ってきた。オムライスは牛肉を赤ワイン等々で丸一日以上はマリネしておきたいから事前の計算が肝要なのだけどすっかり計算違いをおかしたらしく昨日一日切らしてしまっていた。別段オムライスで売っている店のわけではないからそれもまあ問題なかろうという気持ちがある一方、やはりそこはしっかりしなければいけないとは、今のところちゃんと思えている。だから仕込んだ。肉を炒めて、鍋にぶっこんで、野菜を炒めて、布巾に包んでぎゅうぎゅうにエキスを絞りとる。それからひたすら煮てあといろいろ。マリネやエキス絞りがいったいどのような効果を味にもたらしているのか、実感としてはまるでわからない。ただ店を始めて半年以上がたって、やっとオムライスを堂々と出せるようになってきたのは喜ばしいことだった。
休みだったので昼は近くの、名店というか人気店というか、そういった感じの食堂で飯を食い、おいしいけれど別に感動するわけでもなく、タリーズに行って日暮れまでまったく集中しない状態のまま作業や読書をおこなっていた。なんというか、まあ、これは、だから、というかだからというわけではないんだけどだけれども、私にとってはというか私がありたいあり方を実現するためには必要な段取りだと思うようにしていて、どれだけ無意味なことを打ち続けようが、打鍵を繰り返すことはきっとさらなる打鍵を生み出すはずだと思っていて、だからこそ今の、たった今のような状態、特に書くこともないけれども何かを書いて吐き出さなければ気が済まないというか寝たくないという状態が実際に出てきているのであって、それがさらに推進されることによって(岡山弁なのか何弁なのか知らないが「ぶりがつく」と言う)、何かしら別のモードへ移行することが期待され、そうなることで、初めて、やっと、自分の、何かを、こう、満足のいく形かいかない形でかはわからないにしても、何かを、こう、何かを、何か、何かをできるのではないかと、そう思いたい。
タリーズでは、作業に疲れたというかもうできないとなったあとに昨夜読みだした『新潮』掲載の柴崎友香の新作「わたしがいなかった街で」の続きを読んだ。『寝ても覚めても』も異様だったけれども、というかここ数年の柴崎の作品はどれも異様だけれども、まあ本当に怖ろしいことになっている。怖くなって少し泣きそうになりながら読んでいた。
映画を見た。映画を見て、店に行った。本当はそのあとの回のラース・フォン・トリアーの『メランコリア』も見ようかと思っていたのだけど、11時を過ぎてからオムライスの仕込みを始めるなんて無茶だと判断したためやめて、その判断は正解だった。そもそも、トリアーにワクワクしたことなんてこれまでないのだから、見る必要すらないはずだった。でも日曜の晩にまだやっていたら見に行くかもしれない。地球が滅亡する日の話と聞いて、鬱屈した絶望的な話であるならば、今ならば見たいような気がしているのもまた事実だからだ。
私は、と、今ブログで私は「私」を使っているが文章を書く時の感覚は今でもあいかわらずに圧倒的に「僕」で、だけど前のブログからずっと「私」を用いている。その前のブログまでは「僕」だった。「私」を使い始めたのには理由らしい理由があったのだけど今のこのブログにおいては別段「僕」でも構わないはずだが、なんとなく「私」を継続している。ツイッターやフェイスブックではだいたい「僕」で、ブログでは「私」で、この違いは有意なものなのかどうか、それはよくわからない。何を意識して「私」でいるわけでもないのだけど、ただの慣れだろうか。それとも、「私」でいることで私から少し離れられる、文章の責任を私ではない「私」に負わせることができるとでも思っているのだろうか。わからない。
先日フェイスブックで「友達」であるところの大学の後輩の人がシェアしていた記事の一部分(その「友達」が引用していた)が頭から離れない。最近のモードと相まって、脳天を揺さぶってくる。
ソーシャル死ね。ソーシャルゲーム死ね。ゲームを返せ。ゲームから出てけ。 – 真性引き篭もり
僕等にとってビデオゲームは何よりも神聖なものだった。それは、ビデオゲームという名の聖域だった。人間という邪悪な生き物に出会うことなく、人生を楽しめる唯一の場所だった。この憎たらしい人生の、呪われた醜い毎日の中で、生きている事を感謝する為の、唯一無比のツールだった。ビデオゲームを遊んでいる間だけは、自分が人間である事を忘れられた。
ボヴァリー夫人は私だと言ったフローベールよりもきっとよほど強いリアリティで何百の人がこの文章に共感を寄せて自分を投影してブックマークなりツイートなりシェアなりをしたのかもしれないしバズってたからなんとなくブックマークなりツイートなりシェアをしたのかもしれないけれども、たしかに、「ビデオゲーム」を「小説」あるいは「映画」に置き換えれば、そこに現れるのは私というか僕というか俺だった。それはもう完全に俺だった。
←
→
 車から降りた若い女が迎えた男に引き上げられて窓から建物の中に入る。そこで3人だけの上映が行われる。というところから「やくたたず」あるいは「除外された人」というタイトルの映画が始まる。このときの車のエンジン音と、画面には映されていないけれど足元に水たまりでもできているらしくぴちゃぴちゃと鳴る音が妙に印象的に耳に響いて、それだけでなんとなくこれからの2時間への期待が高まった。
車から降りた若い女が迎えた男に引き上げられて窓から建物の中に入る。そこで3人だけの上映が行われる。というところから「やくたたず」あるいは「除外された人」というタイトルの映画が始まる。このときの車のエンジン音と、画面には映されていないけれど足元に水たまりでもできているらしくぴちゃぴちゃと鳴る音が妙に印象的に耳に響いて、それだけでなんとなくこれからの2時間への期待が高まった。
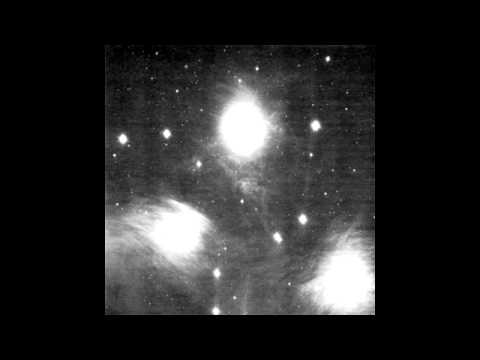

 気分が乗ってないから笑えないと困惑する少女に普段笑っている笑いとは違うの、感情はいらないの、真剣に笑うの、と言って手を握って、走り回りながら大声で笑う年配ダンサーと少女。稽古を見つめながら否応なく体が動いてしまう指導者たち。キャメルの煙を吐き出しながら子供たちを厳しかったり柔らかかったりする顔で見つめるピナ・パウシュ。服を脱ぐなんて恥ずかしいと言っていた少年が舞台で見せるブリーフ姿と自信に満ちた表情。それに対する女の子の見せる若々しい媚態。練習の途中でしゃくりあげながら泣いたガリガリの女の子の、練習時とはまるで違う、完璧に自分のものにしたように見えるおどろおどろしく生々しい歩き、凛とした視線、肩を、あるいは髪をなであげるしぐさ。集団で前方に走りだす椅子のざわめき。舞台裏のちょっとした笑顔。
気分が乗ってないから笑えないと困惑する少女に普段笑っている笑いとは違うの、感情はいらないの、真剣に笑うの、と言って手を握って、走り回りながら大声で笑う年配ダンサーと少女。稽古を見つめながら否応なく体が動いてしまう指導者たち。キャメルの煙を吐き出しながら子供たちを厳しかったり柔らかかったりする顔で見つめるピナ・パウシュ。服を脱ぐなんて恥ずかしいと言っていた少年が舞台で見せるブリーフ姿と自信に満ちた表情。それに対する女の子の見せる若々しい媚態。練習の途中でしゃくりあげながら泣いたガリガリの女の子の、練習時とはまるで違う、完璧に自分のものにしたように見えるおどろおどろしく生々しい歩き、凛とした視線、肩を、あるいは髪をなであげるしぐさ。集団で前方に走りだす椅子のざわめき。舞台裏のちょっとした笑顔。

